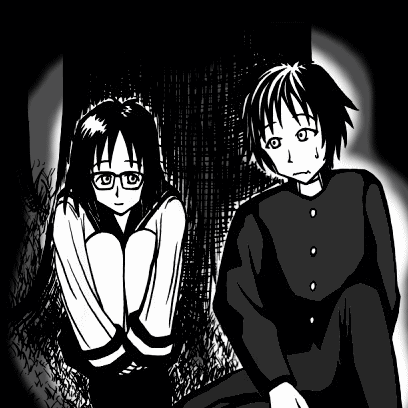99 辺りが一瞬明るくなったと思うと、次の瞬間、ゴロゴロと大きな音が響いた。どこかで雷が落ちたようだ。 雨の勢いは一向に止まらず、島全体に潤いを与えていった。しかしそれと同時に、黒い雲が日を遮り、闇を引きつれ、生徒たちの精神を暗い深淵の底へといざなう。 雅史はなにやら言い知れぬ胸騒ぎを感じた。 何かが…何かが起こっている。 杉山浩二や桜井稔のゲームオーバーを知らずとも、先ほど聞こえた銃声は、雅史を不安な気持ちにさせるには十分だった。 大雨をしのぐため、少し前にこの大木の下で雨宿りする事になった一行。樹齢数百年と思われるこの大木は、枝から開かせた無数の葉を、分厚い屋根へと変え、三人に降り注ぐ天の水を遮ってくれた。 剣崎大樹はゲーム開始から先ほどまで、一度の休息もとっていなかったため、ここでようやく一時の仮眠をとることにした。大木の根元に身を預け、深い眠りについている。しかし万が一に備え、武器であるアイスピックは手元から放さなかった。 石川直美はようやく平静を取り戻したのか、体操座りの状態で木にもたれかかり、何時までも雨を放ち続けている灰色の空を、ただボーっと見上げている。 そんな2人の身の安全を任され、雅史はコルトパイソンを握ったまま、辺りの警戒を続けていた。 浩二と稔は無事だろうか…。 不安な気持ちを押しのけ、なんとか前向きな気持ちを保とうとするが、精神が力を失いつつあるのか、なかなかそうはいかない。絶望と不安により、雅史の心は渇ききっていた。癒しと潤いを求めようとも、こんなプログラムの最中ではどうにも出来ない。もちろん猛スピードで大地を潤していくこの雨でさえも、人間の精神を潤す力にはならないのだ。 ああ、それにしても、俺たちはこの後いったいどうしたら良いのだろうか…。 自分達は今三人で手を組んでいる。そして全てが上手くいけば、浩二や稔、そして忍、さらには他の行方不明のクラスメート達とも手を組む事も出来るかもしれない。しかし、それが出来て何になるのだろうか? プログラムで生き残れるのはたったの一人というルールは変えようもない事実。いくら仲間を作っても、その中で内輪揉めを生み出してしまうに過ぎないのではないだろうか。 もちろん手を組んだ者たち同士で、脱出方法を考えるという選択肢は残されてはいるが、それで上手くいく確率は限りなく低いという事は雅史も分かっている。 ああもう、どうすればいいんだ! 雅史が悩み頭を抱えているのを、側に座っていた直美はじっと見ていた。 「どうしたの?」 突然聞こえた横からの声に、雅史の思考は遮断された。すぐさま声の主へと視線を移し、外見的には平静を取り繕った。 「いや、たいしたことじゃないよ」 直美を不安にさせぬため、考えていたことを全てを自らの内に隠した。人を思いやるには何も話さない方が良い時もあるのだ。しかし納得が出来なかったのか、直美はまだ問いかけを止めなかった。 「嘘。名城君、今ものすごく不安な顔してたよ」 雅史はどう返したらよいのか分からず、ただ口を噤んでしまった。 直美はどちらかと言えば、精神的に強い人間であるとはいえない。ここで不安にさせてしまうような発言は、すべてデメリットにしかならないのだ。 「まあ、皆が無事かどうか、それを考えていただけだよ」 「本当?」 なんとか横道に逸れようと試みるが、なかなか話題を方向転換させることが出来ず、苦戦する雅史。いったい何と言えば良いのだろうか。 しかし雅史の心情をなんとなく感じ取ったのか、直美はこれ以上余計な詮索はしてこなかった。 短い会話がすぐに途切れ、沈黙の時間が訪れた。しかし気まずい雰囲気などではなかった。何も話していなくとも、頭の中は考える事でいっぱいだったからだ。 厚い葉の屋根を通り抜けたのか、一滴の雫が頭上から落ちてきた。まだまだ雨は止みそうにない。沈黙する二人とは対称的に、降り続ける雨はザーザーとテレビのノイズのような雑音を発し、耳の中に延々と入り込んできた。 「ねぇ、名城君知ってた?」 突如耳に入ったノイズ以外の声に、雅史は驚き振り向いた。 「ん?」 何のことか分からず、直美に話の続きを求める雅史。 「クラスの子達の事だよ」 「それがどうしたって?」 はっきりと核心部を語ってくれない直美に、雅史は多少の不信感を覚えた。
「分からない。はっきり言ってくれよ」 一度疑問に思ったことは、はっきりと真相を知らずにいられないタチなのだ。雅史は直美に向かって懇願した。すると直美は少しニヤついたような顔で言った。 「ウチのクラスに、名城君の事が気になってた子、何人もいたんだよ」 雅史はちょっとした衝撃を受けた。突然耳に飛び込んできた、予想だにしなかった事実。うろたえた様子の雅史を見て、直美は再び微笑んだ。 “名城君の事が気になってた子” もちろん男ではないだろう。つまり、3年A組の女子の何人かが、自分のことを好いていてくれていたというのだ。 「ほ、本当なのか? 俺、全然気付かなかったけど…」 「まあ名城君って、そういうところ無頓着っぽかったからね。それだから誰も本人に向かって言い出せなかったんじゃないかな」 突如とてつもない恥ずかしさに襲われ、顔が真っ赤に染まった。そんな様子を見て、直美は楽しそうだ。 「名城君ってさ、なんかこうナイーブな所あるでしょ。それに何より良い人だし、皆そんなところに惹かれるんだと思うよ」 「なあ、聞いていいのかな。いったいそれは誰だったんだ?」 その問いに直美は少し考え、 「やめとく。だって今更こんな事言ってもしょうがないし…」 と言った。 確かにそれもそうであった。既に3年A組の女子は、残った3人以外は既に死亡してしまっているのだ。事実を知ったとしても、それは全て時間切れに過ぎないのだ。 「そうだな…」 「ゴメンね、私から言い出しておきながら」 直美は申し訳なさそうにうつむいた。 「いや、それが分かっただけでも、何だかちょっと嬉しかったよ」 雅史のその言葉を最後に、再び二人の会話が途切れた。 全てが時間切れだった真実。しかし、雅史は何故か心に潤いがもどったような感覚を覚えた。 大木の根元に寝転がり、青い言葉を交わす二人の人間を背に、大樹はつい口をつり上げ笑みをもらしてしまったが、それには誰一人気づかなかった。 まだまだ雨を放ち続ける灰色の雲のはるか下、豆粒のような生徒たちは、それぞれの大切な想いを胸に秘めていた。 【残り 9人】 トップへ戻る BRトップへ戻る 98へ戻る 100へ進む |