沖田秀之はクラスメート達を密かに、安全レベルから危険レベルの四段階に区別している。
これは三年間共に生活するにあたり、あくまでも“秀之にどのような影響を及ぼすか”という観点からの評価であり、プログラムで戦う際の有利不利に直接結びつくものではない。しかし、危険度が高い者ほど他者を貶めることを厭わないため、結果的に安全な者たちほど餌食になってしまうことが多いと予想される。
今まさに、比較的危険度の低い生徒が一名、巨大な悪意の塊と言ってよいほどの危険性を秘めた敵から逃れようと、息絶え絶えになりながら全力疾走していた。
複雑に絡み合った植物の茎に足をとられそうになりながら、必死に逃げているのは高橋宗一(男子十五番)。お調子者で常にテンションが高い彼は、地声が大きくてボリュームの調整がきかず、内緒話等も周囲に聞かれてしまったりすることが度々ある。それがクラスメート同士の諍いの種になってしまう可能性もあるため、秀之からは注意レベルと評価されていた。
「くそっ、なんで俺がこんな目に……」
背後に迫る脅威に怯え、宗一は走りながら時々後ろを振り返る。
視界の中、流れていく森の景色の奥に、禍々しく殺意を滾らせる追跡者の姿をはっきりと捉えた。狐の面を被った転校生、危険レベルの辻斬り狐(男子二十五番)。その手には大型のククリナイフが握られており、重厚で切れ味の鋭そうな刃が暗闇で時折光る。
脳裏をよぎったのは、自らが斬り付けられる凄惨な光景。背筋が、ぞくっ、とした。
絶対に追いつかれてしまっては駄目だ。仮に戦っても勝ち目はない。こちらの武器である手万力は、戦闘においてククリナイフより劣るし、そうでなくても宗一は他人と争うことが苦手だった。
必死に森の奥へ奥へと進む。今、自分が島のどの辺りにいるのか、もはや全く分からない。
位置を確認しようにも、走っている最中にバッグから地図を取り出すのは難しい。
森の中から抜け出すには、いったいどれだけ走らなければならないのだろうか。足場のよい平地に出ないことには、まともに走ることもできない。このままでは追いつかれてしまうのも時間の問題だ。そもそもこういう追いかけっこでは、相手の動きを見て走るコースを選べることから、追いかける側のほうが断然有利なのだ。
「ヘケケケケケケケッ! 待ァーテェーーーーーーッ!」
仮面の内側に仕込んであるらしいボイスチェンジャーを介した、不気味な笑い声が森の中に響く。命がかかっているこのクソゲームを、心の底から楽しんでいるかのようだ。
「誰が待つかー!」
辻斬り狐の挑発に、律儀に反応してしまう生真面目さが、自分でも嫌になる。
船の中にいたときの言動を聞いたかぎり、相手は頭のイかれた快楽殺人者と何ら変わらない。常識が通用しない彼の挙動に、一々反応することは無駄でしかない。
走っている最中、時折足がもつれて転びそうになる。雑草と木の根が這う地面は凸凹していて足場が悪く、そのうえ背負った大きな荷物に身体を揺さぶられるためだ。政府から支給された物品以外に、林間学校のために持ち込んだ余計な私物も持ち歩いていたのが失敗だった。
余分に用意してきた着替えとか、おふざけで持ってきた変装道具なんか、今となってはただただ邪魔だ。
しかし今さら走りながら荷物を仕分けるのは不可能だし、大切な食料などが入っているバッグごと捨てるわけにもいかない。
「ドウシタ? ソンナノロノロ走ッテルカラ、ホラ、モウ追イツイチャッタジャナイカ」
ふいに近距離から囁かれ、首から背中にかけて鋭い痛みが走った。
宗一は背中を押されたかのように大きく前のめりになり、今度こそ地面に派手に転がった。
一瞬何が起こったのか分からなかった。事態を把握したのは、倒れたままの体勢で後ろを振り返り、すぐ傍に立つ辻斬り狐の姿を見てようやく。
もたもたと走っているうちに追いつかれ、ククリナイフで斬りつけられたのだ。
耐え難いほどの痛みに、宗一は背中に手をやった。ほんの少し振れただけで、ペンキ入りのバケツに突っ込んだかのように、掌が真っ赤になった。
「ウソ……だろ?」
自分の身体から流れ出している血の量への驚きから、自然とそんな言葉が出る。いったいどれほど深く斬りつけられれば、これほどの出血が起こるのだろうか。目で見て確認しようにも、傷があるのは背中なので叶わない。
「ヘケケッ! 仕留メタ、仕留メタッ! オマエ、モウ終ワリダネ」
呻き声を漏らし立ち上がれないでいる獲物を見下ろし、辻斬り狐は実に愉快そうに笑い声を上げる。そのふざけた仮面の裏に、いったいどれほど醜悪な笑顔を秘めているのだろうか。
「こ、殺さないでくれ!」
この時点で、宗一の身体自体は、全く動かなくなったわけではない。しかし、心がほぼ折れかかっていた。この状態から逃げること、あるいは戦って勝つとことは難しい。それを悟ってしまったためか、生きたいという思いだけは強く持っているものの、全身の動力に繋がらなかった。
ただただ、命乞いをするばかり。
「ヘケケッ、駄目ダヨー。ブチ殺スー」
当然、辻斬り狐に見逃してくれる気なんて毛頭ない。
自分はここで死ぬのか、と絶望に浸りながら、宗一はただただ背中の痛みにもがき苦しむ。
「イヤー、プログラム参加シテ良カッタ! 一度人ヲ殺シテミタイト思ッテハイタケド、ココマデ楽シメルトハ思ッテナカッタヨ」
と宗一の頭を踏みつける辻斬り狐。
宗一は抵抗できないまま、視線だけを辻斬り狐の顔へと動かした。
「……お前、本当に……人殺しをしたいなんて理由だけで、このプログラムに志願したのか?」
「ソウダヨ」
質問に対して、当然でしょ、とでも言わんばかりに辻斬り狐は平然と答えた。
プログラムに参加することになるのは、全国にある中学校の中から、厳正なる抽選の結果で選ばれた中学三年生のクラス。しかしそれ以外に、自らの意思で志願して参加することもできるらしい。政府はプログラムをより円滑に進めることを目的に、やる気のある人間を一般公募している、と聞いたことがある。辻斬り狐はまさにこういうルートで、今回この島にやってきたのだ。
「別ニ、ソンナノ僕ニ限ッタコトジャナイヨ。他ニアト二人イタ転校生達モ、同ジヨウナ動機デ志願シタンデショ」
鳴神空也(男子二十六番)と山田花子(女子二十五番)のことだ。二人は船の中で口数が少なく、一見した限りでは辻斬り狐ほどの異常性は感じられないが、この糞ゲームに志願する理由なんて、確かに殺人への興味以外に考えられない。
「僕ノ場合ハ、テレビゲームガ好キデサ。特ニ、出テクル敵ヲ銃トカデブッ殺スヤツ。バキューン、バキューン、ッテネ。デモ、ソレニ飽キテキタノカ、近頃ハゲームナンカデハ興奮デキナクナッテキテネ」
「現実でやってみたくなったわけか……」
「ソウイウコト!」
「その仮面は?」
「コレ雰囲気出テイイデショ。イカニモ殺人鬼ッテ感ジデ。顔モ声モ謎ニシタ方ガ、皆ノ恐怖感ヲ高メルト思ッテ、ワザワザ用意シタンダヨ」
などと楽しそうに語りながら、宗一の頭を踏みつけている足に、より体重をかけてくる。
コイツ、マジで狂ってやがる。
宗一は怒りと悔しさのあまり、顔を歪ませる。
「アッ、ソノ表情生意気! カチーン」
唐突に振り下ろされるナイフ。腕を貫通して脇腹にまで到達し、激痛から悲鳴が漏れる。元からそういう色だったのかと見間違うほど、制服全体がもはや血で真っ赤だ。人間は血液の三分の一を失うと死ぬというが、傷を放っておけば、それに近い量が余裕で流れ出してしまいそうだ。
嫌だ。こんなところで死にたくない。
絶望に立ち向かうべく、今度は手足に力を集中させようとするが、既に血を流し過ぎているのか、どうにも身体が言うことを聞いてくれない。僅かに四肢が浮き上がるだけで、それ以上はどうにもならない。
「ヘケケケケケッ」
辻斬り狐のあの独特な笑い声が聞こえる。まず一人目の獲物を順調に仕留め、とても昂揚している様子だ。
もちろんこれで満足したわけではないだろう彼は、宗一の全てを終わらせた後、また新たな獲物を求めて動き出すだろう。そして、第二、第三と殺人を繰り返すに違いない。
他人のことを考えている余裕なんて皆無であったが、自分を陥れた相手に一矢報いたいという思いからか、気がつくと、満足に力が入らない手で、辻斬り狐の足首を掴んでいた。
「……コレ、僕ヲ捕マエタツモリカイ?」
血濡れの手で白い靴下を汚されたからか、ボイスチェンジャー越しの声は僅かに不快感が入り混じったようだった。
「ボケガッ! コノ程度ノ握力デ、僕ヲ止メラレルハズガナイダロ!」
辻斬り狐はいとも簡単に拘束を解き、その足を振り上げて一気に下ろした。
短い、しかし断末魔のような悲鳴が上がる。
バキリと音をたてて砕かれた宗一の指は、あらぬ方向へと曲がっていた。かなり複雑に粉砕したようで、関節がどこにあったのかも分からないような形になってしまっている。本人的には身体の傷よりもこちらのほうが、目も当てられぬ光景に思えた。
「僕ニ逆ラオウナンテ、百年早インダヨ」
獲物の歪んだ表情を見て、気が晴れたのか、今度はのけ反りながら笑っている。
宗一の頭の中は、これ以上ないほどの悔しさで満ちた。何もできない自分に対して、ここまで情けなく思ったことはない。
刻一刻と力はさらに奪われていく。そのうえ利き手は粉砕されており、溜まりに溜まった怒りをぶつけるすべが見つからなかった。怨みの気持ちが篭った目で、憎らしげに相手を見るばかり。
「サテ、カス相手ニ時間を使ッテルノモ勿体ナイナ。ソロソロ死ネ!」
地に伏した宗一にククリナイフが向かってくる。たが、その刃先は首に届く寸前のところで、急に止まった。
辻斬り狐の背後に黒い影が立ち、それが素早く両手を伸ばして、仮面を被っている頭を掴んだのだ。
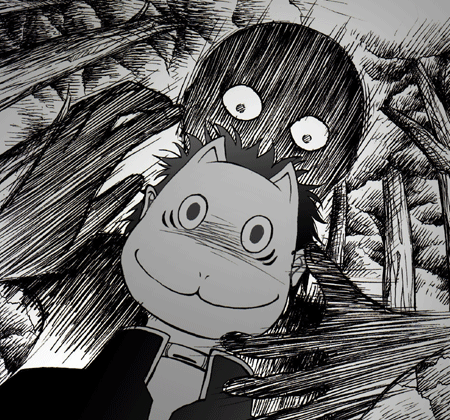
「ヘケッ?」
その存在に気づいていなかった辻斬り狐は、驚きからか間抜けな声を漏らした。
すぐに後ろを振り向こうとしたようだが、頭を掴む手の力が強いのか、全く動かせないでいる。
「誰ダ!」
仮面で表情は見えず、声は機械で偽られているが、彼の中に恐怖感が沸き上がっているのが分かった。
影は質問に反応を示さない。
辻斬り狐が初めて、短く悲鳴のような声を上げた。
それとほぼ同時に、ゴキリ、という音が生々しく響いた。宗一の手が砕けたときよりも、大きく激しい音だった。
先程まで宗一を見下ろす形になっていた仮面が、辻斬り狐の頭の後ろにまわって見えなくなっている。正確には、仮面を被った頭部が――砕けた首より上が百八十度反転してしまっていたのだ。
影が手から力を抜くと、辻斬り狐は土の上に崩れ落ちた。この状態では意識は当然ないだろう。手足をピクピクと痙攣させている様子から、生物学的にはまだ生きていると言えるのかもしれないが、それも長くはもたないだろう。
宗一は影の姿を見上げた。
蓄積された怒りと悔しさが具現化し、憎き敵に鉄槌を下してくれたのかと、最初はちょっとだけ思ったりしたが、当然そんなことが起こりはしない。目を凝らせばそこにいるのは、見馴れたクラスメートの姿だった。
「助けて……」
止血さえすれば、自分はまだ生き長らえることができるかもしれない。そんな思いから、闇に消え入りそうな弱々しい声を絞り出し、クラスメートに訴えかける。
見下ろされた視線は、宗一の方を確かに向いていた。しかしおかしなことに、そのクラスメートはいっこうに救いの手を差し伸べてくれない。
身の凍るほどの冷たい視線に、こちらを助けてくれるような温かな気持ちは、まるで感じられなかった。
そのクラスメートは宗一を観察した後、ふいに身を翻して、辻斬り狐の荷物を漁り始めた。
出血の具合から、予断を許さない状態であるのは明らかなのに、こいつは俺を見殺しにするつもりだ。
「まさかお前……ゲームに乗ったのか?」
懸命に出した言葉は、もう誰にも聞き取れるようなボリュームではなく、ほどなくして宗一は力尽きた。
大きく目を見開いたままのその表情は、まるで地獄でも見たかのように強張っていた。
 高橋宗一(男子十五番) - 死亡 高橋宗一(男子十五番) - 死亡
【残り四十六人】
|
