「ね、ねぇ……、なんか騒がしくない?」
瀬戸口信也(男子十三番)は、すぐ目の前を歩いている男女に問いかけた。しかし、緊張から周囲への警戒心が異常に研ぎ澄まされていた信也とは違い、仲間達は異変に気づいていない模様で、訝しげに首を傾けるばかり。
「確かに聞こえたんだって! 誰かの争うような声と、悲鳴がさ!」
小柄な全身を震わせながら、年齢よりも幼げな印象がある顔を強張らせ、訴える。
「悪りぃ。話している最中だったから、気づかなかった」
と返した、つり気味な目をした男子生徒は、雉島樹(男子八番)。癖毛がこんもりとした頭をかきながら、ほんの少し申し訳なさそうな顔をする。
「この辺りは水音が凄いからね。かき消されちゃったのかも」
そよ風に乱されたミディアムショートを、手ぐしでキッチリとセンター分けに戻しつつ、雛菊咲耶(女子十五番)がフォローに入った。
沢沿いに歩いている三人の耳には、流れる水の音が絶えず入ってくる。見える範囲に、小さな滝のように水が湧き出しているところもあり、水が岩を叩く音が、確かに周囲のあらゆる気配をかき消していた。
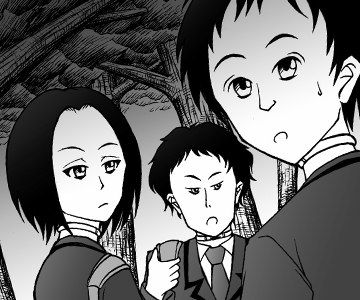
「しかし、瀬戸口が言ってることが本当なら気なるな……。ちょっと様子見に行ってみるか?」
クラスメート同士の争いを止めたいという正義感からか、あるいは単なる好奇心からか、樹が提案する。が、信也はすぐに乗り気にはなれなかった。
向かう先にいるのは、殺し合いゲームに乗り気の危険人物かもしれない。確かに、誰かが襲われているなら助けたい、という気持ちが無いわけではないが、それよりも、危険人物がいるところに行って、自分が襲われることへの恐怖心のほうが、圧倒的に大きかった。
「なんだ、不安か?」
腰が引けている信也の気を察したのか、樹が問いかけてくる。
信也は答えられない。
「ま、そりゃあそうだわな……」
信也と咲耶の顔つきを順に伺い、樹はなにか意を決した様子だった。
「俺は一人でも行ってみるわ。もしかしたら、助けられる命があるかもしれないしな。もちろん、無理について来いとは言わないぜ」
この状況下で、誰かも分からない他人のために正義感を湧き上がらせている樹のことを、素直に凄いと思った。同時に、樹のような考え方に至らない自分に対して、恥ずかしさを覚えた。
一方、咲耶は何を思っているのか表情からは読み取れない。しかし、歩き出した樹の後に黙って付いて行こうとしているのを見る限り、声の主を助けようという考えに同調したようだった。
「……自分も行くよ」
その消え入りそうな声が樹にまで届いたかは分からない。だが、後ろに続く信也と咲耶の姿を確認して、樹は僅かに笑んで前に向き直った。
五人兄弟の長男として育ち、先頭に立って他者を引率する能力に長け、サッカー部の副キャプテンをも務めている樹。
それなりに可愛らしい容姿をしているのに、口数が少ないことや、タロット占いという趣味のせいか、クラスで少々変わり者扱いされている咲耶。
そして、瓶ビールの王冠集めという地味な趣味くらいしか特徴らしい特徴がなく、親しいクラスメート達からよく『凡人』と弄られている信也。
普段あまり接点のない三人が連れ立って行動しているのは、傍からは奇妙な光景に見えることだろう。
信也とて、このメンバーが一緒にいるのが、未だに不思議に思えてならなかった。
そもそもこの三人の中で最初に接触したのは、信也と咲耶だった。
サンセット号内で催眠ガスによって意識を失った生徒達は、軍の手によって烙焔島内にバラバラに配置されたらしいが、信也と咲耶の配置された場所が、同じエリアの山中と近かったため、プログラム開始から十五分も経たずして鉢合わせた。
信也は驚きつつ身構えたが、話しかけてきた咲耶が意外にも冷静だったため、すぐに安堵して共に行動することに決めた。一人でいることがあまりにも心細く、誰でも良いから仲間が欲しかったのだった。
そしてさらに二十分ほどして、今度は樹と鉢合わせた。
先に相手の存在に気づいたのは樹だったが、殺し合いゲームの最中とは思えないほど気軽な感じで話しかけてきたので、逆に驚いてしまった。今思えば、樹の肩の力を抜いた対応は、怯える相手を安心させようという考えからだったのだろう。
それにしても、あんなにも堂々と接触してこられるのは凄いと思った。
集団で行動を始めてそれほど時間は経ってはいないのに、単純で迂闊かもしれないが、信也の中には二人に対する信頼が芽生えていた。
たった一人しか生き残れないというルールの下でも、他者への配慮を失わずにいる樹。
口数が少なくて掴みどころがあまり無いものの、常に平和的な考えを念頭に置く咲耶。
いずれも他者を出し抜こうという悪意は微塵も感じられず、それでいて信也のことも信用してくれている様子だった。
とはいえ、いくら三人が互いを信じ合っても、クラスのたった一人しか生き残れないという捻じ曲げようのないルールの下では、何も解決したとは言えないのが実情だ。あくまでも今を生き抜くための共闘でしかなく、三日後に迫るゲーム終了時までに何をすればいいのかは、誰も分かっていない。
後に仲間割れが起こったりしないだろうか、などといった不安が常に付きまとっていた。
悪い考えを巡らせていると、なんだかお腹がズキズキと痛み出した。
いつものことだ。信也はお腹が弱く、酷く緊張感が高まったりするとよく調子が悪くなる。我ながら厄介な性質を持ったものだ。しかし今ここで体調不良を訴えたりなんてすれば、樹たちに迷惑がかかってしまう。
「瀬戸口、身体どこか調子悪いの?」
信也は痛みを堪え、さも平静を装っていたつもりだったが、隠しきれていなかったのか、前を歩いている咲耶に問いかけられた。
「マジか? なあ瀬戸口、どっか悪いんだったら、ちょっと歩くのやめようか?」
樹も振り返って信也の様子をうかがった。
「べ、別にたいしたことないから、気にしないで」
「つってもよぉ……」
自然と前屈みになってしまっている信也が、身体のどこに痛みを感じているかは、誰が見ても明白だっただろう。いくら当人が強がっていても、それを気にしないで行動することは樹の良心が許さなかったようだ。
「いいから! 二人に迷惑をかけたくないし」
仲間の足は引っ張りたくないという一心で、自分のことなんて気にしないでいいと訴える。
樹は少しの間考えていたが、信也の真剣な様子に根負けしたのか、「分かったよ」と最終的に口にした。
「ただし、体調が悪化するようなら、黙ってないでちゃんと俺達に言えよ」
それが信也の主張を受け入れるための最低限の譲歩なのだろう。
察した信也は、素直に頷いて見せた。
「よしっ、じゃあ進むぞ」
以降ほとんど後ろを振り返らず、信也に対して過剰に気を遣い過ぎないよう姿勢を正す樹。しかし先頭を歩きながら、足場の悪い箇所で注意を促す程度のサポートはしてくれて、正直助かる場面もしばしばあった。
足取りは重いが、移動速度は悪くはない。沢のあった場所からだいぶ離れたため、いつの間にか水音は全く聞こえなくなっていた。
「ところでさぁ、雛菊。お前、船の中でタロット占いやってなかったか?」
口数の少ないメンバーの重い雰囲気を変えようと思ったのか、ふいに樹が話しかけた。もちろん、周囲に注意を払い、安全なのを確認したうえでのこと。
「……やってたけど、それが何?」
「お前自身の今日の運勢とかも占ったのか?」
トランプ等、各種カード類を持ってきている咲耶。その中にはタロットカードもあったようで、クラスメート数人を前にして占っているのを、信也も見かけていた。
「占ったよ」
「どんな結果が出た?」
「聞いても意味ないと思うけど」
何故だか分からないが、咲耶が話すのを躊躇しているように感じた。
「いいから、教えてくれ」
すがるような樹を前に、
「私の占いなんて遊びみたいなもんで、全くあてにならないよ」
と前置きしたうえで、意を決した様子で彼女は話した。
「出たのは『節制』の逆位置――問題が解決する時期ではなく、無理な決断や解決は避け、結果を先延ばしにすることが必要。っていう意味ね」
咲耶が言い淀んでいた理由がなんとなく分かった。捉え方次第ではあるが、信也が聞いた声の主のもとに向かうという行為に対して、何か悪い暗示をしているようにもとれるから。
といっても、占いなんて信じるかどうかはその人次第だし、気にする必要なんてない。しかし、知らない島の中で他にすがれるものが何もない中では、不安を煽るのに十分すぎる効力を発揮していた。
話題を振った張本人である樹も、まさかの不吉な占いに苦笑いするしかない。
「ははっ。嫌な結果がでたものだな」
淀んだ空気の中、何か気の利いたことを言えないか信也が考えていると、ふいに樹が足を止めた。
すぐ後ろを歩いていた咲耶が背中にぶつかりそうになる。
「今度はいったいどうしたって言うのよ?」
「いや……、あれ」
森の奥を指差す樹の様子がおかしい。声が震え、短い言葉に恐怖感が満たされているのが分かる。
何事かと、信也も恐る恐る目線をそちらへと走らせた。
茂みの隙間から、人の手足がはみ出しているのが見える。周囲に飛び散った血が赤い模様を描き、その中心で誰かが倒れているようだ。
「あ、あれ誰?」
「分からねぇ……。見に行くぞ」
恐怖感に足の自由を奪われる中、樹はたった一人で果敢にも現場に踏み込んでいく。
信也と咲耶は互いの顔を見合わせた。
「行く?」
「行かない?」
そんな会話を無言の中、表情の読み合いという形で繰り広げる。
先に決心がついたのは信也だった。女である咲耶よりも勇気を振り絞らなくてはならない、という男としてのプライドが背中を押した結果だ。
「来るな!」
数歩足を進めたとき、既に倒れた人物の傍らに到着していた樹が、掌をこちらに向けて強く制した。
仲間達が近寄ることを彼が拒んだ理由は、見ないほうがいい光景がそこにあったから。しかし時既に遅く、信也の視界の中に、その目を背けたくなるほどの凄惨な光景は入ってきてしまっていた。
身体の数箇所を深く切り裂かれて血塗れになってしまっている、高橋宗一の惨殺体。広く飛散した血痕が、彼を襲った犯人の残虐さを物語っている。そして死の間際に何か恐ろしいものでも見たのか、両眼が大きく見開かれたまま固まっていた。
「死んでるのか……?」
何気なく聞いた直後、信也は慌てて口を噤んだ。宗一の生死の確認を、樹に丸投げする形になってしまっているのに気づいたからだ。
一方、樹は信也の発言について気にしている様子はなく、すぐに屈み込んで宗一の身体を調べ始めた。
「駄目だ……。死んでる」
顔を覗き込み、脈や心拍を確認した結果、残念そうに呟いた。
「さっき瀬戸口が聞いたっていう声は、高橋が誰かに襲われたときの悲鳴だったんだろうな」
信也が悲鳴を聞いた時点からでは、急いで駆けつけていたとしても、宗一を救うことはできなかっただろう。それでも、実際にクラスメートの死を目の当たりにしたことによって、どうにか助けることはできなかったものだろうか、といたたまれない気持ちになった。
「ねえ! あそこにも誰か倒れてる!」
クラスメートの死に対する悲しみが冷めやらぬ中、信也の背後で咲耶が声を上げた。宗一の死体がある方角より右斜め前を凝視したまま、後ずさりしている。
もう一人誰か殺されているのか、と愕然としつつ、樹と共に咲耶が指差す先へと向かった。
奇妙な格好で倒れている男がそこにいた。身体はうつ伏せ状態なのに頭だけが天を仰いでいるのだ。へし折られた首から上を百八十度捻られているらしく、宗一のときと違って確認するまでもなく、死んでいるのは明らかだった。
「これは誰だ?」
信也は死体を見て眉をひそめた。
クラスメートの誰でもない、見たことがない顔だった。
「たぶん転校生だ。ほら、辻斬り狐とか名乗ってた、ふざけたヤツがいただろう」
そういえば、死体が着ている制服は星矢中学校指定のブレザーではない。濃いグレーの学ラン姿をしており、サンセット号の中で見た辻斬り狐の格好と全く同じであった。
「まさか、こいつももう殺されているなんてな……」
あんなにゲームに乗り気であったプレイヤーが、こんなにも早く脱落しているというのは少し意外であった。あからさまに危険だと分かる人物に、あえて近寄ろうとは誰もしないだろうと思っていたから。
「誰かに襲い掛かろうとして、返り討ちにされちまったのかな」
しかし何か妙だ。よく見ると辻斬り狐の身体には返り血が付着しており、おそらく宗一に襲い掛かった犯人は彼だろうと考えられるが、逆にお調子者の宗一が辻斬り狐の首をへし折るという大胆な反撃に出るとは思えない。
となると、辻斬り狐を殺害した人物は別に存在する、という考えに自然と行き着く。
信也は慌てて周囲を見回した。宗一の悲鳴が聞こえてから時間はそれほど経過しておらず、辻斬り狐を殺害した犯人がまだ近くにいる可能性がある。
「……ねぇ。あそこ、誰かいる」
自分達以外の存在に最初に気づいたのは咲耶だった。三人のいる場所から十メートルほど離れた辺りの茂みが、不自然に揺れている。
未知の敵の来襲に、各々が自然と身構える。
強力な武器を得た者は、支給武器がハズレだった者を守るように、いつでも攻撃できるような態勢をとった。
グループ内で一番役立ちそうな武器は、咲耶の手に渡った拳銃、コルト・ベスト・ポケット。スカートのポケットに納まるほど小型だが、殺傷能力は確かなはず。
樹も、咲耶の銃ほどではないが十分に威力は期待できる箱屋金鎚を構える。
そんな中、この場においては活用のしようがない耐火ジェルを武器として引き当ててしまった信也は、迫る恐怖に及び腰にならざるを得なかった。
暗闇の中、茂みに潜んだ何者かは、獲物の様子を確認するかのように間をおいて、そしてふいに飛び出してきた。
こちらの呼吸と呼吸の間を狙ったかのような絶妙なタイミング。
けっして目を離したりはしなかったはずなのに、虚をつかれたかのように、三人共がまるで棒立ち状態であった。
一番先頭に立っていた樹に、真っ先に脅威が迫る。刀身が折れ曲がったナイフのような物が空を切り裂き、その勢いのまま無防備だった首に突き刺さる。
あまりのスピードに反抗する術もなかった。
喉に深々と刺さった刃が、血に塗れた先端を後頭部から覗かせている。
コイツはいったい誰なんだ?
暗闇にもだいぶ目が慣れてきている中で敵の顔を確認するや否や、信也の頭の中に衝撃が走った。
それは人間の顔ではなかった。大きな目と耳が特徴的な獣のような顔――いや、正確には生身ではなく、獣を模した仮面を被っているようである。そしてすぐに、それは辻斬り狐の面であると気付いた。
本来の辻斬り狐が既に死んでいるのは確認済み。つまりコイツはニセモノだ。しかし何故、辻斬り狐の面なんかわざわざ被る必要があるのだろうか。
「瀬戸口、そこどいて!」
咲耶がコルト・ベスト・ポケットを構える。
信也は自らの立ち位置が、銃の狙いの範囲内であることに気づき、慌てて横に退避した。だがニセ辻斬り狐はまるで逃げる様子を見せない。悠長に樹の首からナイフを引き抜こうとしており、銃を脅威に感じていない模様だ。
咲耶とニセ辻斬り狐の間隔は五メートル程度。慣れない銃でも容易に的を撃ち抜ける距離に思えた。
すぐに、ダンッ、と銃声が響き渡った。想像していたよりも大きな音であった。狙いが自分でなかったにしろ、怯まずにはいられない。
同時に、咲耶が後方へと吹っ飛んだ。両手でしっかりとグリップを固定していたはずだが、彼女の細腕と体重では発砲した際の衝撃に耐えられなかったようだ。そのため狙いは大きくずれ、敵は全くの無傷な様子。既にナイフを引き抜いて、倒れた咲耶に猛スピードで向かって来ている。
その堂々さたるや、あらかじめ銃を撃つ際の反動を理解したうえで、咲耶がまともに発砲できず倒れることまで見越していたのではないかと思える。しかし、たかが一中学生が、銃器のことを熟知し、そこまで思考を働かせるなどはたして可能なのだろうか。
敵の急接近に気付いた咲耶が、倒れたまま急いで銃を構え直す。しかし、狙いが定まるよりも、相手がナイフの間合いに飛び込む方が早かった。
まさに瞬きしている間の出来事。
胸に刃を根元まで受け入れた咲耶が一瞬目を見開き、口をパクパクと動かしながら銃を取り落とした。
「ひっ……ひぃ……」
腰を抜かしてしまった信也が、手足全てを地につけたまま後ずさる。その情けない姿は、地面にはいつくばる虫のよう。
ナイフが胸から抜かれると、咲耶は凄まじい量の血を吹き出しながら俯せに倒れた。樹も彼女もピクリとも動かない。ニセ辻斬り狐の一撃一撃がとてつもなく正確に急所を捉え、二人共を一瞬で絶命させたのだ。苦しむ間すらほぼ無かっただろう。
咲耶の傍に落ちたコルト・ベスト・ポケットを拾い上げたニセ辻斬り狐が迫ってくる。腰が抜けた相手にも容赦なく、先ほどまでと同様に猛スピードで。
手が届きそうなほど近い距離になったとき、暗がりで分からなかった相手の身体的特徴をたった一点、おぼろげにだが捉えることができた。
その特徴にあてはまる人物は一人だけ。
「そんな……なんでお前がこんな……」
信也は、頭に浮かんだ人物が残虐な殺人鬼だとは到底信じられなかった。その美しき姿に魅了されたことがある者なら、誰だって疑うことであろう。
もう何がなんだか分からない。額に当てられた銃口の固い感触も、夢の中のことであるように遠くに感じられた。
滲む視界の中、コルト・ベスト・ポケットの引き金にかかった指先が動く。信也はなぜか黙ってそれを見ていた。
距離がゼロのこの状況なら、間違いなく弾は頭を貫くだろう。そんなことをぼんやりと考えているうちに、景色が視界の下へと大きくパンしていった。
瞬間的に聴覚を奪われたのか、至近距離にも関わらず銃声は全く聞こえなかった。
彼にとって唯一幸いだったのは、樹たちと同様に、死ぬまでに苦しむ間が無かったこと。
辻斬り狐の面を被った人物は、辺りに散らばった荷物を一通り漁った後、立ち去る間際に一度だけ、死んだばかりの三人の方を振り返った。
長い金髪をなびかせながら――。

 辻斬り狐(男子二十五番) - 死亡 辻斬り狐(男子二十五番) - 死亡
 雉島樹(男子八番) - 死亡 雉島樹(男子八番) - 死亡
 雛菊咲耶(女子十五番) - 死亡 雛菊咲耶(女子十五番) - 死亡
 瀬戸口信也(男子十三番) - 死亡 瀬戸口信也(男子十三番) - 死亡
【残り四十二人】
|
