森下藍子の唐突な出現に、秀之を襲う緊張は再びピークに達した。
元より彼女の動向には常に気を配ってきていたが、警戒レベルの人間には近づかないようにしようと決めたばかりの今、タイミングがこれ以上なく最悪であった。特に藍子は警戒レベルの中でも、その特性がいまいち明らかになっていない人物であり、気をつけると簡単に言っても、何をどう気をつければいいのか具体的には分からない。
仮に、同じく警戒レベルの足立宏と遭遇してしまった場合ならば、圧力を感じさせないよう柔らかな接し方に終始し、彼が暴走するのを未然に防ぐ、などといった対処法はある。しかし藍子のように特性が不明な者が相手の場合は、近寄らないという以外に良案は思いつかない。
危険を回避したい一心で、秀之は膝を抱えた体勢で限界まで身体を縮め、気配を消すことに努めた。不幸中の幸いか、こういう性格のため隠密行動はそれなりに得意なつもりだ。
草木が擦れ合うガサガサという音は確実に迫ってきているが、現時点で藍子はこちらの存在に気づいてはいないはず。ほんの一時我慢すれば、不吉はすぐに遠のいていくだろうと思っていた。だが、厚い茂みに阻まれているのか、彼女の歩みは非常にゆっくりで、なかなか離れていってくれない。
隠れるのが得意とはいえ、多少無理な格好で身を縮めているので、長時間耐えるのは厳しそうだ。とはいえ、この距離で物音をたてれば間違いなく気づかれるであろうし、いまさら姿勢を変えるわけにはいかない。
藍子が過ぎ去るのが先か、秀之の我慢に限界が訪れるのが先か、という静かな我慢比べが繰り広げられる。
くそっ……早くどっか行ってくれよ。
などと切に願いながら、草葉の隙間から藍子を凝視し続ける秀之。
ふいに首の後ろで得体の知れぬ何かが蠢くのを感じた。突然のことに「うあっ」と反射的に、僅かにだが声を上げてしまい、首に触れている物を必死になって振り払う。
全身に繊毛をまとったグロテスクな姿をした毛虫が、ぼとりと地面に落ちた。枝葉を這って首にまで伝ってきたのだろう。
身の毛のよだつような出来事に背筋がゾワッとした。だが、そんなことに気を取られている場合でないとすぐに気付く。
こちらが漏らしてしまった声に、藍子が気づいたのではないか。
声のボリュームは限りなく小さかったはずだし、相手の耳には届いていないかもしれない、と淡い希望を持つ。しかし、秀之のそんな思いもむなしく、藍子は何者かが潜んでいることを察した様子で、歩みを止めて周囲に目を走らせていた。
「誰かいるの?」
彼女は明らかに秀之が隠れている方を見据えながら問いかけている。正体までは分からずとも、茂みの中に何者かが潜んでいることには確信を持っている様子だ。
たかが毛虫ごときに驚いて声を上げてしまった自らの迂闊さに、苛立ちがこみ上げてくる。生き残るために色々難しく考えていようが、緊張感と真剣さが足りなかったら全て台無しになってしまうだろう、と自分自身に叱咤してやりたかった。
「黙ってないで、ちゃんと答えて!」
一度の大きな失態以降、秀之は衣擦れひとつたてないよう注意していた。もちろん声も出していない。
ただ潮風が森の木々を揺らす音だけが辺りを支配する中、緊張する藍子の心音が今にも聞こえてきそうだった。相手の正体を分かっていないぶん、藍子のほうが秀之よりも大きな不安を抱いているはずなのだ。
いっそこのまま黙って隠れ続けていれば、彼女は恐れをなして勝手に逃げていってくれるかもしれないと思った。
藍子はその場に留まって、片時も秀之の隠れている茂みから目を離さない。双方共に微動だにせず、二人の間だけ時間が止まってしまっているかのよう。
カチューシャを乗せた小さな頭が、一度わずかに上下した。息を飲み、意を決したのか、恐る恐るとこちらに近寄ってくる。
相手の正体を確かめなければ気がすまない性質なのだろうか、何事もなかったかのようにやり過ごすという考えは、残念ながら無いようだ。
それにしても、どんな人間が潜んでいるかも分からないのに不用意に近寄ってくるとは、なんて無鉄砲で危なっかしい奴だろう。相手が誰であろうと恐れる必要が無いほどの、強力な武器でも手にしているのだろうか。
しかし見たところ、彼女の手には武器らしき物は握られていない。カバンの中に仕舞い込んだままなのかもしれないが、だとするなら不用意どころの話ではない。命が懸かっているこの状況で、武器を手から離したまま堂々とプログラム会場内を移動するなんて、これ以上ない馬鹿の所業である。
それとももしや、彼女に支給された武器は、持ち歩いていても無意味なくらいのハズレ武器だったのだろうか。だとするなら藍子が丸腰で行動していることの説明がつくし、可能性はある。
ならば、いっそ全力で逃げだせば上手く撒くことができるかもしれない。
このままじっとしていても藍子に見つかってしまうだけだと考え、秀之は意を決した。
茂みが大きく音を立てて揺れ、藍子は怯んで歩を止める。秀之が勢い良く立ち上がり、藍子に堂々と背を向けたまま走り出したのだ。
「沖田君?」
シルエットの後ろ姿でこちらの正体を把握したのか、背後で藍子が「待って」と大きな声を上げる。
秀之はそれに一切反応せず、強く地を蹴って加速しようとした。
藍子は後ろでまだなにやら言っているようだが、一切頭に入ってこない。彼女が発する言葉の全てを脳が遮断し、思考回路を「逃げる」という考え一点のみに集中させていた。それなのにどういう訳か、築き上げられた分厚い壁をすり抜けて、たった一つの短い言葉が脳裏を貫いた。
「好きなんです!」
電子回路の一角に絶縁体を挟まれたかのように、解放されていた力の全てが急激に低下し、秀之の足を瞬く間に止める。
何故、走るのを止めてしまったのか、自分のことなのに分からなかった。
完全に静止した自らの足を見つめた後、すぐに振り返って彼女を見た。
「沖田君……あの……」
恥ずかしがっているのか僅かに身体をよじらせながら少女が立ち尽くしている。姿は間違いなく森下藍子。先ほど脳裏に届いた声も、彼女のそれであるようだった。
「……お前、今なにか言ったか?」
とりあえず、今すぐ攻撃してくる様子は無いようなので、聞こえた声が幻聴だったのかどうか確かめるように、秀之は藍子に問いかけることにした。
「えっ?」
「今俺に向かって何か言っただろ」
すると藍子は少しの間黙り込み、再び恥ずかしがるようにもじもじする。生死の狭間に追いやられているこの状況下で、いったい何を恥ずかしがるのか理解できなかった。
「あの……私……」
喉の奥に詰まる言葉を一生懸命に吐き出そうと、一度大きく深呼吸する藍子。
「沖田君のことがずっと好きだったんです」
意を決した彼女が放った言葉が、プログラムという場にそぐわなかったためか、一瞬理解ができなかった。耳から入った言葉がそのまま頭の中で何度か反響した後にようやく、次第に意味が分かってくる。それは少なからず秀之を驚かせるものだった。
日ごろから冷たく接していた相手に好意を持たれてしまうなんて、まったくもって予想外。
しかし今になって振り返れば、彼女の気持ちは普段の生活の節々に見え隠れしていたようにも思う。いくら冷たく接しても彼女は執拗に付き纏ってくるし、秀之を前にしたときの目は異様に生き生きとしていた。
ただ秀之の方が藍子の心情から目を背けていただけなのかもしれない。
「だから、あの……」
必死に自らの気持ちを訴えかける少女を見つめている少しの間、秀之は迂闊にも呆然としてしまっていた。プログラムが始まってすぐに起こった予想だにしない展開に、多少の混乱があったのは否定できない。
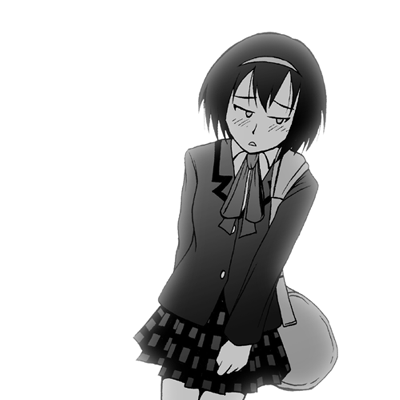
「私を、沖田君の彼女にしてもらえませんか?」
緊張のあまりか呼吸が続かなくなりそうになりながら、強く気持ちの篭った言葉をなんとか出し切った藍子。胸中の全てを曝け出した直後の少女は、まるで全力疾走した直後のように肩を上下させている。
秀之は藍子の告白を、何度も頭の中で反唱し、今起こった出来事を必死に理解しようとした。しかし考えれば考えるほど、死の淵に立っている現在の状況とのミスマッチさから、余計に訳が分からなくなっていく。
なんなんだこの女は? 本当に馬鹿なのか? たった一人しか生き残れないプログラムの最中で、恋人なんて作って何になる?
長くても三日後には、必ずどちらかは死ぬ。よってこの必死の告白は何の意味も成さない。それが分っていないなら、相手の心理状態は普通ではない。
そう思うに至ってから、秀之は一連の出来事について真剣に考えるのを止めることにした。
頭のおかしい人間の考えることなんて、考察するだけ時間の無駄であろう。余計なことに頭を使っている暇なんて無い。
秀之はとりあえず適当に話を合わせながら、これからの戦略についてのみ思考を巡らせるよう切り替える。プログラムの最中に告白されるというイレギュラーも、上手く転がせば何かに利用できるかもしれないと考えた。
「……凄く急な話だな。ただただビックリだ」
他の事を考えているのを悟られないよう演技しつつ対応する。ここはまず、突然のことに戸惑っているように振舞うのが自然であろう。
「あの……、私なんかじゃやっぱり駄目かな?」
「いや、駄目なんかじゃないけど、彼女作るなんて考えたことがなかったからさ」
「そうなの? ゴメンね。私一人で勝手に突っ走っちゃってるよね」
「謝らなくていいって。女の子に面と向かって告白されたのは初めてで、凄く嬉しかったからさ」
藍子に合わせようと意図的に話に乗っているものの、自分の台詞がむず痒くて仕方が無い。有効な戦略が思いつくまで、この歯の浮くような会話に我慢し続けることができるであろうか。
「へー、意外かも。てっきり沖田君なんか、他の女の子とかからもバンバン告白されてるもんだと思ってた」
「全然そんなことないんだけど、なんでそんな風に思う?」
藍子は一呼吸置いてから、秀之の目をじっと見据えながら言った。
「沖田君ってさ、普段ぶっきらぼうな感じだけどさ、本当は凄く優しい人だって分かるもん」
真剣に話す藍子に対し、つい鼻で笑ってしまいそうになる。
この女はいったい自分の何処を見て、そんな妄想めいた考えに至ったのだろうか。好きという感情のみが先走りすぎて、沖田秀之という一人の男のことを妄信してしまっているだけでないか。
「そんな大それた人間なんかじゃないと思うけどな、俺は」
「そうやってまた謙遜する。沖田君はもっと自分に自信を持ったほうがいいよ」
「そうなのかな?」
こちらが話を操っているつもりが、相手が馬鹿すぎて時折調子が狂いそうになる。主導権を維持するためにも、相手のテンションとペースに惑わされないように注意しなければならない。
「それで、どうかな?」
「え?」
「さっきの話の返事……。私と付き合ってもらえる?」
避け続けてきた核心にいきなり迫られると、秀之もさすがに困惑せずにはいられなかった。そこには触れないまま、上手く事を進めたかったが、どうもそうはいかないようだ。
執拗にストレートに迫ってくる相手に、下手な誤魔化しは通用しないであろう。イエスかノーかをはっきりと明言しなければならないようだ。とはいえ、ここでノーと答えるなら、藍子はどう態度を翻してくるか分からない。この馬鹿げたやり取りのせいで忘れてしまいそうだが、仮にも彼女は警戒レベルなのだ。
彼女も納得できるような理にかなった言い訳を立てて、なんとか丁重にお断りできないか考える。
「……付き合うとか、今は考えられないよ」
「えっ?」
動揺した様子の藍子。
「だって、そりゃあそうだろ。今はプログラムの最中で、生きるか死ぬかの瀬戸際で……そんな浮かれた気分にはなれないしさ」
とっさに考えたが、理屈の通った自然な回答ではあると思う。
どこに埋まっているか分からない地雷に触れないよう、一つ一つの言葉に気を使い、秀之は逃げ道を探すのに必死だった。
「沖田君も、やっぱり死ぬのが怖い?」
「そりゃあな。それに、俺の武器こんなだぜ」
ポケットから取り出した十得ナイフを見せる。
「こんな武器でいったいどう戦えってんだよな」
「私も、こんな寂しいところで、一人で生き抜いていくことなんてできないよ。武器がどんなのとか関係なく」
「それもあって俺と一緒にいたいってか? で、そんな森下に支給された武器っていったい何なのさ?」
逃げ道を探る中で、相手の武器を知ることも重要だ。先ほど藍子の武器はハズレであろうと推察したものの、やはりはっきりさせたほうが良いと考え、それとなく問いかけてみた。すると彼女は、やはり武器をバッグの中に仕舞いこんでいたようで、ファスナーを引いて手を中に入れ、ゴソゴソとしだした。
「えっと……。あ、これだこれだ!」
と彼女が取り出して見せた物があまりに予想外で、秀之は「えっ」と声を上げて驚いた。握られた小さな手から大部分をはみ出させたシルエットは、薄暗い中で重厚な金属部分を鈍く光らせている。
「それってモデルガンじゃないよな?」
「一応ちゃんと使えるみたいだけど」
藍子の馬鹿さ加減がそろそろ常識の範囲外に思えてきて、いよいよ真面目に考えるのが馬鹿らしくなってきた。
いくら生きる自信が無いにしろ、せっかく本物の銃を支給されたなら、なぜいつでも撃てるよう手に持っておかないのか。
突っ込みたいことが山のように出てきて止まらない。
しかし、これは強力な武器を我が物にする絶好のチャンスかもしれない。藍子から逃れるのは保留にして、なんとか彼女の銃を自らが手にすることは出来ないか、急いで思考を切り替える。
「なあ、森下」
「何?」
「俺さ、さっきも言ったように、今すぐにお前の告白に対して返事をすることはできない」
「……こんな状況だもんね」
「でも、しばらくお前と一緒にいて、ゆっくり考えたいとは思う。このゲーム、俺と組んで行動しないか?」
恋に妄信している藍子は間違いなくこの提案に乗ってくる。百パーセントの自信があった。
銃を手に入れるのと引き換えに、やっかいな女が付いてくるのには気が重くなるが、どこかのタイミングで上手く振り切れば問題ない。
想像もしない提案だったのか、藍子は驚いた様子で少し黙っていたが、よく頭の中を整理した末に口を開いた。
「それって、まだ私に可能性は残されているってことかな?」
秀之と付き合えるか否かを言っているようだ。
「一緒にすごしているうちに、いいなと思ったらな」
「分かった! 私、沖田君と一緒に行動する!」
秀之のためだけに計算された提案に、やはり頭の弱い女は何の疑いも無く乗ってきた。
こうなってくると馬鹿も捨てたものではない。全部こちらの思うつぼだ。
もしかして、もっと凄い要求をしても、今の彼女なら従ってくれるのではないか。
「ただし、いくつか条件を出させてもらってもいいか?」
「なんでしょう?」
まるで従順な犬のように尻尾を振る藍子。
「せっかく支給された武器を、バッグに仕舞い込んでしまっているのはもったいない。森下が使わないのなら、俺がお前の武器を持っててやろうと思う」
「なんだ、そんなこと。全然、沖田君が持っててくれていいよ」
「それともうひとつ。今はまだ森下のことを百パーセント信用しているわけではない。なにせ異常なゲームの最中だしな。そこで、お前のことを信用できるようになるまで、両手を縛らせてもらいたい。もちろんその代わり、敵が現れたりしたら俺がお前を守るからさ」
さすがにこの条件はやりすぎかなとも考えた。しかし、危険性の高い相手を傍に置いておくにあたり、なるべく優位な立場にいるために、試せることは全て試したかった。
これには藍子もすぐには承諾しかねるようで、両手を組んで考え出した。
「それって、船に乗る前にやった奴隷ごっこ……」
そういえばそんなこともやったっけ。
「ああ、奴隷ごっこみたいなもんだな」
武器を奪い取られ、好き勝手な秀之の言いなりになって、まさに奴隷である。
「そうか、信用されてないのか……。でもこんな状況だし、仕方ないよね」
藍子は一度天を仰ぎ、何か決意したようだった。
「分かった。いいよ、私のこと縛っても」
「本当にいいのか?」
「うん。まずは信用してもらって、好きになってもらうのはそれからでしょ」
不思議なことに、むしろ彼女は浮かれているようにも見えた。思いの丈をすべてぶつけ、これからどうしていけばいいかはっきりしたことで、身が軽くなったのだろうか。
「それじゃ沖田君、早速私を縛ってくれる?」
「あ……ああ」
カバンから取り出した新品のタオルを折って細くし、藍子が差し出した両腕にぐるりと巻く。多少痛いかもしれないが、簡単に解けないよう強く縛った。
「これで一緒にいられるね」
まるで既に恋人にでもなったつもりの言い草だった。だが、それに対してあえて突っ込むことはしないでおく。両手を拘束しているとはいえ、警戒レベルの人間を刺激することは避けたい。
「それじゃあ、お前の武器、持たせてもらうな」
地面に置かれたバッグの上に乗る銃に、遠慮なく手を伸ばす。
掴んでみるとずっしり重い。十得ナイフの軽さとはえらい違いだ。
しかし妙に思うところがあった。本来拳銃にあるはずのリボルバーやマガジンといった断層が、この銃には見られない。そういう特殊な銃もあるのかもしれないが、なにやら胸騒ぎがした。
「なあ森下。この銃、弾とか他に入っていなかったか?」
「えっと、カバンの中にいくつか……。あ、あと説明書みたいなのもあったよ」
「ちょっとカバン見せてもらうな」
ファスナーから手を入れると、すぐにそれらしい箱を見つけたので取り出した。
開けてみると、銃本体が収められていたのであろう空間の傍に、普通の拳銃のものとは似ても似つかない形状とサイズをした特殊な弾と、四つ折にされた簡単な説明書が添えられていた。
秀之はすぐさま説明書だけを取り出して開いてみると、一番上に大きな字で「信号銃」と記されていた。
【残り四十七人】
|
