共和国戦闘実験第六十八番プログラム――それは、全国の中学校から選抜された三年生のクラスが、その中でたった一人の勝者が決まるまで延々と殺し合いを繰り広げなければならないという、まさに地獄のゲーム。
戦闘データの収集だとか、政府への反発心を抑制するためだとか、その開催目的には様々な諸説があるが、秀之はそれをはっきりとは分かっていない。
確かなのは、これは法の下に行われている国家公認の催しであり、宝くじに当たるよりも稀という低い確率の中で選ばれてしまったら最後、何者も逃れることはできない、ということ。
まさか自分達が選ばれてしまうなんて。
と、歴代のプログラム参加者たち全員が思ってきたであろうことを、秀之も頭の中に浮かべて嘆いた。
先程デッキで明斗が呟いていたことの意味が、今更になってようやく理解できた。船の航路が予定とズレていたのは、このクラスが林間学校の会場とは違う、別の場所へと連れていかれようとしていたから、と。
要するに船に乗り込むよりももっと前の段階から、全ては仕組まれていたのである。
他のクラスと出発時間がずらされていたのは、三年三組だけを単体で連れ出すためで、必要以上に大きな船に乗せられたのは、自分達の他に、今この食堂を取り囲んでいる数十人の兵士や、辻斬り狐をはじめとする、三人の転校生とやらもひそかに乗り込むためだったのであろう。
秀之はギリギリと奥歯を噛み締めた。
普段からいつも危険なことに足を踏み入れぬよう気をつけてきたはずなのに、肝心なところで危機を察知できなかった自らの迂闊さに、腹がたって仕方がなかった。
もっと周りをよく見ていれば、いくらでも不可解なことに気づけたはずなのだ。
事実、明斗なんかは真相にこそ迫れなかったものの、航路のズレに気づき、胸騒ぎからか独自に更なる調査に踏み出していた。
見ると、明斗は静かに、しかしそれでいて真剣な眼差しを兵士や転校生達に向けている。大半の生徒達があからさまに動揺している中で、比較的落ち着いているようだった。
秀之も改めて、自分達を取り巻いている殺意の元へと目を向けた。
迷彩服を身に纏い、物々しく硬質な銃を構える兵士達。
辻斬り狐は相変わらず、テーブルの上をステージにテンション高く振る舞っている。
その後ろでは他二名の転校生が、辻斬り狐とは対称的に、ただ静かに立ってこちらに視線を向けている。男女ともに特徴のある姿で、狐の仮面を被った男に負けず劣らずといったほどのインパクトがある。
女のほうは耳や口にピアスを開け、短い髪を金色に染めてパーマをかけていて、とても派手な外見だ。制服をパンクロックテイストに少しアレンジして着こなし、さらに左目の下に涙を模したようなデザインのチークを入れている。しかしそれよりも注目すべきは、顔や腕など身体じゅうのあちこちに巻かれている包帯だ。本当に怪我しているのか、それとも単なる衣装のようなものなのか、見ているだけでは分からない。
男のほうは、髪が長く大柄で、とても力強そうな印象を受ける。顔の中心に大きな傷痕が横一文字に走っており、見ていてとても痛々しい。全体的に「侍」と一言で例えられそうな風貌だと思った。
それぞれに大きな特徴がある転校生達だが、三人ともが共通して、威圧感、不気味さ、ミステリアスさを持っており、それらが三年三組メンバーの恐怖心をよりかきたてている。
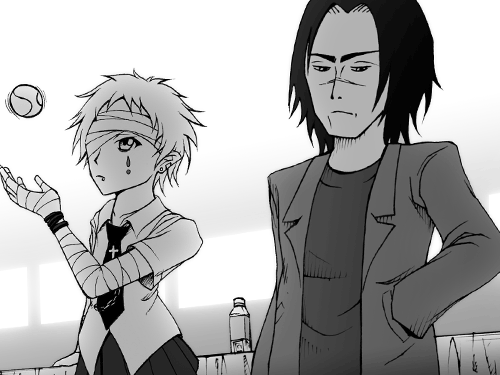
「アレレー? 皆黙リ込ンジャッテ、モシカシテ僕タチノコトヲ怖ガッテル?」
辻斬り狐が楽しそうに、テーブルの上でケタケタと笑っている。感情の変化をほとんど見せていない後ろの二人の分まで、この状況を大いに楽しんでいるようだった。
「ソレジャア、皆ノ元気ガ出ルヨウニ、僕のテーマソングヲ歌ッテアゲヨウ」
オーバーなアクションでリズムを刻み始めたかと思いきや、彼は胸に手を当てて本当に歌い始めた。
不快な機械の声が食堂じゅうに響き渡る。
「ツージ、ツージ、辻、辻斬リダー♪ 赤イ血ノ海カラヤーッテキター♪ ツージ、ツージ、辻、辻斬リダー♪ 皆ヲ葬ル男ノ子ー♪」
それはもはや、完全に悪ふざけ以外の何ものでもなかった。
恐怖に怯えるしかない生徒が多くを占める中、空気を読まない辻斬り狐の振る舞いに苛立ちを覚えた者もいるようで、荒い息遣いが聞こえ、わなわなと肩を震わせる姿も見えた。
「てめぇ! いい加減にしやがれ!」
田神海斗が勢い良く立ち上がった。そして強く握り締めた拳を振り上げながら、辻斬り狐に飛び掛ろうとする。が、その瞬間、兵士達が抱える銃が一斉に海斗に向き、彼はピタリとその足を止める。いくら我を忘れるほど激昂していても、四方八方から襲い掛かってくる死の恐怖に逆らうことは出来なかったようで、悔しそうに歯を噛み締めながら拳を下ろすしかなかった。
武装した兵士達がいる前で逆らうことなんて出来ない。そんな空気が場を支配した時だった。
「どうもー、皆さん、ようこそお越しくださいましたー」
先ほどの放送と同じ声が聞こえ、全員の目が部屋の入口の方を向いた。
開いた扉から手を叩きながら、男が二人入ってきたのだった。短髪で背が低く、ほんのりと猿を思わせる風貌の男と、もう一人は、背丈は普通で髪が少し長めの優男。おそらく共に三十歳代後半。
食堂の一番前は低い台になっており、彼らはそこに立ってセンターマイクのスイッチを入れた。
「あ……、あ〜あ〜」
背の低いほうの男がマイクの音をテストし、問題が無いことを確認すると、コホンと一度咳払いする。
「え〜、お待たせしました皆さん! 今の状況を理解できていない人もいるかもしれませんが、皆さんは今年度の共和国戦闘実験第六十八番プログラムに選ばれました!」
その言葉に反応する者は誰もいない。既に辻斬り狐によって知らされていたからだ。
「あれ? 皆さんもう、そのことについて知っていました?」
予想外の展開だったのか、男はセンターマイクに向かったままの体勢で固まって、キョトンとしている。
おそらく生徒たちのほとんどはこのとき、全く別のことに驚いていたのであった。
「え……エアトラだ……」
口火を切ったのは増田拓海。目の前の光景が信じられないといった様子で、ポカンと口を半開きにしたまま固まっている。
エアトラとは、お笑いコンビエアートラックスのこと。約二十年前に高校時代の先輩と後輩で結成されたコンビであり、背の低い方がボケ担当の岡野隆史。髪が長めの優男がツッコミ担当の矢口浩之である。
今になってようやく分かった。先ほどの放送の声に聞き覚えがあったのは、スピーカーの向こうで話していたのが、実は普段テレビで観ている彼らだったからである。

「岡野さん、もうボクらのこと気付かれてまいましたよ。どないします?」
「バレてんならしゃーないやん。さっさと説明してまおうや」
大阪出身の二人だけあって、コンビ内での掛け合いは関西弁だ。
「皆さんもうご存じの通り、我々コンビの名前はエアートラックス。今回のプログラムでは、担当補佐官を勤めさせていただくことになりました。よろしくお願いします」
寄席に立ったときの挨拶のように、二人はきれいに揃ってセンターマイクの前で礼をする。
それを見ていた生徒達は、これまた予想外のことに、ただただ驚くばかりであった。とくにエアートラックスのラジオの葉書職人をしている拓海は、憧れていた芸人たち本人が目の前にいるにも関わらず、喜ぶ様子も無く、衝撃のあまりか言葉を失ってしまっていた。
今やテレビの人気タレントである彼らが、なぜプログラムの担当補佐をすることになったのだろうか。少し前に選挙のテレビCMにイメージキャラクターとして出演していたことがあったので、その関係なのかもしれない。
「岡野さん、僕らの紹介もええですけど、ゲストチャレンジャーのことも早よぉ話さなあかんのちゃいますか?」
「おお、せやな。三人ともずっと待っとって暇してたやろうし」
こそこそと二人で打ち合わせをしてから、岡野は転校生達に視線を向けた。
「オッ、僕タチノコトヲ紹介シテクレルノ?」
一度外れたスポットライトが再び自分達に向き、辻斬り狐が機嫌良さそうにテーブルの上から飛び降りた。
「プログラムのルール説明をする前に、今回のプログラムに特別参加することになった転校生の方たちを紹介したいと思います。少しの間ですが、今日から皆さんと共に過ごすことになるクラスメートですので、暖かく迎えてあげてくださいね。それではまず一人目……、男子二十五番、辻斬り狐君」
「ハイ、ハイ、ハーイ!」
岡野に紹介されると、辻斬り狐はテンション高く跳びはねながら手を挙げた。
「えー、次はその隣にいる、女子二十五番、山田花子君」
続いて、包帯の女は表情を変えずに、目線だけを動かしてこちらを一瞥する。体格は普通なのに、妙な威圧感があった。
「そして最後に、男子二十六番、鳴神空也君」
顔に傷のある男は、自分のことが紹介されていても、全く反応を見せなかった。
このようにして、転校生三人の紹介は淡白に終了した。
辻斬り狐は当然として、山田花子という名前もおそらく偽名であろう、と秀之は思った。ありきたり過ぎる名前で、いかにも適当に考えて名乗っているような印象を受ける。それに、女の派手な出で立ちに対して、その単純で古風な名前はあまりにミスマッチしているようにも感じたのだった。
鳴神空也については、本名なのか偽名なのか分からない。少し変わった名前だが、前者二人のようなあからさまな、取ってつけた感じは無いように思った。
「急に三人もお友達が増えてしまいましたが、皆さん、仲良くしてあげてくださいね」
三年三組メンバーは誰も、岡野の言葉に反応しない。言いたいことはいくらでもあるだろうが、兵士達の重圧に押し負けて、誰も立ち上がれないのであった。
聞きたいことは、秀之にも沢山あった。
転校生とはいったい何なのか。
どういう経緯でこのプログラムに参加することになったというのか。
政府に無理矢理連れてこられたのか、それとも本人達の意志なのか。
自分達がプログラムに選ばれてしまったということ自体、夢ではないかと未だに疑っている中、色んな疑問が次々と沸いてきて、頭の中がパンクしてしまいそうであった。
「あの……、ちょっとよろしいでしょうか?」
場が一時の静まりをみせたとき、クラス担任の笹野真紀子が恐る恐る手を挙げた。まるで教師に質問をする生徒のよう。
「はい、笹野先生、なんでしょう」
いつもテレビでバラエティ番組を仕切っているときの感じで、矢口が笹野先生に応じる。
「なんとかならないでしょうか? この子たち……このクラスの皆が殺し合うなんて、そんな残酷なこと……、なんとか見逃しては……」
声が震えて言葉が途切れ途切れになる。しかし、発言権を与えられたとはいえ、無数の銃口が注目している中で、彼女ははっきりとプログラムに反対する意志を見せた。その勇気たるや尋常なものでないと秀之だって分かる。
「笹野先生……」
どこからともなく、生徒の泣き声が聞こえてきた。
思えば、笹野先生はいつもこのクラスの生徒たちの味方になってくれていた。成績が悪くて進学するのは難しいという生徒や、他校の生徒に対して暴力沙汰の事件を起こした者など、問題に直面した教え子がいれば、どんな逆境に立たされていても助けてくれた。
独自の捻くれ方をしている秀之ですら思う。彼女こそ最高の教師――、彼女以外に担任になってくれて良かったと思える先生はいない、と。
「先生、優しいですね。僕、泣いてしまいそうですわ――」
岡野は別に泣いてはいなかったが、自ら腕で目元を拭うような仕草をした。それにつられたわけではないが、生徒達の中からも、啜り泣く声や嗚咽が漏れ始めた。死にたくない、という強い思いに、笹野先生から注がれる多大な愛情への感動が重なり、感情の高ぶりが抑えられないレベルに達しているのか。
「……先生。先生!」
笹野先生の訴えを一番近くで聞いていた小栗佳織が、力無く床に膝をついた状態で、顔をくしゃくしゃにしている。
笹野先生はもともと生徒達から人気のある教師だったが、中でもとくに慕ってきているのが、実は佳織であった。世代の違いはありつつも、性格的に距離が近くて、相性が良いように見えた。思えば、笹野先生の結婚が決まったときに、一緒に喜んで一番祝福していたのは佳織だった。
「どないする? 矢口、この子ら見逃してやれんやろか?」
「いやいや、岡野さん、いくらなんでもそれはあきませんよ」
「でも先生凄く良い人やん。俺、ちょっと感動してもうてん」
いくら他人の心情を読み取る力に長けている秀之であっても、初めて会って間もない人間の言動が本心か演技かなんて、さすがに分析できない。しかし、プログラム担当補佐官であるはずの岡野は確かに、こちら側を同情しているかのような発言をした。
思ってもいなかった展開に、この場の張り詰めた緊張が僅かに緩んだように感じた。中には、助かるかも、と本気で期待した者もいたかもしれない。
「あきませんよ、岡野さん。だって、江口先生がもうおかんむりですもん」
言いながら、矢口が急に慌てて、部屋の隅へと飛び退いた。
彼の言葉の後半は、ほとんどの生徒に聞こえていなかっただろう。近い距離から耳をつんざくような火薬の破裂音が響き、他の全ての音という音が遮断されたのだ。
笹野先生のすぐ傍を何かが掠め、白い壁に指一本は入りそうな穴が一瞬にして開いた。
銃だ。
秀之が直感すると、エアートラックスの二人が入ってきた入口から、今度は眼鏡をかけた白衣の男が現れた。医者を思わせる風貌のその男は、四十代くらいの痩せ型で、右手に銃を握っている。そこからはまだ白煙が上がっており、さっき発砲したのは彼に間違いない。
こいつは誰だ?
多分全員がそう思っただろう。

「あ……危なー。噂に聞く通りの銃の腕前やわー」
矢口が冷や汗を流しながら、銃弾で穴が開いた壁を見る。先ほど後ろに飛び退いていなければ、銃弾は矢口に当たっていたかもしれなかった。
「銃なんて適当に何発か撃てばいずれ命中しますし、腕前なんて関係ない」
ボソボソと喋る白衣の男。カツカツと、硬い革靴の音を鳴らしながら歩き、言葉の通りに、銃を適当に数回発砲した。そして、そのうち一発が笹野先生の眉間を捉えた。
それはあまりにあっさりとし過ぎた幕切れだった。
笹野先生は血液と、脳なのか何なのかよく分からないものの欠片を周囲に振り撒きながら、スケートのジャンプのように空中で数回まわり、食堂の冷たい床の上に崩れ落ちた。
「ひっ!」
それを目の前で見ていた佳織が、短く悲鳴を上げながら、ほんの少し後ろに飛び退いた。
笹野先生の頭部を中心に、赤い血溜りが発生し、それがみるみるうちに拡大していく。
信じられないが、間違いなく、彼女はもう生きてはいない。
目の前で、人が人によって死に至らしめられるところを見てしまった。
それは物心ついてから初めて目にした光景であり、ショックがあまりに大きすぎた。
小さい頃から育清園の尾藤園長に言い聞かされてきた、人が人を殺してはいけない、という至極当たり前の常識が、一気に崩れ落ちていくのを感じた。
「嫌ぁぁぁぁぁぁっ!」
「笹野先生! 笹野先生!」
食堂はすぐに大勢の悲鳴に支配された。
生徒達は先生の遺体に駆け寄ったり、その場で崩れ落ちたり、呆然と立ち尽くしていたり、様々。
そんな中で何事も無かったかのように、センターマイクの方へと向かう白衣の男を、岡野が紹介する。
「えー、お仕事がお忙しかったようで遅れてしまいましたが、この方が、今回のプログラムを担当されます、江口恭一先生です」
しかしこの混乱の中、そんな話なんて誰も聞いていない。
「ヘケケケケケケケケケケケッ! 早クモ始マッタ、始マッタ! イイゾ、モット死ネ死ネ死ネ死ネ死ネ死ネ死ネ死ネーッ!」
辻斬り狐が大手を振りながら飛び跳ね、興奮した声を張り上げる。
全て夢であって欲しい。
秀之は自分の頬をつねるというベタなことをしてみたが、残念なことにはっきりと痛みを感じてしまった。
 笹野真紀子(三年三組担任) - 死亡 笹野真紀子(三年三組担任) - 死亡
【残り五十一人】
|
