タラップを登りきり広いデッキに足を着けると、波の揺れが直接全身に伝わって、大海の偉大さ、雄大さに、一瞬にして包み込まれてしまうような不思議な感覚に陥った。
遠くまで一直線に広がる青々とした世界の上では、身に受ける風がとても爽やかに感じる。六月のじっとりとした気候も一瞬忘れてしまうようだった。
そろそろ衣替えの時期ということもあって、デッキに一度集められた生徒達の制服の着こなし方は様々。過半数の生徒がブレザーを着てネクタイをしっかり締めている中、腕まくりしている者や、ワイシャツの胸をはだけている者などが、ほんの一部紛れているのが見られる。
目的地に着くまでの船内での立ち振る舞い方について説明している笹野先生の隣で、学級委員の須王望が、脱いだブレザーを腰に巻くなど制服を着崩したラフな格好をしている。“動の姫”は見た目からして活発な印象だ。
対照的に、デッキに体操座りして笹野先生の説明に耳を傾けている“静の姫”こと千銅亜里沙は、これまたきっちりと制服を正しく着こなしている。ブレザーのボタンは全て留め、胸元のリボンは紐の長さが左右全く同じになるよう結ばれている。
本当に不思議なほど、何もかもが正反対な二人である。どちらかが相手のことを意識しているのではないか、と思わずにはいられないほどだ。
「それでは、船内での諸注意について説明します」
デッキで体操座りして聞いている生徒達に、笹野先生はよく通る声をさらに張り上げる。
「島に着くまでは基本的に自由行動。デッキにいても船内に入ってみてもかまいません。とはいえ、今回はあくまでも島に渡るためだけにこの船に乗っていますので、客室などほとんどの部屋が封鎖されていますが」
「じゃあ先生。逆に入れる部屋ってのはどこなんですか?」
市川啓子(女子二番)が座ったまま手を挙げた。
「えーと、そこの扉から入ってすぐのロビーと、階段を上がった先にある展望室……。この二つだけね」
笹野先生はポケットから取り出した船のパンフレットに目を走らせながら、生徒達に分かりやすいように、入り口の扉と階段を指差しながら、短く簡潔に説明してくれた。
秀之は改めてこの船――サンセット号の姿を見渡した。
昔、育清園の面々で江ノ島の観光遊覧船に乗ったことがあるが、それと比べてもやはりかなり大きい。大型豪華客船というわけではないにしろ、たかが五十人にも満たない人数を乗せて動いてもらうには、あまりに申し訳なく思ってしまう。
デッキからは船の縁に沿って、船内への入り口に向かって甲板が延びており、途中、なにやら大型の機械らしきものにシートがかかっている。隙間なく覆われているため中身は全く見えないが、何か大事な機材なのだろうか。
「そろそろ出航するみたいよ」
笹野先生が言ったのとほぼ同時に、サンセット号はその大きな船体を一度揺らした。近い距離からけたたましく汽笛が鳴り、秀之は驚きながら耳を塞ぐ。
興奮した生徒達の多くが、縁の方へと駆け出して、船が港から離れていく様子を、柵を掴みながら眺めだす。また、一部の生徒は先ほど笹野先生の説明にあった、展望室へと走っていく。
船は瞬く間に陸から離れていき、すぐに広い海の中で孤立した。
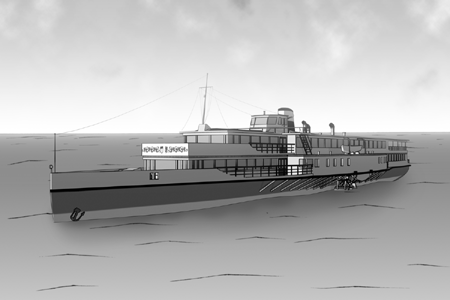
海面を眺めていると、照り返してくる陽光がキラキラと煌いてとても眩しい。その輝きは、まるでスパンコールを散りばめたドレスのようで、これから始まる合宿が楽しいものになることを、予感させているように思えた。
「うわー。すっごい気持ちいい」
船首から身を乗り出しつつ、森下藍子が大手を広げて伸びをしている。彼女の黒髪が、優しく吹く風を受けて柔らかそうになびく。
こうして見ていると、本当にただの無邪気な少女だ。秀之は、自分がなぜ彼女のことをここまで警戒しているのか、ふいに不思議に思ってしまった。
いつも感じている、正体不明の不気味さ。いったいそれは何なのだろうか。
精神的に不安定さは見られないし、行動や言動に暴力的なところも一切ない。なのに、本当にこうも距離感を保つ必要があるのか。
そこまで考えて、秀之は、駄目だ駄目だ、と頭を振った。
不確かな判断で、不用意に近づいては危険なのだ。屈強に見える堤防だって、いざ近づいてみたら崩壊する可能性だってある。それに、彼女は間違いなく警戒レベルの人間だ。絶対の自信がある自らの目測に間違いがあることが証明されない以上、基本方針をたやすく曲げるわけにはいかない。
それが、この闇にまみれた世界の中で生き抜くすべ。
いつしか秀之達が船に乗り込んだ埠頭は、遠くの方で霞がかって見える程度になっていた。近くに陸地は一切見えず、ただ青く壮大な世界が地平線に向かって広がるのみである。
「航路が若干、東寄りか……」
注意レベルの新谷明斗が、秀之のすぐ傍で海を眺めながらつぶやく。
彼はスライド式の携帯電話を開いて手に持っていた。どうやってか分からないが、それで方位を把握しているようである。携帯電話に方位磁石の機能でも付いているのであろうか。
なぜだか明斗の様子が少しおかしい。いつもにも増して表情が固く、それはまるで正体不明の不安に満ち溢れているように見える。楽しい林間学校という行事の最中だとは、とても思えない。
そして何か気になったことがあるのか、甲板の上を船尾へ向かって歩いていった。同じグループの秀之に一言も告げずに、だ。
出た。彼の隠し事をする癖。
もちろん、まとまっていない話を、わざわざ他人に告げる必要なんて一切ない。しかし、何か不安に思うことがあるのであれば、とりあえず近くの人間に相談してほしいものである。
一応注意して観察していると、明斗は甲板上のシートがかかった機材らしき物の前で立ち止まり、腕組みして眺めだした。クラスのほとんどが海上へと目を向けている中、ある意味異様な光景だったのかもしれない。
『えー、星矢中学校の皆さん』
それは明斗がシートをめくって中を覗いたのと同時のことだった。船のそこかしこに設置されているスピーカーから男の声が聞こえ、皆の注意を一斉に集めた。
『突然申し訳ありませんが、ちょっとした報告事項がございます。食堂を解放しましたので、お手数ですが皆さん一度集まってください。食堂はロビーから廊下を歩いて左側にございます』
突然の放送。クラスの誰のものでもない声であるのは確かである。しかし、秀之は全く知らない人間の声でもないように感じた。どこかで聞いたことがある気がする。
「いったい何があったんだろうね」
藍子が不思議そうに首を傾けながら隣に並ぼうとしてきたので、秀之は食堂へと逃れるように先に歩き出し、さりげに距離を保った。
同じく、何事かと話し合いながら歩くクラスメート達の中に、神妙な面持ちをした明斗が混ざっている。
秀之は直感した。
彼は甲板のシートの下で何かを見た。そして、この不思議な状況に対して、なにがしらの不安を覚えている。
今すぐにでも彼の元に駆けつけて、何を見たのか聞き出したい。しかし、狭い通路を五十人近くが歩く中、明斗はかなり前のほうを進んでいて、人ごみを掻き分けながらでは食堂に着くまでに追いつけそうにはない。
「食堂って、何か美味しいものでもサプライズで用意されていたりするのかな?」
痩せの大食いで知られる松永観月(女子十七番)が、能天気に友達とはしゃいでいる。
今の状況にマイナスの事態を想像しているのは、どうやら秀之と明斗くらいのようだった。そりゃあそうだ。みんな林間学校という在学中の三年間に一度きりの行事に浮かれているのだ。むしろこんな楽しい空気の中で神経を研ぎ澄ませているほうが異常なのである。
クラスの先頭を歩いていた柿内日向(女子四番)が、仲良しの津田茜(女子十番)や出町雅巳(女子十一番)とキャッキャと騒ぎながら、食堂の中に入っていくのが見えた。
「えっ……だ、誰?」
そしてすぐに日向の驚く声が廊下に響く。
ほどなくして食堂に着いた秀之も、一歩足を踏み入れた瞬間、声こそ出さなかったものの、部屋の中の光景に驚いて目を見開いてしまった。
そこには迷彩服を着てガスマスクを被った謎の男達が十数人、銃を構えて部屋の壁沿いに等間隔で立っていた。
「おらぁ! とっとと入れ!」
廊下のほうから怒鳴り声が聞こえたかと思いきや、いったいどこから沸いて出てきたのか、そちらからも迷彩服の男が数人現れ、最後尾を歩いていた瀬戸口信也(男子十三番)が押し込まれるようにして食堂の中に転がり込んできた。
――これはいったいどういうことだ?
この予想だにしなかった展開に、秀之の頭の中は混乱状態。ガスマスク越しに、殺意にぎらつく迷彩服の男達の目を見る限り、林間学校のレクリエーションでないのは確かだった。
「ちょっと、いったいなんなんですか?」
恐怖のあまり声を出せない生徒達に代わって笹野先生が、唇を震わせながらだが先頭に立った。
銃口が一斉に彼女に向くが、両手を広げて一切怯まない。
「ヘケケケケケケケケケッ! コノ状況デマダ分カラナイ?」
ふいに聞こえてきたのは、機械を介した無機質な笑い声。
怯える生徒達の目が、声のした方を向き、その不気味な姿を全員が捉えた。
そこに立っていたのは学ランを来た狐だった。正確には、狐らしき面を被った男。顔は見えないが、体格と雰囲気でおそらく自分達と同じくらいの歳であるのが分かる。
「て、てめぇ誰だ!」
不良グループメンバーの関口康輔(男子十二番)がずいずいと前に出て、今にも狐男に掴みかかりそうになっている。
狐男は再び笑い声を上げた。
「僕? 僕ノ名前ハ辻斬リ狐。今日カラ三日間、キミ達ト共ニ過ゴスコトニナル、クラスメートサ」
「辻斬り狐だと?」
「ソウ、ナカナカイカシタ名前デショウ?」
仮面の裏に変声機を仕込んでいるのだろう。その独特の声は、まるで自分達を馬鹿にしているようで、とても不愉快に感じる。いや、この状況を楽しんでいるような彼の様子からして、突然の事態に怯え震えている生徒達を、実際に馬鹿にしているに違いなかった。
「どういうことなんですか! 説明してください!」
クラスの女子で一番体が大きい西村歩美(女子十二番)が、半泣き状態になりながらヒステリックに声を張り上げた。
「察シガ悪イナァ。コノクラスハ馬鹿バッカリノ集マリナノカナ?」
ふぅ、という吐息が機械を介してロボットのうめき声のように聞こえた。
「僕ノ後ロニモ、二人イルノニ気ヅイテル?」
狐男――辻斬り狐が後方を指差す。そこには迷彩服の男達に紛れて、見覚えのない制服を着た男女が立っていたが、秀之は今の今までそれに全く気付いていなかった。
その二人の顔も、やはり見覚えがない。いったい誰なのだろうか。
「ヘケケッ! イイネ皆ノ怯エルソノ顔。ヨーシ、ジャア僕ガ特別ニ教エテアゲル」
辻斬り狐は靴のままテーブルの上に飛び乗り、星矢中学校三年三組の面々を見下ろしながら、大げさなほどのアクションで仰け反って両手を広げて見せた。

「僕タチ三人ハ、コノ三日間ダケ特別編入スル転校生――、君達ト一緒ニ、共和国戦闘実験、第六十八番プログラムヲ楽シム、プレイヤーダヨ」
そこまで言われて、秀之たちは初めて自分達の置かれている状況を理解した。
このクラスはプログラムに選ばれてしまったのだ、と。
【残り五十一人】 |
