沖田秀之は警戒心の高い少年だった。
出会う者全ての内面を疑い、自らになにがしらの障害を与えてるくる可能性があると判断した相手には、その危険度に応じて距離をはかるという徹底ぶり。
安全、注意、警戒、危険。彼は全ての人間をこの四つのレベルに分類する。
ほぼ無害であろう者は安全レベル。対称に、他の生命を脅かすような恐れがある存在が危険レベル。
秀之には、自らの目とあらゆる情報からそれらを正確に判断できる、卓越した観察力と思考力があった。何気ない会話の一部から、裏に潜む嘘やごまかしを見抜いて危険をいち早く察知することもできるのである。
彼がそこまで過敏とも言えるほどに繊細になってしまったのには、幼い頃に親に捨てられてしまったという背景があった。一番自分を愛して大切にしてくれるはずの両親という存在ですら、幼かった我が子に一生消えない傷を負わせたのだ。全く関わりの無い赤の他人なんて、いつどんな攻撃をしてくるか分かったものではない。
あらゆる災厄から逃れるためには、いかなる時も、出会う人間を常に疑うべきだ。
秀之が心に負っているダメージの大きさから考えると、彼の内にこういう猜疑心が芽生えてしまったのも、決して不思議なことではなかった。
月曜日の朝、千葉県私立星矢中学校三年三組の教室に着いてから、秀之は今日も周囲の動きに神経を尖らせていた。
ホームルームまで幾分時間があり、人がまばらな教室はそれなりに静かだ。クラスの半数がまだ姿を現していない。
窓の外遠くに見える校門を、今まさに沢山の生徒が通過している。
人が少ない今のうちに、と自らの机の中に仕掛けたトラップを確認した。
誰かが机の中に手を入れると、セロハンテープで真っ直ぐに張った糸が外れる、という実に単純な仕掛け。
とりあえず、先週下校してから秀之の机は誰にも触れられていないようで安心した。といっても、この仕掛けが作動していたのは、去年の二月十四日の一度きりなのだが。
無記名の薄気味悪いハート型チョコレートが入っていて、すぐに黒板の横のごみ箱に捨てたのを覚えている。もちろんその日がバレンタインデーだったと秀之は分かっていたし、チョコレートの意味も当然理解していたが、誰が作ったか分からないものを口に入れられるほど無防備な人間でなかった。
とりあえず、それ以来は至って平和だ。
鞄から取り出した教科書類を仕舞うのに邪魔なので、秀之はいつものように仕掛けを外そうとした。
「よう、おはよう」
ふいに後ろから投げかけられた陽気な声に飛び上がりそうになった。
「……なんだ清太郎か」
ゆっくり振り返って相手を確認し、迷惑そうな顔をする秀之。
高槻清太郎(男子十四番)は訳が分からないながらも、とりあえず自分が秀之を驚かしてしまったことは察したようで、ばつが悪そうに挨拶のときより声のトーンを落とした。
「昨日話してた本、持ってきたぜ」
彼が鞄から取り出したのは、表紙にくだらないデマや芸能記事のタイトルが踊るゴシップ雑誌だった。巻頭と袋とじにあるグラビアアイドルのビキニ姿に挟まれて、白黒の淡白なトピックスが異様な雰囲気を醸し出している。昨日ひかり莊にいたときに、この本に載っている一つの記事について話し合っていたのだ。
「ほら、ここ」
清太郎が指差して見せてきたページには『千葉工業科学大学テニスサークルOB失踪事件を追跡!!』と、でかでかと銘打たれていた。秀之たちがまだ小学生だった頃に起こった、二十七〜八歳の男女七人が一斉に姿を消したという不可思議な事件の記事だ。もう七年も前のことなので、最近ではテレビでもあまり報道されることが無くなったが、たまに思い出したかのように特集記事が組まれることが未だにある。
差し出された本を手にとって、流し気味に目を文字の列に沿って走らせた。
『元同級生達が証言! サークル内に潜んでいた深い確執』
『仲良しグループの裏の顔。一人の女を取り合った!?』
『多額の借金からの集団自決の可能性を本誌が独自調査!』
必要以上に想像力を書き立てるタイトルの後には、決定打の無い陳腐な文章が広いスペースを無意味に埋めている。読んでいるだけで溜息が出る。
「くっだらねー」
「だろ? もともと謎に包まれていた事件で、あれからとくに大きな進展があった訳でもないのにさ、無理にこんな記事にしちゃって……」
考えるだけ時間の無駄。そう思ってしまうのも仕方がない程の題材だ。しかし不思議なことに、そんなくだらない記事の話についてだって、清太郎となら話していて何故か楽しく思えてしまう。それはきっと、清太郎が心から信用できて、気兼ねなく接せれる相手だからであろう。
秀之の中で、清太郎は安全レベルと判定されている。初めて会ったときから今日に至るまで、ほぼ危険性を感じたことが無いからだ。
そう、清太郎は秀之が接近を許す、限られた人間のうちの一人。秀之が判定する、安全、注意、警戒、危険、の四つのレベルのうち、近寄れるのは妥協しても注意レベルの人間まで。警戒、危険、の人間に対しては、必要最低限の接触すら拒みたいところなのだ。
当然、三年生になってすぐに行われた席順決めでも、各自の希望を総合して並びを決めるというルールの下で行われたのをいいことに、なるべく警戒レベル以上の人間が周囲にいない位置に入り込めるよう努めた。
だから今、秀之が自分の席から周囲を見渡しても、近くには注意レベル以下の人間しかあまり見られない。
後ろの席の清太郎、左の席の浜田智史(男子十八番)、右の席の吉野梓(女子二十三番)、はいずれも安全レベル。
前に座る西村歩美(女子十二番)は精神的に脆く、些細なことで泣き出したりして周囲の人間を困らせることが多いが、所詮は注意レベル。
唯一、歩美のさらに前という比較的近い位置に、警戒レベルの足立宏(男子一番)が座っていることは心配だが、鬱憤を内に溜め込んで限界に達した時に一気に爆発する、という彼の性質は分かっているので対処のしようはある。
秀之にとって最も厄介なのは、警戒レベル以上でありながらも、その性質がイマイチ判明していないような相手だ。防御対策を立てられないからである
「なあ。またあいつ、こっちを見てるぞ」
何かに気づいた清太郎が肩を叩いてきた。
「あぁ?」
教室の中心に目を向けると、それまでこっちを見ていたらしい森下藍子(女子二十番)が、慌てて視線を窓の方へと逸らせた。
「なんなんだ、あいつ」
「さぁね」
と藍子の話はさっさと打ち切る。
彼女こそ、性質が分からない警戒レベルという、もっとも厄介な人種であった。
藍子を見ていると、秀之の中でけたたましく危険信号が鳴り響く。しかしいくら探っても何が危険なのか見えてこない。その正体不明さがかなり不気味だった。だから近寄らないし、話しかけられてもさっさと切り上げてその場を離れるようにする。
女の子に対して酷い対応だと自分でも思うが、身を守るためには仕方が無い。
藍子から外した視線を窓の方に向けると、教室の隅の席で本を読んでいる新谷明斗(男子十番)の姿が目に入ってきた。
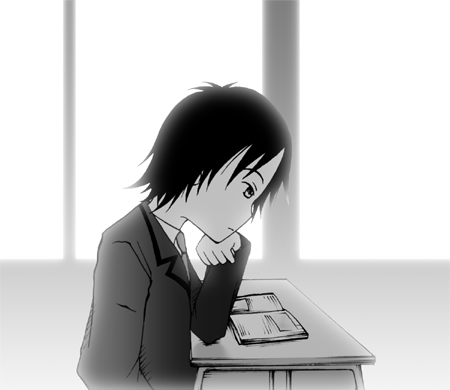
明斗はよく本を読んでいる姿を見かけるが、広く浅く興味を持つという性質のせいか、読む本のジャンルが定まっておらず、ある日は料理のレシピ本、またある日は格闘技の入門書だったりする。ちなみに今日はファッション誌。高校生くらいのチャラいモデルがポーズをとっているスナップを、机に肘をつきながら無表情で眺めている。
彼の特筆すべき点といえば、隠し事が多い、ということであろう。以前、定期試験の範囲について教師が説明を誤っているのに彼一人だけが気づいたが、聞かれなかったから、という理由で他の誰にもそのことを教えなかった。直接他人を傷つけることはないが、間接的に迷惑な存在ともなり得るので注意レベルとしている。
ところで、今この教室には本を読んでいる人間が明斗の他にもう一人、教室の前のほうの席に座っている。こちらは安全レベルの鈴森義人(男子十一番)で、手話の本を真剣な眼差しでたどりながら、両手で次々と形を作っては試している。
義人は、クラスメートの橘冬花(女子九番)と交際しているのだが、冬花が難聴のため会話での交流が難しく、そのため手話で交流を深めようと日々慎ましい努力をしているのだった。
対する冬花も、本来は健常者のクラスで授業を受けるのは困難なはずなのだが、周囲の助けを受けつつ、彼女自身の努力もあって、皆と同じクラスで生活したいという思いを実現させることができていた。
冬花の努力で特に大きかったのは、中学の三年間で読唇術を覚えたということである。耳で言葉を理解することができなくても、相手の唇の動きで、ある程度は話している内容を判断できる。おかげで三年に入ったころには、授業において支障はほぼ無くなったようだった。
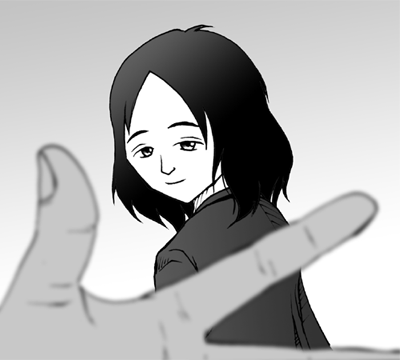
周囲に認知されているカップルはこのクラスに三組存在しているが、中でもこの二人は群を抜いて誠実で努力家なためか、最も応援したくなるカップルだと、皆が口を揃えて言う。
さて、朝のホームルームが始まるまでそろそろという頃になり、教室内にはクラスのほとんどが揃っている。つい先ほどは姿が見られなかった田神海斗(男子十六番)と根来晴美(女子十三番)のカップルも、今し方隣同士の席に揃ったようで、ゲラゲラと下品な笑い声を上げている。きっとまたろくでもない話で盛り上がっているのであろう。
教室の入り口付近の席では増田拓海(男子二十二番)が、サインペンを右手にゴソゴソと何かをしている。海斗と晴美の二人は、その後ろ姿に時折目を向け、ニヤついていた。
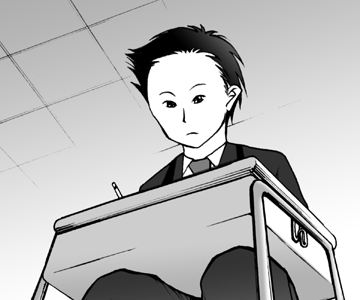
拓海はハガキを書いているようだった。人気お笑いコンビ、エアートラックスがパーソナリティを務めるラジオ番組、『エアトラのオールナイトレディオ』のヘビーリスナーである彼は、プロの作家をも唸らせるほどのネタを書くハガキ職人であるらしい。
今日もまたエアトラのラジオに投稿するためのネタハガキを書いているようだった。
「よう増田、何をしているんだ?」
拓海の背後に忍び寄った海斗が、机の上に並べられていたハガキの一枚を勝手に取り上げた。
「なんだ、また学校でネタハガキなんて陰気なもん書いてんのかよ」
「海斗! 海斗! ちょっとそれ読み上げてみてよ!」
キャハハ、と海斗の後ろで晴美が腹を抱えて笑っている。
海斗と晴美、それと今はここにいない関口康輔(男子十三番)の三人はよく一緒につるんでおり、拓海のような気弱なクラスメートを捕まえては、陰湿な嫌がらせを行うのである。
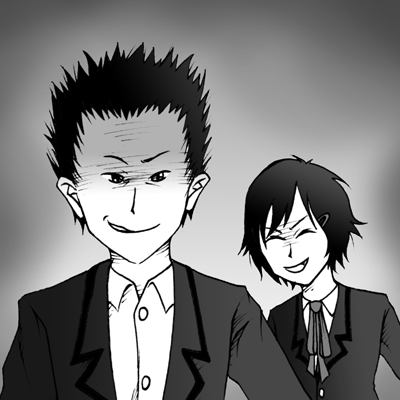
嫌がらせを企む海斗。
炊きつける晴美。
実行する康輔。
揃いも揃って警戒レベルの三人は、集まってしまうと非常に厄介な存在である。逆に、今回はまだ康輔がいないだけ嫌がらせもマシだったと言える。康輔までもが揃っていたら、ハガキを破り捨てるくらいのことはしていたかもしれない。
いずれにしろ、安全レベルである拓海が警戒レベルの人間達から一方的に攻撃されている様は、秀之が行っている危険度ごとの線引がいかに重要かを物語っていた。
「ちょっとアンタ達、いい加減にしなさいよ!」
威勢の良い声を挙げて、女子学級委員の須王望(女子六番)が拓海と海斗たちの間に割って入ってきた。いつまでも収まりそうに無い海斗たちの嫌がらせに見かねて、正義感の強い彼女は抑えが効かなくなったようだった。
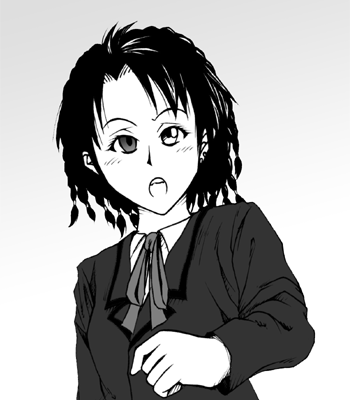
「なんだよ、望、何かあったのか?」
続いて、教室に入ったばかりで状況を飲み込めていない大瀧豪(男子三番)も駆け寄ってきた。
バレー部所属の爽やかスポーツマンであるが、大柄で顔が大きいせいか“ゴリラ系”と称されている豪と、真面目で人望が厚いうえに容姿端麗の望。一見ミスマッチにも思えるこの二人こそが、星矢中三年三組の三組目のカップルである。
「海斗くん達が、増田くんに嫌がらせしてたのよ」
「またかよ! いい加減にしろよな、お前ら!」
正義感の強い二人を相手に、さすがに海斗も一歩後ろに下がらずにはいられなかった。
実際に対面してみなければ分からないが、きっと力強い体躯の持ち主である豪と、威勢の良い望には、それなりに迫力があるのだろう。
海斗より後ろで煽っていた晴美はそれを感じていないのか、そそくさと退散しようとする海斗に、「なんで逃げるのよ?」と不思議そうに詰め寄っている。
秀之は、望のことを本当に凄いと思っていた。いくら安全レベルの人間であっても、普通ならば闇に覆われた部分がどこかに僅かには存在しているものなのだが、彼女はそれすらも感じさせない。これまでの人生の中で秀之が唯一会えた、百点満点の安全レベルの人間――完全なる善人であった。
加えて、容姿端麗で、正義感があって、そのうえ成績も良く、まさにこれ以上無い完璧な存在といえる。
今時の中学生らしいというか、多少服装の乱れや軽い言動があったりはするが、もはやその程度のことを咎める者などいない。教師達にも気に入られていて、服装や言動については軽く口頭で注意されることはあっても、声を荒げて怒られることなどまずありえない。
そんな望と対極に存在するのが、今、後ろの方の窓際の席でぼんやりと外を眺めている千銅亜里沙(女子八番)である。
秀之と同じ施設で生活している身でありながら、彼女と一緒に登校したことは一度もない。それは秀之のほうから避けているからであるが。
今日も二人は別々に学校へと向かい、各々の席に着いてからも全く口を交わしていない。
秀之が亜里沙を避けるのは、クラスでも数少ない危険レベルの人間だから。しかも、藍子と同じくその性質が全く分かっていないという、最も厄介な存在なのである。
亜里沙の何が望と対極しているのかというと、まずはもちろん危険度。方や安全レベルで、もう片方は危険レベル。
あと他に、活発な望と大人しい亜里沙、といった静と動の違いがある。
加えてさらに、亜里沙が西洋人を思わせる青い目を持っているのに対して、望は右目だけだが赤い瞳をしている。望は先天的に右の目の視力が悪く、それで片方だけ色の入ったコンタクトレンズを付けているとのことで、本当の目の色ではないのだが。
とにかく二人共が容姿端麗でありつつも、何から何まで正反対なため、クラスの一部からは「静の姫」「動の姫」と呼ばれ、密かに比べられていたりする。
クラスの皆にとってその比較は、さして大きな意味を持たない単なる戯れに近いことなのであろうが、その二人を並べられると亜里沙の危険性がより際立って見え、秀行はさらに距離をとってしまうのであった。
いずれにしろ、秀之はこれからもこの姿勢を崩すつもりはない。
関わることができる人間は間違いなく限られてしまうが、それがこの世界を生き抜いていくための、もっとも賢い判断であると心から信じている。
「はい! みんな席に着いて!」
ガラガラと音をたてて開いた扉から、このクラスの担任である笹野真紀子が入ってきて手をたたいた。
今年三十七歳のいわゆるアラフォーと呼ばれる世代だが、先月めでたく結婚して以来機嫌がよく、若い生徒にも負けない元気の良さを見せている。
「それではホームルームを始めます。先生からの話は……今日は特にありません!」
と、先生はウザイほどにテンション高く胸を張った。そして、とある生徒の方を見て手招きする。
「そのかわり、今日は学級委員から報告してもらうことがあります。須王さんと角下くん、発表大丈夫?」
「あ、俺一人で大丈夫ですよ」
立ち上がろうとしていた望を制し、男子学級委員の角下優也(男子六番)が先生の代わりに教壇の前に立った。
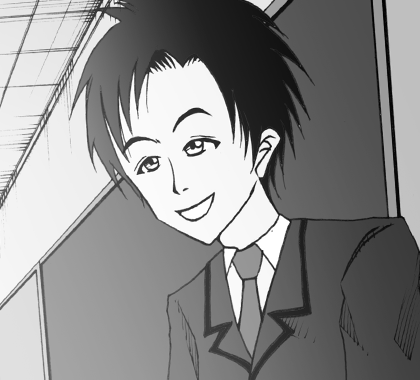
「えーとですね、毎年恒例になっている林間学校ですが、今年の行き先が決まりましたので発表します」
自然に触れながらの生活を体験する、という誘い文句を餌に、受験に向けた勉強会をちゃっかり間に挟んでくる、星矢中で三年生を対象に行われる恒例行事だ。なかなか楽しいイベントが盛り沢山で、環境変化のため勉強もはかどる、と意外にも良い評判を先輩たち聞いている。
「俺、蚊がたくさんいるところは苦手なんだけどー」
優也と仲良しの堀口夏生(男子二十二番)が茶々を入れると、その後ろから若林奈美(女子二十四番)が「じゃあお前は来んなよ」とチョップをかました。
「林間だから、蚊がいないところってのは難しいけど、今年はみんながびっくりするような行き先だと思います」
「えっ、どこどこー?」
たった今、夏生の頭をチョップしたばかりの右手を挙げて、奈美が元気に前に乗り出した。
「なんとですね、今年は船に乗って島に行きます」
紙切れを読みながらだが、さすが学級委員。ハキハキと話す。
おおーっ、とクラスの色んなところから歓声が上がった。この林間学校は大概が内地で行われていて、今回のように海の外に出ていくというケースは珍しいのだ。
今年の三年生でラッキーだった、と秀之もつい柄にもなく浮かれてしまった。
秀之の中に、張り詰めた緊張感が消えることはないが、このときはまだ平和だった。
数週間後に行われる林間学校。
まさかこの日、秀之にとっての人生最悪の事態が訪れるなんて、いくら周囲を警戒していても予測なんてできなかった。
|
