結局、あれから一度も寝付けないまま朝を迎えてしまった。布団の中からだるい身体を無理矢理起こす秀之の隣で、バッチリ寝て元気いっぱいの啓太が騒ぎながら部屋から飛び出していく。あまり寝ていないせいか、その声が頭の中でいつもより大きく響いた。
「おーい起きろ。朝だぞ」
対称的に意識をまだ眠りの中に置いたままでいる純平を、揺すり起こしてやる。こちらは低血圧なのか朝に弱い様子だ。
「ほらっ、顔洗ってこい」
洗面所に行くよう促してから、既に朝の用を全て済ませてしまっている秀之は食堂へと向かうことにした。
止まらない欠伸も、朝食を食べ終わる頃には収まっているかもしれない。
児童六人が対面して座れるサイズのテーブルが三つずつ並んだ長い島が、広い食堂の南北にそれぞれ伸びている。
一人一人の席はとくに決められていないので、日ごとに違う者と並んで食事することができる。
まだ食堂に人の姿はまばらだった。
秀之は何気なく、北側の角の席を陣取った。
食事の準備が整っていないような早い時間に来てしまったときは、園長や職員の人達を気遣って食器を運んだりと、微力ながら手伝うことにしているが、本日はテーブルの上で盛り付けが綺麗に済まされており、とくに手を出す必要は無さそうである。
今日の献立は、トーストにマーガリン、スクランブルエッグ、ヨーグルト、オレンジジュース。
どちらかといえば朝はご飯派の秀之だが、ここの朝食は三日に二度ほどの確率でパン食である。とはいえ、園長特製のスクランブルエッグはとろけるように柔らかく絶品だし、不満などは一切無い。
「みんな席についたか?」
児童たちのほとんどが食堂にやってきた頃になって、隣接する厨房から園長の尾藤泰彦がエプロンで手を拭きながら姿を覗かせた。
「全員いるならさっさと食事を始めよう。料理が冷めてしまうからな」
柔らかに微笑みながら人差し指で眼鏡を持ち上げて、彼が言った。
食事は皆が揃ってから始める、という取り決めがこの施設にはある。誰かが寝坊して姿を現さないという場合もあるが、そんなとき園長は決まって、問題の児童を起こしに行く。
そして今日も姿の無い者が一人。
「おや、珍しい。亜里沙がいないな」
一通り食堂を見回した後に園長は、意外だ、とでも言いたげな顔をした。
秀之は夜明け前に千銅亜里沙がグラウンドで佇んでいるのを目撃している。いったいどういう理由があって、あんな時間に外に出ていたのかは分からない。彼女はあの後に部屋に戻って、今もまだ眠り続けているのだろうか。知る限りでは亜里沙が寝坊したことは一度も無いのだが、彼女が夜中に起きているのを見た今回に限ってはありえる話であった。
「仕方が無い。私は様子を見に行くから、皆は先に頂いておきなさい」
と、尾藤園長が食堂から出て行こうとしたとき、話題の渦中の人物が申し訳なさそうに扉の後ろから顔を覗かせた。
「おはようございます。ごめんなさい、遅れてしまって」
亜里沙ははにかみながら頭を下げて入ってくる。
「どうした? 珍しく遅れて」
「同室の美香ちゃんが一度起こしてくれたんですけど……、二度寝しちゃいまして」
亜里沙は照れ臭そうに人差し指で頬をかく。
要するに、案の定寝坊したわけだ。そのわりには寝癖の一つも無く、きちんと身支度を整えているところがしっかり者の彼女らしいが。
「まあいい。みんな君を待っていたんだから、早く席に着きなさい」
尾藤園長が促すと、亜里沙は再度頭を下げながら、南側の角の席に腰を下ろした。秀之の対角に位置する離れた席だ。
「それでは遅れてしまったが、今度こそ全員揃ったので、いただきます」
園長に合わせ、全員の「いただきます」の声が重なる。
朝食が始まると、たちまち食堂は騒がしくなった。幼い子たちがパンを頬張りながら喋りだし、フォークが皿を叩く硬い音がそこいらじゅうから発される。
秀之はパンにマーガリンを塗りながら、最も離れた席にいる亜里沙をちらりと見た。
いつもとなんら変わった様子は無く、物静かに落ち着いた表情で黙々と、スクランブルエッグを口に運んでいる。
普段通りの彼女である。こちらのことを気にしている様子なんて全く見受けられない。
亜里沙の行動を怪しんできた秀之だったが、考え過ぎだったのだろうか。朝食をほぼ食べ終えた頃には、頭の中で渦巻かせていたものが無意味だったように思えてきた。
食堂の隅にある三十六インチのテレビは今朝のニュースを流しており、園長や職員の目を釘付けにさせている。秀之の目線もいつしか亜里沙からそちらへと移ってしまっていた。
結構大きな事件があったようだ。近年、政府関連の施設にテロをはじめとしたあらゆる攻撃をしかけ、世間にその名前を知られるようになった反政府抵抗組織「トロイ」の幹部と構成員数名が、警官隊と交戦したらしい。
「物騒ねぇ」
職員のおばちゃんがフルーツを口に運びながら呟いた。
最近こういったニュースは多い。国の仕組みについて博識でない秀之ですら、大東亜という国の歪みを感じてしまうほどに、あからさまに情勢が悪くなってきていた。
「――なお、この交戦で警官隊は、幹部の一人で指名手配中であった柊容疑者と、構成員数名を射殺した模様。詳しい情報が入り次第、追って報告させていただきます」
一連のニュースが終わるとコーナーが切り替わり、「今日の血液型占い」という明るいナレーションが流れ、可愛らしいキャラクターが画面の中で踊りだした。
「二十六歳か……。まだ若いのに、可哀相に……」
さっきのニュースで流れていた、射殺された組織の幹部のことを言っているようだ。テレビの画面から目を離した園長が少し悲しそうな顔をしていた。
「この国は本当にもう駄目なのかもしれないな」
その一言はとても印象的で、朝食の間、ずっと秀之の頭から離れなかった。
早い時間に目覚めてしまったせいか、部屋に戻ってからも身体がだるくて仕方が無かった。
今日は一日中動かずダラダラして過ごしたい、なんてぐうたらな思いに支配される。が、相変わらず幼いルームメイトたちは騒がしく、ここではなかなか落ち着いてくつろぐことが出来ない。
そんなとき、秀之には決まって行くところがあった。
誰にも邪魔されず、静かに独りで過ごすことができるプライベート空間が、この町に一箇所ある。
今日もかなり早い段階で、そこへ向かうことを決めていた。
Tシャツの上に薄手のジャケットを羽織って、広い玄関でスニーカーに足を入れる。
「休日の朝から何処に行くの?」
不意に近くから誰かの声が聞こえて、跳び上がりそうになった。べつにこっそりと悪いことをしていたわけでもないのに。
振り返った先にいたのは亜里沙だった。こちらを見る彼女の微笑みはとても柔らかい。そこにはあらゆる男子を虜にできそうなほどの美しさがあった。だが、その内にはやはり得体の知れぬ何かが隠されているように思える。秀之は彼女に対する警戒を解きはしなかった。
「別に」
と、そっけなくよそを向き、極力相手にしないようにして外へ出る。
「行ってらっしゃい」
後ろから投げ掛けられたその柔らかな言葉の中には、何やら深い感情が篭っているように感じた。
不思議な力に操られて再び振り返りそうになるが、慌てて頭の向きを前に正す。
これ以上目を合わせてしまうと、こちらの何もかもを見透かされてしまうような不安を覚えたのだった。
千銅亜里沙はやっぱり危険だ。
本能が打ち鳴らす警鐘を信じて、心の中にあるリストに「危険」と、さらに深く刻み込んだ。
遊具の合間を縫うようにグラウンドを抜けると、施設と外を隔てる黒い格子状の門が待ち構えている。かなり重さがあるため、女子供にとって一人で開くことは容易ではない。秀之が力いっぱい引くと、門の下の車輪とレールの間に細かい砂が挟まり、ギリギリと不快な音が鳴り響いた。
半分くらい開いたところで秀之は手を離した。車でも通らない限り、門を全開にする必要なんて無い。
コンクリートの門柱に埋め込まれたポストを一応確認するが、何も入っていなかったので、そのまま園を後にする。
向かう先は“ひかり荘”という空きアパート。五年前まで実際に人が住んでいたのだが、今はほとんどの扉と窓が封鎖されていて人の出入りは無い。秀之はかつて悪戯心でひかり荘への侵入を試み、釘の打ち付けが甘かった窓を見つけ、以来度々そこから出入りしている。そのことを知っている者はほとんどいない。
市街地の中に建つ二階建てのアパートを独り占めできるというのは、なかなか爽快なものだった。駅から徒歩で七分の距離だし、近くにスーパーやコンビニもあるので、建物そのものがもっと新しく綺麗であれば、本来はそれなりに人気があったはずという物件なのだ。秘密基地としては十分過ぎるほどの贅沢と言えよう。
ひかり荘が使われなくなったのは、家主であった老人が亡くなったためだと聞く。親族の誰かが管理を継ぐこともできたであろうが、老朽化した建物をこれ以上人に貸すにはリフォームが必要で、そのための膨大なコストを捻出できる人間が、元家主の周囲にはいなかったらしい。そのため、ちょうどアパートに住んでいる人もいなかったことだし、と建物ごと封鎖する決断が下されたのだそうだ。
秀之にとってはありがたい話であった。実際に住むとしたらあの老朽化したアパートよりもっと良い物件をいくらでも探すであろうが、秘密基地とするのであれば、河川敷の橋の下や、ブルーシートで作ったテントなんかより、格段に優雅といえた。
気がつくと秀之はひかり荘のすぐ近くにまで来ていた。あと角を一つ曲がれば、目的の建物がもう見える。
背の高い生け垣に沿って歩き、交差点で身体を左に向けようとする。すると、急に目の前の角から犬が飛び出してきた。
あまりに突然のことで、しかもとてつもなく近い距離であったため、秀之は跳び上がりそうなほど驚いてしまった。
その犬は何という犬種の掛け合わせなのかは分からないが、雑種で、野良ではないらしく、首から伸びたリードを目で追っていくと、その先には飼い主の姿があった。
目の前の交差点から人が急に現れたことに驚いたのは犬の飼い主も同じだったらしく、幅の狭い肩を上下させながら、目をビーダマみたいに丸くしてこちらを見ている。あと少しタイミングが違っていれば、出合い頭にぶつかっていたかもしれない。
「……なんだ、沖田君か。ビックリした」
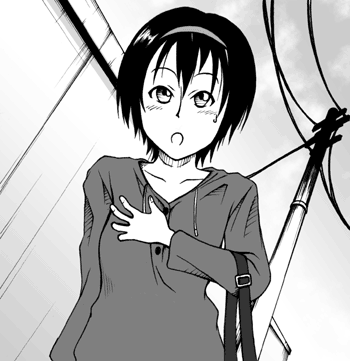
といってにわかに笑みを見せた彼女は知っている人物であった。同じクラスの森下藍子(女子二十番)といい、明るくて社交的な性格の持ち主だ。
だが秀之は彼女のことが苦手だった。それは千銅亜里沙に対する苦手意識にある意味近い。直接お互いが気まずくなるようなエピソードがあったわけでもなく、あらゆる角度から相手を見た結果、「警戒」すべき人物だと一方的に判断したにすぎない。そのために、社交的に歩み寄ってくる藍子と、反発する磁石のように一定以上の距離をとろうとする秀之、という二人の構図ができてしまったのであった。
「これからどこか行くの?」
ピンク色のカチューシャで彩ったショートボブの頭を横にやや傾けながら、藍子が丸い目をパチクリさせて聞いてきた。
秀之は無愛想に視線を外す。
「別に、なんでもない」
亜里沙のときと同様に言葉少なく、この場から逃れようとする。真っ直ぐ前だけを向き、脇をそのまま通過しようとした。
極力、藍子の方を見ないよう気をつけているつもりではあった。しかしそれでも、視界の端に彼女の姿は入り込んできた。
藍子は秀之に軽くあしらわれると、それ以上は何も言ってこなかった。ただ、すれ違いざまに俯いてしまった表情は、どこか曇っている気がした。
ひかり荘に着くと、秀之は針金で封鎖された門を乗り越えて、建物の裏手に回り込んだ。手入れされておらず、そこかしこで草が伸びている庭を大股で進み、茂みの陰になっている窓に手をかける。ここだけ釘の打ち付けが外れているのだが、元々建て付けが悪いのかすんなりとは開かない。力を入れて手を引くと、何回か引っ掛かるような感触があってから、なんとか開いた。
窓枠を乗り越えて中に忍び込む。換気がされていないので空間が湿った空気に支配されており、独特のかび臭さが鼻をついた。
一歩進む毎にギシギシと音をたてる廊下や階段は、たまに大きくしなる箇所がある。初めてここに入ったときはそれに焦らさせたりもしたが、今やもう慣れてしまった。
二階のとある部屋の前にたどり着くと、秀之はおもむろに扉を開いて中に入った。明らかにここだけ異質な空間であった。一見普通の六畳間の和室であるが、かび臭さや埃っぽさが、ここだけさほど感じられないのだ。生活感がどこかにまだ残っている。
それもそのはず。この部屋こそが秀之の秘密基地なのだから。
内側からの打ち付けを外してある窓を空け、まずは換気をする。湿気を帯びた室内の空気が新鮮な外の空気と入れ代わり、差し込む日光が緩やかに部屋を暖めてくれる。
頬をやさしく撫でる風を感じながら、秀之は畳の上にゴロンと寝転がった。
至福の時だ。何も難しいことを考えず、時の流れを気にせず、ただただぐうたらに過ごすこの時間。
誰にも邪魔されず、静かなところで、たった一人でいたい、などと度々思う秀之にとって、ここは楽園といってもいい場所であった。
寝転がって何かをするわけではない。眠くなったら寝て、そうでなくても、まどろみを帯びた意識の中で、薄ぼんやりと見える天井をひたすら眺め続けるのみ。
端から見ると、なんて無駄な時間の使い方だろうと思われそうだが、こういう心の底から休まる時間は大切だ、と秀之は思っていた。ときどきゴロンと寝返りをうつように転がって体勢を変えた。そして何気なく下に向いた方の耳を畳にあてる。
階下から何か音が聞こえた。ミシミシと、誰かが歩を進めて二階に登ってこようとしている。
秀之は慌てず、頭だけを僅かに持ち上げて、部屋の入口を黙って見つめ続けた。
やがて扉が音を立てながら開き、一人の男が姿を覗かせた。
「なんだ秀之、来てたのか」
と言って入ってきたのは同じクラスの高槻清太郎(男子十四番)であった。彼はこの部屋に先客がいることに気付いていなかった様子で、こちらの姿を確認した瞬間に少し驚いた顔をしていた。
「お先してまーす」
と言って秀之はまた頭を倒し、脱力しきった全身をまた転がせた。
清太郎はこの基地唯一の同居人である。彼もまた安息の地を求めてここに辿り着いた人間だった。塾通いの毎日に嫌気がさして、目に入ったこの建物に興味本位で入ってきて、そこで秀之とバッタリ会ってしまったのが同居の始まりであった。
最初は一人だけの空間に割り込んできた彼を邪魔に思ったりもしたが、必要以上にこちらに干渉してこないし、結構すぐに慣れてしまった。
まあ、秀之にとって害とならない「安全」な人間である、という前提を彼がクリアできていなかったら、そもそもこの同居を認めることは無かったであろうが。
「相変わらず、ここは静かでいいな」
と、清太郎は靴を脱いで畳みの上にあがってきた。いつものことなのだが、今日も靴下を穿いていない様子。こだわりとかではなく、彼は少し変わったところがあるのだ。いつもかけている眼鏡の度は合っていないし、ボサボサの髪を整えようともしない。
天才というのはいつの時代も変わり者だというが、彼もまたそうなのかもしれない。実際、勉強なんてしなくても、テストの成績はいつもトップクラスだし、秀之のような一般人とは何かが違うというのは確かだ。
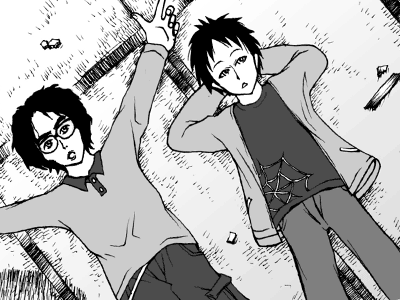
部屋の隅に置いてあった箒で秀之のすぐ隣を軽く掃いて、清太郎がそこに寝転がった。
「今日、塾は?」
「さぼった」
「ふーん……」
ぼんやりとしながら、たまにとりとめの無い会話を交わすのみ。
特別なことなんて何も無い。ただ静かで穏やかなこの時間が、これからもずっと、永遠に続いていけばいい。
秀之はそんなことを思いながら、ゆっくりと瞼を閉じた。
|
