千秋たちはまず出入り口から一番奥のベッドへと真緒を運んだ。窓際だと外から誰かに見られてしまうのではと一瞬思ったが、カーテンは閉められていたので気にする必要はなさそうだ。
「本当にかなりの血を流したようね。体温がかなり低下しているわ」
真緒の容態を見た風花は、これ以上の体温低下を防ぐために、乾いた服に着替えさせて暖かくしてあげるべきと提案した。それに従い、千秋は早速真緒の濡れた制服を上下とも脱がせ、先ほど受け取ったバスタオルの一枚で、念入りに身体を拭き始める。真っ白い肌をした彼女の弱々しき小さな身体は、戦いの場の中に存在するにはあまりに痛々しいように思えた。
真緒の全身を拭き終えたころ、風花がまた何かを投げてよこしてきた。全開ボタン止めの長袖のショートパジャマとパンツのセット。上下とも淡いピンク色をしたそれは、入院患者用として病院内に用意されていたものらしい。ミドルサイズと表示されていたので少し大きすぎるかと思っていたら、案の定、真緒が着るとぶかぶかだった。しかしまあ、これを着てどこかに出かけるというわけでもないし、このままでいても大丈夫であろう。
それにしても、いくら幼馴染同士とはいえ、真緒の生まれたままの姿なんて見たのは幼稚舎に通っていたころ以来だと思う。それでもここまでの作業を恥ずかしがらずに行えたのは、自分と彼女が同性であったから。この時ほど男に生まれなくて良かったと思ったことはないかもしれない。ちなみにこの病室内には「男」が一人だけいるが、ベッドの周りはカーテンでシャットダウンしていたので問題は無い。
「あとはちゃんと傷の手当てをし直した方が良さそうね。運良く銃弾は腕の中に残されてはいないようだけど、ろくな治療もしないで放っておけば、傷口が化膿して高熱を発し、最悪の場合そのまま壊疽する恐れもあるから」
いつの間に用意したのやら、ベッド脇の床頭台の上には何本かの薬ビンやらガーゼ、包帯などが並べられている。ここが病院であったことが幸いしたようだ。驚いたことに、どこかから持ってきたカセットコンロを使って湯沸しまで始めている。
「治療は私がするから、あなたは下手に手を出さないで」
言われ、千秋はしぶしぶながらここから先の処置は風花に委ねることにした。真緒の様子を見てすぐに必要な薬品と器具を判断し、かき集めてくる手際の良さから察するに、風花はもしかすると医療について少しは詳しいのかもしれない。それなら、銃で撃たれた時の治療方法なんて全く知らないという人間が手出しするよりも、彼女に任せておいたほうが安全だと判断したのだった。そして風花が真緒の治療に勤しんでいる合間、千秋は横で見ている以外にすることが無いので、これを機会に、真緒の腕から止血用の布を解いている風花のことをじっくり観察してみることにした。
蓮木風花。去年突然転校してきて、何故か被災者特別クラス入りした謎の少女。整った顔立ちと抜群のプロポーションを誇るスタイルの良さに、今まで何人の男達が魅了されてきたか計り知れない。ルックスで彼女に対抗できる可能性のある人物といえば、同じクラスの烏丸翠くらいだったが、そちらには風間雅晴という交際相手が一年のころから存在していたので、もはや男達の視線は独り占めといった状態だった。だが、幾度となく申し込まれる交際の全てを拒否し続けてきたがために、いつしか『百人斬り女』なんて呼ばれるようになっていた彼女。こうして同性の目から改めて見ても、姿形はその名に恥じぬほど美しい。パッチリとした目は少々つり上がり気味でもあるようだが、それを含めた顔のパーツ一つ一つの形と位置関係が絶妙なのである。見ているうちに気がついたのだが、顔全体に薄く化粧も施されているようで、中学生でありながら既に大人の女性の雰囲気を感じさせられる。
そんな彼女、実は成績もかなり優秀で、頭の良さは間違いなく学校全体でもトップレベル。神々の悪戯というものが本当にあるとするならば、風花という完璧超人がこの世に生まれたことこそが、それに当てはまると思えてならない。
千秋が風花を観察している間に、一連の処置はひとまず終了したらしい。薬品の染み込んだ綿球は屑篭の中に捨てられ、床頭台の上の銀のトレイにピンセットが置かれる。
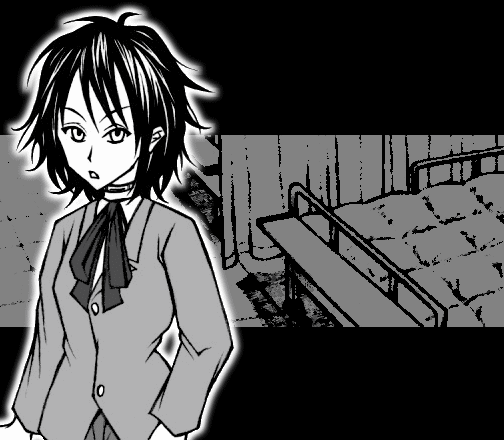
「あとは傷口を塞ぐだけなんだけど、やっぱり縫合したほうが良さそうね」
「縫合?」
床頭台の上に針付縫合糸らしき物があるのに気付いて驚いた。いくら医療知識に秀でていたとしても、まさか自分と同じ中学生に、人間の皮膚を縫い合わせるような技術までも備わっているとは思わなかったから。
この女、本当に何者なのだろうか。
「私だって実践したことは無いわよ。ただ知識を持っていることと、手先が器用ということに自信があるだけのこと」
千秋の考えていることを察したのか風花はそう言ったが、それにしたって一種の手術ともいえる縫合に堂々と手を出せるというだけで、全く別世界の人間であるのは明らかだ。
「縫合するってことは、麻酔もあなたが打つの?」
皮膚に針を通す際、どんなに上手くやっても患者は激痛を覚えることとなる。それを抑えるために使用されるのが麻酔。ふと思いついたことを聞いてみただけだったが、それに対する風花の返事は驚くべきものだった。
「残念ながら、プログラムが始まる以前に薬物の多くは島から持ち出されてしまったみたいで、特に麻酔なんて危険なものは全く残されていなかった」
「麻酔が無いって、それじゃあどうやって真緒の腕を縫うつもりなの?」
「そのままよ。麻酔無しで直接」
あまりに馬鹿げた返事に頭がくらくらした。
「そんなの出来るわけ無いでしょ! 考えてみてよ! 麻酔もしないで肌を直接縫うなんて、どれだけ痛いことなのか! 反対! 私は絶対に反対!」
真緒の身を案じての抗議のつもりだった。だけど風花は容赦なく千秋を睨みつけながら襟首を掴んで引き寄せて、潤いのあるサーモンピンクの唇を耳元へと近づけてきた。
「なに甘っちょろいこと言ってるの? こんなの野戦病院なんかじゃあごく当たり前のことよ。そう、ここは戦場なの。平和な町の診療所みたいな待遇を受けられるかと思ったら大間違い。雑念は振り払って、生きるか死ぬか、ただそれだけを考えなさい」
そう言ってから風花は襟首を離して開放してくれた。耳元で囁かれたどすのきいた刺々しい声に圧倒されてしまい、千秋にはもうこれ以上反抗する気なんて起こらない。
「心配しないで。実行するかどうか決める権限なんて私には無いから。決めるのは患者ご本人。これなら文句ないでしょ? 春日千秋さん」
もしかすると、蓮木風花という一人の少女を何かに喩えるとするならば、薔薇という植物が最も適切かもしれない。多くの人々を魅了させるほどの美しき花を咲かせるが、近づく者には茎に生えた鋭い棘で手痛い思いをさせるのである。過去に交際希望者全てを拒絶してきたことや、ほとんど初めて接した千秋にきつい言葉を浴びせたことなど、考えれば考えるほどぴったりだ。
「今までの話聞いていたでしょう。このまま死ぬか、一時の痛みに耐えて生き続けるか。羽村真緒さん、どうするかはあなたが選びなさい」
かつてここまで究極の選択はあっただろうか。生きるか死ぬかなんてどう考えても風花が誇張したオーバーな話に過ぎないだろうが、半袖パジャマから覗く肩口を白い布で強く結ばれた状態のまま、真緒は明らかに表情を強張らせていた。少しの間沈黙が辺りを包み、真緒が「お願いします」と言って傷ついた腕を前に出したのは、じつに三十秒も経ってからのことだった。
「患者様からのご希望よ。これなら文句ないでしょ?」
僅かに目を細めて勝ち誇るような顔をしてから、風花は手術用のゴム手袋をはめ、ついに縫合糸を手に取った。先端のカーブのかかった針を、いきなり深い方の傷口の端に押し付け、「痛いけど我慢しなさい」なんて真緒に言ってから、ついにナイロン製の糸を皮膚に通し始めた。もちろんその作業は一度だけでは終わらない。傷が大きければ大きいほど縫う回数は増え、痛みに襲われる時間は長くなる。
真緒はぎゅっと目を閉じて、下唇を力いっぱい噛んで耐えようとしている。しかし激痛のあまり閉じられた瞼の間からは涙が溢れ出し、額からはじんわりと汗が滲み出す。
千秋は最後までその様子を見届けるつもりだったが、ほんの数秒で早くも耐えられなくなり、思わず目を逸らしてしまった。傷口を縫うという痛々しい作業に恐怖を覚えたからからというよりも、辛い試練に苦しんでいる幼馴染の姿を見ることに辛さを感じたのだった。
たまらずカーテンで仕切られた一角から飛び出して思った。たぶん千秋の視線を感じなくなったことで、真緒の気も少しは楽になったのではないか、と。もしも自分が真緒の立場だったら、苦しんでいる姿を幼馴染に見せて心配させたくは無いので。
カーテンの外に出ると当然、残り五つのベッドが並ぶ病室の光景と、壁にもたれるようにして窓際に立つ圭吾の姿が目に入った。建物周囲の様子を気にしているようで、カーテンの端をめくって窓の外を眺めていたが、自分を見る視線に気がついたらしく千秋の方を振り向いた。
「何か用か?」
相変わらずの愛想の無い言い草。
「そんなに堂々と窓の外を見ていて大丈夫なの。誰かに見られるかもしれないよ」
心配していたことを正直に述べると、圭吾は気だるそうに窓際に置いてあった何かを手にとって弄り、傍らのベッドの上に放った。
「そいつを見てみろ」
言われるよりも先に、千秋はベッドシーツの上で一回バウンドしたその四角い物体を拾い上げていた。表面にいくつかのボタンとデジタル画面のような部分があったので、はじめは液晶小型テレビかと思ったが、どうやらそうではないらしい。
画面の中央部には赤いドットが四つ固まっており、そこから遥か離れたところに同じようなドットがバラバラになって点在している。
「これは何なの?」
「レーダーだよ。どれが誰なのかまでは分からないが、島内にいるプログラム参加者達の位置はそれで全て把握できる」
驚いた。まさかそんな便利なものまで支給されているとは思っていなかったから。
「えーと、ということは、この画面の中央に集まっている四つの点が私達で、そこから離れたところで光っているのが――」
「他のクラスメート達だ」
レーダーの表示からすると、千秋たちが潜むこの病院の付近には今のところ誰もいないらしい。だからこそ圭吾は堂々と窓の外を覗き込むことが出来たのであろう。
頭の中で宙ぶらりんのままだった謎の一つが解けた。
「分かった。これがあったから、廃ビルの建つエリアに七人の人間がいたことを、訪れる前から知っていたのね」
「そういうことだ」
「でも、それだけではまだ解決できないことがある」
「何だ?」
もちろん、このレーダーでは個々の点が誰を表しているのかまでは分からないはずだというのに、E−六エリアに磐田猛がいることを、圭吾があらかじめ知っていたという事だ。
「知っていたというよりも、予測していたと言った方が正しいだろう」
「どういうことよ?」
千秋が詰め寄ると圭吾は説明し始める。
「プログラムに巻き込まれて皆が疑心暗鬼に陥っている中、七人もの人間が集まるなんてそう簡単なことではない。それが成し遂げられた理由として考えられるのは、力の無い者同士が助けを求め合うようにして集まったか、あるいは大人数を率いられるほどの指導者としての資質を持ち備えている者がいるか、この二つしか考えられない。俺が思うに、このクラスで指導者として最も適任であるのは磐田猛。逆に彼以外の人間ではここまで大掛かりな集まりを築き上げるなんて難しい。だからこそ、この集団の中心には磐田がいる可能性が高いと睨んだ」
「比田くんがわざわざここに出向いた訳は?」
「簡単に言えば、能力値が高くて信用も出来る磐田を仲間に引き込みたかったから。何があったのかよく知らないが、七つあったはずのレーダーの反応が徐々に減り始めたので、急いで駆けつけたというわけだ。残念ながら手遅れで、磐田はもう殺されていたが」
復讐鬼へと成り果てた御影霞に。
「それじゃあ最後に、私達を助けてくれた理由は?」
「ただなんとなく。しいて言うなら、目の前で誰かに死なれては後味が悪くなるから」
猛に関する質問に比べて、最後の返答は端的ながら短かった。興味が無いという気持ちの現われだろうか。
しかし、結局圭吾が猛を信用していた理由は何なのだろうか。普段の生活態度を見ているだけでも猛は確かに信用するに値する人物であると判断できるかもしれないが、圭吾の場合はどうもそれだけではない気がする。
「終わったよ」
千秋の背後でカーテンが開き、そこから風花がゆっくりと姿を現した。その奥では腰から下を布団の中に埋めたまま上半身だけを起こし、涙にまみれた顔をタオルで拭く真緒がいる。
「驚いたわ。この子意外に忍耐力ある」
一度たりとも泣き言を漏らさなかった真緒の頭を、いいこいいこ、と撫でる風花。いつ間にやら姉貴分気取りか。
傷ついていたはずの腕を確認すると、確かに皮膚の表面に埋め込まれたばかりの黒い線が見える。あくまでも素人の目から見た感想だが、縫い目はきれいで、とても中学生が処置したものだとは思えない。本人は知識と器用さに自信があるだけだと言っていたが、それだけではここまで出来るはずが無い。きっと並外れた度胸をも持っているに違いない。
「それで、何の話をしていたの?」
これまで千秋と圭吾のやり取りに耳を傾けている場合でなかった風花が、二人の脇に立って尋ねてきた。そういえば、プログラムに巻き込まれてから今まで、こちらがどんな体験をしてきたのか聞きたいと、彼女は初めて会ったときに言っていた。そしてここに来るまで一切の無駄口を許してくれなかった圭吾にも、猛が死ぬことになった経緯も含め、まだほとんど何も話していない。
別に隠すようなことは無いが、全て思い出していてはきりがないので、自分自身で重要であると判断した事柄のみを抜粋して語る事にした。
プログラム開始直前のトラック内での出来事。千秋と猛が出会ったときのこと。新田慶介の死体発見から、廃ビルで七人が集合するまで。湯川利久の裏切り。御影霞の来襲。などなど。
「なるほどね。たしかに大人数で集まるのは心強いことだけど、今回に限ってはそれが裏目に出てしまったわけか」
仲間を集めすぎてしまったために、善人の皮をかぶった裏切り者の存在に気付かなかったことについて風花は言っているのだろう。
「許せないよ! 楽しみたいがためにクラスメートをあっさりと殺しちゃうなんて」
風花に命令されるようにしてベッドの上で横になっていた真緒が、悔しそうに歯を噛み締めている。千秋も全く同じ気持ちだった。
「本当に、湯川はそれだけで凶行に及んだと思うか?」
握り締めていた手にさらに力が入ろうとしたとき、圭吾が突然思いもよらぬことを呟いた。
「どういう意味?」
圭吾の口から発された言葉の意味がよく分からない。まさか、湯川が廃ビルのメンバー達を死に至らしめた理由が他にもあるとでも言うのだろうか。
「確証なんて無い。しかし、俺にはどうも奴の裏にはさらに何かが隠されているように思えてならない」
「そしてそれが彼を殺人に走らせることになったのかもしれない、と?」
「ああ」
「そう考える理由は」
問いかけると、圭吾は一息置いてから「勘だ」とだけ答えた。いくら利久と正面から対峙したことのある人物の言葉であっても、これでは信用できるはずもない。だがどうしたことか、千秋は一瞬とはいえ「そうかもしれない」なんて思ってしまった。その理由は自分でも分からない。
千秋が一通り話し終えた後、今度は圭吾と出会うまでの経緯を風花が話してくれた。
二人が鉢合わせたのはプログラムが始まってから二時間も経っていなかった頃らしく、とくにやり合うような素振りはどちらも見せなかったらしい。
「殺気が全く感じられなかったからな。一目見て相手に戦う気なんて無いと分かった」
そう話したのは圭吾。だが、相手がもしも湯川利久のような演技派だったとしても、彼は内に潜む殺気までも感じ取ることが出来るのだろうか。
ともかく、以来二人は成り行きで行動を共にすることになり、しばらくの間、この建物の中で過ごしていたのだそうだ。
「私が考えた案を実行するには、一人ではどうしても荷が重かったから、彼の力を借りることにしたのよ」
と風花。そうそう、圭吾がずっと言っていた『風花の発案』については、まだ全く話してもらっていない。
「蓮木さんが考えた案って、いったい何なの?」
このとき、千秋は興味津々ながらもまだ軽い気持ちだった。だからこそ、風花から返ってきた言葉にはより驚かされることとなってしまった。
彼女ははっきりと言った。私が考えたのはここから脱出するための計画、と。
【残り 十九人】 |
