怜二はもはや戦意を喪失していた。迫る龍輔に立ち向かえるだけの気力はもう残されておらず、身体は勝手に後退を始めてしまう。もちろん相手に対する怒りが失われてしまったわけではないが、大きく膨張した絶望という名の感情がそれを押し退けて、いつの間にか頭の中の大部分を占めていたのだった。
視界に写る龍輔の姿が大きくなるにつれて、怜二の中に根付いていた恐怖感の塊が、水を与えられた植物のように成長していき、その影響なのか、薬物投与で絶大なる力を得た強靭な足が一歩を踏み出すたびに、大地がぐらぐらと揺らされているような錯覚を感じた。
「おいおい、さっきまでの威勢はどうした? まさか逃げようってんじゃないだろうな? まあいい、好きにすればいいさ。俺はお前を逃がすつもりなど無いけどな」
恐れおののき後ずさる怜二の姿を見て、龍輔はたいそう愉快そうに言う。しかしそんな口ぶりとは裏腹に、充血した目には殺意が凄まじいほどに満ち溢れており、真正面に立っただけでも、ギリシャ神話のメデューサに睨まれるかの如く、身体が一瞬にして固まってしまいそうに思った。
怜二はもう分かっていた。単に身体能力に自信があるだけの凡人では、悪魔との契約で超人的力を手に入れたこの男から勝利をもぎ取るなど、ほぼ不可能であると。
逃げなければ! 委員長たちを殺し、さらには渉までもを傷つけた許し難き敵に背中を向けてしまうことは癪だけど、このまま俺までもが奴の思い通りにされてしまうわけにもいかない。
頭の中で考えがまとまった途端、怜二は動き出していた。相手と向き合っていた身体を後方へと翻し、この危険地帯から抜け出すことのみを考えて、ただひたすらに足を動かした。
どんな破壊力を持つ敵の攻撃にも真正面から立ち向かってきたサッカー部ゴールキーパーの土屋怜二にとって、初めての屈辱。逃げることの悔しさから、両手がわなわなと震えていた。
ちくしょう! まさかあんな男に背を向けることになるだなんて――いや、今はそんなことに悔しがっている場合ではない。生命の危機に立たされているのは俺だけじゃないんだ。渉だ。渉を連れて逃げるためにも、私情のみに捕らわれているわけにはいかない。もちろん、怪我人を連れての逃走は安易なことではないだろうが、見殺しにしてしまうくらいなら、自分なんて死んでしまったほうがマシだ。
「馬鹿が! 逃がすかよ!」
渉の元へと向かう怜二の姿を見て、龍輔もまたそれを追って走り出す。強靭な脚力で地面を蹴るたびに、硬く引き締まった重戦車のごとき肉体が高く跳躍する。二人の間に開いていた数メートルもの距離は、ぐんぐんと縮められていった。
押し潰されそうになるほどの強烈な圧力を背中に感じ、怜二は走りながら後方を振り返った。
鋭い牙を生やした口を大きく開く猛獣の姿が、もうすぐ側にまで迫っていた。
強靭な肉体から伸びた太い腕に首根っこを捕まれた怜二は、前に進もうとする身体の勢いを止めることができず、そのまま脇に立っていた太い木の幹に身体を打ちつけてしまう。その衝撃があまりにも大きすぎたためか、森林内の鬱蒼とした景色が視界の中で激しく揺らいだ。
「がはっ!」
うめき声を漏らしながら、その場に倒れ込む。
高笑う男の声が辺りにこだました。
「言っただろ、逃がさねぇって。無駄な足掻きをしたところで、お前がここで死ぬという運命は変えられやしねぇよ」
血管を浮き上がらせた不気味な顔をにやにやとさせながら、龍輔は悠々と近づいてくる。
再び立ち上がって逃げようとするにも、もはや相手との距離は縮まり過ぎている。走り出したところで今と同じように掴まってしまうのがオチだろう。
「さて、逃げ惑うお前の情けない姿もそろそろ見納めかな。まあとりあえず死ねや」
悔しそうに敵の姿を見上げる怜二の目の前で、血に塗れたファイティングナイフが振り上げられる。しかし絶体絶命な状態でありながらも、怜二はまだ諦めてはいなかった。
ポケットの中に手を突っ込んで、最後の一つとなった炸裂閃光弾を急いで取り出す。上手く相手の視聴覚を奪うことができれば、渉を連れてこの場から逃げ出すことも、まだ可能であると考えたのだった。しかし唯一の突破口かと思われたその策を実行するとしても、実際のところ生存の確率はほとんど無いに等しい。炸裂閃光弾が効果を発揮するのに要する時間は、着火から約三秒。つまり、急いで先端のピンを抜いたとしても、効果が発動された頃には、ナイフの刃が身体に突き立てられて、もう手遅れの状態になっているという可能性が極めて高いのだ。
しかし他の道が残されていない以上、引き下がるわけにはいかなかった。ナイフが振り下ろされるよりも先に、閃光弾のピンに人差し指を引っ掛けて、力にまかせて引き抜いた。だがやはりもう遅し。龍輔が握るファイティングナイフの先端は既に、怜二の胸元へと狙いを定めて、真っ直ぐ正確に向かってきている。
全てを諦めかけたそのとき、怜二の前に何かが飛びだしてきた。そして龍輔の前に立ちはだかったかと思いきや、振り下ろされたナイフの刃を、その身体で受け止めた。ボウガンの矢が脇腹に突き刺さったままの状態でありながらも、死に物狂いで走ってきて、怜二の盾となって代わりに刃を突き刺されたその男。紛れも無く武田渉だった。
「渉!」
胸部を深く刺されて後方へと倒れ込むその身体を受け止めると同時に、ピンの抜けた閃光弾を、ごく自然な動作で放り投げた。
「くそっ、この野郎! 邪魔しやがって!」
再びナイフが振り上げられた瞬間、ゆっくりと宙を漂っていた閃光弾が、凄まじき音と光を発しながら炸裂した。ピンが引き抜かれてから、ちょうど三秒が経過したのだった。
一瞬早く目を瞑り、前回の反省も踏まえて耳も両方共を押さえていたが、それでも距離が近すぎたためか、聴覚はかろうじて守られたものの、酷い耳鳴りを防止するには至らなかった。
「ぎゃああああああああ!」
予期せぬ敵の反撃に対応できなかった龍輔は、間近で炸裂した閃光弾の効果に視覚と聴覚の両方を奪われ、目が焼け付くような感覚に悶え苦しみ、頭を抱えてその場に倒れ込む。その隙に、怜二は切り裂かれた腕の痛みに耐えながら、渉を抱えて駆け出した。皆の敵を討とうなどといった考えはなく、とにかく渉を助けたいという思いのみで、頭の中はいっぱいだった。
「渉、お前、俺のために身代わりを――」
とても立ち上がれるとも思えないほどの重傷を負いながらも、自分を庇ってくれた仲間の体温を間近で感じていると、何とも言い表しようの無い感情がこみ上げてくる。
龍輔の姿が見えなくなるまで、怜二は渉の身体を抱えたまま、ただひたすらに走り続けた。
二人共のデイパックを置いてきてしまったが、そんなことはもうどうでもよかった。安全が確認できる所まで逃げ切って、早く応急処置をしなければ、などと考えていた。だが、ぐったりとして動かない渉の様子を不審に思って、顔をふと覗き込んだとき、頭の中に稲妻が走った。
渉の顔中に見覚えのある不吉な変化が起こっていた。いや顔だけではない。手も足も、少なくとも身体の露出している部分には全て、薄ぼんやりと紫色の斑模様が浮かび上がっていた。
まさか、さっき渉の脇腹に突き刺さった矢は――。
怜二は身が凍るような感覚に襲われた。
間違いなかった。これは毒の矢の餌食となった三上圭子の身体に起こっていたのと全く同じ現象。
「おい渉! しっかりしろ!」
怜二が必死に呼びかけるも、渉は瞳孔を拡大させたまま身動き一つしなかった。怜二には知る由も無いことだが、龍輔が振り下ろしたナイフの傷は心臓にまで達しており、つまり、渉は怜二を庇った直後にはもう死んでいたのだった。
怜二は歩を止めて、命を助けてくれた恩人の身体を地面の上にゆっくりと下ろした。
お前、あの毒の苦しみ襲われながらも、無理に身体を動かして、俺を庇ってくれたんだな……。
斑の模様に支配され、本来の面影をも感じさせぬほどに変貌してしまった渉の顔を見下ろしていると、いつまでも溢れ出す涙が止まりそうになかった。
『命を助けるために手を尽くそうとしたことが、逆に罪になることだってあると思うんだ』
ふと渉のそんな言葉を思い出した。そして怜二は決心した。
「渉、俺は決めたよ。お前が言ったあの言葉は正しかったのかどうか、未だによく分からない。だからその答えを見つけるために、俺はまだ生き続ける。そして、俺達が助け出した“あの人”にもう一度会って、二年前の行いは正しかったのかどうか、全て突き止めてみせる」
渉の側に屈み込み、力なく指を開いたまま動かなくなってしまった手を握り締め、強く誓った。
渉が握り返してくることはなかったが、その手はまだ微かな温かみを帯びていた。
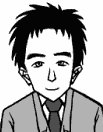 武田渉(男子十一番)――『死亡』 武田渉(男子十一番)――『死亡』
【残り 二十一人】 |
