身を翻す暇もなかった。木漏れ日を浴びて鈍い光を放つ銀色の矢は、百キロ近い速度で空を切り裂きながら向かってきて、一瞬にして渉の脇腹に深く突き刺さった。
「あああああああああ!」
怜二の腰を強く抱きしめていた腕からふいに力が抜けて、渉は地面へとずり落ち、負傷箇所を押さえながら声を上げた。
傷口を押さえる手の指の隙間から染み出した血液が、矢を伝って地面に滴っている。あの様子では、いくつかの臓器が傷つけられていてもおかしくない。
怜二は渉へと向けていた視線をとっさに龍輔の方へと移し、相手の顔をキッと睨みつける。
「黒河、なんてことをしやがる!」
だが怒号を浴びせられながらも、龍輔は身じろぎ一つすることなく、表情から余裕の笑みが消えることはなかった。
黒河龍輔。六条寛吉や田村由唯らに対して執拗なイジメを繰り返すなど、クラスの秩序を乱し続け、また、他校の不良たちとつるんで街に繰り出しては様々な悪行に手を染めていたなど、まさに悪の根源とでも言うべき存在。プログラムの最中に遭遇したくない人物の一人であったが、まさかこんなタイミングで出くわしてしまうとは――。
「へっ、誰かと思えば土屋じゃねぇか。威勢の良さは相変わらずだな」
既に次の攻撃の準備も整えていた龍輔は、言い切る前に矢を放つ。だが相手の動きに注意を払っていた怜二は一瞬早く木の後ろへと退避していたため、その矢は標的を射抜くことなく、森林の奥へと姿を消した。
「なかなかいい反応をするじゃないか。さすがはサッカー部レギュラーメンバーの一人といったところか」
「うるせぇ! 委員長達に続いて、さらには渉までも――絶対に許さねぇぞ!」
怜二の怒声が森林じゅうに響く。プログラム中に大声を出すことは危険極まりないなどといった考えも、もはや頭の片隅へと追いやられ、力の限り叫んでいた。
学級委員長の三上圭子は死ぬ前にこう言っていた。横田真知子の頭を射抜いたのは黒河龍輔。そして、死すことよりも辛い苦しみを圭子に与えたのも彼だと。その話を聞いた時点で、人の命をなんとも思っていない龍輔に対する怒りは頂点に達していたが、今回さらに渉までもがその手中に落とされてしまったことにより、怜二はもはや自分を制御できないほどに激昂してしまったのだった。
しかし龍輔の余裕な態度は変わらなかった。自分が負けるはずがないという自信に満ち溢れているのか、マイペースに次の矢を発射する準備を始めている。その態度が怜二の中で燃え滾る怒りの炎をさらに激しくさせた。
「余裕面こいてられるのも今のうちだ! すぐにその顔を恐怖に歪ませてやる! そして、お前の悪行もここで終わりだ!」
「面白いこと言うじゃねぇか。丁度いい。いつも正義感ぶっているお前の態度は前々から気に入らなかったんだ。そこに倒れてる女たちみてぇにぶっ殺してやるよ」
龍輔はへへっと笑いながら、怜二の足元に倒れている三上圭子と横田真知子の亡骸をちらりと見やる。その汚らわしいものを見るような目つきがまた、怜二の感情の高ぶりを後押しすることとなった。
この男、クラスメートを殺すことに何の躊躇もないどころか、それが罪であるとも思っていない。あの様子から察すると、委員長たち以外にも既に何人かがやられている可能性は高い。そしてこのまま野放しにしておけば、コイツの犠牲になる者は、きっとこれからも出てくるに違いない。そんなこと、絶対に許すわけにはいかない。
「れ……いじ……」
怒りに打ち震える拳を強く握り締めたとき、渉が小さくうめき声を上げながら、うずくまったままの状態で、助けを求めるようにこちらに手を伸ばしてきた。
矢は急所を外れたのか、彼にはまだ意識はあったが、深い傷口からは赤黒い血液が未だ止まることなく流れ出している。一刻も早く手当てをしなければ命が危ないと、医療に詳しくもない怜二でさえすぐに分かるほどに。
龍輔のさらなる攻撃を恐れた怜二は、自分が身を潜めていた木の裏へと渉の身体を引き寄せた。既に重傷を負っている渉にこれ以上の被害が及ばないようにするための、ほんのささやかな配慮。
「いいか渉、お前はここから動くな」
怜二はそれだけ言うと渉からの返事も待たずに立ち上がり、長く伸ばした髪を風になびかせながら、殺意に目をぎらぎらと光らせている相手と正面から向き合った。本当ならば、今すぐに渉の手当てに専念したいところだが、鋭い牙をむき出しにしている龍輔を前にして、悠長にそんなことをしている暇などない。それに、大切なクラスメート達を死に至らしめたうえ、さらには渉までもを傷つけた龍輔に対する復讐心は沈まることを知らず、いずれにしても相手を討ち取る他にはないのだった。
「なかなか感動的な芝居をするじゃないか。しかし、偽善者ぶるのもほどほどにしたほうがいいぜ。お前だってもう十分に噛み締めているだろう? 武田をはじめ、自分を除く生徒全員を消さなければ、生きて帰れはしないという現実を。な、そろそろ俺みたいに本性を剥き出しにして、自分のことだけを考えて殺しに転じてみてはどうだ?」
挑発するようにせせら笑う龍輔。しかし既に決心を固めている怜二は、もはや表情に僅かな変化すら見せない。
これにはさすがに龍輔も不快感をあらわにした。
「だんまりかよ。お前のそういうところが気に食わねぇんだよ!」
龍輔はボウガンに番えていた矢を発射した。これが開戦の合図だと言わんばかりに。
龍輔の手元から放たれたボウガンの矢は、怜二めがけて猛スピードで宙を駆けるものの、間に立ちはだかる木の幹に案の定邪魔をされて、負傷させるには至らない。
矢が外れたのを確認したとたん、怜二は木の陰から飛び出して龍輔めがけて猛進する。そのとき彼は手袋をはめたままの右手に、例によって栄養ドリンクのビンほどの大きさをした金属製の物体を握り締めていた。氷室歩から逃れる際にも使用した炸裂閃光弾の残りの内一つ。
こいつで視聴覚の機能を奪ってやれば、この戦い、圧倒的有利に進めることができるはず、などと考えながら、先端のピンを引き抜こうとした。が、思いがけぬ事態に驚かされることとなった。
まだ数メートルは離れているだろうと思っていた敵の姿が、何故かもう目と鼻の先にまで迫っていた。
馬鹿な! この男、俺との間にはかなりの間合いがあったはず。それをいったい、どうやって一瞬にして縮めたんだ?
見開かれた自らの目に、不気味な笑みを浮かべながらバタフライナイフを振り下ろす龍輔の姿が映る。もはやそれを避ける暇もなかった。
怜二はとっさに右手を持ち上げて、自分の身体をガードする体勢をとった。直後、肘の辺りを一文字に切り裂かれた右腕から血が飛び散り、全身に鋭い激痛が駆け巡った。そのとき、不覚にも炸裂閃光弾を取り落としてしまったが、それを拾うために屈むこともできない。猛獣と化した龍輔を前に、一瞬でも隙を見せることは許されないからだ。
取り落とした武器を拾うことを諦めた怜二。しかし龍輔は攻撃の手を休める様子はない。バタフライナイフを固く握り締める右腕を大きく振りかぶり、勢いをつけて素早く薙いだ。
さらなる攻撃を予期していた怜二は、一瞬早く後方へと飛び退いていたが、それでも龍輔の攻撃射程圏外まで逃げ切れてはいない。襲い来るナイフの切っ先に胴体を切り裂かれるのを防ぐために、とっさに相手の腕を両手で掴む。
怜二の身体まであと数センチというところで、龍輔の握るバタフライナイフはぴたりと動きを止めた。毎日のクラブ活動で肉体を鍛え上げていた怜二に、しかも両手で腕をつかまれてしまっては、さすがの龍輔も身動きすることはできないはず。しかしこのときは何かがおかしかった。
「この程度かよ」
龍輔はふんと鼻を鳴らして、ありったけの力を右腕へと送り込んだ。すると、大きく膨らんだ腕は怜二の両手による拘束をものともせず、バタフライナイフの刃を標的へと近づけていく。
ナイフの先が胸の辺りに触れ、危険を感じた怜二は龍輔の腕を振り払い、慌てて後方へと大きく飛び退く。
いったいなんなんだ? 中学生――いや、人間のものとは思えぬこの桁違いな力は。
とてつもない力を相手にして、怜二の息は早くも上がってしまっている。それはもう、サッカーの試合をワンゲーム終えたばかりのときと同じくらいに。
「ひゃはは、威勢が良かったわりには大したことねぇな。所詮はお前の力もその程度だったってことか」
ぜいぜいと激しく呼吸する怜二の姿を見て、龍輔はたいそう楽しそうに嘲笑している。怜二は何も言えず、鋭い視線を返すことで応戦することしかできなかった。
「なあ土屋よぉ、組み合いで俺に勝てるなんて思うなよ。今の俺は悪魔の薬、ホワイトデビルで素晴らしき力を得た、最強の身体を持つ男なんだからなぁ」
「ホワイトデビルだと?」
怜二もその薬のことは聞いたことがあった。たしか最近出回りだした新種ドラッグで、そいつを体内に取り込むことによって、『白き悪魔の抱擁』と呼ばれる心地よい快感を得ることができるのだとか。
「この薬は本当にすげぇぞ。頭の中が真っ白になるような快感を得られるだけでなく、刺激を与えられた体中の筋肉が増強されて、さらには麻酔を打ったかのように、いかなる痛みも緩和されてしまう。最強の身体を手に入れるために、まさにうってつけの薬品だ」
なるほど、その妙な薬を体内に取り込むことによって、あの驚くべきスピードと怪力を得たというわけか。
龍輔の自信たっぷりの態度の訳が分かった。しかし相手がいくら薬で強化された人間だとはいえ、怯むことは許されない。呼吸の乱れは未だ収まらないままだが、次なる攻撃がいつやってくるとも限らないので、それに備えて身構える。
「さて、戯れはこの辺りで止めにして、そろそろ本気で畳んでしまうとするか」
龍輔は手の平の上でくるりとバタフライナイフを回転させたかと思いきや、すぐにそれを握り締めて、怜二に向かって再び駆け出した。
龍輔が言ったとおり、組み合いの勝負ではまず勝ち目はないだろう。そのうえこちらは武器も持たず、全くの丸腰状態。いや、左のポケットの中には炸裂閃光弾がまだ残されてはいるが、先ほどと同じ失敗を繰り返してしまう可能性も高いので、最後の一発は不用意に取り出すわけにはいかない。
色々考えた結果、導き出された龍輔への対抗手段はただ一つだった。
「腸ぶち撒けて死にやがれぇ!」
相手の手前五メートル辺りにまで迫った龍輔は、上半身を左後方へと捻りながら、バタフライナイフを振りかぶる。怜二はそのタイミングを見逃しはしなかった。
相手の動きに合わせて後ろに跳び、しっかりと地面に固着させた左の足を軸に、右足を後方に思いっきり振り上げる。そして、龍輔がナイフを左から右へと薙ぐのと同時に、重心移動と体のバネを生かして、振り上げた足を素早く前に引き戻し、その勢いを保ったまま凶器を力いっぱい蹴り上げる。日々のクラブ活動にて、時速百キロを超えるボールを相手に真っ向から挑み続けてきた梅林中サッカー部のゴールキーパー、土屋怜二だからこそ出来た芸当であるといえよう。
蹴り上げられた凶器は龍輔の手から離れ、スローモーションのようにゆっくりと宙を舞う。予想外の出来事に龍輔の動きが止まっている隙に、怜二は落下してきたバタフライナイフへと手を伸ばし、空中で見事それをキャッチする。
チャンスは今しかない。
バタフライナイフの柄をしっかりと握り締めた怜二は、相手の首元に狙いを定めて素早く薙いだ。肉を切り裂く感覚がナイフを介して手にしっかりと伝わる。
勝った。怜二は疑うことなくそう思った。だけどさすがにそこまで上手く事が進みはしなかったようだ。
バタフライナイフが切り裂いたのは首元ではなく、急所をガードする形で持ち上げられていた龍輔の右腕だった。どうやら、怜二が振ったナイフの刃が首元へと届くよりも、我に返った相手の反応の方が一瞬早かったらしい。あとほんの少しこちらの行動が素早ければと悔やまれる。
しかし流れはまだこちらにあると判断し、怜二は攻撃の手を緩めることなく、今度は相手の腹部めがけてナイフを突き出す。だが残念なことに、龍輔の姿は既にそこにはなく、ナイフはむなしく空を切るだけだった。
怜二の意外な反撃に驚いたか、後退した龍輔は切り裂かれた腕をじっと見つめている。傷口からはかなりの勢いで血が流れ出している。破裂した水道管から溢れ出た水が、亀裂が走ったアスファルトの隙間から地上へと流出するかのように。だがどうしたことか、龍輔は落ち着き払った態度を変えはしなかった。
そういやこいつ、薬の影響で痛みを感じてないんだっけ。
変異した身体を持つ相手を、改めて厄介に思った。
ふいに、腕の傷に釘付けだった龍輔の眼球がぐるりと動き、カメラの焦点が怜二の顔へと合わせられる。
「考えてもなかったぜ。まさか薬で強化された状態の俺が、てめぇみてぇなザコ野郎に斬られるなんてな……」
傷口から溢れ出す血を舐め取る彼の表情が、みるみるうちに歪んでいく。
「もう容赦はしねぇ! さらなる絶望のどん底へと突き落とし、恐れおののく貴様の生命を、木っ端微塵に砕き割ってくれる!」
龍輔が咆哮した途端、怜二に纏わりついていた空気が一斉に震えだし、体中にびりびりとした痛みが走った。
自然と一歩たじろいでしまった怜二の目の前で、龍輔はポケットの中から透明な円筒形の物体を取り出した。注射器だ。鋭く尖った先端を左腕にあてがい、右手の親指でピストンをシリンダー内へとゆっくり押し込む。円筒の中を満たしていた白濁りの液体は、少しずつ体内へと送り込まれていく。
「たった一度の注射であれだけの効果が現れたんだ。さらに薬を追加注入することによって、身体にどのような変化が現れるのか、本当に楽しみだぜぇ」
薄気味悪く笑った龍輔は、空となった注射器をその場に放り投げ、両手を広げて大きく息を吸った。
相手の懐に踏み込む隙は何度かあった。だけど、敵に立ち向かえという怜二の意思に反して、両足は石膏で塗り固められてしまったかのように全く動かず、一歩前へと踏み出すこともできなかった。まさか、底知れぬ可能性を秘める白い悪魔の効能を前にして、怯えてしまっているのだろうか。
不穏な空気が漂う中、龍輔の身体に明らかな変化が次第に現れ始める。隆々と膨らまされていた四肢の筋肉は、薬を追加注入されたことによって、さらにはちきれんばかりに膨れ上がる。それだけではない。限界近くまで早まった心拍によって、血液は体内に広がるネットワーク上をとんでもないスピードで駆け巡り、パンパンに膨らんだ血管が、顔の表面をはじめ体中のあちらこちらから、その姿をはっきりと浮かび上がらせている。
元の面影をも感じさせぬ強大な体躯を手にした男は、薬の快感に酔いしれながら、フーフーと呼吸を荒げている。限界まで吊り上げられた口元からは、荒い呼吸によって押し出された唾液が僅かに垂れ、その様はまさに、弱者を食いつぶすことで我が生命を維持しようとする、飢えた肉食獣の姿の他に例えようがない。
怜二は全身の毛がよだつ思いをした。
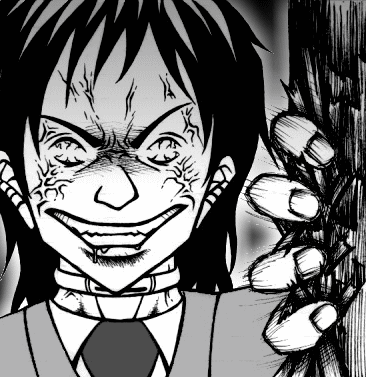
「ふははははは! これだ、まさしくこれだ! 全身にみなぎるこの力! これさえあればもはや敵なし! 俺の行く手に立ちふさがる邪魔な存在を、全てこの強靭な肉体の力でねじ伏せてくれる」
真っ赤に充血した目を最大限に見開きながら、龍輔は脇に立つ大木を掴む手に力を入れる。すると信じられないことに、幹の表面を覆う固い樹皮が彼の手の内でめきめきと音を立てながら砕かれていく。もはや生身の人間にできる芸当ではない。自らの身体を捧げることによって白い悪魔との契約を果たした男の力は、既に怜二だけでは止めることもできない域にまで進化していた。
勝てるわけがない。逃げなければ間違いなく食われる。渉も、俺も。
「さあ、先ほどの屈辱を晴らすのも兼ねて、この力をお前で試させてもらおうか」
剥ぎ取った木の皮を手の内で粉々に砕くや否や、龍輔は腰からもう一本のナイフ――血塗られたファイティングナイフを抜きつつ、こちらへとゆっくり歩みだした。
【残り 二十二人】 |
