「由美子」
背後に立つ少女の存在に気づき、千秋は振り向きざまにその名を口にした。そして、つま先から頭のてっぺんへと視界をスクロールさせながら、その全身を見つめた。
由美子の様子がおかしいのは、一見して明らかだった。
まるで何かに祈りを捧げるかのように、胸の前で組んだ両手をぎゅっと握り合わせながら、全身を小刻みに震わせており、僅かに開いた口元では、ぶつかり合う上下の歯がカタカタと音を鳴らせている。眼前の絶望的光景に怯えきった蒼白な顔の表面では、穴という穴から湧き上がる冷や汗が涙と混じり合って白濁り、土に薄汚れた床の上へと、止めどなく滴り落ちる。
怯えに怯えたその挙句、精神状態を保つことが出来なくなってしまった、といった状態だった。
そんな由美子を落ち着かせようと、逆さ吊りの亜美の身体から離れた猛が、彼女の方へと近寄ろうとした。だが由美子は、
「い、嫌ぁ!」
と一度叫び、踵を返して階段へと駆け出してしまった。
猛はすぐさま彼女を追おうとしたが、もはや落ち着かせることは難しいと判断したのか、足の動きを止めて、階段を駆け上がっていく由美子の後ろ姿を、ただ心配そうに見つめていた。
由美子の姿が見えなくなった、ちょうどそのとき、入れ替わるように上階から、杉田光輝と湯川利久が駆けつけてきた。
「何かあったの? 今そこですれ違った小島さんの様子が、なにやらおかしかったようだけど」
先にそう問いかけてきたのは利久。真緒の声を聞きつけるなり、最上階から全速力で走ってきたらしく、息を荒げながら苦しそうに眉を寄せている。
千秋、真緒、猛の三人は、利久の問いかけに対して、返事をすることが出来なかった。しかし、状況を説明する必要も、直後すぐになくなった。利久と光輝の二人は、斜め上に向いていた千秋たちの視線を追うことにより、すぐさま事態を把握したらしく、逆さ吊りにされた少女の姿を見た途端、やはりその遺体と同じように両目と口を大きく開き、驚いた表情を見せた。
「ふ、藤木! 何が……いったい何が起こったんや!」
変わり果てた姿となった亜美の遺体へとにじり寄りながら、その場にいた者たちに回答を求めたのは光輝。
「分からねぇ……。俺と春日も、羽村の声を聞きつけるなり、急いでこの場にやってきたんだが、そのときには既に……」
猛がそう言ったのを最後に、その場にいた全員の口が、堅く閉ざされてしまった。猛の言葉により、もはや第一発見者の真緒に問い詰めるのも無駄だと判断したらしく、光輝も利久も、それ以上の質問を続けようとはしない。
全員の身が固まり、沈黙が支配する重苦しい雰囲気の中、意外にも最初に声を発したのは真緒だった。
「とにかく、このままじゃあ亜美が可愛そうだよ。せめて下に下ろしてあげようよ」
すると猛も、
「そうだな。とりあえずは藤木の身体を下ろそう。難しいことを考えるのは、その後だ」
と、真緒の意見に賛同した。
猛の指揮により、利久と光輝は、亜美の身体をぶら下げているロープを解くために、三階へと急ぎ足で駆け上がって行った。ほどなくして、男子二人は吹き抜けの三階から頭を出し、到着したと合図を送る。
「ロープの根元はどうなってる?」
「吹き抜けの手すりに結ばれている。かなり固く結んであるようだから解くのに時間がかかるかもしれないけど、やってみる」
「ああ、頼むぞ湯川。それと、杉田も掴んだロープは放さないように気をつけてくれよ」
「分かった」
猛が考えた筋書きはこうだ。まず三階へと上がった男子二人のうち、どちらかが結び目を解いた後、二人がかりでロープを掴んで亜美の身体をゆっくりと下ろす。それを一階にいる三人が、慎重に受け止める。
「まだか?」
「もうちょっと待って」
猛にせかされ、焦りながらロープを解こうとする利久の声が、ビル内部で反響する。
もしもこんな無防備な状態のところに敵がやってきたなら、ひとたまりもないだろう。しかし、今やそんなことを気にすることが出来るほど、精神的に余裕のある者は、メンバーの中には誰一人としていなかった。
「解けた。杉田、ロープをしっかりと持っててくれ」
「分かった」
固く結ばれていたロープが解け、三階の二人によって支えられた亜美の身体が、ゆっくりと下がってくる。
徐々に近づいてくる亜美の苦しげな表情を見つめていると、腰が引けそうに思えたが、逃げ出したい気持ちをなんとかこらえて、千秋は亜美の身体を受け止めた。
亜美の身体は予想以上に重く感じられた。もちろん、人一人の体重が何十キロもあることは分かっていたが、まさか三人がかりで受け止めても、これほどの重さが感じられるとは思ってもいなかった。
「これが、人間一人の命の重さだ」
千秋の隣で、亜美の身体を支えながら猛が呟いた。誰かに向かって言うでもなく、ただ自然と口からこぼれ出た言葉、といった感じだった。
一階と三階、合わせて五人によって支えられていた亜美の身体が、慎重にゆっくりと床に下ろされた。寝かせた亜美の身体の隣に屈んだ猛が、見開かれたままだった目をやさしく閉じさせ、両足を拘束していた太いロープを解き始める。その間に、上階へと上がっていた男子二人が、再び一階へと戻ってきた。
「ねえ、今さら聞くようなことじゃないと分かってるけど、藤木さん、本当に死んだんだよね?」
目の前の光景が未だに現実だと信じられないのか、利久はその場にいた全員に問いかける。すると問いかけに対して、何人かがはっきりと首を縦に振った。
「ちょっ、ちょっと待ちぃや!」
うわずった声を上げたのは光輝。
「藤木がこうして死んでるってことは、彼女を殺した人間は、このビル内に侵入していた、ってことやろ? だけど、ビル内にはワイらの他には誰もいなかったって、前に磐田も言っとったし、ビル周辺への監視も抜かりなかったはずや。なのにどうして、こうやって仲間一人が死ぬこととなってもうたんや?」
光輝の言葉を聞いて、千秋もこのとき始めて気がついた。状況から見て、亜美の死は事故や自殺によるものでないのは明らかだ。しかし、光輝が言うように、東西南北への監視を常に続けていた以上、外の人間が内部に入り込むなど考えられないし、かといって、メンバーたちが訪れる前から、ビル内に誰かが隠れ続けていたなど、さらにありえない。
いったい何がどうなっているのか、千秋は訳が分からなくなった。
「いや、穴ならあったさ」
いつの間にか結び目を解き終えたらしく、猛は亜美の両足を拘束していたロープを握り締めたまま、皆の方を振り返る。
「確かに俺や春日が到着してから、ビルの外を監視し始めたし、建物内部の見回りも済ませた。だがほんの一瞬、俺たちは敵の侵入を許してしまうかもしれない、あるミスを犯していた」
はっきりとそう言い切った猛を前に、いつの間にか、誰もが真剣な表情で話を聞く体勢となっている。
「何? そのミスって」
目を細めた利久の問いかけに、猛は「銃声さ」と答えた。
「銃声が聞こえたとき――坂本と氷室の二人が銃撃戦を展開していた際、俺たちは全員、南東の一つのフロアに集まってしまい、他方面への監視を一時的に怠ってしまった。もしかしたらその瞬間に、招かれざる殺人鬼が、このビルに侵入していた可能性も考えられる」
皆が一斉に辺りを見回し始めた。猛の言葉により、自分達の他に誰かがこのビル内に潜んでいるかもしれない、という考えが脳裏をよぎり、安全だと思っていたはずのこの場所が、突如危険地帯とも見えだしたのだ。
フロアの隅に立つ太い柱の裏。置き去られた資材の山の陰。どこもかしこも、何者かが隠れているような気がし始め、辺りを見回せば見回すほど、千秋は胸の鼓動が高まっていくのを感じた。
「じゃ……じゃあ、これからどうすれば良いんだ磐田?」
「慌てるな。誰も姿を見ていないという状況から考えて、敵はおそらく一人だけ。しかも藤木を素手で絞め殺していることから考えても、大した武器は持っていないはずだ。これから全員でビル全体を捜索して、犯人をこの場に引きずり出す。それで一件落着だ」
利久にそう返した猛は、足元に置いたままだったバットを拾い上げ、強く握り締めた。そして他のメンバーの言葉を待ちもせず、一人で階段へと向けて駆け出した。
「待てよ! 単独行動は危険すぎる! もしも犯人に襲われたらどうするんだ」
「俺の心配なんかするな! もしもお前たちの誰かが襲われたなら、すぐに声を上げるなり、大きな音を鳴らすなりして知らせろ! そうすればすぐに俺が駆けつけてやる!」
これまで冷静だった猛も、もはや仲間を殺された怒りで自分を制御できなくなっていたのか、呼び止める利久の声に振り向きもせず、そのまま姿を消してしまった。そしてその後ろ姿を追うようにして、利久も階段を駆け上がっていった。
気がつけば、その場に残されていたのは、千秋、真緒、そして光輝の三人だけとなっていた。
真緒は寝そべった亜美の姿を見下ろしたまま、相変わらず一言も言葉を発さないので、千秋も無理に話しかけようとはしなかった。
「なあ、春日」
自分を呼ぶ声に振り向くと、そこには千秋に背を向け、力なく壁に片手をついた状態で立っている、光輝の後ろ姿があった。
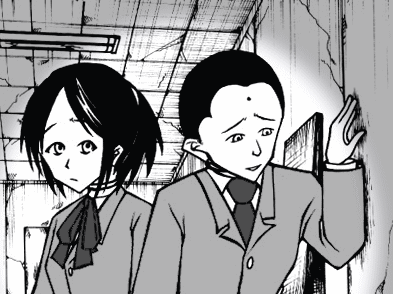
「どうしたの?」
「いや、大したことやないんや。ただ、人が死ぬのを目にするのって、なんでこんなにも辛いんやろな……」
千秋は彼に何と返せばよいのか分からなかった。だが、どちらにしろ間に言葉を挟む暇もなく、彼の言葉はまだ続く。
「ワイなぁ、人間の死ってものの辛さを、誰よりも分かってるつもりなんや。もちろん、クラスの皆も過去の事件のせいで、人間の死というものを身近に感じてるんやろうけど……、だけど、ワイは別格なんや。だからもう、こんなことが続くのに耐え切れへん」
そう言い切った後、空いていた右手で頭をかいてみせる光輝。泣きそうになっているのか、一向にこちらを振り向く様子はない。
「何かあったの? あの事件のときに」
人の心の中には必ずしも、他人には踏み込んでほしくないという領域が存在している。千秋も自分の経験から、それについてはよく分かっているつもりだった。だけど、ある種の好奇心が湧き出したのか、がっくりと肩を落とす光輝の心の中に、土足で堂々と上がり込もうとしてしまった。
千秋が自分の無神経さに後悔した頃には時遅く、光輝は黙り込んでしまっていた。だがしばらくして、こちらを振り向き、
「変なこと言ってスマンかったな。ワイ、怖さのせいかどうかしとったみたいや。忘れてくれへんか? 今言ったこと」
と言った。そのとき彼は、今作れるだけの笑顔を顔の表面上に形成しようと努めていたようだが、脳内を恐怖と悲しみに侵食されてしまった影響なのか、とても粗悪な作り笑いにしかなっていなかった。
そんな光輝の姿を見てしまった千秋は、ますます上手い言葉を見つけることが出来なくなってしまい、「ワイも猛らを手伝ってくるわ」と言ってフロアから出て行った彼に対して、何一つ反応らしき反応をとることができなかった。
【残り 二十六人】 |
