「だめだぁ〜、何も見つからない」
千秋は誰に向かって言うでもなく、一人で呟き、資材の山を漁る手の動きを止めて、埃まみれの床の上に、両手と尻をべたんとついた。そして、頭を天井に向けて、はぁ、と一度ため息を吐き出す。猛と別れて以来、何か役立ちそうなものはないかと、ビル三階の一室を探索し続けてきた彼女だったが、予想以上に体力を消耗するこの仕事に、そろそろ参ってしまったようだ。
部屋に残った資材の山は、思った以上に膨大で、それら全てを調べるのには時間がかかる。実際、千秋が探索を済ませたエリアなど、まだ部屋の半分程度にしか過ぎない。その中で、何か一つでも目を惹くような物を見つけていたならば、ある程度やる気も持続していたかもしれないが、見つかるのはダラクタも同然というものばかりで、活力は奪われていく一方。疲れを感じだしてしまうのも仕方が無いことだった。
「それにしても、所有建物を手放したときに、中にある物くらい全部自分で処分しなさいよね、まったく……」
埃にまみれたブレザーを、両手で適当に掃いながら、そんなことをぼやいてみる。はじめは宝の山であるように思っていた資材の山に対して、千秋が抱く感情も、ここ数十分の間でかなり変化してしまっていたようだ。
「どうだ。何か見つかったか?」
部屋の入り口から誰かがそう問いかけてきたので、千秋はすぐさま振り向く。二階での探索を一時中断してやって来たのか、猛がそこにいた。
「だ〜めね。武器はおろか、役立ちそうなものなんて何も見つからないよ。しまいには、床に散らばってたガラスの破片で、指先ちょっと切っちゃったよ」
と言って、僅かに血が滲む右手の指先を、猛へと差し出して見せる千秋。
「大丈夫かよ」
「ま、ヘーキだけどさ。毎日包丁使う生活送ってた私でも、こんな所に切り傷作っちゃったのなんか、本当に何年かぶりだわ。で、そっちはどう?」
「こっちも今のところ駄目だ。役立つ物はビルの元所有者がちゃっかり持ち帰っちまったのか、残されてる資材ってのはガラクタばかりでな」
と、口では残念がっているようだった猛だが、全くめげた様子のない千秋を見たせいか、表情はあまり沈んでいないように思えた。
「まあ、使えそうな物ってのは、今のところこれくらいだ。持っときな」
猛が千秋に差し出してきたもの、それは腐食が進み、かなり錆が付いている古めかしい鉄製の筒だった。
「この鉄パイプは?」
「ガス管を無理やり外した。工具も何も無かったから苦労はしたが、なんとかそれ一つだけは手にすることが出来たんでな。まあ、何もないよりは、いくらかマシだろう」
「磐田くんは?」
「俺はコレがあるから、別にいらないさ」
と言って、脇に抱えてあったバットを、猛は高らかと掲げて見せた。
「わざわざありがとう。そんなことのために作業中断してまで来てくれて」
「礼には及ばないさ。それに、俺がここへとやってきた理由は、何もそれを届けるためではなかったからな」
突如、両眉を寄せて真剣な面持ちを見せる猛に、千秋はなにやら嫌な予感を与えられた。彼の口から次に飛び出してくる言葉を、なぜか聞きたくないような、そんな気がした。
「なあ春日、正直に思ったことを言ってくれないか。ここに集まると誓った俺たち以外のメンバー、新田を除く三人は、何故か未だに姿を見せない。これは何を意味すると思う?」
新田を除く三人のメンバーとはもちろん、鳴瀬学、諸星淳、田村由唯、のことである。
「どういう意味かって……」
「プログラム開始からは、既に十時間以上経過している。普通に考えてみろ。ここに向かっているはずの人間が三人も、未だに姿を見せないんだ。何かが起こったのだとしか考えられない」
確かにおかしいと感じてはいたが、それには何か理由があるに違いないと、千秋はこれまで自分に言い聞かせてきた。だが、猛が言いたいことをなんとなくは予測できてしまった今、それを実際に聞いてしまうことで、自分の中の考え方が変わってしまうような気がして、その後に続く言葉を耳にするのが怖かった。
だけど千秋は、真実に背を向けてはならぬと観念し、猛の考えを聞く覚悟をした。
「言っていいよ……、磐田君の考えを」
そして猛は、千秋の予想を裏切らぬ、とてつもなく不吉な考えを返した。
「もし奴らが今もまだ無事でいるなら、こんなに時間が経っても現れないなど考えられない。おそらく、奴らはもう無事な状態ではないのだろう」
気を遣ったのだろうか、その言葉は直接的な表現を避けた、ある程度オブラートに包まれたものだった。だが結局、その言葉が意味することは一つしかない。それは仲間達の死。
考えられないことではない。前回の放送の時点で、死者の数は十数人にも上っていた。そしてその後も、死者の数はいくらか増えていることだろう。そんな中、千秋たちの仲間だけ、無事に集合場所に集まるなど、たいへん虫の良すぎる話だ。ここに到達する前に、仲間のうち何人かは誰かの手にかかってしまった、というのが、ごく自然な考え方なのかもしれない。
「仲間が死ぬのって……、本当に、辛いよ」
「ああ。だが残念なことに、それをなんとも感じていない者もいる。新田を殺した犯人なんかもな」
力なく肩を落とす千秋にそう返した猛も、どこか元気がない様子。
素手で首を絞められた挙句、磔にまでされた新田慶介の死体――、思い返すだけでも恐ろしい。
犯人は何を思って、あそこまで凶悪な犯行に及んだのだろうか。プログラムで生き残りたいだけなら、わざわざあのような面倒な行動に出る必要はないはずだ。
犯人の心理が、千秋には全く理解できなかった。
「しかし、ここに集まったメンバーたちだけは、絶対に死なせたくない。とりあえず今はビルの周囲全方位への監視のおかげで、敵が建物内に入り込んでくる心配は無いはずだが、危険は神出鬼没、意外な形で訪れるとも限らない。だが、もしそんな時がやってきたとしても、俺は前に小島にも言ったとおり、どんなことが起ころうとも、身を挺してでも全員を守り通してやる」
握りこぶしに全ての思いを込めるように、ぐっと強く力を入れる猛に、千秋は「頼りにしてる」と心からのエールを送った。
千秋は、猛がすぐ側にいてくれているということに、たいそう心強く思っていた。そして、そんな彼のために、ほんの少しでも力になりたかった。だが、自分という存在はとても弱いと分かっており、足を引っ張らずに猛の役に立てるなどとは、とても思えない。残念だが今の千秋には、猛に激励の言葉を送ることしか出来なかった。そして、そんな自分が少し情けなかった。
「どうしたんだ、柄にもなく力ない表情なんかして。元気出せ」
丸まった千秋の小さな背中を、猛の大きな手が、ばん、と叩いた。彼なりの元気付けようという気持ちに、これ以上ないほどのありがたみを感じた千秋は、「ありがとう」と返そうとした。だがその言葉は喉元あたりで止まってしまい、一向に外に出てくることはなかった。千秋たちのいる部屋の外から、切羽詰ったような誰かの悲痛な呼び声が聞こえたからだ。
「誰か! 誰か来て!」
突然のことに、千秋と猛は目を見合わせた。そして何かに突き動かされるようにして、部屋の外へと飛び出した。
声は階下から聞こえる。
二人の足は自然に階段へと向き、かかとを地に付ける時間をも惜しんでとにかく駆けた。ヒビの走ったコンクリート製の階段を一段飛ばしで駆け下りて、二階になんて目もくれず、とにかく一階を目指す。その間も呼び声は止まない。二人は声の主の居場所をまっすぐ目指した。
階段を下りきると、視界を狭めていた左右の壁が突然途切れ、吹き抜けが三階まで続く広々としたフロアの光景が目に飛び込んできた。
声は確かにここから聞こえたはず。千秋はすぐさま辺りを見回す。
フロアの中心に、腰を抜かして座り込んでいる誰かがいる。真緒だ。どうやらあの悲痛な呼び声は、彼女のものだったらしい。
顔面蒼白の真緒を見た千秋と猛の二人は、ただならぬ事態の訪れを感知し、すぐさま彼女の元へと駆け寄って、「どうした? なにがあった?」と問い詰めた。
真緒は何か言いたいらしいが、口から出る声が言葉にならず、ただ「あっ……、あっ……」と、かすれた音を出すだけだった。だが彼女の指先は、ある方角をしっかりと指差していたので、真緒の言葉を待つことなく、二人はすぐさまそちらへと目を向けた。
そこには、信じられないような光景が待ち受けていた。
上階から垂れ下がった一本のロープ。その先にぶら下がっているのは、巨大冷蔵庫に貯蔵されている豚肉か何かのように、両足を結ばれた状態で逆さ吊りとなっている少女の身体。何かに驚いているかのように、両目を最大限にまで見開き、そのまま硬直している顔は血の気を失い、生命の温かみなど微塵も感じさせない。
吊るされているのは藤木亜美。千秋たちの仲間であり、いつも明るく笑顔で皆を元気付けてくれていた、とても優しい少女だ。
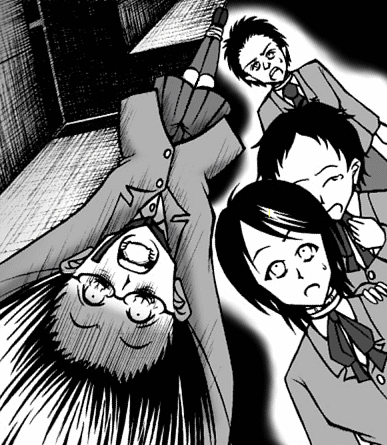
建物内部を通り抜ける風によって揺れ動く、どこか古時計の振り子を思わせるその様を見て、千秋はごくりと息を飲んだ。
「ち、千秋ぃ!」
ようやくちゃんとした言葉を出せるようになった真緒が、千秋の背後に隠れるようにしながら泣きついてきた。
あまりに衝撃的な光景を目にし、緊張に固まってしまった千秋だったが、なんとかして喉の奥から声を押し出そうと試みた。だがどうしたことか声が震えてしまい、いつものようにすんなりと話すことが出来ない。
「こ、これは……、いったいどういうことなの?」
「分からないよ! 上の階から降りてきて、何気なく見上げたら、こんな……」
緊張に小刻みに震える真緒の口からは、それ以上の言葉は続かなかった。級友の絶望的姿を見てしまったことによって、彼女は完全に怯えてしまっている。そんな横を、背後にいた猛がゆっくりと通り過ぎ、亜美の身体へと恐る恐る近づいていく。そして、なにやら首元を確認したかと思うと、小声で、「同じだ」と呟いた。
千秋が猛に「何が同じなの?」と聞こうとした、そのときだった。
「い、嫌っ!」
いつの間に階段を下ってきたのか、亜美の死体と同じくらいに顔面を蒼白させた小島由美子が、千秋たちの後ろで泣きべそをかきながら立ち尽くしていた。
 藤木亜美(女子十八番)―――『死亡』 藤木亜美(女子十八番)―――『死亡』
【残り 二十六人】
|
