キーボードを叩く指を休め、木田聡は椅子の背もたれに全体重を預け、つかの間の休息をとった。交代時間まではまだまだ時間があるため、こういった短い休憩の間に、できるだけ体の疲れを癒さねばならない。
机の上に置かれたままだったコーヒーカップに手を伸ばし、ゆっくりと口へと運ぶ。甘党の彼が砂糖をたっぷりと入れていたエスプレッソコーヒーは、長時間放置されていたため、もはや生ぬるくなっており、けっして美味いものではなかった。
背もたれに身体を傾けながら、木田はマウスを動かし、ヘッドホンの設定を、ある女生徒の首輪へとあわせた。すると、対象となった生徒の声はもちろん、もう一人別の生徒の声も聞こえた。男の声だった。
二人は一緒に行動している仲間なのか、言い争うでもなく何かを話し合っていた。とりあえず、二人の会話には今のところ気にすべき点もなく、変わったことも無い様子だったので、木田はリラックスして物思いにふけり始めた。
木田はプログラムに参加している生徒達のことよりも、むしろ自分と同じくプログラム管理をしている同僚の桂木幸太郎のことが気になっていた。自分の隣に座る彼が時々見せる、何か思い悩んでいるような複雑な表情の裏に、なにやらとんでもない思いが秘められているような気がしてならなかったからだ。
桂木幸太郎という人物は、とにかく生真面目な性格の持ち主なのだと木田は知っている。
真性愛国者だとか、ろくな考えを持たずに兵士になった者達が大半を占める中、桂木は、自分にとっての大切な人たちを守るために兵になることを志願した、という珍しい人物だ。だからか、周りの人間達が持ち備えていない正義感というものを彼は持っている。
だからこそ彼のことが心配だった。この国の暴走を間近で感じたとき、国家を相手に異議を唱える恐れが十分にあったからだ。
案の定、政府の側で働き出してから大東亜共和国の突き進む道のズレに気がついたらしく、彼は何度も不満げな表情を見せた。だがさすがに、国家を相手に一人で立ち向かうほどの無鉄砲ではなかったらしく、表立って危険な行動に出たりはしなかった。少なくとも、今までは。
今回のプログラムが始まってから、桂木の様子は明らかにおかしい。もちろん、罪無き学童達が無駄に命を落としていくことに、彼が眉をひそめるのは前々から予測できていたことだが、なぜか妙な胸騒ぎが止まない。
気になる節はいくつかあった。ヘッドホンの音声に耳を傾けながら見せた、悩ましげなあの表情。そして、木田に向かって言った、あの言葉。
――なあ木田。プログラムって止められないのかな?
あいつ、プログラムに支障をきたすような行動に出たりしないだろうか。
そんなことを考えた木田だったが、すぐに「まさか」と思った。プログラムを止めるように頼み込んだとしても、担当教官たちがそれを許してくれるはずなどないし、たった一人で中止させることが出来るほど、プログラムというものはヤワではないと彼も分かっているはずだからだ。
あー駄目だ駄目だ。無駄に気疲れしてしまう。交代時間はまだまだ先なんだ。変なことを考えるのはこれにて終了。
木田はそう自分に言い聞かせて、意識をヘッドホンへと引き戻した。その瞬間、なにやら妙な言動がヘッドホンから聞こえた気がした。
気になったので、ヘッドホンの音声に全意識を集中させ、先ほどの男女が何を話しているのかを確かめようとしたが、突如その音声は途絶えてしまった。何者かによって背後からヘッドホンを外されたのだ。
「どうですかぁ? 何か面白いことでもありましたかぁ?」
木田のヘッドホンを持ち上げながら言ったのは、担当教官の田中一郎だった。
「いえ、今のところは特に……」
「そうですかぁ。いやね、ここ三時間ほど脱落者もいなくて、ちょっと退屈してるんですよねぇ。なので、なにか面白いことに気づいたら、すぐに教えてくださいねぇ。私も室内スピーカーで聞いていたいですからねぇ。ウンコちゃん達の断末魔の叫びとかねぇ。フフフ」
生徒達が死んでいくのを心から楽しんでいる田中の笑いに、木田はぞっとした。ヘッドホンを返してもらう際、自分の手が少し震えているのを感じた。
田中がソファーへと戻っていくのを見届けてから、気を取り直してヘッドホンをかぶりなおした。そして先ほどの続き、とある男女の会話を聞くことに集中した。
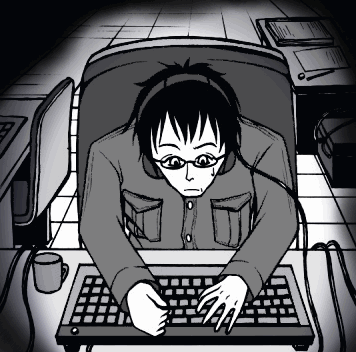
ヘッドホンを介して男女の声がすぐ側に聞こえる。気の強そうな女の声と、クールさを漂わせている低トーンの男の声が、なにやら真剣そうに話し合っている。
妙な胸騒ぎを感じた木田は、集中してその会話内容を拾い続けた。
不安は的中した。二人の内、女の方が話していた内容、それは驚くべき計画の全貌だった。粗さが気になるものの、もしもそれが本当に行われるならば、今プログラムは停止せざるを得ないかもしれないというほどの、なんとも大胆で恐ろしい発想。
木田は急いで周りを見回してみたが、自分と同じようにヘッドホンで生徒達の会話を拾っている兵達も、スピーカーの隣で雑談している田中と御堂一尉も、誰一人その恐るべき会話に気づいている者はいないようだった。
すぐさま田中にこのことを伝えようかと思った。だが、木田は田中を呼びはしなかった。
慌てることは無い。計画がもしも遂行されるとしても、それまではまだ時間がかかるはずだし、成功する確率もおそらく低い。それに、まずは“あいつ”の意見を仰ぐべきなのかもしれない。
木田は部屋から出て行ったきりの桂木のことを考えながら思った。どうしてこんなことを思ったのかは彼自身も分からない。ただ、彼の内にある勘が、このことを桂木に伝えるべきだと訴えていた。
【残り 二十八人】
|
