部屋から一歩外に出ると、壁も天井も木で造られた古びた廊下の様子が、視界いっぱいに広がった。
万が一の生徒達の反乱に備え、窓に分厚い鉄板が張り巡らされているため、朝だというのに日の光は差し込まず、その場はとても薄暗い。そのせいで、木の壁にこびり付いている黒い染みが、よりくっきりと浮かび上がっているように感じた。
電力節約のために半分に抑えられている照明の下を、桂木はゆっくりと歩き、桑原教諭のもとへと向かった。
途中、なにやら雑談しながら歩いている二人の兵士たちとすれ違った。
「さっき衛星中継見てたんだが、どうやらまた雨降り始めるらしいぞ」
「本当か。せっかく止んだと思ったのに、うっとおしいことこの上ないな」
「まあ、俺達は屋内で仕事してるだけだから、さほど影響はないだろう。それよりも、大変なのは中学生達の方だ。奴ら傘も持たされず島の中に放り出されて……まあ、どうせほとんどの奴が死ぬんだから、今さら風邪なんか気にする必要なんか無いだろうけどな」
「ちがいねぇ」
すれ違いざまに、彼らがこんな会話をしているのが聞こえた。すると、桂木は無意識のうちに、こぶしを強く握り締めていた。
木田の言葉が思い出される。
――ここにいる人間の多くは、ただの真性愛国者達だ。奴ら、お国が決めたことは正しいと言うばかりか、中学生同士の殺し合いを楽しんでるんだよ。
たしかに彼が言ったとおりだった。
そもそも、共和国戦闘実験第六十八番プログラムは、その名の通り、戦闘上において見られる各種統計を重ねるために始められたものだったはず。しかし今や、それも半分身勝手な大人たちの娯楽へと成り果てている。
桂木は思った。
五十年以上も前から始められたこの実験を、今もまだ続ける必要はあるのだろうか。
もはや惰性のみで突き進んでいるように思われる、この無意味な殺戮ゲームについて考えれば考えるほど、その存在意義が分からなくなっていった。
ほどなくして、桂木は桑原教諭がいる部屋の前へとたどり着いた。もう目を覚ましていると聞いたが、中は不気味なほどに静まり返っており、物音一つ聞こえない。
一度深呼吸をしてから、ドアをゆっくりと開く。
古びたドアはスライドさせると、ガタガタと音を鳴らす。長い年月の間に変形してしまったのだろう。
扉が完全に開くと、桂木は部屋へと踏み込んだ。
中は廊下と同じく薄暗い、いや、部屋中に満ちた澱んだ空気のせいで、廊下よりも暗いように感じた。
何もない木造教室の真ん中に、古びたテーブルと横長のソファーが置かれている。桑原教諭はその上に腰掛けており、桂木が部屋へと踏み込んでも振り向きすらしなかった。相当落ち込んでいる様子だ。
茶色の毛布が乱雑にソファーの端へと追いやられている様子が、彼はつい先ほどまでこの場で深い眠りについていたのだと物語っている。
物音にも反応すら見せない態度にも構わず、桂木は桑原教諭のほうへと歩み寄った。
「兵庫県立梅林中学校三年六組の担任、桑原先生ですね」
桑原教諭の隣に立ち言った。聞く必要もない回答の分かりきったことだったが、相手の反応を探るため、あえて返答しやすいだろうという質問をした。あまり難しい質問をして、だんまりとされてしまっても困るからだ。
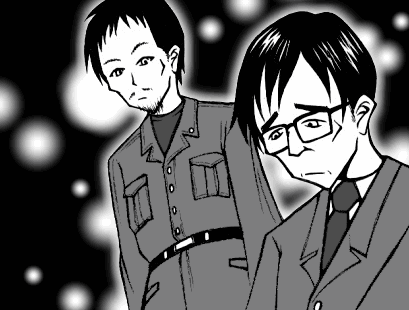
何か深い考え事をしていたのだろうか、桑原教諭は桂木の存在に今さら気づいたらしく、こちらをゆっくりと振り向いた。
「……はい……そうですが」
力の無い口調。自分の受け持つクラスがプログラムに選ばれてしまったということに、そうとう参っている様子だ。どうやら彼はそうとうに精神面の弱い人間らしい。写真を見て感じた印象どおりだった。
桂木は彼に対面する形でソファーに腰を下ろし、顔をじっと見つめた。気のせいか、始めて会った人間のはずなのだが、写真で見たときよりも頬がこけて見えた。
「あの……プログラムに同意するかどうかについてのお話でしょうか?」
桑原が言った。だが目線をこちらに合わせようとは全くせず、頭はずっと下を向いたままだった。
「いえ、私はただの兵にすぎないので。それについては、後ほど最高責任者のほうからお話されるかと思います」
「そうですか……」
桑原はそこで一度言葉を切った。しかしすぐに口を開き、「ところで今、生徒達は……?」と桂木に聞く。
「現在、プログラムが始まってからかなりの時間が経過しています。残念ながら、これまでに没した生徒は少なくはありません」
桂木は言った。
既に何人もの教え子達が死んでいることが相当ショックだったのか、桑原は黙り込んで、さらに深く頭を垂れてしまった。
返答こそしなかったが、その態度から、彼は自分の受け持つクラスがプログラムに参加することに、納得できていないと一目瞭然。だからこそ、桂木は桑原とは一度話してみる価値があると思った。
「……少し、お話よろしいでしょうか?」
桑原は少し間をおいてから、頭を垂れたまま「なんでしょうか?」と返した。
「ずばり聞きます。あなたは自分の教え子達が、今回のプログラムに選ばれてしまったということについて、どう思っていますか?」
「それは……」
「案ずる必要はありません。返答によってあなたや教え子たちに、何か制裁を加えたりするわけではありませんから。私を政府の人間だと思わず、ただの一人の人間として見て、正直に答えてください」
すると、桑原はゆっくりと頭を上げて、じっと桂木の目を見つめ始めた。言葉の真偽を確かめようと、こちらの様子を伺っているらしい。
桂木は、彼の力無い瞳の奥に、何か哀しき思いが隠されているのが、垣間見えたように感じた。
十秒ほどの沈黙の後、桑原は何かを決意したらしく、表情をきゅっと引き締めた。
「正直な話、私は今回のプログラムに納得なんてしておりません」
「と言うと、今回のプログラムには、やはり反対だということでしょうか」
「当たり前です。あんなに良い生徒達が殺し合うことに、どうして担任の私が同意しなければならないんですか」
桑原の顔は真剣そのものだった。桂木はこのとき、初めて桑原の顔を正面から見た気がした。
彼の話は続いた。もはや正面に座っている男が政府関係者だと忘れてしまったかのように、思いの丈を打ち明けだした。
「それにしても、本当に自分が情けないですよ。今回の件につきましても、私は気絶してしまって、生徒達を助けることもできなかった。本当に、担任失格です。思えば、生徒達の心身は成長し続けていたというのに、私のほうは全く成長していなかったんですね。二年前の、あの事件以来……」
「二年前の事件?」
桂木は何か引っかかりを感じたので口を挟んだ。
「今回プログラムに参加させられている、梅林中三年六組は、二年前に起こった松乃中大火災の被災者達が集まった特別クラスなんです」
「それは話に聞いていましたが、事件当時あなたはまだ担任ではなかったはずでは?」
「担任だったんですよ。あの火災で松乃中が燃えてしまうまで、私はそこで教師をしておりました。ですが、突然の火災で職場から追い出され、梅林中へと移ったんです」
「生徒達と一緒に、今の学校に移ったということですね」
「はい。火災で同じ傷を負ったもの同志が一番分かり合えるだろうということで、梅林中に設けられた被災者特別クラスの担任に私が抜擢されたんです。その話を初めて聞いたときは不安でした。気の弱さが災いして、炎の中で慌ててしまい、生徒達の役に立てなかった私のことを、皆は迎え入れてくれるのだろうかと……。しかし――」
突然、桑原の目から堰を切ったように涙が溢れ出した。しかし彼は微笑んでいた。
「皆は私を笑顔で迎えてくれたんです。燃える校舎の中で走り回るも、結局は何人もの生徒が死に行く様を、ただ見ていることしかできなかった私を……」
嗚咽が混じった彼の言葉はそこで途切れた。
桂木は黙って聞いていたが、少なからず衝撃を受けていた。
彼は知らなかったのだ。梅林中三年六組一同が二年前の大事件の被災者だったということはまだしも、担任の桑原までが、当時の火災の体験者だったということを。
とにかく、桑原の話を聞いているうちに、頭の中に存在していた相反する二つの思いの内、桂木の考えはある片方へと傾きつつあった。そして、政府関係者として選んではならぬ、禁断の決断へと手を伸ばそうとしていた。だがそれを実行するとなると、自分の身は保証されない。しかし彼は思った。
千秋は元より、梅林中三年六組の生徒は、桑原の言うとおり、こんな理不尽なことで死ぬべき人間達ではない、と。
桂木は立ち上がった。そして、泣き崩れた桑原を見下ろしながら言った。
「つらい思いをしている中、お話していただいてありがとうございます。おかげで、ようやく決心することができました」
【残り 二十八人】
|
