視界の利かぬ闇の中、千秋は出口を探して彷徨っていた。しかし、何も見えないこの空間の中でいくら動き回ろうとも、目の前に出口が姿を現すことは無い。それは蓋の無い密閉空間の中から脱出しようとしているに等しく、無意味な行動でしかなかった。
突如、千秋の心の中に向けて誰かが話しかけてきた。
『そこから外に出たいか?』
千秋は辺りを見回す。しかし誰の姿も見えず、声の主の正体は掴めなかった。声色から察するに、相手は四十から五十ほどの中年男性だと思われるのだが。
相手の姿が見えないものの、暗闇の恐怖に耐え切れなくなっていた千秋は大声で言った。ここから外に出たいです、と。
『なるほど。しかしそれには一つ条件がある』
千秋は外に出たいという一心で、続く相手の言葉に集中する。はたして、ここから外に出るにはいかなる条件を飲まねばならないのだろうか。
ふと相手が笑みをこぼしつつ、ゆっくりと口を開こうとしているように思えた。暗くて何も見えないはずなのに、それが分かるとは不思議だ。相手へと向けて精神を研ぎ澄ましていたからなのだろうか。
『ここから外に出るにはだな……』
そこまで言ったときだった。突如世界が大きく揺れ、謎の男の声はそこでかき消されてしまった。
何が起こったのか理解できず、千秋は視界の利かぬ世界の中で、ただただ呆然とするばかり。そんな彼女の耳に聞き慣れた少女の声が入ってくる。
『…ち…あき……千秋』
遠くに思えたその声がだんだんと近くに感じるようになり、すぐにはっきりと聞こえるようにまでなった。それは紛れも無く、幼き頃から知り合っていたかけがえのない大親友の声だった。
ゆさゆさと揺れる世界の中、立って歩くのはあまりにも困難。未だ揺れを止めることのない地面に這い蹲りながら、千秋は声のほうへと手を伸ばし、そして叫んだ。
「真緒!」
カッと千秋の目が開かれた。するとそれまで千秋の身体をゆすり続けていた真緒が安堵の表情を浮かべた。
「よかった、気が付いたんだね」
安心した様子で親友がこちらを見下ろしているが、千秋は自分が置かれている状況を理解できていなかった。
……ここは?
辺りを見回す。目に映るのは学校の教室。しかし自分達の兵庫県立梅林中等学校の校舎ではない。木材によって構成されている古びた様子の教室は、むしろかつての自分達の母校、兵庫県立松乃中等学校内部を彷彿とさせているようにも思える。
「ここはどこ? あたし達、何でこんなところにいるの?」
その疑問はもっともだった。千秋はいくら自分の記憶を辿ってみても、こんな見知らぬ教室に入った覚えなど無いのだから。
それは問われた真緒も分かっていないらしく、ただ困った顔をするばかりだった。
「分からないよ。私達が慰霊碑を後にして、帰ろうとバスに乗り込んだら急に眠くなって、そして気が付いたらここにいたとしか」
千秋が目を覚まし、一度は顔に安堵の色を見せていた真緒だったが、それもすぐさま不安という感情に支配されてしまった。
真緒の言葉を聞き、千秋もおぼろげながら記憶を取り戻していった。
たしかに真緒が言うとおり、私達は慰霊碑を後にしてバスに乗り込んだ。そして出発……それ以降の記憶は無い。そして今、見知らぬ教室で眠っていたのだと気づいた。
これはいったいどういうことなのだろうか。
つい先ほどまで自らが突っ伏していた机に両手を付き、立ち上がって周りの様子をさらに詳しく調べた。
室内では既に梅林中三年六組のメンバーの多くが目を覚ましており、各々状況を理解できておらず騒然としている。
千秋の右斜め後ろの席で眠っていた智香も、今ようやく目覚めたばかりらしく、これはいったいどうなっているのかと問うてくるが、むしろこっちが聞きたい。
どうやら、誰一人状況を理解できている者はいないようだ。
そんな中ふと気が付く。何気なく触れた首元に巻きついた、硬く冷たい金属の存在に。
首輪……か?
無理に引っ張ってみるが、しっかりと固定された金属の輪は外れるどころかびくともしない。これはいったい何なのだろうか?
机と椅子のみが並べられた無機質な木造部屋の中、なぜか言い知れぬ不安がよぎる。そんな時、教室の外からコツコツと何者かが近づいてくる足音が聞こえた。
音を立てながら開くスライド式の木造扉。皆の視線を浴びながら、その男は姿を現した。
「初めましてウンコちゃんたち。少し早めの就寝時間は存分に活用できましたかなぁ?」
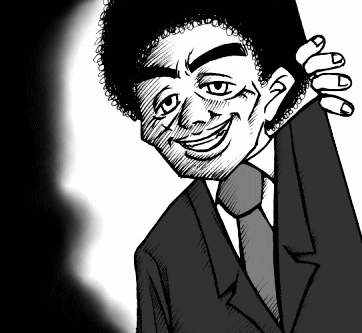
教室に入ってきた中年の男はつかつかと教卓へと歩み寄り、黒板の前ど真ん中へと陣取った。
クラスメートの誰一人声を発しない。ただ呆然と男の方へと視線を向けるばかり。
生徒達全員が自分を見ているのを確認し、男は身体をくるりと黒板へと向け、チョークでなにやら文字を書き始めた。
「田中一郎、これが私の名前です。数日間皆さんのお世話になりますので、是非ともお見知りおきを」
田中一郎と名乗る男の口調はとても丁寧だった。しかしその丁寧な言葉遣いは濃い造りの顔には不釣り合いに思える。鳥の巣を思わせるような豪快なアフロヘアーと、右の頬に残された切り傷跡が嫌でも目に入る。陳腐な名前とは対照的に、外見はかなりインパクト大。
あっけにとられている生徒達を見回し、田中は何かに気づいたらしく、右のこぶしで左手のひらをポンと叩いた。
「そうでした。皆さんの反応がやけに薄いと思いきや、まだ肝心なことを言ってませんでしたねぇ。うっかりしていましたよぉ。自己紹介なんかよりも、こちらを先に伝えておくべきでしたねぇ」
分厚いたらこ唇を巧みに動かしながら、田中はなおも丁寧な口調でしゃべる。しかしその声はネチネチとした粘着質に包まれているようで、いくら丁寧でも聞いていて良い気にはなれない。
彼の声を聞いているうちに、千秋はふと気がついた。夢の中で聞いた謎の男の声。それがこの田中という男の声とあまりにも酷似していたということに。
不安がよぎった。そして千秋の本能が警告する。この男の言葉を聞いてはならないと。
これまで紳士的な態度で話していた田中だったが、突如口の端を吊り上げて不気味な笑みを漏らした。
「おめでとう。君たち兵庫県立梅林中等学校三年六組のウンコちゃんたちは、今回のプログラムに選ばれました」
田中が言葉を切ると、教室内に静寂が訪れた。しかし、それもほんの一瞬のことだった。
「……ウ……ソだろ?」
「プ、プログラムって……まさか」
ざわめく生徒達の様子を一瞥すると、田中はさらに不気味に笑む。
「そうです。あなたたち四十五人のウンコちゃんたちには、これから最後の一人になるまで殺し合ってもらいます」
先ほどから気にはなっていたが、彼が言う「ウンコちゃんたち」とはおそらく生徒達を指すのだろう。この蔑んだ呼び方に本来ならば抗議を申し立てたいところだが、今はそれどころではなかった。プログラムに選ばれたという恐るべき事実を生徒全員が今ようやく理解したらしく、室内では多数の悲鳴がこだましていたのだ。
無理もなかった。田中が言ったプログラムとは、最後の一人が生き残るまでクラスメート間で繰り広げられる殺戮ゲーム、共和国戦闘実験第六十八番プログラムの略称なのだから。
選ばれる確率は宝くじの当選より低いと言われているこのゲームに選ばれてしまったという事実には、誰もが驚愕せずにはいられなかったであろう。
「待ってください!」
長身の陸上部員、中沢彩音(女子十二番)が手を挙げながら立ち上がった。
「私たち、梅林中に帰る途中のバス内で眠らされてここに連れてこられたんですよね? それじゃあ、一緒にバスに乗っていた桑原先生は何処に行ったんですか?」
多くのクラスメート達がパニックに陥っている中、彩音は堂々とした口ぶりで質問した。体育会系の人間はプレッシャーに強いといえば偏見かもしれないが、彼女を見てはそう思ってしまっても仕方がないだろう。しかし千秋は気がついた。一見平然としているように見える彩音だが、その足元がガクガクと震えているということに。
田中が答える。
「桑原先生にはウンコちゃんたちがプログラムに参加するということに同意していただこうと思ったのですがぁ、当選の事実をお伝えしたところ、突如気絶してしまいましたのでぇ、仕方なく皆さんと共に当プログラム会場へと連れて来させていただきましたぁ。とりあえずお目覚めになるまでは他の部屋で安静にしていただき、意識が戻ってから再び同意していただく形になるかと思われます」
桑原先生は優しいためか、年配ながらも生徒達にとてもよく慕われていた。そんな彼の欠点は気が弱いということだった。自らが受け持っていたクラスがプログラムに選ばれたと知り、ショックのあまり気を失っている姿は想像に難しくはない。
「はい」
またしても生徒の中の一人が声をあげた。新田慶介(男子十五番)だった。田中の視線が彼へと向く。
「はい、新田君どうぞぉ」
慶介が席から立ち上がる。
「知っているかどうか分かりませんが、僕達は二年前に起こった松乃中火災の被災者なんです。何もかもが焼き尽くされていくあの地獄の中、たくさんの犠牲者を出しながら生き残ったんです。僕達はもう十分すぎるほどに苦しみました。なのに、どうして僕達が選ばれなければならないんですか? 理由を教えてください」
慶介は涙ぐみなが訴えかけた。しかし田中はまったく動じることもなく、笑みさえ浮かべながら軽々と返す。
「僕達はもう十分に苦しみましたぁ? なのにどうして僕達が選ばれなければならないんですかぁ? 理由を教えてくださいだぁ? バカなことを言ってはいけません。いいですかぁ? 人の人生は平等なんかじゃあないんです。生まれてから死ぬまで幸せに生きる人もいれば、一生を不幸に生きなければならない人もいるんです。ウンコちゃんたちは不幸にも後者となってしまった、それだけの話です。プログラムの対象校の決定は抽選に全てをゆだねています。単に運が悪かっただけ、だから理由なんてものはありません。以上」
呆然と立ち尽くす慶介へと近寄った田中は、相手の肩をぽんと叩いて席に座らせると、また黒板の前へと戻っていった。
「それから皆さんに紹介したい人がいます」
田中は唐突にそう切り出すと、廊下の方へと身体を向けて、両手をパンパンと叩き始めた。
「待たせたねぇ。そろそろ入ってきていいですよぉ」
すると教室の前の扉が開き、何者かが中へと入ってきた。
その姿を一目見たとき、誰もが驚かずにはいられなかったであろう。
教室へと入ってきた人物は全身を真っ白な包帯で巻かれていた。それはまるでミイラのようだったが、奇妙なことに、千秋たちと全く同じ、兵庫県立梅林中等学校の女子の制服を着ていた。
「紹介するまでもないですよねぇ。なにせこの方は皆さんのクラスメートなんですからねぇ」
梅林中三年六組は生徒数四十五人の学級だ。しかし松乃中火災の被災者である生徒達の中に一人、重傷を負って未だに入院生活を送っているという女生徒がいた。そのため、千秋たちのクラスには座る人間のいない机が二年間ずっと放置されていた。
千秋はいつしか聞いたことがある。当時炎に全身を包まれた少女は、見るに耐えない姿へと変貌したと。
「お久しぶりね、皆さん」
包帯の隙間から彼女の口元が笑んでいるのが見えた。
間違いなかった。田中の隣に立つ包帯の人物こそ、あの事件によって全身を焼かれたという女生徒、御影霞(女子二十番)だった。
【残り 四十五人】
|
