龍輔は懐から、円筒形の細長い物体を取り出した。白く濁った液体が入った注射器だ。
不穏な動きを見せる彼を見て、警戒した和歌子はボウガンの狙いをしっかりと定めて、いつでも発射できるようにと身構えた。
「なんだいそれは! 変な素振りを見せたら承知しないよ!」
和歌子が言った。龍輔が取り出した注射器を見て、何やら嫌な予感でも感じたのか、余裕な態度を保ちつつも、その口調は先ほどよりも荒くなっているように感じる。
龍輔は彼女の言葉に構わず、注射器の先端から生えている針の先を、怪我した右足へと当てて、浮き上がって見えていた静脈に突き刺した。そして円筒の尻の部分にあるピストンを親指で押し、液状化させてあったホワイトデビルを、注射器内部から体内へと送り込んだ。
警告を無視された和歌子は、あらかじめ龍輔の胴へと狙いを定めていたボウガンの引き金を絞り、矢を放った。
「チィッ」と舌打ちしながら身体を横に倒し、ギリギリのところでそれを回避する龍輔。ほんの一瞬でも反応が遅れていたなら、危うく大事に至っていたところだ。
「往生際の悪い男ね。あんたみたいな人間でも、一秒でも長く生きたいって思うのかい」
矢を避けられたというのに、和歌子の口調にはまだ余裕がある。
二人の間は距離があり、さらに龍輔は足に傷を負っているため、次の矢を装填し終わるよりも早く飛びかかってこられることはない、と安心しているのだろう。
案の定、和歌子は龍輔の動きに注意しつつも、冷静に次の矢をボウガンにセットし始めた。かなり練習を積んでいたらしく、その手際はたいへん良かった。
くそっ、この薬、本当に効くのかよ。とっとと足の痛みが引いてくれねえと、走ることすらままないんだぞ。
そんなことを思ったとき、彼の身体の中で異変が起きた。
液体を注入した方の足の感覚が薄れ始め、ボウガンに抉られた皮膚の痛みも消えていく。直後、痺れのような感覚を覚えたかと思うと、それは徐々に身体の他の部位へと浸透していき、やがては全身にまで広がってしまった。
頭の中が洗浄されて、軽くなった身体が宙へと浮くような感覚。
目に見える景色は微かにぶれて、全体的に白みがかったように映る。
龍輔にはそれが、生涯かつて感じたことも無いような至高の快楽であるように感じた。
こいつが、噂に聞いた『白き悪魔の抱擁』か。
気が付いた時には、足に感じていたはずの痛みなど、もはや微塵も残されてはいなかった。
体内へと送り込まれた薬物が体中の細胞や神経を刺激し、五感から得られる情報を薄めてしまったために、そのような現象が起こったのだ。
悪魔の薬を服用したことによって起こった、身体の変化はこれだけではない。
薬は、体中の筋力を増強させるという、まるでドーピングのような効果をも存分に発揮していた。普段よりも肉体が引き締まっているのが自分でも分かる。
これら自身に起こった異変を実感すると、龍輔はたまらず声を出して笑い出してしまった。体内へと注入されたホワイトデビルは微々たる量だったが、それでも彼の想像を遥かに超えるほどの効力を発揮していたのだ。
俺はとんでもない力を手にしてしまった。負ける訳が無い。負ける気がしねぇ。
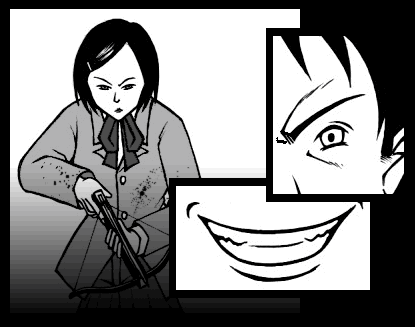
「何がおかしい!」
劣勢状態であるはずの龍輔が笑い出したのを見て、これまで冷静だった和歌子もさすがに不快を感じたらしい。
脅しをかけるようにボウガンを標的へと向け直すその表情は、これまでにないほど怒りに満ちていた。
「へっへっへ、何がって? なぁに、お前の最期が近いと実感して、ちょっとおかしく思っただけだ」
「馬鹿な。その傷ついた足では満足に動くこともできないくせに」
「痛みぃ? そんなもん、こいつのおかげで既にきれいさっぱり消えちまってるぜ」
龍輔は空になった注射器を和歌子に見せつけた。
「注射器……、まさかさっきあんたが自分に打ってたのは鎮痛剤か何かの類か?」
「鎮痛剤か。まぁそんなところだと言っておこうか」
足の痛みが引いたため、龍輔はゆっくりと立ち上がり、再び和歌子と対峙した。そして懐に隠していたもう一つの武器、ファイティングナイフを取り出して、構えた。
「さあもう一発撃ってこいよ。もっとも、もはや痛みを感じなくなってしまった俺を倒すには、一撃で仕留める必要があるがな」
「中途半端に傷めても無意味ってことか。仕方ないね、まさかこんなにも早く使うことになるとは思ってなかったけど、私の方も切り札を出させてもらうよ」
和歌子はボウガンにセットしていた矢を外すと、デイパックの中から取り出した別の矢にすばやく付け替えた。
「毒矢よ。いくら痛覚が麻痺しているあんたでも、この猛毒が体内へと進入すれば、なすすべなく苦しみもがき、そして死ぬこととなる。ボウガンの特別付録として、たった三本だけ支給されていた貴重品よ。感謝しなさい。薬に溺れたあんたのことを、切り札を使うに相当する相手だと過剰評価してあげてるんだからね」
勝利を確信しているのか、和歌子は話しながらにやりと笑んでいた。
「まだそんなおっかねぇ物を隠し持っていたのか。だが、結果は変わらんと思うぞ」
同じく余裕の笑みを浮かべていた龍輔だったが、凶器を構える相手をしっかりと見据え、強く地を蹴ってイノシシの如くまっすぐ突進し始めた。
「ほざけ!」
和歌子の大声と同時に、ボウガンの上でスタンバイしていた猛毒の矢は発射された。まるであらかじめレールが敷かれていた電車のように正確に、標的の身体の中心へとまっすぐに飛んだ。
ほんの僅かなズレもない矢の軌道上で走っている龍輔には、本来ならそれを避けれるはずがなかった。だが、悪魔が彼に与えていた信じられない力が、予想し得なかった展開を招く事となった。
ホワイトデビルによって神経を刺激され、筋肉を増強された足はとんでもない瞬発力を生み出し、いつもとは比較にならないほどの素晴らしきスピードで彼を動かした。そのすばやさは学校一のスプリンターである和歌子と同等、いや、もしかするとそれ以上だったかもしれない。
高速で向かってくる猛毒の矢を、素早い動きで上手く避けた龍輔は、そのまま勢いを緩めることなく突っ走る。
薬の力など知りもしなかった和歌子は、避けられるはずがなかった攻撃が外れた事に驚き、目を大きく見開いた。
予想だにしなかった事態を前に、もはや次の矢を装填する時間すらない。
迫り来る敵に恐怖してしまった和歌子は、矢のセットされていないボウガンを投げ捨てて、急いで拾い上げた園芸用シャベルを振り下ろし、抵抗するしか手段は無かった。
和歌子の渾身の力が込められたシャベルの先端が、龍輔の頭をかち割ろうと急接近する。だが先ほどと同様に、とんでもないほどの身体能力向上をはたした彼は、すばやく和歌子の背後に周り込む。振り下ろされたシャベルは標的にダメージを与える事も無く、むなしく宙で空振りしただけとなった。
相手の背後へと回り込んだ龍輔は、体制を整える暇すら与えず、和歌子の首に腕を巻き付けて捕らえた。
和歌子は逃れようと龍輔の腕を首元から引き剥がそうとするが、もともと喧嘩で鍛えられていたうえに、薬によって増強されていた太腕はびくともしない。
「馬鹿な! こんなことが……!」
勝利を確信していた彼女は、突如裏返った優劣に信じられないといった様子だ。
「いい様だな、山崎。いつも勝ち気なお前が悔しがってるのを、まさかこうして間近で見る事になるなんてな」
「何故だ! 矢の狙いに間違いはなかったはずよ! どうしてお前はあの距離から避ける事ができたんだ!」
首を締め付けられて表情を歪めている和歌子が、悔しそうに吠えるのを見て、龍輔は薬が与えてくれるものとは別の快感を感じた。
「いいだろう。死に土産として一つだけ教えてやる。俺はな、悪魔と契約したのさ」
「悪魔との契約だと? どういうことだそれは!」
「これ以上は教える義理は無ぇな。あの世に行ってから、その陳腐な脳で一生懸命考えるこった」
龍輔は皮肉タップリにそう言うと、和歌子の首に巻きつけていた腕の力を一気に強めた。すると彼女は目を見開いて何か唸っていたが、首からゴキリと何かが砕けるような音が聞こえたとたん、見開かれていた目から色が失われた。
龍輔が腕の力を抜くと、和歌子の身体は力なく地の上に倒れた。
三人姉妹の一番上である和歌子は、その力強くたくましい風格から、祖母にもっとも信頼されていた。
祖母にとって初めての孫であった和歌子は、小さな頃からあり余るほどの愛情を注がれてきた。そのためか、和歌子の方も祖母の事を大切に思い、それは老い衰えがいくら目に見えるようになってきても変わることはなかった。
和歌子が中学校に入学した直後、祖母は突然の病に倒れた。以来、歩くどころか立ち上がることすらままならず、寝たきりとなってしまった。それがいけなかった。
以前から物忘れの多さが気になっていた祖母だったが、寝たきりになってしまったことにより、まだ正常ライン上で持ちこたえていた意識が、だんだんと崩れだした。痴呆症の始まりだった。
日に日に物忘れは酷くなっていき、今は何月だとか、飯はもう食べたかとか、そういうことが分からなくなり始めて、果ては、頭の中に深く根付いていたはずの、孫と過ごした楽しき日々の思い出すら消え去り始めた。
それを知った和歌子は悲しんだ。
日に日に衰えていく老婆の姿を目にするたびに、ぶつけようのない憤り感じた。
何とかして祖母を元に戻す事はできないだろうかと考えた和歌子は、ふとあることを思い出した。
祖母は無類のスポーツ観戦好きで、自分も昔は町中を走っていたという理由から、とくにテレビで流されるマラソン中継なんかは欠かさずに見ていた。
「おばあちゃん、私、今度の県内マラソン大会で絶対に優勝するよ。居間のカレンダーよりも大きな賞状を持って帰ってくるから、元気なままでその日まで待っててちょうだい」
布団のそばでそう言うと、病状を進行させながらもまだなんとか意識を保っていた祖母は、間違いなくにっこりと微笑んで頷いてくれた。
以来、陸上部に所属していた和歌子は、これまで以上に一生懸命になって走り始めた。すべては祖母とした約束を果たすため。
マラソン大会まであと数日、そんな十月のある日に事件は起こった。松乃中大火災。
和歌子は燃え盛る校舎の中から、なんとか生きて逃げ出す事はできたが、瓦礫に躓いて転んだときに足首を捻ってしまい、入院しなければならなかった。そのため、マラソン大会当日、スタートラインに並ぶ群衆の中に和歌子の姿は無かった。
和歌子は退院後、家に帰るやいなや祖母の部屋へと入り、約束を果たせなかったことを詫びようとした。
おばあちゃん、残念がるだろうな。
悔しがる祖母の顔を思い浮かべると胸が痛んだ。だが神は何を思ったのか、さらに残酷な展開を和歌子に用意していた。
「あんた……誰だい?」
目の前で頭を下げている少女の事を、自分の孫だと理解できていないらしく、祖母は不思議そうな目をしてこちらを見ていた。
和歌子が入院している最中に、祖母の様態は驚くほどのスピードで悪化しており、もはやすべてが手遅れの状態にまでなっていたのだ。
後に、火災の原因は放火である疑いがあるとの見解が世間で高まると、和歌子はいるかどうかも分からない犯人に対して怒りを抱くようになった。
あの火災さえなければ、私はおばあちゃんとの約束を果たせていた。そして喜ぶおばあちゃんの優しい笑顔を、もう一度見ることができたはずだ。私は、あの火災を引き起こした犯人を、絶対に許さない。と。
だが彼女は運悪くプログラムに巻き込まれてしまい、火災の真相を知る事もできずに命を落とす事となった。
「ハーッハッハッハッハ! こいつは凄ぇ! この薬、まさかこれほどまでにとんでもない効果を発揮するとは! 負けねぇ! これなら誰にも負けるはずがねぇ! 俺は今、最強の身体を手に入れたんだ!」
地に伏したままもはや身動き一つとしない和歌子の亡骸のそばに立っていた龍輔は、喜びと快楽に酔いしれて、天に向かって大きく吼えた。
 山崎和歌子(女子二十二番)―――『死亡』 山崎和歌子(女子二十二番)―――『死亡』
【残り 三十一人】
|
