私達は時が経つのも忘れて、互いのことについて色々と語り合った。
プログラムの後から今日まで、どのようにして過ごしてきたのか。どんなことで泣いて、どんなことで笑ったか。
しばらくして木田は突然立ち上がり、そして言った。
「さて、そろそろ私は出るとするよ」
「えっ、もう帰っちゃうの?」
私は木田を引き留めようとするが、首を振って断られてしまう。
「家内が待っているからさ。この後、食事に行く約束をしていてね」
「そっかー。じゃあ仕方がないね」
結婚してから二十年以上、一緒に過ごしてきた木田夫婦の仲は未だに良いらしい。
木田は竹倉学園の火災で息子を亡くして受けたダメージを、梅林中プログラムの際はまだ引きずっていたらしいが、支え合えるものが存在したおかげで苦しみから抜け出すことができたようだ。
彼に今一番大切なのは奥さんだ。もう少しここに居てほしいという気持ちはあったが、不倫みたいになってしまうのは嫌だし、潔く帰してあげることにした。
「明日香さんはまだ残るのかい?」
木田は長財布から札を取り出そうとしている。
「もちろん。私が今日ここへ来た目的はまだ達成されていないから」
「そうだよね」
と、彼はテーブルの上に札を二枚置いた。お茶代二人分である。
「あらら、そんな気を使ってもらっちゃあ悪いわよ」
「いいから、いいから。じゃあ元気でね」
そして木田は席から離れ、出口のほうへと行ってしまった。
「ご馳走様、パパ」
ふざけて言うと、彼は最後に手を振って応えてくれた。
木田が店から出ていってから、私は参考書との睨めっこを続けていた。辞書を引きながらなので、ドイツ語の文章を辿る目線はなかなか進まない。
私は頭を掻きながらコーヒーを一口だけ啜った。なぜ三杯目は例の蜂蜜ティーにしなかったかというと、単純に温かいものを飲みたくなったから。
「ありがとうございました」
会計のためにレジに立っていた女性店員に見送られ、客が一人、外の通りに出ていく。
夕方となって日が沈みかかり、店の中にいる客の数はだいぶ少なくなっていた。
もう少し粘っていたら貸し切りみたいになるかしら。
なんて考えながらまた参考書に目を落としたとき、店の奥から男性店員が出てきた。つい先程までエプロン姿だったのに、今はコートを羽織って首にマフラーを巻き、いかにも外行きの格好になっている。
「あ、時間ですか?」
女性店員が問い掛けると。
「ああ。悪いね、後を任せちゃって」
と男性店員が手を合わせる。
「しかし本当に一人で大丈夫かい?」
「ええ。この時間になればもう閉店までそんなにお客さんも来ないでしょうし」
「そうかい。なら俺は安心して行くけど、閉店時の戸締まりだけはしっかりね」
「任せてください」
女性店員が元気よく自らの胸を叩くと、男性店員は優しく笑って扉をくぐっていった。
会話の内容からすると、やはり男性が店長で、女性がアルバイトなのだと分かる。
「お勘定お願いします」
店長が出ていってから間もなくして、大学生と思わしきカップルがレジにやってきた。それとほぼ同時に「すみませーん、メニューください」と店内の中央部の席に座っていた女子高生集団の一人が手を挙げる。
新規の客が来なくとも、アルバイト少女一人で店を回すのは大変そうだった。
店内の壁面には古びたランプがいくつかかかっている。オレンジ色に光る炎が揺らめきながらテーブルの上を照らしてくれて、ある種の趣が感じられる。しかし照明器具としては頼りなく、日が完全に落ちてしまうと少々薄暗い。食事するだけならそれでもさほど問題は無いだろうが、書物の文字を読むとなると大変だった。
私は諦めて参考書と辞書を閉じ、鞄の中にしまう。
「申し訳ありません。お客様、そろそろ閉店の時間でございます」
奥の席に座っていたOL風の客に向かって、店員が申し訳なさそうに頭を下げている。
「あれ、ここっていつもは八時過ぎまでやっているはずでしょ。まだ七時にもなっていないけど……」
驚いた様子でOLは時計に目を向ける。
「おっしゃる通りなのですが、本日は十九時から貸し切りの予約が入っておりまして」
説明を聞いて、OLは冷めきった紅茶を一気に飲み干し、渋々と立ち上がった。
「恐れ入ります」
会計後、店員は深々と頭を下げてOLを送り出す。
私を除くと、それが本日最後の客だった。
「さて」
店員はレジを閉めると私の方へと歩み寄ってくる。
「お客様、本日は……」
「分かっているわ。お会計でしょ?」
相手の言葉を遮って財布を開こうとする。しかし突然、店員の腕が伸びてきて、私の手は動きを封じられた。
「ご冗談を……」
彼女は私の前に回り込み、目を見つめて微笑んだ。
「本日は当店にお越しいただき、誠にありがとうございます。感謝の意を込めまして、独断により本日はお客様一人のために貸し切りとさせていただきました」
その芝居がかった言動に、私は思わず吹き出してしまった。
「あはは。閉店って言うからどうするのかと思えば、なるほど、そうやって二人っきりになれる時間を作ったわけね」
相手の目を見つめ返して言った。
「春日さん」
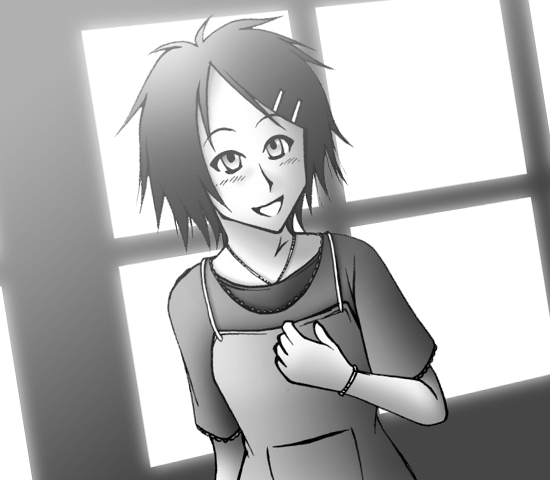
すると店員もまた、私のほうを見ながら吹き出す。
「違うわよ。今の名前は木村恭子。春日千秋は六年前に死んだわ」
「ああ、そうだったわね。うっかりしてた」
拳で自らの頭をコチンと叩く。
そう、喫茶店でアルバイトをしていたこの女性の正体は、梅林中プログラムの中で私と共に戦った少女、春日千秋なのであった。
彼女とは手紙でたまに連絡を取り合っていたが、実際に会うのはプログラム以来なので、六年ぶりとなる。
「それにしても久しぶりね。元気にしてた?」
つい数時間前まで木田が座っていた席に、千秋はおもむろに腰を下ろした。
「その話題はあなたが働いている間に、木田さんと二人で散々したんだけどね」
「いいじゃない、あたしはそれに参加できなかったんだから」
「でも、どうせ聞き耳立てていたんでしょ」
「まあね。久々に蓮木さんたちに会えたんだから、そりゃあ仕事だけに集中なんてできないよ」
窮屈なのか、千秋は話しながらエプロンを脱ぐ。
「それにしても、蓮木さんったら砕けたよねぇ」
「砕けた?」
ニヤついた顔を向けられるも、相手が何の話をしているのかピンとこない。
「ほら、木田さんに向かって『パパぁ』ってさ。昔の蓮木さんは今より堅くて、こんな冗談なんて口にしなかった」
そういうことか、と私は心の中で相槌する。
「六年会わないうちに変わったね」
「あらら、幻滅した?」
「ううん。元気そうで安心した」
千秋は腕を伸ばして、テーブルの上で組んでいた私の手を強く握ってきた。先程皿洗いをしていたせいか、ちょっと冷たい。
「大学の獣医学部、本当に入れたんだね」
大学に関してはこちらからの手紙に記したことがある。しかし、参考書を読みながら勉強している私の姿を見るのは、千秋にとって今日が初めて。
「さっき読んでいた本、凄く難しそうだね」
「私にしてみれば楽勝よ。人生のキャリアが違うもの」
千秋に握られて冷えた手を、今度は逆に千秋の手の上から重ねてやった。
「春日さんも仕事頑張っているみたいじゃない。ここのお店の仕事って、自分で探して見つけたんでしょ?」
「そうだよ。といってもこの店の前を通り掛かったのは単なる気まぐれで、そこに偶然アルバイト募集の貼り紙があったというだけなんだけどね。ちょっとした料理ができて、尚且つ時給が良いからさ、即座にここで働こうって決めたんだ」
「へぇー。じゃあさ、春日さんが来るまではさ、店長さん一人で店が回っていたわけ?」
「ほんの一瞬だけね。前のアルバイトが辞めてから二週間後にあたしが入ってきたらしいから」
「でも二週間だけと言ったって、店長さん一人でやっていくのは大変だったんじゃない?」
「大丈夫だよ。凄く仕事のできる人だから。以前ホテルのレストランで働いていたらしくて、特にフライパン捌きの凄さにはビックリさせられたよ。あ、でもトイレに行きたくなったときとかは、一人だと大変だったって言っていたな」
千秋の語り口調はとても熱心だ。最初は、久々に私に会えたために興奮しているのかと思ったが、どうやらそれだけではなさそうだ。
「さてはあなた、あの店長のこと好きなんじゃない?」
話を遮るように言ってやると、千秋は魔法でもかけられたかのように、ぴたっと口の動きを止めてしまった。
「なっ、ななななななな……」
慌てながら訳の分からないことを言い出した相手を見て、図星だったのだと確信した。
「なるほどね。店長さんそこそこイケメンだったもんね。そのうえ料理という趣味が合えば、そりゃあ惹かれちゃっても仕方がないか」
からかってやると、千秋は両手をぶんぶんと振って、力いっぱい否定しだした。
「そ、そんなのとっくの昔の話だよ。彼が前のアルバイトの子とくっついているって、働き始めて一ヶ月も経ったころには知っちゃっていたし……。今は何とも思っていない」
なるほど、中学生の頃は恋愛とは無縁そうだった彼女も、ここ六年の間に大きく変わっていたようだ。
「なによ、その目。蓮木さんだって好きな人くらいいるんでしょ」
私の薬指にはめられた指輪を見ながら、千秋は眉を寄せた。
「ノーコメント。私の話なんて面白くも何ともないでしょうから」
「あ、ズルイー。あたしの方は話したのにー」
千秋はテーブルの向かいから身を乗り出して、私の頭をポカポカと叩いた。
大して中身の無い会話であるが、なぜだかとても楽しい。中学時代の私は、転校してから妙にツンケンとした調子でいたため、クラスメートが気さくに関わりを求めてくることなんてほとんど無かった。今になって思えば、当時の私は自分のせいで損ばかりしていた。
もしもこの世にタイムマシンが存在するならば、中学時代の蓮木風花に注意しに行ってやりたいくらいだ。
「なんだか楽しそうだね」
千秋が私の顔をじっと見ている。どうやら無意識のうちに顔の筋肉を緩めてしまっていたらしい。
「そりゃあ楽しいわよ。昔だったら話せなかったようなことが、今なら不思議とすんなりできる。なにもなも見えていると思えた場所から、新たな発見が次々と出てきて、まるで宝探しでもしているかのようなんだもの」
両手を胸元にもっていくと、心臓の鼓動がはっきりと分かった。いつもより激しく感じられるのは興奮のせいだろうか。
生きることって素晴らしい。楽で単純に思ってしまいがちだが、その日その日を生き抜くことは実は容易ではなく、しかしその分、様々な記憶が私の中に刻まれて、大きな感動が育まれていくのだ。
今、私はとても幸せだ。
「じゃあ今日は、あたしと蓮木さんが再び会えたこの素晴らしい日を祝うために乾杯するとしましょう」
と千秋は立ち上がって言った。そして急に、仕事中のような丁寧な口調になる。
「本日はより腕を奮って、私自慢の料理の数々を用意しますので、どうかゆっくりとお楽しみください」
「……もしかして、お店を貸し切っちゃったのは、これをするためだった?」
聞くと千秋は大きく頷いた
「ええ、店長が私用で店を空けることを前々から知っていたからね。あたしの好き勝手にやらさせていただいちゃいました」
満面の笑みを浮かべている千秋もまた幸せそうだ。
「お客様、ワインはお飲みになりますか?」
「わざわざ買ってきたの? そうね……、今日のメニューは何なの?」
「鮭のムニエルをメインに、野菜スープとライス、あるいはパンをセットで出させていただくつもりです」
「ああ、店の外に貼紙してあったセットね」
鮭のムニエルと野菜スープは本日のお勧めメニューであった。
「ここでバイトしている間に覚えたメニューなんだけどね。今では得意料理の一つになっちゃったよ」
「へぇー。それじゃあワインもいただきましょうか」
二人の笑い声が行き交う中、楽しい一時は過ぎていく。
「またいつか、自分の店を持てるといいね」
「うん。もう店の名前も考えてあるしね」
「なんて名前?」
「んーとね、松乃屋」
料理はとても美味しく、野菜の欠片も残さないほど、きれいに平らげてしまった。
すっかり夜がふけていたが、あまりに話に夢中になりすぎて、時計を見なければどれほど時間が経過したかも分からない。まさに夢のような一時だった。
|
