「もうすぐって、いったい何が起こるというのよ!」
霞の意味深な発言を受けて、千秋は困惑気な表情を浮かべながら問いただす。
命に関わるほどの大怪我を負いながらも、微かに笑みすら見せる霞を前に、得体の知れない不安を感じずにはいられなかった。
「ねぇ、黙っていないで何とか言ってよ!」
地面の上で仰向けになったまま、荒い呼吸をひたすら繰り返す霞に向かって、さらに強く言及しようとした。
その時、どこかから何かが爆発したかのような轟音が聞こえてきた。
「えっ。な、何……今の?」
遅れてやってきた微かな地響きを足の裏で感じ、千秋は動揺しながら辺りを見回した。そんな短い間にも、同様の爆発音が二度、三度と連続して起こる。
「煙……」
上空に起こっている異変にいち早く気が付いたのは怜二だった。
彼が指差す方向に視線を走らせると、確かにだだっ広い曇り空の中心に黒煙が上がっているのが確認できた。千秋達の四方を囲む木々に邪魔されて下の方は見えないが、どうも分校のある辺りから立ち上っているらしい。
「午前七時二十九分……。若干の狂いはあるけれど、ほぼ計画通りね……」
時計の盤面に目を落としながら呟く霞。
「まさか、あれはお前の仕業なのか? 答えろ。今の爆発はいったい何なんだ?」
興奮気味に問いただす怜二。瞬間的に大気中を駆け巡った大音響に驚かされたためか、若干冷静さを欠いている様子だった。そこにさらに千秋も質問を並べる。そんなに一遍に聞いたところで、霞がすぐに答えられるはずもないのに。
「復讐がまだ終わっていないって、どういうことよ? いったい何を企んでいるというの?」
落ち着くべきだと気付いたのは、疑問の全てを霞にぶつけた後。そしてそれは怜二も同じだった。
霞が微笑む。
「……まさか、クラスメートたち全員を殺すことだけで、私の復讐が終わるとでも思っていた?」
そんなわけ無いでしょうに、とでも、さも言いたげな口調だった。しかし当然のように言われても、千秋には一切理解できない。
「私が復讐の対象と定めていたのは、自らを除いたクラスメート全員。そして、もう一人……」
「えっ……? もう一人って……」
素っ頓狂な声を思わず上げてしまう。いったい霞が誰のことを言っているのか、全く見当がつかなかった。
「あなた達が知るはずも無いわ。私が“彼”を復讐の対象に加えたのは、本当につい最近のことだったから……」
「勿体振っていないで教えろ」
眉間にしわを走らせながら怜二が問うと、霞は一拍置いて憎々しげに答えた。
「田中一郎……。今回のプログラムの最高責任者であるあの男よ……」
「えっ!」
思いがけぬ回答に千秋はまた驚かされた。
田中といえば、梅林中三年六組のメンバーをプログラムという地獄に落として苦しめ、尚且つ霞に復讐の機会をわざわざ与えた人物。
プログラム参加は、霞にとって願ったり叶ったりの話であっただろうし、田中が復讐の対象とされなければならない要素などとくに無いように思える。少なくとも千秋にとっては解せない話であった。
「分からない……。眠らされて、無理矢理この島に連れてこられた私達ならともかくとして、どうしてあなたが田中のことを恨むのかが」
すると霞は微かに笑った。何かに対して面白がっているわけではなく、怒りを通り越した複雑な感情の表れだったかのように感じた。その形容し難い不気味さは、千秋をぞっとさせるには十分だった。
「確かに、田中が提示してきた案自体は私にとって都合が良かったし、彼に対して感謝の思いを抱かずにはいられなかったわ……。でも、その直前に抱いてしまった憎しみのほうが、あまりに大きかった……」
そして彼女は悔しそうに歯を食いしばる。
「ある日、プログラムの開催と参加権利について私に伝えるため、田中が病院へとやってきた……。その時の……あいつが病室の戸を開いて初めて私の姿を目の当たりにしたときの目つきが、とてつもなく気に入らなかった……」
常軌を逸した返答に、千秋は戸惑いを隠せない。
「それだけなの? 田中を殺そうと決めた理由って」
人間一人を殺そうと思い至るまでの過程があまりに短絡的過ぎる。少なくとも、常人の感覚レベルからは逸脱していた。千秋が戸惑ってしまうのも無理はない。
「それだけ、ですって?」
しかし、霞は反発の様子を見せた。まるで自らの感覚のほうが正常だと主張するかのように。
「あなたに私の気持ちの何が分かる? 日常という幸せのレールから突き落とされて、化け物を見るような目つきを四方から浴びせられた苦しさなんか、想像もできないくせに!」
そうだ、あまりに異常な動機にばかり囚われて忘れてしまってはいけない。全身火傷を負って本来の姿を失ってしまった霞の辛さを。
心を開いていた相手から、ある日から突然冷ややかな目を向けられるようになるなんて、どれだけ悲しいことだろう。彼女の位置に自らの姿を当てはめて考えてみれば、なんとなくだが見えてくる。
全ての髪が焼け落ちて、爛れた肌に支配された身体。鏡越しにその姿を見て涙する私に、誰かが冷たい視線を投げ掛けてくる。私が恐る恐る振り向くと、そこにいたのは、真緒、智香、葉月を始めとする沢山の友達……。ああ、駄目だ……辛すぎる。これ以上は恐ろし過ぎてとても想像なんかできない。しかし紛れも無く、霞はこんな辛いことを実際に体験しながら生きてきたのだ。
「松乃中大火災以来、私はその冷ややかな目つきを極端に忌み嫌うようになった。そんな中で起こった一件よ。病室を訪問しに来た田中はあろうことか、私がこの世で一番憎んでいるその目つきを、一瞬とはいえ見せやがった」
力の入らなくなった拳を、弱々しく握り締める彼女。
「田中の目が言っていたわ。ああ、なんて酷い姿をした化け物だろう、って……。そんなことを思った上で、奴は私のことを殺しの道具として利用しようとしたのよ。こんなこと、許せる訳が無いわ……」
最後の方の声は上擦っていた。過去の辛い記憶を思い出し、当時の悲しみが鮮明に甦ってきたのだろう。
霞の行いが正しいものだとは決して言えない。しかし、凶行に走ってしまいたくなるような深い感情については、なんとなく理解できるようになってきた。あまりはっきりと言うべきではない話だが、もしも自分が霞と同じ境遇に立たされたなら、やはり誰かを殺さずにはいられなくなっていたのかもしれない。クラスメート達、田中、親友、そして自らをも――。
もちろん、考えたくも無い話だが。
「まあ、そんなわけで私は田中を殺そうと決めたわけよ。……そうそう、さっき聞こえた爆発音だけど、あれはあなたたちが島に連れられて来られるよりも以前に、私が校舎に仕掛けていた爆弾が破裂した音ね。プログラムが終了するであろう頃を見計らって時間を合わせていたのだけれど……、驚いたことに、タイミングはほぼバッチリだったみたいね」
あっさりと言う霞。だが怜二は解せない様子。
「まさか……。何十人も兵士がいる中で、そんな容易に爆弾なんて仕掛けられるものなのか? プログラムが開始されるまで、政府側だってお前のことを自由にしているわけではないだろう?」
「もちろんよ。一応兵士の一人が傍にいたわ――。付き人だとかほざいていたけれど、実質あれは監視だったのでしょうね……」
「だったらやはり、お前には自由に動く隙なんて無かったはずじゃ……」
「それがあるのよ。上官である田中は私を信用しきっていたし……、だから監視がいたとは言っても、それは本当に甘いものだった。それに、私はこの姿をなるべく人目に晒したくないからとか適当な理由をつけて、奴らに用意させた部屋に閉じこもっていたしね。一人になれさえすれば後はどうにでも行動できたわ。天井裏を通じて移動することも、お手洗いに行くふりをして本部近くに爆弾を仕掛けることもね」
復讐を達成させるためならば、どんなに危険な死線すらも潜り抜けて見せるという、彼女の決心が垣間見えた。
「爆弾はいったいどこで調達したと言うんだ?」
「あらかじめ、この島に来る前から用意していたわよ……。好都合なことに、私が入院していた病院には、材料となる薬物などがいくらでもあったし……。島に持ち込むこともそんなに難しくはなかった。私が女であることを利用して、これまた適当な事情を述べてみれば、兵士の男どもは、むやみやたらに身体検査はおろか、荷物の中身もチェックしなかったわ。殺意がたっぷりと込められた爆弾が詰まっていたとも知らずにね」
「適当な事情ってのは?」
聞くと、霞がニヤリと笑んだ。
「性的なこと……って言えば分かってもらえるかしら? ちょっと恥ずかしがっているような仕草を見せれば、いくら私のことを化け物扱いしている彼らでも、深く探りを入れてはこなかったわ。プライバシーに関わる部分までは踏み入り辛かったのかしら」
「だが……」
怜二はまだ納得できていないようだ。
「そんなずさんな計画、今回はそれで上手くいったから良かったものの、失敗する可能性だってあっただろう? もしかしたら政府は荷物のチェックを強行するかもしれないし、お前に一人きりになる時間なんて与えないかもしれない。もしそんなことになったら、計画は全て失敗に終わる、と事前に考えたりはしなかったのか?」
「もちろんそういうことも想定したわ。だからこちらがプログラムに参加する変わりに、田中には私用の個室を用意することを約束させた。荷物チェックも確かに危ういと思ったから、爆弾そのものをヌイグルミの中に仕込んだりと偽装を施した……。でも、そこまでしてもこちらの思惑を見抜かれることはあったでしょうね……。そうなったら、その時は……」
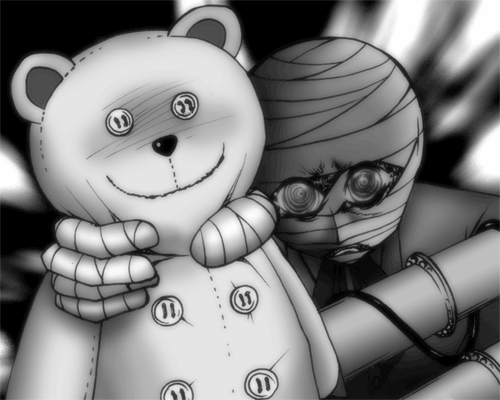
次の言葉を発するまで霞が一呼吸入れている間に、千秋は得体の知れぬ緊張感を覚えた。
「仮に気付かれたならあらゆる強硬手段をとるつもりだったわ――。最悪の場合、田中もろとも自爆する覚悟すらあった……」
強い決意で塗り固められていたその言葉は、まるでコンクリートのように硬く感じられる。
霞は自らの命も惜しまずに、復讐に関することのみを考えて過ごしてきた。それが彼女にとって唯一の、生きるための活力源だったのである。
自分と同じ年に生まれた、同じ性別の子なのに、一つの悲劇でここまで生きる世界が違ってしまうものなのか。
友の死を噛み締めながら、楽しかった頃の思い出を糧に生きてきた自分とは、そもそも比較にならなかった。
額に浮かんできた汗を親指で拭う。
「ふふ……、思えば長い戦いだったわ。あの火災が起きてから二年間、よく今日まで耐えてこられたものだと思う」
しみじみと言うと、霞はゆっくりと瞼をつむる。
「でもようやく、これで私の中の戦いは終わり――いや、当初の標的に含まれていたあなたたちをまだ殺せてはいないけれど、それはもういいや……」
疲れた、と霞が溜息のように漏らす。
脱力しきった身体から、生気が水蒸気のように上がっていく様が見えた気がした。彼女の中にあった復讐心が完全に冷めてしまったためだろうか。少なくとも、一連の語りが始まる前と後では、顔付きが明らかに違っていた。いくら包帯の下に肌が隠れているとは言っても、そのくらいの変化は認識できる。
時間が経つにつれて、体力と気力の両面で衰えが進行していったのだろう。
「なぜだろう……急に目が霞んできた……」
一度閉じた目を開かせる霞。
全身からの出血具合からして、これ以上生を継続させることは極めて難しいように思える。それを理解したうえで、彼女は自らが生きた世界の光景を、最後に記憶として焼き付けようとしているのだろうか。
「駄目ね……、もうほとんど何も見えない。思考も働かない……。真っ黒い煙のようなもやが、薄っすらと見えるだけ……」
あながち、それは間違いでは無かった。霞が見上げる空は事実、分校から立ち上る黒煙に支配されていのだから。
すうっ、と深呼吸をするかのように、霞が大きく息を吐いた。そうかと思えば、直後には寝息のような弱々しい息遣いに変わる。復讐劇から退いた彼女は、穏やかな大気の渦に流されるままに、眠りにつこうとしているのか。その安らかさは怪我の具合とはあまりに不釣合いだった。
安息の時を、怜二と千秋は並んで見守る。今までいくつもの辛いことがあったが、可哀相な少女――霞の最期が安らかであれば、全ての出来事も少しは浄化されるような、そんな気がした。
「……ん……」
意識の殆どを失って、時折うなされているような声を上げるだけとなった少女。
殺気の抜けた顔を見ていると、やはり自分と同じ十代の女の子なんだな、と思った。
千秋が見つめる目の前を、突然何かが通過する。小さな白い蝶だった。穏やかな空気の流れを受けて踊る草木の間を、優雅に元気に飛んでいく。分校から煙が上っている以外は、辺り一面に至極平穏な光景が満ち溢れていた。地獄の中のような今日までの出来事が、まるで夢か幻だったかのよう。
心に刻まれた傷が消えることは無いだろうけど、ほんの少しは癒えた気になった。
「……何かが……聞こえる」
そんな中、ふいに霞が寝言とは異なる声を発した。千秋はすぐさま振り向く。突然のことを不審に思うと同時に、ある種の不安が頭をよぎった。
「どうしたの?」
すると、霞の表情がみるみるうちに恐怖に汚染されていく。
「何かが焼けるような音……、感じる……煙の臭い……」
千秋が予想もしなかった事態が起こったのは、この直後だった。
「燃えて……るの? 燃えてるの? 燃えてるの?」
半ばパニック状態に陥った様子の霞は、両手で顔を押さえながら、さらには声を上げて喚き始めた。
「ひっ、嫌ぁっ! 嫌だぁっ! 消してっ! は……早くっ!」
怜二と並んで唖然とするしかなかった。
彼女は分校が燃える音と、そこから立ち上っている煙の臭いを感知して恐がっているようだった。しかし訳が分からない。分校が炎上するように自ら仕組みながら、どうして過剰とも言えるほどそれに恐怖を抱くのかが。
「落ち着け、御影! 燃えているのは分校だ! ここは関係ない」
怜二は霞を落ち着かせようとするが、少女は静かになるどころか、さらに声量を上げるばかりだった。
「誰か、助けて! 焼ける! 焼けちゃうよ! 嫌だ、誰かっ! 誰かぁぁぁぁぁぁぁっ!」
ここまでくると、もう異常としか思えなかった。
霞は寝転がったまま悶え、全身を激しく掻きむしった。
「嫌ぁぁぁぁぁぁっ! 私の顔がっ! 腕が! 足が! 髪がぁっ! 身体がぁぁぁぁっ!」
爪を立てて掻いた箇所の包帯が破け、下から爛れた肌が姿を覗かせる。
「駄目だ! 力ずくで押さえるぞ」
そう言って、怜二は霞の両腕を掴んで無理矢理動きを止める。千秋はすぐに、じたばたと地面を蹴り続けている両足を押さえた。
「ねえ、御影さんどうなっちゃったの?」
怜二が苦い顔をした。
「……気になっていたが、こいつの身体、普通じゃない! くそっ、まさかあの薬物か!」
「薬物って?」
「白い悪魔――ホワイトデビルのことだ! 鎮痛や筋力の増強に使えるため支給武器の一つとされていたらしい。かつて黒河が所持しているのを見たが……、御影のやつ、あんな物まで手にしていたとは……」
千秋は、とある霞の言葉を思い出した。
『私、悪魔に魂を売ったの』
もしや、あの発言の意味って……。
「つまり御影さんは一時の力を手に入れるために、悪魔の薬に手を出した。ということ?」
「ああ。しかも筋肉の異常な膨らみ方からして、一度や二度注射しただけとは思えない。血を流し過ぎて意識が朦朧とする状態の中で、幻覚など副作用があるホワイトデビルを、何度も体内に流し入れていたならば、それはとても大変なことだ」
暴れる霞を力で押さえることは容易ではない。相手は肉体を強化しているのだ。負傷している千秋はもちろんのこと、それなりに腕力がありそうな怜二ですら、すぐに振り払われてしまう。
「火の存在を近くに感じて、彼女の中で過去の記憶がフラッシュバックしているのか……。ダメだ、とても押さえきれない。」
霞は今まさに、二年前のあの日を繰り返して体験している。大地を震わせてしまいそうなこの絶叫も、過去の彼女が実際に発したそのものに限りなく近いだろう。
「嫌だ……そんな……」
炎に苦しむ同級生を間近に見て、千秋の中にもかつての地獄絵図が鮮明に甦ってくる。
燃え盛る炎の熱。人体の焼ける臭い。そして聞こえてくる幾多もの呻き声。千秋は見た。瓦礫に押さえ付けられた親友の側で嘆いている、二年前の自分達を。
「ひっ……」
短い悲鳴を上げつつ、自らの肩を抱えてしゃがみ込む。震えを止められない。すると、誰かの両手がさらに上からやさしく両肩を包んでくれた。
「落ち着くんだ。お前を脅かすものなんて、今この場には何も無い」
怜二は言いつつ、僅かに潤いを含んだ目を霞に向けた。瞳に映るは、死の渕で彷徨いながら悪夢に苦しんでいる少女一人の姿のみ。
千秋は落ち着き取り戻すべく、頭の中を支配している悲劇の記憶を振り払うよう努めた。怜二の言葉があったおかげか、やがて本来の景色が目の前に甦ってくる。ぼんやりとしか認識できなかった霞の姿も、くっきりとしたものに移り変わっていった。
「御影さん……助けることはできないの……?」
「無理だ。今から病院に連れていったとしても手遅れだろう」
そもそもプログラムが行われているこの島から、迅速に本島の病院へと搬送することは不可能だ。霞の命は絶望的だった。
「彼女はあまりにクラスメートを殺し過ぎた。これはその報いなのだろうか……」
そんな呟きももうほとんど千秋の耳には入ってこない。哀れな最期を迎えようとしている霞の様子を見つめることに、意識の大半が集中していたからだ。
薬の影響で隆起していた筋肉が、だんだんと緩んで平坦になっていく。がっちりとした体格が、丸みのある元の体形に変わっていく様子が、まるで魔法が解けたかのようだった。
全身に巻かれた包帯のあちこちが破け、血の滲んだ皮膚が露出している。出血は止まりそうになく、それどころか、掻きむしった箇所が次々と新たな傷になっていっている。真っ白だったはずの全身がいつしか赤に支配されて郵便ポストのようになっていた。出血量は人が死に至るレベルにまでとうに達している。
「御影さん!」
千秋の声と重なるように、狂ったかのような甲高い悲鳴が走った。
「キィィィィィエェェェェェェッ!」
鼓膜を叩かれる感覚に耐えられず、人差し指で両耳に栓をする。
霞は、ハッハッ、と弱り切った呼吸を、途切れ途切れに繰り返しながら、片手では喉を掴み、もう片方の手は真っ直ぐ空へと伸ばしている。そこにある何かを掴み取ろうとしているように見える。とても苦しそう。
「終わったな……」
残念そうに怜二がその言葉を発したのが合図だったかのように、空へと伸ばされていた手が突然崩れた。力が完全に失われたのだ。
「御影さん!」
千秋はもう一度名前を呼んでみる。しかし相手からの返事が無いどころか、もう微かな息遣いすらも聞こえてこない。
復讐という唯一の生きる目的に心を支配されて、何人もの級友達を葬り去ってきた御影霞。長い戦いの末に迎えようとしている彼女の最期は、安らかとは言い難いものだった。
【残り 四人】 |
