ここはいったい何処だろう……。
私はなんとも不思議な空間にいた。学校の教室――記憶の隅に残されている松乃中の教室にそっくりだった。横に六つ、縦に七つずつ並べられた机と椅子。窓際に置かれたポトスの鉢植え。席の後ろに何ヶ月も貼られたままになっている、合唱コンクールのポスター。
それら全てを取り囲む木製の壁面。
一見、何から何まで同じに思える。しかし、どこかが違うような気もする。教室全体に歪みかズレが生じているような違和感があったのだ。
「カースミっ」
いきなり呼ばれて私は驚く。すぐに辺りを見回して相手が誰なのか確認しようとした。
そのとき、私は気付いた。目の前の席に、黒い長髪の女生徒が静かに座っているということに。机に突っ伏したまま眠りについていたらしき彼女は、眠たそうな目を擦りながら頭を上げた。
「もー、寝てたの?」
少女の友人らしき人物が、腰に手を当てた恰好で近づいてくる。
二人は包帯ずくめの私の存在になんて気付いていない。そもそも見えてすらいないらしかった。
「ごめん、昨日夜遅くまでテレビに夢中になっちゃって……」
顔から手が離されると、たしかに少し眠そうな目が赤く腫れていた。
あ……。
私は思わず声を上げそうになった。少女の気だるそうな顔に見覚えがあったのだ。
「あんまり夜明かしばかりしていたら、よくないよ。肌にも、健康にも」
「分かってる……けど、こればっかりはなかなか止められなくってさ」
それは紛れも無く、御影霞――かつての自分の姿に他ならなかった。そう、これはあの大火災に巻き込まれるよりも以前の光景。まだ私が『普通の中学生』として過ごしていた、平穏な日々。
「あ、そういえば今日は買い物に行く約束していたんだっけ」
「そうだよ。委員会が終わったら私も行くから、五時ごろに校門前で集合だって言ってたでしょ?」
「だからゴメンって。待ってる間に寝ちゃって」
枕にしていた文庫本を畳みながら、席から立ち上がる昔の私。
「じゃあ早く出る準備をして。みんな外で待ってるから」
とりとめのない会話に花が咲く。当時は全く特別に思わなかった日常が、今になってみるとどんなに幸せなことだったかがよく分かった。
あの輝かしい頃にもう一度触れたいという一心で、私は必死に手を伸ばす。だが何も触れることは無かった。
普通に友達と笑い合いながら過ごした日々は、今やとてつもなく遠く、手の届かないものになってしまっていたのだった。
私は悲しさのあまりに泣き出してしまいそうだった。
窓から差し込む日光がもう一人の私を明るく照らしている。しかし肌の焼けた醜い私のいるところまでは照らしてくれない。光と建物の影の境目が、二年間ですっかり変わってしまった二人を隔てていた。これほどにまで解りやすい明と暗の区別はない、と笑いそうになる。
「どうしたの? ぼーっと立ったままで……。早く行こうよ」
「ごめんなさい。後で追いかけるから先に行っててくれないかしら」
そう答えられると、友人は不思議そうな顔をしながらも、一拍おいて「分かった」と背を向けた。
「何の用事があるのか知らないけど、早く来てよね」
そう言って教室を後にする友達に、かつての私はひらひらと手を振っていた。
教室に残されたのは二人の私。不思議な感覚だった。
「さて……」
寝ている間に乱れてしまっていた髪を手ぐしで整えて、ふいに真っ直ぐ前を見据えるもう一人の私。
「初めまして。こうして面と向かってお話する機会ができて、とても嬉しいわ」
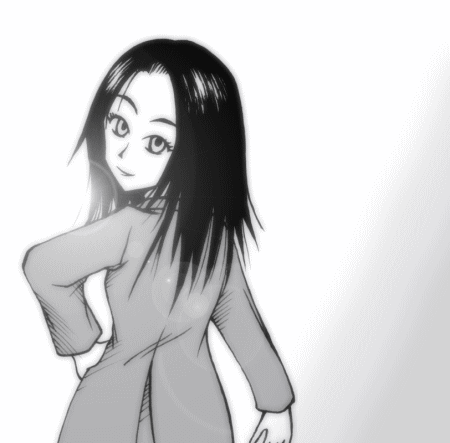
えっ……。
私は突然のことに驚いた。
「あなた……、私のことが見えているの?」
「もちろんよ。御影霞さん――、もう一人の私……」
相手に戸惑っているような様子は無い。この不思議な状況を平然と受け入れている。
「これはどういうことなの? ここは私が通っていた松乃中学校なの?」
混乱を解くためには、この世界を理解しているらしい目の前の私から何か聞き出す必要があった。だから必死になって疑問をぶつける。
クスクスクスと、相手はこちらの形相を見て笑っていた。
「おっしゃる通り、ここは松乃中学生よ。私達の記憶の中のね」
彼女の言っていることが全く理解できない。
「難しかったかしら。まあ要するに、あなたは今、夢を見ているような状態なの。そして心の奥底に姿を消してしまっていた私に、こうして出会うことになった、ということ」
簡潔に言うと、今見ている光景は現実世界ではなく、私の中に記憶として構築されていた内面世界ということか。
頭がこんがらがってくる。
「しかし……」
もう一人の私は、こちらの全身を舐めるように見渡した。
「こうして近づいて見ると、より醜く感じられるわね。とても凝視できないわ」
私は、相手に何を言われているのか、一瞬理解できなかった。まさか過去の自分からも、この姿のことを酷く言われるなんて思ってもいなかったから。
投げ掛けられた言葉の処理が頭の中で進んでいくと、怒りが急激に沸き上がってきた。
「信じられない……。まさか自分からもこの姿のことを、そんなふうに言われるだなんて」
殺意の塊を握り締めるように拳に力を入れていると、相手はうんざりとした顔をしながら首を横に振った。
「私が醜いと思ったのは、別に容姿のことなんかじゃないわ」
「じゃあ何が醜いと言うのよ!」
「心よ」
あっさりと言い切られると、相手に詰め寄るように前進していた私の体が、ふいにピタリと止まってしまった。魔法にでもかかったかのように。
「心、ですって?」
私は何故か動揺してしまっていた。今まで姿形について何か言われることはあっても、内面についてこうもストレートに言われたことは無かったから。
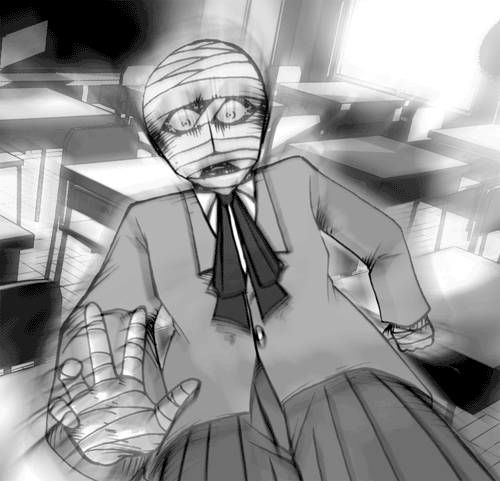
「そうよ。復讐なんてつまらない思いなんかに囚われて、簡単に級友を殺せてしまうあなたの心が綺麗なはずがない。こんなことになってしまって、同じ御影霞として私はとてもがっかりしている」
毛先を指で摘んで遊ばせながら、彼女は私から目を反らせた。
「本当はね、私だって気付いているの。あなたは元々はこんなことをするような人ではない。ただ、鬼に支配されてしまっただけだ、って……」
「鬼……」
ぽつりと私は呟く。
自分が思う通りに今まで行動してきたつもりだった。しかしそれは間違いだと相手が言っている。
「かつて色んな大切なものを失ってしまったときに、私の心にはとても大きな穴が開いてしまった。鬼はそんな隙を見逃しはしない。本来は深い闇の中からなかなか出てこないはずのあなたが、強大な力を手に入れて、私を押し退けて、思想の大部分を占拠してしまった……。それは本当に一瞬の出来事だったわ」
私はもはや何も言えなかった。相手の語りをただ延々と聞き続けていた。
「隅へと追いやられた私は、心の支配権を取り戻すべく、ずっとあなたの力が弱まる隙を狙っていた。とても長い持久戦だった……。そして今ようやくチャンスが訪れた。あなたは過ちに気付き、そして急激に衰えた。今度は私がこのチャンスを見逃さない。私の心、返してもらうわよ」
相手の伸ばした手が、私の肩を強く掴んでいる。もはやそれを振り払う気も起こらない。
全て受け入れる覚悟ができていたというよりも、どちらかといえば拒絶する気力すらも失っていただけなのかもしれない。
「もうどうでもいいわ……。心も身体も、何もかも私はもういらない……。好きにしたらいいわ……。でも、あなたはいいの? この肉体は手に入れたところで、どうせもうじきに死んでしまうわよ……」
「それでもいい。私は鬼のまま死にたくはない。最期の時くらい人間でいたい。あなただって、そう思うでしょ?」
そんなに長く話していたつもりはなかったのに、過去の私のみを照らしていた太陽が、気付くと遠くに見えるマンション群の後ろに隠れてしまいそうなほどに高度を下げていた。
光の入射角度が変わり、日光は教室のより奥までを照らすようになっている。
やれやれ、と私は溜息をつく。
「あなたは私を納得させるのが上手すぎる……」
「当然よ。だって私はあなただもの」
窓の枠に区切られた四角い光の空間内で相手と向き合い、私は笑った。
「これで鬼の呪縛から解き放たれる……。私、こうしてあなた――いえ、本当の自分に会えて、本当によかった」
いつもは無理に笑っても筋肉が引き攣って不気味な笑みになるだけなのに、不思議なことに、今なら何よりもの清々しい笑顔になることができた。私を包む光が七色に輝いて、さらに美しく彩ってくれる。
なんだかとても幸せな気分だった。こんな感覚は久しぶりだ。
クスッ。
私の幸せなそうな顔を見て、かつての私も満足そうに微笑む。すると突然、彼女は全身から眩ゆい光を放ちだした。
「よかった……」
と小さく言い残し、発光体のようになった彼女は弾けて光の粒となり、そして消えた。
まるで夢のような出来事――いや、これはまさに夢なのだった。
外はすっかり暗くなって、夢の世界はもう何も見えなくなっている。代わりに、窓ガラスに私の姿が映し出される。
かつての綺麗だった頃の私だった。鬼に支配された醜い姿はどこにも無い。
心が澄み渡っている。悪意が欠片ほどにも湧いてこない。
こんなにも清々しい気分を味わったのは、いつ以来だろう……。
周囲が真っ暗になっていく中で、気持ち良さのあまり私は目を閉じた。
意識はそこで完全に途絶えた。
 御影霞(女子二十番)――『死亡』 御影霞(女子二十番)――『死亡』
【残り 三人】 |
