私には、物を触ることのできる手がある。何かを見ることの出来る目がある。音を聞くことの出来る耳がある。味を知ることのできる舌がある。それらから得られる情報について考えて処理することが出来る頭がある。そして、感じることの出来る心がある。
だけどある時期を境に、何かを感じたという記憶が私の中から消え去ってしまった。
目の前にあるものを掴んで、見て聞いて舐めてみても、心の中は満たされない。経験の全てが処理されないまま頭の中に蓄積されていくばかりで、心は空腹に陥っていった。でも、私自身がそうなることを望んでいたのだからしょうがない。
過去に感じた数多の記憶も、空白によって心の隅にだんだんと押しやられて、白い靄の中に溶け込んで見えなくなっていく。
目印を失った私は、無限に続く平原を行く宛もなくただただ歩き続けていた。
過去の記憶が遠ざかり、新たに何かが流れ込んでくることも無い心の中では、当然私を満たしてくれるような物が見つかることもない。だけど足を止めたりはしなかった。この空白の世界の中で身体の動きを止めてしまえば、私という存在そのものが、霞の中に飲み込まれて消えてしまいそうに思えたから。
何も感じない世界の中を、意味無くひたすら歩き続ける――生き続ける。始まってから既に二年が経過していた。
促されるままに歩き続けた道を振り返っても、足跡一つ残されていない。きっと私はふわふわと宙に浮いていたのだろう。人間として歩いているようなことを装っていたが、そもそも足が地面に着いてはいなかった。
はたしてこれを人間と言って良いのか、自分でも分からない。試しに掌で自らの肌に触れてみても、人間特有の温かみを感じることは出来なかった。
空白から抜け出さない限りは、自分を知ることすらも叶わないのか――。
霞がかっていた世界に変化が起こったのは突然のことだった。身体が震えだして、濃厚の霧がうっすらとはれていく。外部からの圧力に、空白だった心が揺さぶられたのだ。
「火……?」
私は何も無かったはずの空間に、小さな灯しを確かに見た。どうやらこれが原因で、白い世界に変動が起こったようだ。
赤々と私を照らす小さな炎はなかなか消えず、穏やかに揺らめき続ける。その熱が原因か、乾燥された土壁の如く、真っ白な空間の中に小さなひび割れが生じる。
えもいわれぬ感覚に捕らわれた途端、足が勝手に後ろに下がり始めていた。それに合わせるかのように、炎は私のほうへと近寄ってくる。
「やめて! お願い、来ないで!」
必死に叫んだ。だけど声は心の中に留まり、外には飛び出してこない。
ひび割れがだんだんと広域に渡っていくのが目に見える。臆病になった心の鉄壁が弱体化していっているのだ。
ほどなくして、ひび割れの中に小さいながらも隙間といっていいほどの穴が生じ、そこから何かが転がり込んできた。拾い上げて封を広げ、中を確認してみると、それは二年前の火災の記憶だった。赤々と燃える校舎の中で、大切にしていた命を目の前で失った、思い出したくもない忌々しい一件。
それを見て思い出した。
そうだ、私は火が怖いんだ……。
封印されていた記憶の一つが解き放たれて外気に触れた直後、目の前から炎の灯りが消え失せた。だけど身体が震えて止まらない。ひび割れた箇所から隙間風と一緒に数々の情報――私が今目にしているもの、耳にしているもの、全てが凄い勢いで舞い込んでくる。それが素手で生傷に触れられているかのように感じられた。
長きに渡って空腹に満たされて機能を停止していた心は、急に雪崩れ込んできた大量の情報の処理に追いつけず、オーバーヒートしてしまいそうだった。とても一つ一つを感じているような余裕は無い。
身体の痛みとは別の痛みに襲われる。頭、いや、それ以上に心が痛んだ。
このままでは自分が壊れてしまいそうだ。心に走ったひび割れはさらに伝播していき、ついには私の世界そのものを多い尽くしてしまう。
なぜだか分からないが、このままではいけないと思った。身を包む鉄壁が破れて、今まで守ってきていたものが解き放たれてしまえば、自分はまた危険に晒されてしまう。そんな気になった。
はやく修繕しないと、と、私は再び心を閉ざすよう試みる。しかしその行為を妨げるかのように、なんだが懐かしい温もりが身体を包んできた。それは紛れも無く人間の体温だった。
普段は人に触れられても、堅く厚い壁に阻まれてその温もりが伝わってくることは無かった。だけど今は心の壁がひび割れて劣化しており、熱なんてそこかしこに開いた隙間からいくらでも入って来放題。
この温かみを感じたのは、いったいいつ以来だっただろうか。
心の壁が、ついに音をたてて崩れ始める。倒壊する建物のように一気にではなく、穏やかにゆっくりと。破片が一つ一つと足元に落ちてくる。
開けた天頂から光が差し込み、色の無い世界を照らし始めた。
ようやく気がついた。真っ白で何も無いと思っていた足元にはひんやりと冷たい土の地面があり、そこから青々とした木々と草花が無数に伸びている。視線の先には真っ直ぐに足跡が並んでいる。それは人間としての私がこの世界に存在しているという象徴。なぜ今までこれに気付くことが出来なかったのだろうか。
見ている物は同じはずなのに、そこから感じるものがこれまでとは全く違う。だけど、これこそが私が感じるべき本当の世界だと思った。
なんだか懐かしい気がする。長い間閉じ込められていた狭い部屋から解放されたような、そんな感覚に満たされた。
瞳孔が大きく開き切る。目の前に開けた色のある世界を、もっとたくさん取り入れたいとでも言うように。
大量に入ってくる情報の処理に、もはや頭は追いつかない。五感を通して取り入れられたもの全てが未処理のまま、心の中に積み上げられていく。
何も考えられない。だけど心の中に何も無くて考えられなかった先ほどまでとは全然違う。今の私は満たされている。満たされ過ぎていて、無数にある箱のうちどれを開いて処理していけば良いのかが分からず、立ち尽くしてしまっているのだ。
半開きだった口からはだらしなく涎が流れ出す。まるで廃人だった。そして目からは涙が――。
瞬きするのも惜しんで開きっぱなしだったためだろうか。いや違う。感覚に満たされた心が嬉しさのあまり悲鳴を上げているのだ。
私はずっとこのままでいたいと思った。外界からの危険に怯えて心に壁を作っているよりも、無数の感動の中に浸って漂っている方が、気持ちが良い。この温もりを逃してやるものかと腕に力を入れ、自分を抱き締めてくれているものを更に強く抱き締め返そうとした。
だが、私が伸ばした二本の腕は何ものにも触れず、ただ宙をかくだけに終わった。背中に強い衝撃を感じ、自分を抱き締めてくれていた温もりがどこかに飛ばされてしまったのだ。
何が起こったのか分からないまま、私は背後を振り返った。
温もりの無い冷たい刃が自分の背中に、深くめり込んでいるのが見えた。
それでも状況が理解できない。誰かに攻撃されたということが、唯一分かっただけだった。
いったいなぜ、自分は襲われなければならないのだろうか。
続けざまに肩に刃がめり込む衝撃が伝わり、私は大きく揺さぶられる。何が起こっているにしろ、命が危機に晒されているのは確かだった。
恐ろしさのあまり、私は右手に握っていた何かを大きく振り回して応戦しようとする。だが敵は素早く後ろに下がってそれを回避。
視界に自らの右手が入ってきたとき、握っているものの正体が分かった。銃だ。鈍く光る真っ黒い物体は非力な身体にとってはとてつもなく重い。その威圧感を前に、私は混乱してさらに訳が分からなくなる。
これはいったいどういうこと? 私は今まで戦っていたというの? 何故? いったい誰と戦っていたの?
考えても思い出せない。私は状況を知るために、積み上げられた無数の箱から一つを手にとって中を覗いた。
四十五人の少年少女が薄暗い部屋の中に集められ、教壇の前に立つ一人の男の話を強制的に聞かされている。そんな光景が頭の中に映写された。
プログラム?
教壇の前に立つアフロヘアーの男は確かにそんな言葉を口にした。
まさか、私が戦っていたのは、自分と同じクラスの人間たちなのか。
信じられない事実に驚愕しつつ、目の前の敵に向かって握り締めた銃を振り下ろす。が、相手の動作は人間業と思えないほどに素早くて、どうにもならない。
直後に頭に強い衝撃を受けて、私は倒れ込んだ。
今までに無かった一番大きな衝撃に揺さぶられ、緩やかに崩れていた私の中の壁が一気に崩壊した。これを期に、封印されていた全ての記憶が一斉になだれ込んできて、足元で跳ねた拍子に中身を飛び散らせる。
数多の過去の出来事が、広大な世界の中で物凄いスピードで展開されていく。
小柄で少し幼げな顔をした少年に手を引かれる、白い髪の私が見えた。虚ろな目でぼんやりと色の無い世界を見つめている私に、少年は優しく接してくれている。思い出した。あれは私のたった一人の兄だ。
微笑みかけてくれる兄を前に、私は全く表情を変えようとしない。そのせいか、たまに兄は少し悲しい顔をしていた。
何故あの時、私は無理やりにでも笑みを作って見せてあげられなかったのだろうかと、今さらになって悔やまれる。
学校でも同じだ。兄は私のために色々尽くしてくれるのに、礼の一つも言ってやれない。心一つを閉ざしてしまっただけで、ここまでコミュニケーションが取れなくなるものなのか。
クラスの皆も私のことを心配してくれている。火災で自らも傷ついているはずなのに、他人のことまでも気遣ってくれる優しい友人たち。でも私はそれらを相手にすることなく、どこか遠くを見つめている。
とてつもなく悲しくなった。
そして場面は急に先へと進む。次に目の前に映されたのは、プログラム開始後の様子。
私は自分の華奢な身体には似合わないような威圧感ある銃器を握っている。その目の前にはクラスメートである男子が一人。
「さあ、奴らを殺してこい」
そう言った彼はコンテナに寄りかかりながら遠くを指差す。示された方を振り向くと、そこには数人の女子が身を潜めながら固まっているのが見えた。
まさかと思っていると、私が見ている映像の中で、ほんの数時間前の私が銃を構えながら動き始めた。
当時の私には物事を考えて処理する力は無かったはず。しかし、やるべきことを簡潔に示された考える必要の無い命令に対しては、私は驚くべきほど優秀に応えていた。そういえば、私の兄も常日頃、ほとんど無意識の内に同様の手で私を導いていた。
『桜、ちゃんと歯磨いてから寝ろよ』
『チャイムが鳴る。桜、急いで走れ』
『悪いけど桜、そこに転がってる消しゴム取って』
私は指示された通りに動き、何から何まで完璧にこなす。恐怖に表情を凍りつかせるクラスメート達を前にしても、動じることなく淡々と任務を遂行するべく銃を向ける。
「やめて!」
映像の中の自分に向かって叫んだ。だが小さな手に握られた銃は、容赦なく火を噴く。必死に逃げようとしていた少女一人をあっさりと殺してしまった私は、その死体を前にしても悲しい顔一つ見せはしなかった。
「うそ……でしょ……」
自分のしたことが信じられない。しかしこれは真実だ。今になって記憶が鮮明になってきた。確かに命令されるがままにクラスメートを殺した覚えがある。
そのあまりの酷さに、手で顔を覆いたくなった。だけどそんなこともしていられない。こんなのはまだ序の口。
記憶の中の私はそこで狂走を止めはせず、その後も素早く確実にクラスメートを撃ち殺していく。どんなに怖がられても情け容赦なく。
悪夢のようだった。自分の手によって次々と人が死に追いやられていく様子は。ましてや、自分が殺しているのは皆、クラスメート――仲間なのだ。自らのこととはいえ、とても人間の沙汰とは思えない。
「もうやめて……。こんなのおかしいよ。もうやめて……」
だが私は更に別の人物を次なるターゲットとし、銃口を向ける。次に狙うのは男子。
「嘘……」
記憶の映像の中に出てきたその標的を見て、今の私は驚愕することとなった。なぜならそれは、他ならぬ私の兄だったからだ。
まさか、まさか、まさか……。
地面の上に倒れた兄は、悲しそうな目で私を見ている。対する私は銃を構えながら――泣いていた。相変わらず色の無い目つきは冷たいままだが、確かに涙が溢れている。
片方の手で兄と繋がりながら、片方の手で銃口を向けるという、とてつもなく奇妙な様子。当時の私なりに、兄のことを悲しんでいたのかもしれない。
そしてまもなく、辺りに銃声が短く響き渡った。
記憶から目を逸らした私は、恐る恐る自分の手を見てみる。蝶の鱗粉が付着したままの掌には、まだ命を握りつぶした感触が残っている。私が兄を殺したという出来事は、紛れもなく事実だった。
「あ……あ……っ、うあああああああああああああああああああああああああっ!」
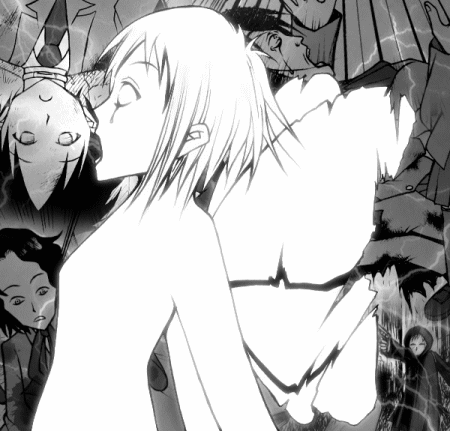
あまりの悲しみから頭の中がおかしくなりそうだった。いや、もうおかしくなっていたかもしれない。心の中の崩壊は最終局面を迎え、壁の全てが崩れ落ちたかと思うと、今度は心そのものが激しく音を立てながら砕け始めた。
世界で一番大切だったものを自らの手で壊してしまった悲しみは、他のどんな苦痛よりも耐え難い。
生まれる以前、母の腹の中にいたときから兄の対だった私。私の対だった兄。同じ大きさの布団に寝て、同じ柄の服を着て、同じ形の食器を使って、同じ番組を楽しんで観て、同じ玩具を欲しがって、同じクラスで学んで……。いつまでも二人で一つのはずだった。だけどその関係を私が断ち切ってしまった。
謝って済むかどうかとか、そんな問題ではない。私にとってこれは世界の終りを意味する。
思った。もう私自身も終りにしたい、と。
幸いというべきか、心だけでなく、既に身体も壊れきっていた私は、実際にもうすぐ死ねそうだった。自殺する必要はない。もうじき、この壊滅した世界から飛び立つことが出来る。
意識が徐々に薄れていき、景色がだんだんとぼやけてきた。
もうすぐだ。
そんな時、壊れきってしまった私の心に聞き覚えのある声が響く。
『桜。大好きだよ』
それは兄の声だった。どうやら死に際に彼が心の中で放った言葉が、今さらになって届いたらしい。
その言葉が胸に突き刺さった痛みは、背中を折られる痛みよりも、肩を砕かれる痛みよりも、頭を割られる痛みよりも酷かった。
それにしても、本当に兄はお人好しだ。自分を殺した妹に向かって大好きだなんて、どうかしている。
とは言いつつ、人のことばかり言ってはいられない。どうかしているのは私も同じだ。
私は薄っすらと笑みを浮かべて、声に出して言った。
「私もだよ……。お兄ちゃん……」
実に二年ぶりに見せた笑顔だった。
【残り 五人】 |
