水槽の中に放り込まれた魚に自由なんてものはない。
四面を透明なガラス板で囲まれた狭い空間こそが世界のすべて。えらで呼吸をする小さな生命たちは、水面より上の空気中では命を維持することが出来ないものだ。
魚たちは故郷である広大な湖や河川を夢見つつも、外界から隔離された小さな世界に閉じ込められたまま、やがて力尽きていってしまう。
今のあたしたちは、まさにそれと同じような状態だった。
直径数キロメートルばかりの小さな島に閉じ込められ、爆薬入りの首輪を無理やり身につけられた中学生達は、かつて自分たちが過ごした平和な世界に戻れぬまま順に命を落としていき、着実にその数を減らしていった。このままじっとしていれば、あたしもいつかクラスメートたちと同様に、この島の中で死を迎えることになってしまうだろう。
しかし、そんなのは御免だ。政府の人間たちの勝手で行われるプログラムで、なぜ私たちが命を奪われなければならないのか。当然納得なんてできない。
だから、あたしたちは政府に逆らい、この島からの脱出を試みることにした。
過去数十年間にわたって行われてきたプログラムの中、脱走に成功した者なんてほとんどいない。政府の手から逃れるということの難しさは、過去の大会データが証明している。
でもあたしたちは諦めなかった。
あたしはまさに自由を奪われた魚。この島は淡水に満ちた水槽の中。干上がった外は死の世界かもしれないが、あたしはそれでも水面から大きくジャンプして外に出て、腐臭に満ちた下水の中を泳いででも元の世界に戻ってやる。
「これで作業は終わりか?」
肥料で汚れた手を擦り合わせながら比田圭吾(男子十七番)が聞くと、「ええ」と蓮木風花(女子十三番)はベッドの上で横になったまま短く答えた。
ここは、すっかりおなじみとなってしまった病院の一室。白く清潔なシーツが被せられたベッドの間に、分解されたテレビなどの細かい部品が散らばっている。床の上には硝酸アンモニウムの袋や、一階のガレージからガソリンを運ぶのに使ったポリタンクも置かれている。その周囲はまさに足の踏み場も無い状態で、身体の大きな圭吾は少し窮屈そうに、狭いスペースに座っていた。
「足りるのか、これで?」
と、圭吾が自分の目の前を指さす。彼の視線の先には床用ワックスのドラム缶が三つ、同じ方向にロゴの書かれた面を向けながら並んでいる。
「さぁね」
「さぁ、じゃねえだろ、おい。チャンスはおそらく一度きりなんだ。これが上手くいかなければ、俺たちには死しか残されないんだぞ」
圭吾は目つきを厳しくしながら風花を見る。本当ならむなぐらを掴んでやりたいところだが、衰弱した相手に手荒いことはできない、と自分を落ち着かせようとしている様子だった。といっても、風花の様態も一時のことを思えば、多少はマシになっているように思える。
羽村真緒が亡くなったばかりのころ、風花は普段の冷静さを失って、珍しく取り乱していた。だが、横になってしばらく休んでいるうちに気分が落ち着いていったのか、青ざめていた顔も今ではほんの少しだけ血の気を取り戻しているような気がする。血液不足による体調不良は相変わらずのはずだが、精神的なダメージが軽減されるだけで、彼女が感じる苦しさはだいぶ薄らいだらしい。圭吾に向かって出す指示は的確で分かりやすく、身体の調子の悪さをほとんど感じさせなかった。
蓮木風花という人物の強さを、改めて実感した。
しかし、上半身のふらつきや頭痛が治まったわけではないようで、風花はまだ腕で身体を支えながら片手で頭をおさえている。
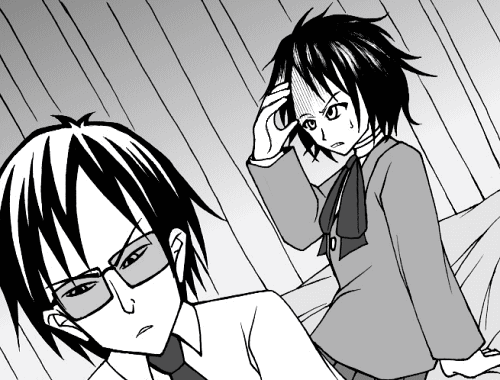
「おい、なんとか言えよ」
返事をしない風花に、圭吾は苛立っている様子。
「うるさいわね。あまり大きな声を出さないでよ。頭にガンガンと響く」
風花も負けじと相手を睨み返し、そしてベッドの上で身をよじった。圭吾の方を向く体勢になった。
「足りるかどうかなんて私にだって分からないわよ。前に言ったでしょ」
圭吾と風花が何を言い合っているのか、簡単に説明するとこういうことだ。
現在行おうとしている計画とは、手製の爆弾で島の中央部にあるダムを破壊し、プログラム本部へと大量の水を流し込んでメインコンピューターを破壊する、というもの。
圭吾はこれまで風花の指示に従って集めた材料を配合し、なんとか爆弾を完成させた。硝酸アンモニウムや硫黄、それにガソリンなどを混合した爆薬が入ったワックスのドラム缶。これにテレビなどを分解して手に入れた部品を使って製造した簡単な着火装置を接続。あとはこれに衝撃が加われば装置内部のストッパーが外れて回線に電気が走り、着火剤に引火して爆発が自動的に起こるはずだ。(風花は最初、衝撃で側薬がスライドすると黄燐に着火するというマッチの原理を用いた発火装置の製造も考えていたが、湿った空気の中では黄燐が自然発火してしまう恐れがあり、危険なので今の方法が採用された)
着火装置は何度も衝撃を与えて機能をチェックしたし、問題はない。誤作動対策として取り付けた手製の防火レバーを下げておけば、安全に持ち運ぶことも出来る。
ただ一つ問題があった。それは、この爆弾がどれほどの威力を持っているかが分からないということ。
風花は医療関係について懸命に勉強していたが、時々興味本位で横道に逸れてしまうことがあった。爆弾の製造方法は、その過程で偶然知っただけと言う。だから作り方は分かっていても、どれほどの強度を誇っているのか不明のダムの水門を破ることが出来るのかどうかまでは、予想もできないのだった。
爆弾一つの威力で事足りるのかどうか分からないので、念のために同じ物を三つ作った。しかしその威力が全く不明なため、いくら数があっても安心はできない。だから圭吾は「爆弾三つで足りるのか」と聞いていたのである。
しかし、大量の爆薬が詰められたドラム缶はかなり重く、ここにいる人間だけで運ぶには三つ程度が限界だろう。材料にも限りがあるし、どのみちこれ以上爆弾の数を増やすなんて不可能だ。
途中で圭吾もそれに気付いたのか、風花に向かって強く問い掛けるのをしぶしぶ止めた。そもそも風花は言っていた。これは成功確率も分からないようなとてつもなく頭の悪い作戦だ、と。それを聞いた上で策に乗ってしまった彼に、文句を言う権利など始めから無いのだ。
圭吾が大人しくなると、風花はやれやれといった顔をして、窓の方へと目を向けた。
「雨がだいぶ大人しくなってきたみたい。今こそ出発時なのかもしれないわね」
かつて聞こえていた窓ガラスを叩くような激しい雨音は、だいぶ静まってきている。窓際へと寄ってカーテンを少し開けてみると、真っ暗だった外の世界に僅かに光が差し込み始めていた。短い休みをとっている間に、朝は静かに近づいてきていたのだ。
「準備が整った以上、ここにとどまっている理由はないな」
「ええ。いくつもの苦境をくぐり抜けて、ようやくここまで辿り着いた。全てが終わるまであと少し。さあ、行きましょう」
春日さん、と後ろから呼ばれた。春日千秋(女子三番)は「ええ」と返し、窓際のカーテンを再び閉めながら振り向いた。
風花は手で身体を支えながら、ゆっくりとベッドから下りる。いくら雨の勢いが弱まったとはいえ、爆薬が濡れてしまう恐れが無くなったわけではないので、圭吾は念のために出来上がった爆弾三つに透明のビニールをかぶせる。
三人それぞれが武器を手に持ち、出発の準備はすぐに整った。
爆薬入りのドラム缶の取っ手を掴み、廊下へと出て行こうとする圭吾。それに続いて部屋から出ようとした千秋は、扉の前で立ち止まって、最後に一度病室の中に視線を向けた。
部屋の奥のベッドを囲むように閉められた白いカーテン。千秋からは見えていないが、その内側に親友の羽村真緒が静かに眠っている。両手を組んで穏やかな表情をしている真緒の姿が、頭の中に自然と浮かんでくる。
「真緒。あたし、行ってくるよ」
それは親友に向けた、最後の別れの言葉であった。人気が無くなり静かになった部屋に、様々な感情が入り交じった千秋の声ははっきりと響き渡った。
間違いなく、真緒の耳に届いたはずだ。
千秋は自分の胸の上で重ねた両手を強く握り締め、そして真緒の眠るベッドに背中を向ける。
小さく震える肩の振動が全身に伝播する中、千秋は決心の固まった強い目をしていた。
【残り 六人】 |
