銃器を構える敵に見つかってしまっては、もはやグズグズと考えている時間は一秒たりとも無かった。
怜二はすぐに立ち上がって茂みの裏から抜け出し、黒衣の人物から逃れるためにとにかく走り出す。どす黒い殺意を身の回りで渦巻かせている相手に、無防備な背中を見せてしまうことは大変危険であったが、全速力で疾走するためにはやむをえなかった。サッカー部で鍛え上げてきた自慢の足の能力を発揮すれば、大抵の敵からは逃れられるはず、と怜二は思っていた。
走り出してすぐのこと、後方からタタタタタッと軽快な射撃音が聞こえた。怜二の姿を確認した敵が、背中に向かって容赦なく銃器を向け、発砲しているのだ。音の感じからサブマシンガンの類だとすぐに分かった。
「ちっ」
舌打ちしながら頭だけで後ろを振り返る。敵はマガジンの中に詰められた弾が切れるまで、一切トリガーを戻すことなくひたすら撃ち続けている。しかし、無数に立ち並ぶ木々の間をすり抜けながら波を描くようジグザグに走行していたおかげか、とりあえず幸運にも一発たりとも被弾することなく済んだ。どんなに腕の優れた銃の使い手だって、障害物の多い場所でこうも小回りに動き回られたら、そう簡単には的を撃ち抜くことはできないものだ。そもそも走りながらでは、構えた銃の狙い自体がなかなか安定しないだろう。
マシンガンの連続した射撃音は二秒近く鳴り続いてから止まった。装填されていた弾が全て撃ち尽くされてしまったようだ。敵は肩にかけていたデイパックに手を突っ込み、予備のマガジンを取り出そうとしている様子。
引き離すなら今がチャンスだ。相手はもともと荷物を抱えているというハンデを背負っていたというのに、さらに今はデイパックの中をまさぐりながら追走を続けなければならない。そんな状態では本来の走力を出し切ることなんてできないはずだ。
荷物ゼロで身軽な怜二は、相手がサブマシンガンに新たなマガジンを取り付け終わるまでジグザグに動くのをやめ、森の奥を目指して真っ直ぐに走ることにした。できる限り余計な距離を走るのを避け、最短のルートで前に進んだほうが、より効率的に銃の射程から逃れることができる。
不思議なことに、彼はこの期におよんでもまだ冷静さを失っていなかった。驚異的な武力を手にした敵の出現に戦慄しながらも、瞬時に適切な判断を行ってその通りに行動できるあたり、さすが数々の真剣勝負を経験してきたスポーツマンであるといえる。
「あっ」
追走してくる敵の様子を確認するために振り返ったとき、前方から強い風が吹いて、黒いフードの下の顔が一瞬だけはっきりと見えた。真っ白な頭髪が特徴的な白石桜(女子十番)だった。
襲撃者の正体が彼女だとは全く予想していなかったため驚いた。二年前の松乃中等学校大火災に巻き込まれてから、精神に深い傷を負って自我や感情を失ってしまっていたという桜が、まさかこうしてゲームに乗ってしまうなどとはとても考えられなかったのである。
いったい何が、彼女をこのような凶行に走らせてしまったというのだろうか。
命令形の言葉にのみ反応するという桜の特性を知らない怜二は、そんな疑問を頭の中に浮かばせた。兄である幹久に支えられながら黙々と日々を過ごしていた大人しい様子からも、無邪気に笑顔を見せていた、学校火災に巻き込まれる以前の可愛らしい姿からも、桜が心の内側に真っ黒な闇の部分を潜ませていたなんてとても思えない。
もしかすると、今回の凶行は彼女自身の意思で行われたのではないのかもしれない、と怜二は何気に考えた。が、それを立証する手立ては無かった。
再び後ろを振り返ったとき、桜がマシンガンに予備のマガジンを付け替えようとしているのが見えた。そろそろ第二射がやってくる。マシンガンとは弾丸をシャワーの如く発射する銃器であるため、一度それに狙われてしまったら、遮蔽物を弾除けにしながらでも動き回らなければ掃射によって簡単にやられてしまう。
と、怜二はある重大な事態に気がついた。速さに自信のある足をこれまで懸命に動かし続けてきたというのに、未だ敵との距離はほとんど開いていなかったのだ。
べつに桜の足が特別速いというわけではない。丸一日以上、休み無しに移動を続けてきたことによって発生した身体中の疲れが、怜二の足から本来の走力を奪っていたのである。
後方からまたマシンガンの連続した銃撃音が聞こえた。何発もの弾が怜二のすぐ横を通り過ぎて、ある一発は土の地面に深く突き刺さり、また別の一発はすぐ側に生えていた木を掠めて固い樹皮を剥ぎ取っていった。そんな中、怜二は身体を横から強く殴られたような感覚に襲われた。乱射された弾のうちの一つが彼の脇腹付近を捉え、深さ二センチほど肉を抉り取っていったのである。
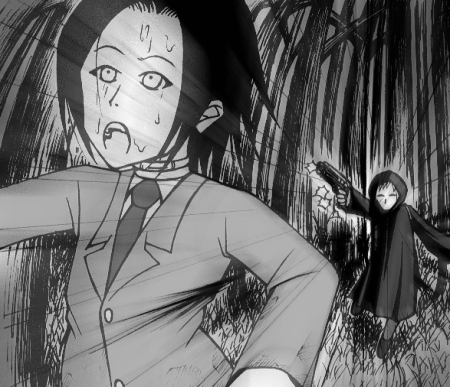
一瞬硬直してしまった身体が大きく前のめりになり、そのまま倒れてしまいそうになった。しかし、ここで転んでしまったら一気に桜に追いつかれ、死は確実なものとなってしまう。大きく前に伸ばした足に力を込めて、すんでのところで踏みとどまった。
激痛を発する脇腹から血があふれ出しているのが分かる。土の上に残される足跡に並んで、滴った血液が緋色の点線をまっすぐに描いていた。しかし怜二はそれに構わず走り続ける。生き延びるために残された道は細く不安定であるかもしれないが、だからといって今ここで躊躇し、立ち止まることは許されなかった。
そしてまた後方からの射撃音が途絶えた。相手のマシンガンが再び弾を撃ち尽くしてしまったのだ。一度に数十発しか弾を装填できないマシンガンは、トリガーを引いたままひたすら乱射し続けていると、意外とすぐに弾切れを起こしてしまうものなのである。
桜がマガジンを交換するのに多少の時間を費やすであろうと見越して、怜二はラストスパートのつもりでがむしゃらにダッシュした。足をひっかけられないよう、地面の上に転がっている石や、植物の根や枝を大股で飛び越え、素晴らしいスピードで前へ前へと突き進む。
勢い良く足を下ろすと地面の泥が大きくはねて、黄土色の水滴が額の高さにまでとんできた。
少しして、怜二の走る前方に小さな建物が見えてきた。資材置場にでも使われていたらしい木でできた小さな小屋で、かなり古くに建てられたのか屋根や壁面など所々が朽ちてきている様子だった。
怜二は桜の視界から姿を眩ませるべく、その建物の裏に回り込もうとした。相手はまだマガジンの付け替え作業を終えはしないだろう、などと思いつつ、小屋の周りの開けた空間に飛び出た途端、近くからドンと大きな音が響いた。爆発音のようだった。
身体に強い力を受けて、怜二は堪え切れず建物の後ろへと吹っ飛び、地面の上でニ、三回ほど転がった。
何事か、と、すぐに立ち上がって辺りに目を向ける。すると、そばに建つ小屋の一角が真っ赤な炎に包まれているのが目に入った。
どうやら、桜はマシンガンに新たなマガジンを装着させようとはせず、デイパックの中に入れていた別の銃機――グレネードランチャーでも取り出して発砲したらしかった。
爆風で怜二の身体が飛ばされると同時に、小屋に残されていた燃料か何かに爆発の炎が移ったのだろう。いくら建物そのものが雨に濡らされているといっても、腐りかけていた材木はたった一個の榴弾が火花を散らしただけで簡単に燃えてしまったのだ。
近距離で燃え上がっている炎がとても熱かった。爆発で一部壊された建物の破片が散らばる中で、肌を焼かれるような感覚を怜二は嫌がり、まだ火の手が延びていない小屋のさらに裏へとまわった。そして自分がやってきた方向を覗き見る。
ここまでか……。
すぐに立ち上がったとはいえ、倒れてしまったために生じた時間のロスはあまりに大きい。その間に桜に距離を詰められてしまったことを考えると、自らの生存はもはや絶望的に思えた。
脇腹をおさえる手のひらの下からにじみ出てくる鮮血が、ブレザーを鮮やかな赤色に彩っていく。激痛の酷さからすると、もしかしたらあばらの一本くらい持っていかれてしまっているのかもしれない。
すぐ横では、徐々に勢いを増していっている炎が、ぱちぱちと音をたてながら大きく揺らめいている。
恐る恐る森の奥へと目を向ける怜二。しかし不思議なことに、いくら目を凝らしても、桜の姿はもうどこにも見られなかった。
【残り 六人】 |
