首輪の爆発によって頭の大部分を損失してしまった利久は、崩れた体勢のまま周囲に鮮血を撒き散らし、草の生い茂る大地の上へとゆっくりと身を倒した。腰から下を捻じった状態で仰向けになった彼の四方、広範囲にわたって金属製の首輪の破片がバラバラと散らばる。
急激な広がりを見せる赤黒い血の池の真ん中で、利久はもうぴくりとも動くことは無かった。力の失われた腕は緩やかに湾曲し、掌は椀を持つような形を保ったまま下を向いている。首輪が爆発した際に片方の靴が脱げてしまったようで、普段は隠れて見えないはずの白いソックスが泥に汚れている様子も、肉眼でしっかりと確認できた。
クラスメート達を自分勝手に憎しみ、罪の無い桜を操っていくつもの惨劇を起こしてきた悪魔のような男の最期は、あまりにもあっけないものであった。そして、こうやって目の前で無残に死んでしまっているのを見ると、いくら自分たちを苦しめてきた敵であろうとも不思議と可哀想だと感じてしまうものだった。
それにしても、彼の首輪はなぜ爆発してしまったのだろうか。
時間と場所の感覚が麻痺してきてしまっていたためか、幹久は一瞬だけ、利久の立っていた場所が禁止エリアへと変わってしまったのではないかと推測した。だが、計算高く用心深そうな彼がそんな単純なミスをおかすなんて考えにくかったし、そもそも利久のすぐ側にいた二人の人間の首輪には未だに変化が見られないことから、すぐに自らの考えを否定せざるをえなかった。
結局、どうして利久が死んだのか、その理由に幹久が辿り着くことはなかった。というより、悠長にそんなことを考えているほどの余裕なんて、瀕死の重体となってしまっている彼にはもともと無かったのである。
利久と違って幹久はまだ辛うじて生を繋ぎ止めてはいるものの、負傷箇所の見た目の酷さは優るとも劣らないというほどだった。
胴体部分に負った傷はとてつもなく深く、今こうして生きているのも不思議なくらい。マシンガンから発射された弾丸によって破壊された臓器の多くは、すぐにでも活動を停止してしまってもおかしくはない。テレビゲームのようにダメージの大きさなどを数値化できるならば、幹久のライフポイントは残すところほとんどゼロに近かったと言ってもよい。
立ち上がることはおろか、もう這いずることすら出来ない幹久は、ただ仰向けに倒れたまま雨に打たれ続けるしかなかった。
辛うじて動かすことの出来る頭だけを回して、首から上の大部分が消失してしまっている死体の隣で尻餅をついている白髪の少女へと目を向ける。黒いレインコートを羽織り右手にスコーピオンサブマシンガンを握っている白石桜は、何が起こったのか理解出来ていなかったのか、ほんの少しの間だけ身体の動きを止めていた。だが数秒後にはゆらりと立ち上がって何事もなかったかのようにこちらへと視線を向ける。感情の篭らない濁った瞳は、相変わらず幹久の姿なんて薄っすらとも映し出していなかった。
きっと彼女は目の前にいる兄のことを、世界中に溢れんばかりに存在する人間のうちの一人としか認識できていないのだろう。あるいは、それどころか目の前の生物が何なのかも分かっていないのかもしれない。
幹久は自暴自棄がちにそんなことを思った。
桜……。
それでも二人で仲良く過ごした昔のことを、もしかすると思い出してくれるかもしれないという微かな望みにかけて、深淵の底に閉じ篭ってしまっている妹の心を呼び覚まそうと、幹久は彼女の名前を呼ぼうとする。しかし駄目だった。さっきは必死になれば僅かに発することが出来た声も、今では全く口から出てこない。大きな通風孔をいくつも開けられてしまっている肺では、体内の空気を外へと送り出すことなんてもはや不可能なのであった。
当然、新たな空気を吸うこともできないため、幹久は続かぬ息にも苦しまなければならなかった。
桜……。
涙でコーティングを施した両眼を動かして、すぐ側に立っている妹と視線を交差させる。しかし桜の方は顔の表面上に感情を浮かばせることなんてなく、弾の入ったマシンガンを再び幹久へと向けるだけ。
そうだった。桜は首輪の爆発で利久が亡くなるよりも前に、兄を殺すよう命令されていたのだ。そして、その命令を取り消すような言葉はまだ誰の口からも発されていない。つまり生前に利久が桜に出した命令は、未だ消えることなく続いているのだ。
早く、銃を降ろすよう桜に次なる指示を出さなければ。
幹久は焦った。このままでは、桜はマシンガンで実の兄を殺し、そして利久が出した「現在生き残っているクラスメートも全員殺せ」というもう一つの命令にも従って、残り少なくなっている級友達を消し去るために動き出してしまうだろう。それだけは絶対に阻止しなければならない。
桜、馬鹿なことはやめろ! 今すぐ銃を降ろすんだ!
幹久は必死に口を動かした。だがやはり声は出てこない。穴の開いた肺は膨らみも縮みもせず、ただ自然体を保ち続けるばかりだ。
命令が取り消されない限り、桜の暴走は止まらない。マシンガンの銃口はぴったりと幹久の頭へと向けられたまま。
今にも銃弾が飛び出してきそうな恐怖に、幹久は身を固めてしまう。桜の手によって薬莢内部の火薬が破裂させられるのは、一秒後か、それとも数分かかるのか分からない。いずれにせよ、終りがすぐ近くにまで訪れていることは間違い無い。
幹久は悲しみに満ちた目でもう一度桜の顔を見上げようとした。だが涙のせいで、視界に入る大好きな妹の姿はぼやけてしまう。
息が止まってから数十秒が経過してしまい、胸の苦しさは最高潮にまで達してきている。しかしそんなことを気にしている暇なんてもう全く無い。血で汚れてしまっている制服の袖で目の周りを拭い、泥の上に寝転がったまま再び頭上を見つめ直してみる。するとレインコートのフードの奥に真っ白い頭髪を見え隠れさせている桜の姿が、今度こそははっきりと確認できた。そして驚いた。
涙?
幹久は見た。スコーピオンを手に構えながら相変わらず冷たい目つきをしている桜だったが、その両眼からは透明に輝く綺麗な涙が、止めど無く流れ出していた。その様はまるで生死の間をさまよっている兄の姿を目の前にして悲しむ、妹の心を象徴しているかのようだった。
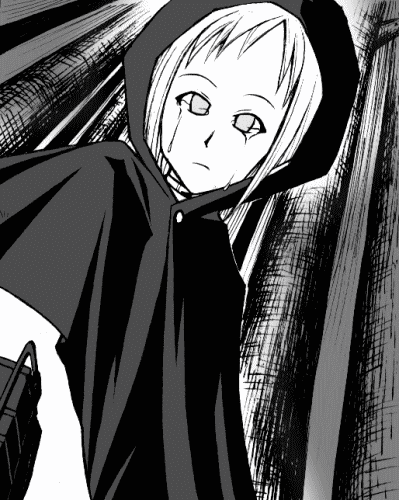
桜。まさか僕のことを思い出してくれたのか?
幹久は問い掛けるような目で桜を見た。しかし彼女は無機質な表情を変化させることなく、構えた銃を下ろそうともしない。兄を殺そうとする妹の意思に変化が起こったわけではないのだろうか。涙は間違いなく今も流れ続けている。
桜にいったい何が起こったのか。
松乃中の火災で精神に大きな傷を負って心を閉ざしてしまった彼女。だが、もしかすると深層心理のレベルでは、自らの分身――十五年間共に過ごしてきた兄との記憶は失われずに残されていたのではないだろうか。と、幹久はふいに思った。だとすると、瀕死の幹久をすぐ目の前にしたことが原因で、その命が今にも消え去ろうとしていることを感じ取った途端に過去の記憶がに呼び起こされて、桜は突然涙した、ということも考えられる。しかし己をコントロールできるほどにまで意識が回復したわけではないのだろう。心の底から記憶が僅かに頭を覗かせた程度では、外部からの命令だけに従って行動しようとする身体を制御するには至らなかったのかもしれない。
その説が正しいのかどうかは分からない。しかし、桜が幹久のことを僅かながらも覚えてくれていたというのは、おそらくもう間違いないだろう。共に過ごしてきた十五年という月日の思い出は、腐っても彼女の中では大きな存在に変わりはなかったということだ。自分の命がもうすぐ尽きるとしても、幹久はそう思うだけでなんだか救われたような気がした。
気がつくと、彼は妹の方へと向かってまっすぐに手を伸ばしていた。二人並んで歩いていた昔のように、もう一度だけで良いから手を繋いで欲しい。そんな気持ちから身体が勝手に動いたのだろう。
桜はしばらく身体の動きを止めて、じっと兄の泥だらけの手を見ていた。マシンガンは相変わらず足元の幹久へと向けられたままだったが、引き金にかかった指に力が入れられることはなかった。
すると突如、桜は涙を流したまま、マシンガンを持っていない方の手を動かした。そして傷だらけになった兄の手に指を絡めてきた。それは意識的にとった行動なのだろうか。いや、もしかすると、彼女はなぜ幹久と再び手を繋いだのか自分では分かっていなかったかもしれない。機械のような冷たい目つきがそれを物語っている。
片方の手は兄と繋ぎ、もう片方の手ではマシンガンを構える。その光景はあまりに不思議で奇妙だった。外部からの命令に従ってただ行動するだけの空虚な肉体に、桜の本来の意識が今立ち向かっている最中なのかもしれない。
がんばれ、桜。
破壊された身体中の痛みは凄まじく、プログラム中に負った心の傷も修復不能なほどに深い。しかしなぜかこの時の幹久は、安らかに笑みを浮かべていた。桜の手によって自分が殺されるという運命に変わりが無いとしても、幹久はもう一度妹と心を通じ合わせることができたのだと思うだけで、嬉しくてたまらないのであった。
桜。大好きだよ。
酸素欠乏により幹久の意識が失われかけた瞬間、兄妹の繋いだ手がすべるようにして解かれた。それが合図だったかのようにスコーピオンサブマシンガンが連続して火花を散らす。幹久の頭部は一瞬にして粉々に砕け散り、そしてすぐに辺りは静寂に包まれた。
何もかもが穏やかに流れて行こうとしている時間の中、桜の頬を伝う涙だけが激しさを増していた。
 白石幹久(男子八番)――『死亡』 白石幹久(男子八番)――『死亡』
【残り 七人】 |
