コンピューター内部で回転するファンの唸りが小さく響く薄暗い部屋の中で、兵士達は皆一様に目を見開かせて身体を固めてしまっている。
首輪の爆発によって湯川利久が亡くなった直後、プログラム会場本部で、ざわめきは少しずつ大きく広がっていった。
「い、いったい何をしているんですか!」
御堂一尉がメインコンピューターの手前へと恐る恐る歩み寄る。
モニターと対面する位置に立つ男が、太い人差指でキーボードのエンターキーを強く押していた。指先から腕をたどりながら登っていくと、頭のてっぺんには見事と言って良いほどの立派なアフロヘアーが形作られている。
「何しているかって、何がだ?」
プログラム担当教官の田中一郎は質問に質問で返した。高まる感情を抑えられない様子で、ふぅふぅと荒い息遣いをしている。
「いや、なぜ湯川利久の首輪を爆破したんですか、と……」
御堂一尉はほんの少したじろいだ。振り向いた田中の顔があまりに不機嫌そうだったので。トマトの果実みたいに紅潮した顔は、まさに鬼のようで迫力があった。
ゲジゲジの太い眉の間に深いしわが何本も寄せられる。いったい彼は何に対して怒り、そしてプログラムに参加している生徒の首輪を突然爆破するという、奇行とも思える行動に出たのであろうか。
「あの……」
なかなか次の言葉を発しようとしない田中に困った様子で、御堂は身を縮めながら声をかける。
桂木幸太郎はコンピューター一台の前に座ったまま、離れた位置からその光景をうかがっていた。
わなわなと震える手を伸ばしてティーカップの取っ手を掴む田中。白い陶器の縁を口につけた瞬間に、既に中身が無くなってしまっていたことに気が付いたようだが、無言のまま、まるで何事もなかったかのようにカップをテーブルの上におろした。
「見つけた……。やっと見つけたんだ……」
ようやく口を開いてくれた田中は俯き加減のまま、額に脂汗を浮かべている。
「何をです?」
と御堂がさらに追求すると、田中はゆっくりと頭をあげた。
「ワシの子供を――たった一人の大切な娘を殺した犯人をだ」
「娘……ですか……?」
御堂は意外そうに聞き返した。担当教官の補佐的な役割を担う一尉の彼ですら、田中に子供がいたということを知らなかったらしい。当然桂木だってそんな話を聞いたのは初めてだ。
感情の高まりによって血が沸き立ち、体温上昇の影響からか顔が真っ赤になっていた田中だったが、時間が経つとともに落ち着きを取り戻していったようだった。呼吸の乱れは落ち着き始め、握り締められていた拳からも力がゆっくりと抜けていく。
「ワシの娘は、二年前に殺されたんだ」
と突然田中が言った。
「二年前と言いますと……」
「兵庫県立松乃中等学校大火災があった年だ。当時十三歳だった娘はそこの生徒だったんだよ。そしてあの日、炎に焼かれて黒焦げとなって死んだ」
本部にまたざわめきが起こった。今度は先ほどのように小さなものではなく、大きくはっきりと兵士達の動揺する声が耳に入ってくる。
「政府で勤めていたワシは仕事のことしか頭に無い人間で、娘のことなんて気にかけてもいない最低の父親だった。でも、実際に娘が死んでから思い出したよ。彼女が小さかった頃――まだワシが父親としての実感を持っていた時の、共に過ごしたあの楽しかった日々を。娘の頭を優しく撫でていたときの、あの感触を」
あの冷酷な田中のものとは思えない、必死に涙を堪えているような声。
「事件の後、ワシは娘の変わり果てた姿を見て、柄にもなく大泣きした。校舎全体を跡形も無く消してしまうほどの炎によって、ほとんど骨だけの状態になるまで焼かれてしまっていたんだ」
御堂を含め、兵士達は全員黙って話を聞いている。とても横から口を挟めるような空気ではなかった。
肉親を失うということの悲しさは誰だって知っている。桂木は話を聞いているうちに、田中のことが少しだけ可哀相に思えてきた。
「それでは、松乃中等学校大火災の生き残りである梅林中三年六組の面々がプログラムに選ばれた今回、田中さんが担当教官に立候補したのは――」
一文字に閉じていた口を御堂一尉がタイミングを見計らいながら開くと、田中は険しい声で言った。
「級友の死を何とも思わない冷徹な人間達に鉄槌を下すためだ!」
田中が厳しい目つきを部屋中に向けると、兵士達は脅えるように一歩後ろに下がる。その際に誰かがコンピューターの電源コードに足を引っかけて転んだのか、ドシンと派手な音が部屋に響いた。しかし田中はそれを全く気にしない。
「娘が死んでしばらくした頃、ワシは一度だけ梅林中を訪れたことがあったんだ。そのとき、被災者特別クラスの人間達が元気良く暮しているのを見て、心の底から呆れたよ。ワシの娘は苦しみながら死んだというのに、どうしてコイツらは明るく笑って生活することができるんだ、とね。だからワシは思ったんだ。娘の苦しみも知らずに自分達だけ楽しく日々を送っている奴等にも、同等の苦しみを与えてやりたいとね」
要約すると、田中は火災で生き残った生徒達を逆恨みし、梅林中三年六組のメンバー達を苦しませて殺すために、自ら担当教官をかってでたということらしい。
「それだけではない」
田中はさらに話を続けた。
「今回担当教官を勤めることによって、詳しい出火理由やその背景など謎の多い二年前の事件の真相を知ることができるチャンスが訪れるかもしれないとも思っていたんだ」
「だから盗聴に障害が生じたとき、あんなにもお気を悪くさせていたのですか」
「そうだ。生徒達の会話の中に事件の真相を知るための鍵が隠されているかもしれないというのに、何も聞くことができないというのは苦痛でしかなかった。その反動か、盗聴回路が回復して湯川が火災の話を始めたときなんかは、スピーカーに耳を押し当てるようにして必死に声を聞いていたね。そして湯川が学校に火を放った犯人だったということと、動機のくだらなさを知ったときにはもう、湧き上がる怒りを抑えることが出来なかった。無意識のうちに湯川の首輪を爆破させていたよ」
辺りがしんと静まり返る。
火事で娘を亡くした後、明るく生きる梅林中三年六組の一同を逆恨みした田中一郎。
薬物が流通する原因を作った学生たち全てを皆殺しにしようと企んだ湯川利久。
炎で身を焼かれた際に手を差し伸べてくれなかった者達への復讐を誓った御影霞。
その他、火災で深い傷を負い、それぞれの思いを胸に今日まで生きてきた生徒達。
国内で年間に五十回も開催されるプログラムの数十年にもわたる歴史の中、一つの事件を元にここまで人間の憎悪や陰謀を巻き込んだ大会はあっただろうか。今大会の異常さに今さら気付いた兵士達の一部は、血色の悪くなった顔を石膏像のように固めてしまっている。
「まさかとは思うのですが、田中一郎という名前は……」
誰一人として口を開けなくなってしまっている中、御堂一尉が意を決して発言した。
「偽名だよ。といっても名字だけだがな。今大会の参加者である梅林中三年六組の者達なら、名字を聞いた瞬間に、ワシが二年前に死んだ女生徒の親だと気付いてしまうかもしれないからな。プログラムの恐怖を純粋に味わってもらうためには、やつらにワシの正体をばらしてしまうわけにはいかなかった」
「それでは、本当の名字とは、いったい」
「醍醐だ。ワシの名前は醍醐一郎だ」
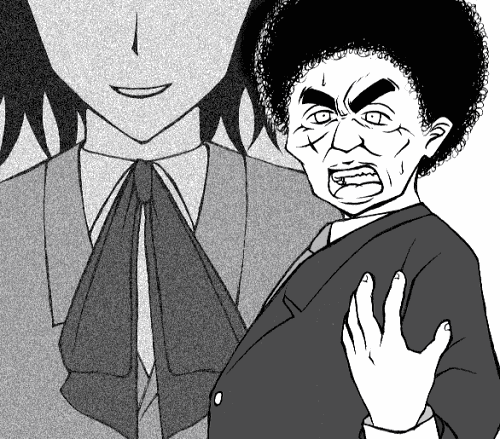
醍醐。その名字を耳にして一人驚く男がいた。田中の語りを遠巻きに聞いていた桂木だ。なぜなら彼はつい三日前に、その醍醐という名字を耳にしたばかりだったのだ。
――明日は……特別な日なんです……。
プログラム開催のために梅林中三年六組のメンバーが拉致される前日、飲食店『松乃屋』の看板娘の春日千秋(女子三番)から聞いた話が頭の中に蘇ってくる。
――親友の醍醐葉月が亡くなった、松乃中等学校大火災が起こった日なんです。
桂木はふいに驚くべき事実に気が付いた。田中一郎の正体とは、春日千秋の大親友、醍醐葉月の父親だったのである。
【残り 八人】 |
