千秋はぐるりと頭だけを回転させて真緒の方を向いた。病室に入ってすぐに幼馴染と二人で無事に再開できたことを喜び合うつもりだったのに、血みどろになった部屋の様子に気をとられてしまい、今までそれどころではなかった。
多少混乱していた千秋の目を覚まさせてくれた親友の声は、明らかに力が無くて弱々しい。
「真緒……」
恐る恐るベッドの上を覗き込むと、真緒もこちらへと視線を返してきた。だが彼女の目はほとんど閉じかけの状態で、千秋の姿を映し出す黒い瞳もなんだか虚ろで淀んでいる。意思に関係なく勝手に閉まりそうになる瞼を、必死になって持ち上げようとしている感じだった。また、彼女の顔からは血の気が失せて、千秋たちが病院から出て行く前よりもさらに容態が悪くなっているように思えた。肌の色はもう限りなく白に近い。
何気なく掌で真緒の頬に触れてみたところ、まるでゴム製の人形でも触っているかのように体温が全くといっていいほど伝わってこなかった。
「どうしたのよ。いったい何があったの?」
小倉光彦の死体。血だらけになった病室内。そして悪化してしまっている真緒の容態。それらを目の当たりにして、千秋はもう訳が分からなくなってしまっていた。
「私のせいなの」
千秋の隣で俯き加減になって黙り込んでしまっていた風花が、ふいに小さく声を出した。
「この広い病院の中、誰かがこの病室へと一直線に向かってくることは無いだろうと、高をくくっていたから……。ほんの一時とはいえ、私が不用意に羽村さんから目を離してしまったから……」
「小倉の侵入を許してしまい、そして羽村を傷つけられてしまった、というわけか」
千秋の跡を追ってきたらしい圭吾が、扉の側に硝酸アンモニウムの袋二つを落として病室へと入ってきた。彼は部屋の様子から事の詳細をもうある程度理解しているらしかった。
「輸血をしたのか」
床の上に落ちた血液パックを見下ろしながら圭吾は風花に問いかける。
「ええ、偶然私と彼女の血液型が一致し、尚且つやり方もちゃんと知っていたから。でもそこに邪魔が入った」
「小倉くん」
死体が転がっている後方へと視線を向けながら千秋が恐る恐る口を挟んだ。
「そうよ。あの男、暗視スコープなんか持ってて、暗闇の中でも足跡を辿って、迷わずこの部屋へとやってきた。そして抵抗した羽村さんの手首を手術用のメスで容赦なく切ったのよ」
「羽村を傷つけられたことで我を忘れてしまい、お前は勢いで小倉を射殺してしまった。そんなところか」
自らの軽率な行動が結果的に災いをもたらしてしまったということに悔しがっているのだろうか、風花は圭吾の言葉を耳にしながら、キュロットスカートの膝の辺りを両手で強く握り締めていた。鼠色の布地に深いしわが走る。
「小倉を殺してしまった後、またしても多量の血が体内から失われてしまった羽村さんのために、私は再び自らの血を抜いて輸血を始めようとした」
「でも、そんなに血を抜いてしまったら、今度は蓮木さんの身体の具合が……」
「そんなことを気にしている場合じゃなかった。何か手を施さない限り、羽村さんはもう助からないかもしれなかったから。ところがそこで、私はとんでもないミスを犯してしまった」
「ミスって、いったい」
「自分はどうなっても構わないと思いながら、私は自らの血を抜いた。ところが採血による急激な血圧低下が原因で、私は貧血を起こしてしまったの。膝から床の上に崩れ落ちた際、血液パックを吊るす支柱をも誤って一緒に倒してしまった」
千秋は床の上へと目を向けた。さっきも見たが、そこには倒れたスチール製の支柱と、破れて中身が流れ出してしまっている血液パックが落ちている。血液パックはおそらく風花の体重が加わった重い支柱に上から圧し掛かられたことによって潰れてしまったのだろう。
「二度に渡る輸血作業を、結局私は一度も上手くすることが出来なかった。ただ自分の血液を無駄にしただけ」
膝から離した手で、今度は頭を抱える風花。
「ごめんなさい春日さん。私、あなたの大切な幼馴染を救うことが出来なかった。いや、これはもう私が殺したも同然……」
「ちょっと、そんなことを言うのはやめてよ、蓮木さん。それじゃあまるで、真緒はもう助からないみたいじゃない!」
「その通りよ。あなたか比田くんの血液型が羽村さんと同じAで輸血が可能だったとしても、あるいは私の血をもう一度無理やりに採血したとしても、いずれにしろもう時間的に間に合わない。見れば分かるでしょ。彼女に残された時間はもうほとんど無いって」
確かに、顔面蒼白の真緒の姿は、一目にはもはや生きているのか死んでいるのかも判断しづらいほどの状態だ。呼吸の音が僅かに聞こえることで、辛うじて命が保たれていると分かるくらいで。
「でも、だからってそんな言い方しなくたっていいでしょ!」
胸の奥から込み上げてくるイライラに耐えられなくなって大声を出した途端、誰かに腕をつかまれた。
「千秋……、蓮木さんに当たらないで……」
真緒だった。ベッドから伸ばした手で千秋のワイシャツの裾を捕まえながら、潤んだ瞳をこちらへと向けてくる。
「蓮木さんは……自分を犠牲にしてまで、何度も私を助けようと必死になってくれたんだよ……。私が今まで生き永らえることが出来たのは彼女のおかげなの……」
言われなくてもそんなことくらい分かっていた。最初にこの病院へとやって来た時だって、風花は懸命に適切な処置を真緒に施してくれたし、幼馴染を救ってくれた彼女に対して誰よりも感謝していたはずだった。だけどとてつもなく大きな不安に頭の中を満たされてしまって、それを振り払うために何にぶつかればよいのか一瞬分からなくなってしまい、全て目の前に座る風花のせいにしてしまった。それがどれだけ理不尽なことだったかは考えるまでもない。
「ごめん……。私、今ちょっとおかしくなってた。蓮木さんは何も悪く無いのに……」
「分かってくれたらいいよ……。私、もう感じているんだ。蓮木さんが言ったとおり、もう時間はあまり残されていないって」
「やめてよ。そんなこと言わないでよ」
真緒の手をワイシャツの裾から引き剥がして両手で握り、ベッドの隣に膝をつく千秋。堰を切ったように流れ出した涙が顎の先端から落ちて、女二人の掌が合わさって出来た谷間をゆっくりと流れた。
「千秋……、それに皆、本当に迷惑かけてごめんね。私がいなかったら、脱出のための計画だって、もっとスムーズに進行したかもしれないのに……」
真緒は一瞬だけ悲しそうな表情をしたが、すぐに薄っすらとやさしい笑みを浮かべる。
「でも私、皆に良くしてもらって、本当に嬉しかった……。幸せでした……」
「羽村さん……」
ステンレスチェアーから腰を浮かせ、風花が真緒の顔を覗き込む。
「蓮木さん……、今まで私なんかの為に尽くしてくれて、本当にありがとう……。感謝しています……。それに比田くん……、もし良かったら、これからもみんなを守ってあげて……」
風花、圭吾、と順番に向けた視線を、真緒は最期に千秋の顔へと向けた。目を細めながら微笑む彼女。
「みんな、頑張って生きて……。私の分だけじゃなくて、先に死んだ智香や、クラスみんなの分も……」
真緒の笑顔は間近から何度も見てきたけれど、このときほど様々な感情が複雑に入り混じった表情は、かつて目にしたことが無かった。
さらに目を細めながら、彼女はゆっくりと口を動かす。
「千秋……、大す……」
途端、千秋の両手の中に納まっていた真緒の手から力が失われた。恐る恐る離すと、彼女の手は操り手を失った人形の物のように、重力に引っ張られるままベッドの上に崩れ落ち、ボスッと音を立てながら掛け布団に窪みを作った。
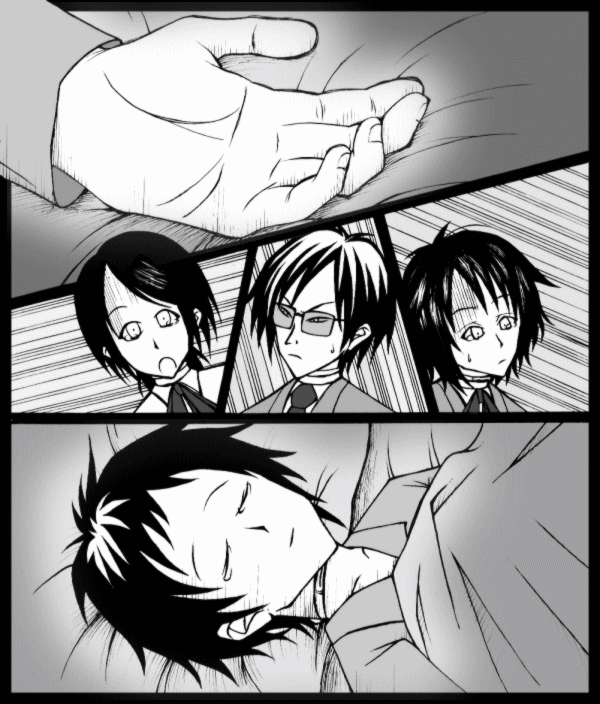
千秋はそれを呆然と見たまま固まってしまう。
「嘘……でしょ? だって真緒、今言おうとしていた言葉、まだちゃんと最後まで言い切れてないよ。ねぇ、もう一度ちゃんと言ってよ! 真緒! 真緒っ!」
目を閉じて、まるで眠っているかのように安らかな顔をしている真緒の身体を、千秋はベッドの上で左右に揺さぶった。しかし一向に、幼馴染は微動だにしない。
「真緒っ! 嫌! 嫌ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ!」
千秋の悲痛な叫び声は病院の壁を突き抜けて、雨の降り止まぬ鬼鳴島じゅうに響いていった。
 羽村真緒(女子十四番)――『死亡』 羽村真緒(女子十四番)――『死亡』
【残り 九人】 |
