生徒達が出払った後の木造校舎内。ほぼ正方形に近い教室内では、幾人もの兵士達が所狭しと動き回っている。皆それぞれの任務を全うしようと、真剣に何度も資料を読み返したり、あるいはコンピューターの操作、及び監視に勤しんでいる。
隆々とした筋肉質の身体を持つ彼らだが、自慢なのは体力だけではない。頭脳もなかなかに切れる者が揃っており、その仕事振りには穴など全くと言ってよいほど見られない。それだけに、担当教官である田中一郎からは大いに信用されていた。
そして田中自身は優れた兵たちに囲まれることによって、安心してプログラムの流れを見物することができる。
スポーツ観戦でもしているかのように、ゲームに変化が生じるたびに笑みをこぼす田中。先ほど男女一名ずつ死者が出たと知った際も、これまた満面の笑みを浮かべていた。
「よしよしよし! これで死者が五人。残りはちょうど四十人になったわけかぁ。いいぞいいぞ〜、なかなかのペースだなぁ」
田中は生徒名簿のコピーを手に取って眺めた。紙上では四十五人のフルネームが並列しており、そのうち五人の死者の名には上から赤ボールペンで打ち消し線が引かれている。
「しかし爆弾入りロッカーによる番狂わせは起こりませんでしたね。有力選手たちは皆無事に動き始めていますので、身体的に劣る生徒達はこれから厳しい戦いを強いられることになるでしょう」
横長のソファーに寝転んでいる田中へと歩み寄ってそう言ったのは、兵士達の長である御堂一尉。彼もまたプログラムの流れを司る存在であり、また田中をサポートする役割も担っている。抜群の統率力を誇る御堂は、田中には他の兵よりもさらに高く信頼されている。
そんな彼に田中は聞いた。
「ところで御堂。お前は今回のプログラム参加者の中で、特に目に付いた存在ってのはいたかぁ?」
その質問を受けた御堂は、しばし考えてから返した。
「そうですねぇ。まだ事前に得たデータと見た目でしかほとんど判断できませんが、気になっている存在はいくつか見られましたねぇ」
「ほぉ、誰だ? 言ってみろ」
「まずは男子の磐田猛ですね。心身共に強く鍛えられているだけでなく、行動力は目を見張るほど優れています。首輪に内蔵されている盗聴器から得た情報によりますと、プログラム開始前のトラック内では、他の生徒達に集合を呼びかけるという高い行動力を披露していたようですし」
「なるほどなぁ。他にはいるかぁ?」
「既に殺人を始めている御影霞なんかも実に興味深いですね。まあこれは説明不要でしょうね」
「ハァーッハッハッハ! 当たり前だ。何しろ彼女は――」
くだらない会話に花を咲かせる二人。同じ頃、生死の縁をさ迷っている学童達が存在するというのに、管理側の人間は実に上機嫌だ。自分達には危険が及ぶことのない高みからゲームを見物できる立場の人間達は気楽だ。仕事に勤しんでいるはずの兵たちも、モニターを見ながら時々微笑している。
しかし全員がそうではない。たった一人だけ、不測の事態発生に狼狽している者がいた。その男、桂木幸太郎という。
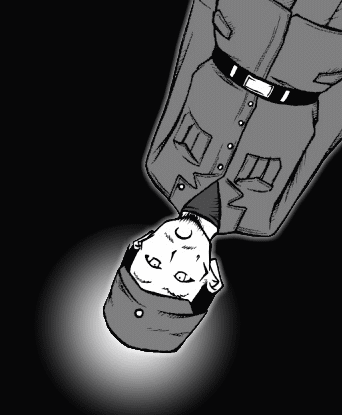
……なんで……なんで千秋ちゃんがこんな所にいるんだ?
プログラムの管理をしている兵の一人である桂木は、『松乃屋』という食堂の常連でもある。そしてその店の看板娘が春日千秋。今回のプログラム参加者の一人であった。
そういう理由で千秋とはもともと知り合った仲であった桂木。そのため、彼女が今回の殺し合いゲームの参加者としてこの島にいると知ったときは、心臓が張り裂けてしまいそうなほどに驚いた。
しかしだ。管理側であるはずの桂木が、何故当日までプログラム参加者の中に千秋が含まれていることを知らなかったのだろうか。実はこれには意外な理由があった。
もともと桂木は、今回の兵庫県市立梅林中等学校三年六組対象プログラムの管理に参加するはずではなかった。しかし、今回の作戦に参加するために事前に収集されていた兵の一人が、直前になって事故に遭ってしまったのだ。プログラムを運営する上で、開始前から人員が欠けてしまうのは許されない。そこでその穴を埋めるために、プログラム二日前にも迫っていたときになって、管理に協力して欲しいと桂木に連絡が届いた。桂木が選ばれた理由は単純明快。担当官の補佐である御堂の傘下の人間だったから。
あまりにも突然の連絡だったし、中学生同士に殺し合わせるということにも良い印象は抱いていなかったが、上官の命令とあらば逆らうわけにもいかなかった。
急遽、補充要員としてプログラム管理に参加する羽目になってしまった桂木は、前日にプログラム管理に必要な最低限の説明を受けた。しかしこの際、上官は管理に必要な説明だけを行い、プログラムに参加する生徒達に関しての情報は何一つ伝えてはくれなかった。開始日が目前に迫り、無駄なことを説明している暇がなかったのだ。
だが、もしも上官が対象校の名を口にしていたとしても、桂木はそれが千秋の学校であると分からなかっただろう。
桂木の職を知らなかった千秋と同じく、桂木も千秋が通う学校の名を知らなかったのだから。
所詮、二人の関係なんてこの程度のもの。相手のことで知っている部分なんて氷山の一角に過ぎない。しかし桂木は思った。
死なせたくない。あんなに良い娘を死なせるわけにはいかない。
自慢の料理を振舞いながら、女神のように微笑んでいた彼女の姿を思い浮かべた。
プログラムの説明を受けた帰りに、何気なく立ち寄った松乃屋。明日は殺し合いゲームの管理をしなければならないとうんざりしていた桂木の精神は、健気に接客に勤しむ千秋の姿を見ているうちに癒された。しかしこのときは、まさかこの少女が明日の殺し合いに参加することとなるとは思ってもいなかった。
一度プログラムに巻き込まれてしまった生徒を生還させるためには、この殺し合いの中で生き残ってもらう、それしかない。だが、あの女神のような少女がクラスメート達を殺しまでして、最後まで生き残ろうとするなどとは到底思えない。
上官に頼み込んでプログラムを中止させることも不可能だ。法律で決められたこの作戦は、ただの一兵士が止められるほどヤワなものではない。
いったいどうすれば良いんだ。
多数いる兵士達の中で、桂木一人が苦悩していた。そうとも知らず、田中と御堂の二人は未だにくだらない話に盛り上がっている。
プログラムはまだ始まったばかり。不安の色を浮かべる桂木の目線の先で、モニターは島の全景と生徒達の番号を表示している。その中で、赤い数字の3が、青の2に寄り添いながら、画面左下へとゆっくりと動いていた。
【残り 四十人】
|
