油断していたわけではない。いつ何処から誰に襲われてもすぐに反応できるよう身構えていたつもりだったけれど、一度見て誰もいないと判断してしまっていた方角から奇襲されては、さすがに驚かないわけにはいかなかった。心拍数が一気に急上昇したために、あまり豊かでない胸元が物凄いスピードで波打っている。
里見亜澄は太い木の幹を背にしながら、襲撃者の更なる攻撃に備えて武器を構えた。キャリコM950――螺旋状マガジンの長所である装填弾のコンパクトさを生かした、五十発という総弾数の多さが魅力的なサブマシンガンだ。
敵はすぐに迫ってくる様子もなく、また、身を隠した亜澄に向かってさらに銃を撃ってくることもなかった。懐から取り出した鏡に景色を反射させながら背後を確認してみたが、動くものは何一つ見られず。まるで誰もいないかのように静かだった。おそらくこちらが姿を見せるまで、向こうも下手に動くつもりはないのだろう。なかなか手ごわい相手かもしれない。
亜澄はチッと舌打ちしながら、ハードワックスでツンツンに立たせていたベリーショートの毛束をつまんで捻った。彼女の癖だった。
雨が茂みを叩くバラバラという音だけが辺りに延々と響き渡り続けている。時折、高い木の枝から滴り落ちる大粒の水玉がピシャンという音をたてる。
どうしよう。このままここに隠れ続けていても埒が明かないし、身を隠しながら荷物を持って密かに逃亡したほうが良いだろうか。
亜澄は眉をひそめながら考えた。そしてふと、自分の荷物に相手の銃弾が当たってしまったらしいということを思い出した。
そうだ、ギターは無事だろうか。
生まれ持つ防衛本能が働いて身の安全を確保することばかりに集中してしまい、大切な宝物の安否を確認することにまで、今の今まで頭が回らなかった。亜澄はすぐにショルダーベルトをひっぱり、ギターケースを手元に寄せる。
二年以上使い続けてきた愛用の合成皮革製のライトケースは、今は防水カバーに包み込まれている。そのため内側のギターが雨に濡らされる心配はなかった。命と同じくらい大切に思っている宝物なので、もし駄目になってしまうようなことがあれば、もう正気ではいられなくなってしまうかもしれない。
亜澄はすぐに異変に気がついた。防水カバーの真ん中に人差し指の先ほどの大きさの穴が開き、そこから雨水が内側へと流れ込んでいたのだ。
まさか……、そんな……。
我が目を疑った。相手が放った銃弾は、よりにもよってギターケースを、しかもど真ん中を貫いていたのだった。
急いでファスナーを下ろして中身を取り出すと、思った通り、亜澄にとって絶望的な現実が姿を現した。真ん中にあいた穴を中心に、スプルースの単板に長い亀裂が走っていた。
里見亜澄は昔からストリートミュージシャンというものに憧れていた。プロダクションからの指示に縛り付けられながらしか活動できないプロの音楽家たちとは違い、好きなときに好きな場所で気の向くまま自由に演奏出来るという生活スタイルが、とても輝いて見えたのだった。
そんな彼女が自分のギターを手に入れたのは中学一年の梅雨時。僅かしかない小遣いを小学校の頃から少しずつ溜め、そしてある程度額がまとまった頃を見計らって楽器店に入り、自ら購入したのだった。しかし所詮は中学生の買い物。あまり高級な品に手を伸ばすことはできない。
結局彼女が購入したのは、セール販売の目玉の一つとして半額にまで下げられていた安物のフォークギターだった。安物とはいっても、亜澄はその買い物にはとても満足していた。雑誌を読んで事前に決めていたボディの形状も、使われている木材の種類も、希望はほとんど叶っていたから。単板ではなく合板だったことが唯一願いとは違っていたけれど、それはもうこの価格では当たり前だとすぐに諦めがついていた。単板のギターというのは、何枚もの板をつなぎ合わせて表面を形成されたものではなく、大きな板一枚を贅沢にもそのまま使って作られたというものなので、大抵は値段が少し張ってしまうのだ。
ちなみにエレキギターではなくフォークギターを欲したのは、弦が奏でるアナログ的で味のある音色が好きだったから。主観だが、機械の楽器が生み出す音から深みというものは感じられなかった。
その日から、彼女は寝る間も惜しんでギターの練習に励んだ。雑誌を読みながらコードを覚え、楽譜の通りに弾いてみる。弦をはじく音自体が初めはおぼつかない感じだったが、時間が経つとともにそれもなかなか様にはなってきた。コードFも最初は少し苦戦したが、熱心に練習に励んでいたおかげか、弾けるようになるまでそれほど時間はかからなかった。
一ヶ月も経った頃には、亜澄はもうかなり自在にギターを扱えるようになっていた。といっても、弾ける人の目からすれば、亜澄の腕なんて人前で演奏するにはまだ早すぎるくらいだったが。それでも彼女は早く外で弾きたいという衝動に駆られて、ギターを抱えて家を飛び出した。
こうして彼女もストリートミュージシャンの仲間入りを果たすこととなった。ちょうど夏休みが始まった頃のことだった。
亜澄たちがよく利用する地元の駅(といっても自宅から自転車で二十分くらいかかる)は、国鉄と二本の市営鉄道が立体的に交差する点の上に存在し、かなりの規模を誇っている。
その辺りは人通りがとても多い活気のある場所であった。駅前広場の周囲には背の高いビルが群れを成すように建ち並んでいる。カフェテリアや駅前英会話教室の落ち着いた色合いの看板に挟まれるようにして、壁面モニターの中ではキャスターがニュースを読み上げている。一昨日から行われていた2005年第十八号プログラムの優勝者が決まったとか、なんとか。あまり興味は無かったのでしっかりとは聞いていなかったが。
ファッションビルがいくつか点在する中、亜澄は中央口の正面に建つ窓の多い開放的な外観の建物がお洒落な感じで気に入っていた。最近三階に入ってきたカジュアルショップが今マイブーム。自分の趣味とよく合った。
亜澄が演奏場所として陣取ったのは、中央口から少し西に離れたスペースだった。一番人が集まる駅前広場は三人組の素人バンドが占拠しており、入り込む余地はどこにも残されていなかった。自主制作したCDを出来るだけ多く人に売ろうと、三人は懸命にエレキギター、ベース、ドラムの音を響かせて自己アピールしようとしているが、遠巻きに見ている客達はなかなか動いてはくれない様子。
彼らの楽器が生み出す大音響は、離れた場所にいる亜澄の耳にもはっきりと届く。
よくやるよな彼ら、と客観的に思った。かつて『退廃音楽は禁止』とされていたこの国の中でロックを嗜むには、それなりの勇気が必要だ。最近は規制が少し緩和されてきているが、まだ世間的には鼻摘み者という印象が強い。
そういえば、一度だけ見学しに行った軽音楽部の先輩達も、世間体なんて気にすることなくエレキギターをかき鳴らしていた。同じく音楽を愛する者として、強調されたビートを好む先輩達の気持ちはよく分かった。自分だって音楽の趣味が彼らと同じだったなら、法で定められていようがなんだろうが、気にすることなく演奏するだろう。音楽とは誰でも自由に嗜むことができるからこそ素晴らしいものなのだ。何かに制限されてコソコソ隠れてしか演奏できない音楽なんて、楽しく思えるはずがない。
亜澄は地べたに座って、あるときは立ちながらギターを弾いた。修行不足のせいか初日は納得できるような演奏は出来なかったが、回を重ねるごとに路上で歌うことに慣れていき、十回目となると亜澄の演奏する姿はもう街の景色の中に完全に溶け込んでしまっていた。立ち止まって曲を聴いてくれる人も、少しずつだが増えていった。
「演奏上手ねぇ」
「なかなか良い曲だったよ」
わざわざ話しかけてくれる人もいた。若者だけではなく、帰宅途中のサラリーマンなんかも手を叩いてくれた。そういうふうに激励してもらえるととても嬉しかった。また、曲を聴いてくれる客の中には、ごくたまにお金を置いていってくれる人もいた。べつにこちとらお金が欲しくて歌っているわけではなかったが、そういう心遣いは正直言ってありがたかった。中学一年生で経済的余裕があるわけではない少女にとって、弦や楽譜を新たに買うための資金はとても貴重だったから。
そんな中、ある日、路上でギターを弾きながら歌っていた亜澄は、演奏の合間に突然見知らぬ男に話しかけられた。
「君、もしかして松乃中の生徒?」
亜澄はチューニングを中断して男の方を見た。グレーのブレザーに赤いネクタイといった見覚えのある服装。それはまさしく自らが通う松乃中等学校の男子の制服であった。
「ええ、そうよ」
亜澄は相手の好意的な態度に少しばかり好感を覚えたので、笑顔を作って答えることにした。
「やっぱり。もしかして梅林の子かもしれないと思っていたけど、同じ学校だったんだ」
松乃、竹倉、梅林の三姉妹校の制服はデザインが全く一緒。微妙に色の濃さが異なっているらしいが、並べて見比べても違いはよく分からない。また、竹倉を除いた二校の最寄り駅はここなので、制服姿のままこの付近をうろついている学生は、松乃中生なのか梅林中生なのか見分けが全くつかないのであった。
「何年生?」
「一年よ。中学に入ってまだそれほど経っていないわね。名前は里見亜澄」
「へぇ、一年でもう路上デビューか。凄いね。勇気いるだろうに」
「そうでもないわよ。前々から憧れていたし、早く路上に出たいってずっと思っていたから。ところであんたは?」
「ああ、俺は三年のオカダってんだ。路上は二年の終わりごろに始めた」
「そう。じゃあ年齢的にもストリートミュージシャンとしても先輩なわけだ」
見ると、オカダと名乗る男は右腕にギターを抱えていた。スプルース単板で作られている、たぶん亜澄の安物よりは高級な品。
「あんたも学校帰りに演奏しに来たの?」
「そう。本当はそろそろ受験勉強始めないとまずい時期なんだけれど、どうも部屋に篭ってじっと机に向かうってのは性に合わないらしくてね。結局チャリンコでここまで来ちゃったというわけさ」
ショートレイヤーの頭をかきながら白い歯を見せて笑うオカダ。別段美少年というわけではなかったけれど、笑顔はどこか爽やかで、見ていて少し清々しく感じた。
オカダの歌うポジションは、亜澄のいるスペースから十メートルちょっとほど離れたバス停の側と、いつもだいたい決まっていた。この辺りで演奏しているストリートミュージシャンは他にも何組か存在しているので、それに紛れて今まで彼の存在に気付けなかったようだ。
初めて言葉を交わした日以来、オカダはちょくちょく自分のポジションを離れて、亜澄に話しかけてくるようになった。話題となるのはほとんど音楽に関すること。何処其処のライブハウスに少し名の売れたグループがやってくるとか、誰々の新曲のプロモーションビデオはカッコイイとか。他愛も無い雑談だったかもしれないけど、同じ趣味を持つ者同士でのそういった会話はとても楽しく、ちょっと刺激的にすら感じた。
亜澄とオカダの間はみるみるうちに縮まっていった。といっても、同じギターを嗜む者同士として仲が良いだけであって、それ以上とも以下とも考えたことはなかった。ただ、彼と語り合うのはとても楽しく、もはや亜澄にとって無くてはならない時間となってしまっていた。
ある日、いつものように駅前へとやってきた亜澄は、正体不明の違和感を覚えた。駅周辺の様子がなんだか少し違っているように思えたのだ。
亜澄はすぐに辺りを見渡す。人が集まる駅の様子に変化は無く、ファッションビルの群れもいつもと同じように建ち並んでいる。ビルの壁面に付けられたモニターの中で、キャスターがニュースを読み上げているが、その内容が毎日変わっているのは当然のこと。違和感の原因であるはずが無かった。
では、いったい何がいつもと違うのか。
もう一度自分の周りを見回して、駅前広場内にいつも陣取っている三人組のバンドグループの姿が無いということにようやく気付いた。亜澄が路上で演奏するようになってから、彼らの姿が見られないのはこの日が初めてだった。
メンバーが身体の調子でも崩したのだろうか。
亜澄は勝手にそんなことを思っていたが、近寄ってきたオカダの言葉により、その考えは間違っていたと知ることとなる。
「ウワサで聞いたんだけど、彼らの内一人がプログラムに選ばれてしまったらしい」
「プログラム?」
毎年五十の中学三年生のクラスを無作為に選び、級友同士での殺し合いを強要するという、共和国戦闘実験第六十八番プログラム。
「あのバンドのメンバー、中三だったんだ」
「らしい。どこの学校の生徒かは知らないけど、俺と同じ学年だったんだ」
オカダは少し複雑な表情を浮かべる。自分と同じ歳の人間がおそらく近日中に命を落とすなどと考えると、嫌な気分になるのは当然だった。
亜澄が何気なくビルのモニターを見上げると、『2005年第二十一号目のプログラム開催される』という字幕が目に飛び込んできた。キャスターは感情の篭っていない口調で、淡々とそのニュースを読み上げている。
「人間って、いつ死ぬか分からないものなんだな」
突然オカダが言った。
「何を言いだすのよ、急に」
「急にじゃないだろ。いつも見ていた人間が、こうやって前触れもなく死に直面することになったんだ。次に俺が死ぬこととなる可能性だって十分にある」
その真剣な口ぶりを前に、亜澄はつい笑い出してしまう。
「何がおかしい」
「だってそんな真剣な態度、あんたらしくなかったからさ」
「それにしたって笑い事じゃないだろ」
「ごめんごめん」
一応口先だけ謝っておく亜澄。その態度にオカダは少し不満そうな顔をするが、話は続ける。
「なあ。もしも自分の死が間近に迫っていると分かってしまったとしたら、最期を迎える前に何がしたい?」
「私?」
「そう。運命に抗って死から逃れようとするか。最後に何処か行きたい場所に足を運んでみるとか。何かあるだろ」
「そうね……」
なぜオカダは突然こんなことを聞いてきたのかと疑問に思ったが、亜澄はついつい真面目に考えてしまった。相手の態度がとても真剣で、冗談めかした答えを返せる雰囲気ではなかったから。
「もし明日死ぬのだとしても、私は今日もいつもと変わらない生活を送るでしょうね」
「それはどうして?」
「そりゃあ、どうせ死ぬなら自分が今一番したいことをやっておきたいじゃない。で、私が一番やりたいことといえば音楽。だから死の直前も結局ここにやってきてしまう」
「呆れた。本当に音楽が好きなんだ」
「ええ。死ぬ間際までここで演奏し続けてやるわよ」
亜澄は強く言い切った。死ぬ間際にしたいことなんて他には何も考え付かない。いつもここから見ている景色を最後に目に焼き付けながら、自らが奏でる弦の音色を胸にしっかりと刻みつける。それさえ出来れば、あとは死んでも悔いは残らないと思っていた。
「決めた」
オカダは少しの間何かを考えていた様子だったが、急に自分の両膝を叩いて立ち上がった。
「もしさ、近々俺が死ぬようなことがあったら、このギターはお前が貰ってくれないかな。高級な品とは言い難いが、少なくともお前のものよりは良い品だ。音もいいし、お前ならきっと気に入るはず」
「はぁ? 唐突に何を言い出すのさ」
「まあ聞けって。俺だって自分がおかしなことを言っているのはよく分かってるさ。でもさ、俺だって今は中学三年だぜ。いつプログラムに巻き込まれても不思議じゃないし」
「プログラムに選ばれるのって、宝くじの当選確率よりも低いって聞くけど」
「プログラムっていうのは単なる例え話さ。それ以外の理由で死ぬ可能性だってある。事故とか病気とか」
「自殺とか?」
「おいおい。それはちょっと冗談が過ぎるぜ」
お互い様よ、と亜澄は思った。オカダの話は人の生死をネタにした質の悪い冗談ともとれる内容だったから。
「とにかく、もしものことがあったら俺のギターはお前に頼む。いつもは軽音楽部の部室に置かせてもらっているから、そこから勝手に持って行ってくれればいい」
「あんたが死んだらそのギターは遺品になるわけでしょ。当然あんたの家に持って行って家族に返すことになるわ」
「それはやめてくれ。うちの家族は受験勉強の妨げとなる俺の音楽活動を快くは思っていないんだ。ギターなんか返したところで、放置されたままホコリをかぶるだけだ。それなら俺と同じように音楽をこよなく愛するお前のような人間に渡ったほうがいい」
風に乗って聴こえてきていたストリートミュージックの旋律に、一瞬マヌケな音が混じった。演奏の途中で弦が一本切れてしまったのだろう。
「なんで急にこんなことを言うの?」
まるでもうすぐ自分は死ぬと決め付けているかのようなオカダの言い草に、亜澄は当然疑問を覚えた。
「嫌な予感がするんだ」
「予感ですって?」
「ああ。どうもここ最近妙な胸騒ぎがしてな。近いうちに何かよくない出来事が起こる気がする」
亜澄はプッと笑ってしまった。
「何を言い出すかと思えば。根拠もクソもあったもんじゃない」
「お前は笑っているが、実際のところそういう直感だってバカにはならないぞ。動物的勘ってのは聞いたことがあるだろう。危機が迫るのを感覚的に捉えるという能力は、生まれながら人間に備わっているのかもしれない」
「考えすぎじゃないの?」
「それならそれで良いんだが、困ったことに俺の勘は昔からよく当たるんでな。こないだも、雨の中交差点にさしかかったとき、胸騒ぎを覚えた直後、通りかかった車に雨水をはねられた」
「はいはい、分かりました。もしものことがありましたら、あなたのギターはありがたく頂戴させていただきます」
このとき亜澄は、オカダの予感とやらを全く信用していなかった。
数ヵ月後、亜澄の予想に反し、オカダの不安は見事に適中してしまった。彼はとある惨事に巻き込まれ、帰らぬ人となってしまったのだった。
オカダの命を奪ったのはプログラムではなかった。理科実験室からの出火が原因とされる学校火災。亜澄は素早く外へと避難したおかげで火傷一つ負うことなく済んだが、オカダは逃げ遅れ、炎の暑さに耐え切れなくなって三階から飛び降りたのが原因で死んだ。足から落ちれば骨折だけで済んだかもしれないが、飛び降り方が悪かったせいで全身を強く打ってしまったらしい。彼のクラスは二階にあったのだが、後輩に用があったとかで不運にも事件当時は上の階へと上がってきてしまっていたのだそうだ。軽音楽部の知り合いがそう言っていた。
亜澄はそれからも変わらず、駅前へとほぼ毎日足を運んだが、もちろんオカダが姿を現すことはもう二度となかった。相変わらず路上で演奏することは何よりも楽しかったが、いくらギターをかき鳴らしても欠けてしまった何かを満たすことは出来なかった。
被災者達が梅林中へと通うようになってからしばらく経ち、松乃中の跡地にいくつか残っていた施設の建物が潰されるという話が耳に入ってきた。その中の一つにクラブハウスがあった。校舎から少し離れた場所にあったため、炎の被害に遭わずにすんだのである。
クラブハウスの中には軽音楽部の部室もあった。オカダのことを思い出すと何故か悲しくなってしまうので、亜澄はとにかく彼のことを忘れようと、いままであえて軽音楽部の部室には近寄ろうとしなかった。しかし、クラブハウスが取り壊されると知ってからは居ても立ってもいられなくなり、ある日ついにその敷地内へと踏み入ってしまった。
火災発生からかなりの時間が経っていたので、オカダのギターはもう彼の実家へと返されているかと思っていたが、意外なことにまだ軽音楽部の部室の隅に置かれたままになっていた。
亜澄は迷わずそれを手に取った。ドレッドノートのボディは窓から差し込む太陽光を反射させ、美しい曲線を際立たせている。
試しに指先で弦を軽く弾いてみると、まるでチューニングされたばかりのように美しく洗練された音色が部屋中に弾んだ。
これは確かに良いギターだ、と亜澄は思った。ボディを形成する素材の質もそれなりに高いが、それよりも、音楽を愛する者に長きに渡って使われ続けたことによって経験が染み付き、練磨された深みのある音を出せる楽器に仕上がっていたのだった。
きっとオカダも、亜澄と同様に、演奏しながらギターに自らの愛情を注ぎ続けてきたのだろう。
そんな彼の思いが詰まった、いわば宝物ともいえるギターを、このまま埃をかぶらせたまま放置させておくのはもったいなかった。
「分かったよ。あんたのギターは私が貰う。そして、あんたの代わりにこのギターを毎日弾いてやる」
ギターの美しい音色を天上へと送り続けてやると決めた亜澄。気がつくと、彼女の潤んだ両眼から溢れた涙が頬に筋を作っていた。
それからというもの、亜澄は宝物となったオカダのギターを片時も手放すことなく持ち歩くようになった。そう、火事の前と後では、彼女が持ち歩くギターそのものが全く違ったものとなってしまっていたのである。ギターケースは前々から使用していた物だったので、その中身が変わっていることに気付く者は、当然クラスの中には一人たりともいなかった。
そして今、そんな彼女の宝物は、思い出とともに傷つけられることとなった。
銃弾に貫かれた表面板に走った亀裂は長い。亜澄は試しに弦を弾いてみたが、あの美しかった音色はもう生まれてこなかった。
「ぶっ殺してやるっ!」
亜澄はついに切れてしまった。プログラムに巻き込まれたと知った時点で、早々に自らの死を覚悟していた彼女だったが、生きている間に宝物のギターを壊されることについては我慢ならなかったのだった。
町中で坂本達郎に襲われた時以来、亜澄は一度も武器に頼ることはなかったが、ここにきて再びマシンガンの引き金を引くこととなった。大木の裏から彼女が飛び出した途端、ギターを撃ち抜いた犯人がいる方角に向かって、キャリコM950が火を噴いた。
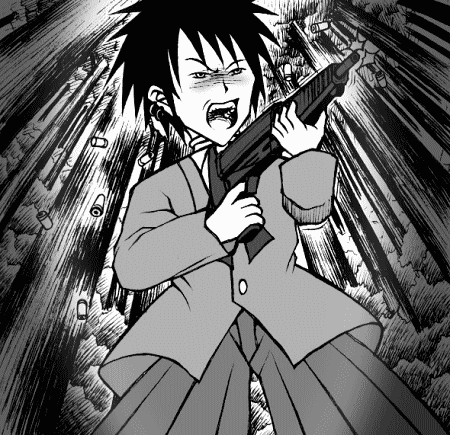
【残り 十一人】 |
