突然辺りに響き渡るキャリコM950の銃声。無数に立ち並ぶ木々の間で反響するそれは、射程内に隠れていた霞の耳にも当然届いた。
思わず身をすくめてしまう彼女。相手が何らかの武器を持っていることは分かっていたが、まさかサブマシンガンだとは予想してもいなかった。
仇である湯川利久を倒すためにより強力な武器を欲している霞にとって、サブマシンガンは喉から手が出そうなほど魅力的に思える品であったが、相手にするとなると非常に厄介だ。何十発もの弾を、間を空けることなく撃ち続けられたら、こちらが反撃に出る隙なんてほとんど無い。
嬉しさ半分、鬱陶しさ半分、といった感じだった。
さて、せっかく相手が姿を現してくれたわけだが。どうするべきか……。
ここで亜澄に向かって銃を撃ち返すために、下手に身を乗り出したりしたら、逆にこちらが鉛の雨を浴びせられてしまうかもしれない。もちろん、こちらが姿を見せないよう隠れながら発砲するなら、いきなり狙い撃ちされる心配はあまりないけれど、比較的危険が少ないというのは最初だけだ。初弾で仕留めることができなければ、すぐに銃声で相手にこちらの位置を知られてしまうだろう。
こちらの正確な位置がばれる前に亜澄を倒すには、一発で的を撃ち抜けるほどの至極正確な狙いが要求される。しかし、ついさっき分かったが、銃とはそう簡単に狙ったところに弾を飛ばせるものではない。そういう意味では、反動の少ない麻酔銃のほうが扱いやすいのかもしれない。
今回は麻酔銃に頼った方が良いかな、と霞は一瞬だけ思ったが、すぐに考えを改め直した。麻酔銃は上手く命中できたとしても、効果が現れるまでに少しだけ時間がかかってしまう、短期戦にはあまり向かない武器である。撃ったことによってこちらの位置を把握され、麻酔が効き始めるよりも前に攻め込まれてしまったらひとたまりも無い
おそらく、銃器という強力な武器を互いに持つ今回の戦いは、短い時間で決着が付くだろう。麻酔が利くのを悠長に待っている時間なんて無い中、結局は銃に頼る他ないのだった。
頭の中をフル稼働させて考えている間にも、マシンガンの九ミリ弾が、遮蔽物の後ろに隠れている霞の横を掠めるように過ぎ去っていく。無数に飛ぶ弾丸は、辺り一面に立ち並ぶ木々の固い幹に突き刺さり、または茂みの葉をピシピシとはじきながら森の奥へと消えていく。
程なくして銃声が一時的にだが止んだ。キャリコに装填されていた弾丸五十発全てが撃ち出されてしまったのだ。亜澄はすぐに後ろへと飛び退いて、デイパックの中から取り出した新たな弾を詰め込む作業に入る。どう考えても今が霞にとって最高のチャンスであった。
火災で負った傷の痛みに苦しむ私を放っておきながら、のうのうと今日まで生きてきたことを悔いて死になさい!
霞は頭の中で叫びながら、木の後ろから身体を出し、振り向きざまに一発撃った。いや、一発だけでなく、弾が尽きるまで連続して何回も引き金を絞った。
ダンダンダンダンダン……。
一定の間を崩さずに鳴り響く銃声は、まるで曲のリズムを刻んでいるかのようにも聴こえる。意識して間隔を揃えたわけではない。なるべく素早く、短い時間で弾を撃ち尽くそうとしたところ、引き金がやたらと重かったために、ブレス一つ分ほどの間が一発ごとに入ってしまったのであった。
ほどなくしてグロックは、いくら引き金にあてた指に力を入れてもカチカチとしか音がしなくなった。装填されていた弾が尽きたのだ。
やったか?
霞は半身を木の後ろに隠したまま、亜澄の方を覗き見た。が、亜澄は倒れてはいなかった。十発以上撃った弾の内いくつかは、相手の身体を掠めるくらいしたかもしれないが、大きな怪我を与えるには至らなかったようだ。弾の詰め込み作業を終えた彼女は素早く立ち上がって、がちゃんと音をたてながらマシンガンを再び前に構えた。
霞は、やっぱり、と思った。グロックを連続して撃っていたとき、どうも手元が安定しなかったのだ。腕に力が入らず、照準が震えた。仕方が無い。クラスメート達を地獄の業火に突き落とすため島中を駆け回り続けていた彼女は、プログラムが始まってから一度も休憩を取っておらず、体力がかなり磨耗されてしまっていたのだった。そんな状態で銃のグリップを握る手にいつも通りに力を込められるはずがなかった。
「そっちか!」
照準の定まっていなかった亜澄のマシンガンが、今度はほぼ正確に霞の方へと向けられた。恐れていた通り、グロックの銃声や銃弾がとった軌道から、こちらの居場所は大体割り出されてしまったようだ。
「死にやがれっ!」
マシンガンを乱射しながら亜澄が物凄い勢いで走り寄ってくる。
荷物を引き寄せてから、霞はたまらず後方へと駆けだした。相手に背中を見せるのは危険だが、仕方が無かった。このまま同じ位置に留まり続けたところで、数秒後にはどうせ亜澄に攻め込まれてしまうだけだったから。
走りながら弾の切れたグロックからジェリコへと銃を持ち替え、後ろに向けて数発撃つ。ろくに相手を見ずに発砲したところで命中するわけは無かったが、少しでも足止めになれば良いと思っていた。だが激昂した亜澄は二発三発の銃声なんかに恐れおののくこともなく、全力での疾走を一瞬たりとも止めはしなかった。
霞は森林の中をジグザグにカーブしながら走る。相手に銃の照準を合わせにくくさせる作戦だ。木々が盾の役割となってマシンガンの弾から身を守ってくれたおかげで、何とかすぐに被弾せずには済んだ。運が良かった。だがこのまま走ってばかりいても状況が好転することはないだろう。相手と自分の走力はおそらくほぼ互角。簡単に追いつかれることはないだろうが、引き離すことも容易ではない。この一定の間隔を保ったまま、相手にマシンガンを撃ち続けさせてしまうのは非常に危険だった。
分厚い茂みの中に飛び込んで相手の視界から姿を消した一瞬のうちに、霞は方向転換して左手に見えるブッシュの方へと走り、その後ろに身を隠した。直後、跡を追ってきた亜澄も茂みを突き破るようにして姿を現したが、彼女は霞の姿を見失ってしまったらしく、四方をキョロキョロと見回している。
「野郎、どこへいった!」
亜澄は怒声をあげながらマシンガンをでたらめに掃射し続ける。低木の合間を縫うようにして藪の中を突き抜けてきた銃弾が、霞の足元の地面に深く潜り込んだ。
しっかりとジェリコのグリップを握り締め、銃口を亜澄の身体へと向ける霞。だが、疲労が溜まっていたうえ全力で走ったために、息が荒くなって肩が大きく上下する。また、僅かに震えている肘から掌にかけて力が入らず、銃の照準は一向に安定しない。このまま発砲したところで、また狙いを外してしまうだけだ。そしてまた亜澄に追いかけられることとなる。同じことの繰り返し。
先ほどは運良く傷一つ負わずに済んだが、次もまた上手く逃れられるとは限らない。だから今度こそは正確な射撃を行い、こちらの位置を悟らせる暇も与えぬよう相手を仕留める必要があった。
なんとか銃の狙いを安定させる方法は無いか、と霞は考えた。疲労のせいで力の入らない身体では、もはや発砲時の大きな衝撃を抑えることはできない。
ふと頭の中を何かがよぎり、霞は傍らに目をやった。地面の上に置かれ、底が泥だらけになっている自らのデイパックがすぐそこにある。音を立てないように気をつけながらファスナーを引くと、妖しく光るナタの刃と麻酔銃の間から、注射器と白い薬物が頭を覗かせていた。ホワイトデビルだ。
霞はまるで何かに操られたかのようにそれを手にとり、じっと見つめた。劇薬の一種であるホワイトデビルは一度でも使用してしまうと、あまりの心地良さから身体はそれに依存してしまい、まるで悪魔に取り憑かれてしまったかのように止められなくなってしまうのだという。そして主に心臓や血管系に影響を及ぼす薬物に蝕まれた身体は内側からどんどん破壊されていき、限度を越えた使用を続けると、最悪の場合死に至ってしまうこともあるという。
しかし今はそんなことを気にしている場合ではない。かつて世界大戦時に軍需工場の労働者たちが徹夜作業を行う際にヒロポンを服用したように、霞もまた疲労した身体に力を取り戻すためにホワイトデビルの副作用に頼るしかなかった。薬に手を出すことだけは避けたかったが、復讐を遂げてもいない今、こんなところでやられてしまうよりは僅かな勝利の可能性に賭けるほうがマシだった。
急いで水に溶かした粉末を注射器で吸い上げ、針の先を腕に突き刺す。親指に力を入れてピストンを筒の中に押し込むと、白く濁った液体はゆっくりと身体の中へと流れ込んでいった。
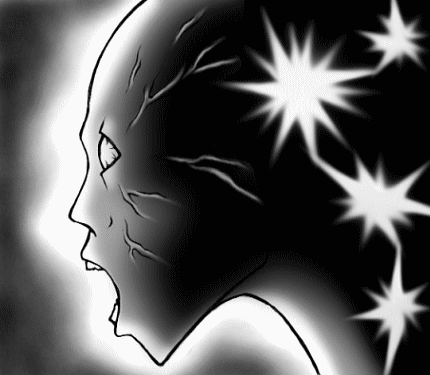
効果が現れるまで時間はあまりかからなかった。心拍数が急激に上昇して血液が物凄いスピードで体内を駆け巡り始めると、身体じゅうがだんだんと熱を帯びていく。
霞はその予想以上の効果に驚いた。身体の底から力が勝手に沸きあがり、疲れきっていた全身がまた自由自在に動くようになっていた。
これなら銃だって楽々と撃てるかもしれない。
試しにジェリコを前に突き出して構えてみた。重さというものがまるで感じられず、紙製の玩具でも持ち上げているような感覚だった。手の僅かな震えも完全に消え、照準も楽々と標的に合わせることが出来る。
藪の向こうでは亜澄がまだ何かを叫びながらマシンガンを乱射している。その姿はとても見苦しい。
霞は人差し指に力を入れて引き金を絞った。以前は固く感じられた引き金も簡単に動かすことが出来る。力を得た今となっては発砲時の反動もさほどたいしたものではなく、真っ直ぐ前を向いた銃口はほとんど傾きもしなかった。
勝負はたった一撃であっさりと決まった。藪の裏に霞が隠れているのにも気付いていなかった亜澄は真横からの狙撃に全く反応することも出来ず、一発の銃弾によって左の耳の下から右のこめかみへと頭を貫かれ、一瞬にして意識をなくしてしまったのだった。
「なるほど、これは素晴らしいわね」
霞は残った粉と注射器を少しの間見つめ、そして大事にデイパックの中へと戻した。もしかしたらこれから先にもまた世話になることがあるかもしれないから。危険な薬物だが、今回のようにほんの少量を服用するくらいなら大丈夫だろうと考えたのだった。
それにしてもなんという心地良さだろう。薬の効果なのか、それとも獲物を仕留めた充実感なのか、とにかく気分がとても清々しく感じられた。
「さて……」
霞は立ち上がって亜澄の死体のほうへと歩み寄る。ツンツンに固めた頭から赤いドロドロとした液体を流し続けている死体を足で転がして、その手から離れたサブマシンガンを拾い上げた。
「苦労した甲斐があったわね。奴に対抗できそうな武器がようやく手に入った」
奴、とはもちろん松乃中等学校を炎で包んだ犯人、湯川利久のこと。霞はサブマシンガン――キャリコM950を手にして微笑んだ。
クスクスクス、と、彼女の笑いが森林の中で静かに反響する。
 里見亜澄(女子九番)――『死亡』 里見亜澄(女子九番)――『死亡』
【残り 十人】 |
