「誰っ!」
風花は闇に向かって大きく叫ぶ。すると部屋の奥のベッド脇に屈んでいた黒い影が、ギクリと身体を一瞬だけ揺らした。
「なに……どうしたの?」
どうやら真緒はいつの間にか眠りについていたらしい。風花の大声によって目を覚ました彼女は、枕の上から頭だけをゆっくり浮かし、そして自分の横に立つ何者かの存在に気がついた瞬間「ひっ」と声を洩らした。驚くのも無理はなかった。千秋でも圭吾でもない正体不明の人物は、真緒の片腕をタオルでベッドの柵に縛り付けようとしていたのだ。
双眼鏡とゴーグルを合体させたかのような機器を顔面に装着した不気味な人影が、ゆっくりとこちらを振り返る。
「誰かと思えば、蓮木さんじゃないかぁ。なるほど、羽村さんと君は一緒に行動していたんだね」
男の声がした。
「誰よ! 大人しく両手を挙げてから名を名乗りなさい」
風花は腰に挿していたデザートイーグルを手にとって、暗闇の中に立つ影に向かって瞬時に構えた。
「物騒だなぁ。せっかくの可愛い顔を歪ませちゃって。いつもみたいにクールな表情をしているほうが、蓮木さんらしくて僕は好きなのに」
「さっさと名乗れ!」
言いつつも、風花はもう相手が誰なのか、声色から大体の目星をつけていた。生き残りが少ない男子の中から該当者を見つけ出すなんて造作も無いこと。
「つれないなぁ。小倉だよ。小倉光彦」
小倉光彦(男子三番)を名乗る影は、銃口を向けられても少しも恐怖を感じていないのか、「ヒヒッ」と小さく笑っていた。大人しく手を上げる様子は無い。
馬鹿にするような相手の態度に、さすがの風花も苛立ちを抑えることは出来なかった。
「手を上げろって言ってるだろ!」
「なぁに言ってるの。そっちこそ武器を下ろすべきだと思うよ」
「なに?」
「この子がどうなっても良いのかなぁ?」
直後、風花は恐るべき事態に気がついて、歪めていた表情をそのまま固めてしまう。いったい何処から調達してきたのか、光彦は手元で手術用のメスらしきものを鈍く光らせており、その刃先を真緒の首筋へとあてがっていたのだった。
「そんな物騒なもの、いったい何処で手に入れた?」
「そりゃあこの病院の中に決まってるじゃない。最初に入ったICU集中治療室にいっぱいあったから、ちょっと失敬してきちゃった。そんなことよりも蓮木さぁん、早くその銃を下ろさないと、君の大切な仲間の首が切り裂かれちゃうよ」
「馬鹿な。そんなこと、おまえの頭を撃ち抜いてでも阻止してやるわ」
「じゃあ試してみる? 君が引き金を絞るのと、僕が羽村さんの首筋を切るのとでは、どっちが早いか」
挑発するように言う光彦に対して、風花はとても「試してやろう」と返す気にはなれなかった。べつに光彦がメスを振るよりも早くトリガーを引く自信が無いというわけではなかったが、銃なんて触ったこともなかった自分が一発で光彦を撃ち抜けるという確証なんてどこにも無いのだ。怪我人である真緒をさらに傷つけられてしまうという可能性が一パーセントでもある以上、危険な賭けに出るわけにはいかなかった。
「おっと、羽村さんも動かない方がいいよ。少しでも妙な素振りを見せたら、その白い首が真っ赤に染まることになるから」
抵抗しないよう釘を刺された真緒は、恐怖のあまり身体を硬直させてしまう。きっと彼女、すっぱりと切られた自らの首から赤身が覗くグロテスクな光景を、一瞬頭に思い浮かべたに違いない。
「ほらほら蓮木さんも、いつまでも眉間にしわを寄せたままじゃ、可愛い顔が台無しだよ。ここはもう大人しく銃を下ろしてしまおうよ。さあ」
「なるほど。お前が顔に装着しているその機械、暗視スコープね。それが支給武器というわけか」
風花は光彦の言葉を無視し、状況から整理した自らの考えを口にした。この暗闇の中、相手の表情を鮮明に見ることができる理由なんて、これ以外に考えられない。
「外からこの部屋まで迷わず一直線に来られたのは、廊下に並ぶ足跡をスコープ越しに見つけ、それを辿ってきたから。そんなところかしら」
以前、雨が降る中、山中を歩き続けてきた千秋や圭吾の靴は、かなり泥にまみれていたはず。暗闇のせいで風花は気づいていなかったが、きっとICU集中治療室からこの病室まで、二人の足跡は道標のごとく床の上にくっきりと残されているのだろう。そして暗視スコープなら、暗闇の中でもそれを見つけることができる。もちろん、ICU集中治療室の窓へと続く、裏庭の土についた足跡も。
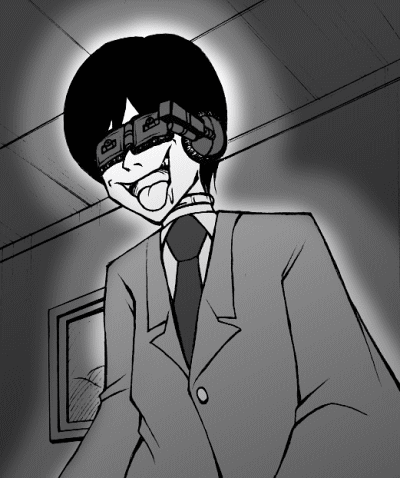
「ご名答。さすが蓮木さんだなぁ」
光彦の視線はずっと、銃を握る風花の手元へと向けられたままだ。「暗視スコープ越しに少しでも指先が動くのが見えたら、即座にメスで真緒の首の筋を切り裂く」、などと彼が無言の忠告をしているかのように感じた。
「言っておくけど、僕は死ぬこと対して恐怖を感じたりはしていないよ。むしろ才色兼備として名高い蓮木さんに殺されるなら本望だと思っているくらいさ」
「何が言いたい?」
「つまり、君がいくら武器で僕に圧力をかけようとしても無駄だってこと。この一触即発の時を終わらせるには、羽村さんが死ぬか、君が銃を下ろすが、そのどちらかしか無いのさ」
「……」
光彦の目的は何なのだろうか。態度や言葉から推察するに、この場にいる全員を殺そうとか、隙を見て逃げ出そうとか、そんなことを考えているわけでは無さそうだ。
「いったいお前は何がしたいんだ?」
「ちょっと蓮木さんとゆっくり話がしたいだけだよ。だから抵抗さえ止めてくれれば、君達に危害を加えるつもりは無い」
「なるほど……」
光彦は嘘を言ってはいない。クラスメート達より三年も長い人生経験を積んでいる風花は、相手の堂々とした様子からそのように判断した。不自然な動作をするとか、話し方が不自然になるなど、嘘をつく人間によく見られる変化が全く無かったから。
「分かった。とりあえず銃は下ろしましょう。もしあなたが悪意なんて本当に持っていないのだとしたら、私のしていることは失礼極まりないものね」
「さすが僕らのアイドル蓮木さん。話が分かるぅ」
風花は銃を握る右の手をゆっくりと下げた。だが、光彦が悪意を抱いてはいないなどとは、芥ほどにも思っていない。彼が真緒の腕を縛り付けていたのは、きっと彼女に何かよからぬことをしようと考えていたからだろう。思春期の男が考えそうなことだ。そんな光彦のことだから、おそらく今もろくでもない考えを頭に満たしているに違いない。
風花は万が一のことを考えて、下ろした銃を手から離したりはしなかった。
「とりあえず、大人しくあなたの話を聞こうかしら。じゃないと羽村さんの身が危ないというわけだし。でも、もしも妙な動きを見せたりしたら、そのときは問答無用であなたを撃つわよ」
念のためにこちらからも相手に圧力をかけておくことを忘れない。目には目を、だ。
と、そんなとき、風花は一瞬だけ意識が遠のくような感覚に襲われた。貧血による立ち眩みが起こったのだった。今の緊張状態を長く続けることは、あまり賢明ではなさそうだ。
「それで、話って何なの?」
さっさと光彦の気を済ませ、この場はお引取り願いたい。そんな一心で風花は話を切り出した。光彦は笑みを浮かべながら、ねとついた舌で唇を舐め回す。
「分かるでしょ。この時が来るのを、僕がどれだけ待ち望んでいたことか」
「何のことやら、さっぱり」
「あの日以来、僕はずっと君の事を見続けていたんだよ。恨みのこもった眼差しでね。まさかそれにも気付いていなかったの?」
「知るわけないでしょ。そもそも私はあなたに恨まれる理由も分からない。あと『あの日』っていったい何なのよ」
光彦は「やれやれ」とでも言いたげに、大きく溜息をついた。
「ショックだよ。全然覚えていないんだね。今からおよそ半年前の放課後に、僕は学校の下駄箱前で君に告白したんだよ。好きな女の子に向かって自らの想いをぶつけた、初めての告白だった。あの時の一言一言に、僕がどれだけ勇気を注いでいたか分かるかい? 分からないだろうね。なんせ蓮木さんには選び放題というくらいに男が群がっていたからね。結局、君は僕の気持ちなんて全く考えもせず、『あなたに興味が沸かない』なーんて言って、そのままどこかに消えてしまった。あの時、僕の心はズタズタに引き裂かれてしまったんだ。本当に胸が痛かった」
正直言って、風花は光彦に告白されたなんて全く覚えていなかった。実際、風花に近づいてくる男なんて何十人もいたわけだし、その中に光彦のような地味な男が一人混じっていたって、忘れてしまうのは無理もないだろう。
「蓮木さんを心から愛していたがゆえに、僕を斬り捨てた君への憎悪は大きく膨らんだ。そして自らが感じたのと同等の苦しみを返すチャンスは無いかと、僕はずっと君の事を監視し続けるようになった。授業中も、休み時間中も、下校中も、ずっと君の跡をつけ続けたよ。そうそう、だいたいの入浴時間を突き止めてから、一度だけ浴室を窓の外から覗き込んだこともあったっけなぁ。あの時はさすがに興奮した」
「最低ね」
光彦のしていることは、ほとんど――いや、完全にストーカー行為だ。たしかに彼の勇気を足蹴にしてしまった自分も悪かったのかもしれないけど、だからと言って不当行為を許すことはできない。風花は徐々に苛立ち始めた。
「でもさ、休日だって張っていたのに、いつまで経っても僕の復讐を遂げるチャンスは見つからなかった」
「あたりまえよ。好きな相手に振られた辛さは、他の苦しみとは全く違う。私に同等の苦しみを与えようとするなら、なんとかして私があなたに告白するように仕向けなければならない。けれど、私は絶対にあなたなんて好きにならない」
年上じゃないという理由もあるが、風花は光彦のような人目につかないような所でコソコソと何かをするような男は大嫌いだった。
「ふっふっふ、そんなこと僕だって分かっているよ。だけどね、あれだけ君を追いつづけても見つけられなかったチャンスが、今やっと目の前に訪れた」
「どういうことよ……」
いったい何がチャンスなのか分からない。風花は顔をしかめた。
「実はね、長い間君の生活を見ているうちに、一つだけ掴んだ事実があるんだ」
「どうせくだらないことでしょ」
「まあ最後まで聞いて。あれだけ沢山の男に言い寄られながらも、蓮木さんに特定の彼氏が出来るような様子はいつまでも見られなかった。近づいてきた男を全員斬り捨てたという噂は本当だったのさ。それで僕の頭には一つの考えが浮かんだんだ。もしかして蓮木さんって、そんな可愛い顔していながら、まだ生娘なんじゃないかってね。それどころかキスすらも……」
「……」
このご時世に『生娘』なんて言葉を使う中学生がいるとは珍しい。風花は級友たちよりも三つ歳が上だけど、もしかして光彦は何百という単位で歳を誤魔化しているのではないだろうか。
とまあそれはともかく、彼の予想は正解だった。中学生になってから告白にまともに応じたことも無い風花は当然、男性経験など皆無である。しかし、それがいったい何だと言うのだ。
すると光彦は突然、とんでもないことを口にした。
「それでは本題に入ろうか。蓮木さん。もし本当に羽村さんを傷つけられたくないのなら、今、この場で僕に向かって『好き』って言うんだ。いや、それだけじゃ物足りないな。『ずっと好きでした。私と付き合ってください』……。うん、これくらいの方がいいなぁ。それもちょっと頭を前に傾けて、恥ずかしそうに上目遣いで」
身体をくねくねとさせながら、一人で陳腐な脳内ストーリーを展開していく光彦。はっきり言って気持ち悪い。
「そして最後にキスをせがむんだ。『私の初めてをあなたにあげたい』って」
「その三流少女漫画みたいな告白を、あなたに向かってやれ、と?」
「そうそう。僕は気持ち良い思いができるし、お高くとまった君に屈辱味わわせることもできる」
満面の笑みを浮かべて頷く光彦。もともと血圧の低下で頭がふらふらとしていたのに、今度は頭痛まで始まってしまった。
「馬鹿じゃないの。そんなこと私がするわけ無いじゃない」
すると突然、光彦の表情が険しくなった。
「言う通りにしろ!」
左の手でもう一本隠し持っていたメスを取り出し、勢い良く宙で振り回す。支柱に吊るされていた輸血用の血液パックに切れ目が走り、真緒を助ける為に風花が採血した貴重な血液が流れ出した。
「なっ……」
「動くな! 一歩でも近寄ったり、銃を持ち上げたりしたら、今度こそこの子の首筋を断ち切るぞっ!」
突然のことに驚いた風花だったが、光彦の言葉によって再び身体の動きを止められる。メスの刃は真緒の白い首に食い込んでおり、ほんの少しでも動けば動脈が断ち切られることは明白である。
風花はどうすれば良いのか分からない。そのうえ、身体の調子がさらに悪化してしまったようで、目の前で二本のメスを構える光彦の姿が波打って見えさえした。
【残り 十二人】 |
