右腕に走る激痛が、だんだんと増してきている気がする。松原雛乃は走るスピードを急激に落とし、そして道の端で立ち止まった。
「大丈夫、雛乃?」
少し前を走っていた福原千代が、雛乃の異変に気付いて近寄ってきた。道の脇にあるコンテナに寄りかかって、雛乃はゼイゼイと息を荒げる。怪我を負っている状態での全力疾走は、体力の消耗が通常時とは比べものにならないほど激しかった。
「私のことなんかどうでもいいから、先に逃げて」
「何言っているの。雛乃を放っておいて自分だけ助かるなんて出来るはずが無いじゃない」
言って、雛乃の腕を引っ張ろうとする千代。しかし、苦悶の表情を見た途端、とっさに手を引くこととなった。
「ちょっと、怪我してるじゃない!」
肘の少し上辺りから、ストロベリージャムに似たドロドロとした血液が滲み出している。白石桜が乱射した、およそ十発の銃弾は、中沢彩音の命を奪うだけには留まらず、雛乃の右腕をも貫いていたのである。薄いグレーのブレザーが、だんだんと赤に侵食されていく。
「大変。早く手当てしないと」
千代は雛乃に肩を貸し、すぐ側にあるコンテナの裏へと移動した。コンテナ置場の中央に伸びる道からは死角になるそこを、一時的な隠れ場所にするつもりらしい。
「痛っ」
ほんの少し肘を動かすだけで、全身を駆け巡るほどの強烈な痛みが傷口から発せられる。かなりの重傷だった。雛乃は右腕を押さえたままコンテナの表面に背中をつけ、ズルズルと力無く屈み込んだ。
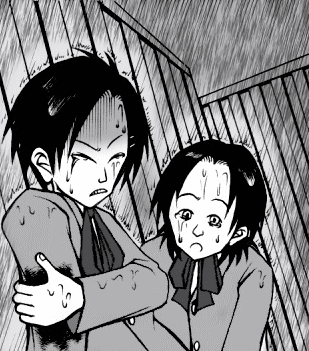
「と、とにかく腕を縛って止血しよう」
このまま傷を放っておけば、出血多量で大変なことになってしまう。早く血を止める必要があった。しかし、止血に適した布なんて、そう都合よく持ち合わせているはずがない。唯一千代の手元にあるのはハンカチだったらしいが、いくら雛乃の腕が細くても、腕を一周させられるほどの長さなんて無い。また、衣服を破いて止血に用いるという方法もあるが、ブレザーは頑丈な生地でつくられているため、まず破くことが難しいだろう。
「ごめん雛乃。こんなのしか無いんだけど、今は少し我慢してて」
挙句、千代が手にしたのは、脱いだばかりの自らのソックスだった。梅林中指定のそれは膝上までの長さがあるので、たしかに腕を縛るだけの長さは十分にある。なるほど、考えたものだ。
すぐにソックスはブレザーの上から腕にあてられ、そして傷口よりも肩に近い部分が強く縛られる。その際に、また耐え難いほどの痛みを感じはしたが、千代に気を遣って、漏れそうになった声をなんとかかみ殺した。
応急処置をなんとか終えると、千代は力を失ったかのように、急に隣に座り込んだ。見ると、彼女は雛乃のように重傷こそ負ってはいないものの、膝の辺りに弾丸がかすったことによってできたらしい擦り傷が見られた。
「ねえ雛乃、どうしよう。彩音が……彩音が死んじゃった……」
千代の声が震えていた。いや、声だけではない。雛乃の左肩に触れる体そのものが、恐怖に耐えかねて小刻みに振動している。
怖いのは雛乃も同じだった。突如目の前に現れた桜がマシンガンを乱射し、彩音の全身が貫かれる。そのときの光景がフラッシュバックするたびに、冷たい何かが全身を駆け巡るのだ。
「気にしないで千代だけでも遠くに逃げてくれればよかったのに」
「さっきも言ったでしょ。雛乃が苦しんでいるのを見て、放っておくことなんて私にはできない」
雛乃はふと思い出す。
――雛乃ガ苦シンデイルノヲ見テ、放ッテオクコトナンテ私ニハデキナイ。
昔、全く同じことを言われたことがある。たしか今から二年前のことだ。松乃中等学校大火災が起こったあの日。校舎西側の二階にある技術工作室で、「犯行」を終えたばかりの雛乃の前に現れた千代たちが発した言葉だった。
そうそう。私が自分の罪を彼女達にまで背負わせてしまったのは、まさにそのときだったな――。
過去に起こった出来事に思いをはせる雛乃。しかし、再び腕に激痛が走ったことにより、現実へと引き戻されることとなる。
危なかった。もう二度と開けぬと決めたはずの記憶の引き出しを、またしても引っ張り出してしまうところだった。精神状態が不安定になっているせいなのか、過去を封印すべく厳重にかけていたはずの鍵が、緩くなってしまっているようだ。これからは、より気をつけなければならない。
「ところで、フミは?」
千代は急に辺りを見回し始める。雛乃も混乱していたためか、フミの姿が見えないことに、つい先ほどまで気付いていなかった。というより、他人のことを気にしていられるだけの余裕なんて無かったのだった。
「どうやら、逃げる途中ではぐれちゃったみたい」
桜に襲われたとき、フミは間違いなく自分達と一緒に駆け出していた。おそらく、コンテナ置場に入るか否かというところで、違う道に入ってしまったか、あるいは置いてきぼりにしてしまったのだろう。
「まさかフミ、もう追いつかれて殺されちゃったりしてないよね」
「たぶん、それは大丈夫でしょう」
「ならいいけど」
彩音が殺されてからは、付近で銃声が鳴り響いたりはしていない。とりあえずフミも今はまだ襲われてはいないはずだ。しかし早くこの危険な場所から逃れなければ、桜を引き連れた利久に追いつかれて本当に命の危機に晒されてしまう。フミだけではなく、それは雛乃たちにも言えることだった。
「でも、なんで桜は私たちを襲ったの……」
膝を抱えていた自らの腕の中に顔を埋める千代。桜は今でこそ精神に異常をきたしてしまっているが、かつては人間だけではなく、万物を愛せる優しい子であった。三年間同じ学校で過ごしてきて、桜のことを少しでも知っていた人間であれば、彼女の変化を信じ難く思ってしまっても仕方が無い。
「彼女、たぶん何らかの方法で湯川に操られているんだと思う」
「湯川?」
千代が眉をひそめる。
「どうしてそんなことを思ったの?」
「私、見たんだ。彩音が死んで、私たちが逃げ出した直後、桜の後ろから彼が現れたのをね。あの醜悪な笑みは忘れようにも忘れられない」
「……最低」
千代が歯を噛み締めた。そして、脇に置いていた武器――HK69グレネードランチャーを拾い上げ、その一般の拳銃よりも一回り大きな銃身をじっと見つめた。
「私、絶対にあんな奴の思っている通りに殺されはしない。もしも私に向かって牙を剥くなら、逆にこちらから噛み付いてやる。そして、湯川に操られていた桜を救出する」
そう言っている時の彼女の目は本気だった。自分の目の前で彩音が殺されてしまったことに、激しく熱り立っているのだ。
福原千代とは一見大人しそうに思えるが、実のところ、そのイメージは全くの誤りなのである。意外なことに、彼女は地元に拠点を置くプロサッカーチームのサポーターであり、ホームスタジアムで試合があるごとに、チームカラーである黒の法被を着て、試合会場へと出向くのだ。そしてメガホン越しに声を張り上げてチームの応援をする。そんな人一倍熱い精神を持ち備えた少女なのである。
元々は、とある選手の追っかけをしていた友人に誘われるままに試合観戦していただけだったが、いつしか自分の方がはまってしまったのだ、と彼女は以前言っていた。
「雛乃、歩ける?」
「う、うん。一応」
「良かった。それじゃあ早いうちにここを離れよう」
「フミを探すの?」
「もちろん」
ろくな武器も持っていないフミは、マシンガンを携える湯川たちに見つかってしまえば一巻の終りだ。
「そして無事にフミと再会できた暁には、彩音の敵討ちとして湯川を殺そう」
怒りに満たされてしまっているせいなのか、もはや千代が最後に放った言葉とは、実に彼女らしくない過激なものだった。
【残り 十五人】 |
