倉庫街の中心をまっすぐ伸びる道の上を、必死になって走っているのは三人の少女。慌てて逃げるその姿は後ろから見ていると、サバンナの真ん中でライオンにでも襲われた、インパラかトムソンガゼルみたいに思えて、なんだか面白かった。
「二手に分かれたか……」
雛乃たちが倉庫街の奥へと姿を消すのを見届けてから、湯川利久はゆっくりと白石桜のほうへと歩み寄る。銃撃の勢いで後方に倒れてしまった彼女は、何が起こったのか理解できていないのか、立ち上がりもせずに、ただぼんやりと遠くを見つめている。そういえば、彼女に本物の銃を撃たせてみたのは、今回が初めてだった。
「銃を撃つ時に生じる衝撃への対策を、まだ教えていなかったな。いいか、よく聞け、桜。射撃時は前に突き出すように利き腕をまっすぐ伸ばし、反対側の脇はしっかりと締めるようにしろ。そして利き手には力を入れない。重心は前に出した足に七割、後ろに引いた足には三割だ。これでいくらかバランスを取りやすくなるはず。次からはこれをしっかりと守れ」
桜はコクンと頷いた。彼女は本当に聞き分けが良く、主の言葉を忠実に守ってくれるので、こちらとしては凄く楽である。この倉庫街に入って彩音たちの姿を見つけた際に出した、「やつらに向かってマシンガンを乱射してこい」という命令にもしっかりと従ってくれたし。あとは銃器の扱いにさえ慣れてくれれば、操り人形としてとても優秀だと言えるようになるだろう。
「さて」
桜の手を引いて立たせてから、血塗れになって倒れている彩音の死体へと歩み寄る。かつては陸上選手として活躍していた彼女の成れの果ては、大変惨たらしいものであったが、可哀想などと哀れむ気持ちなんて一切沸いてはこなかった。大きく振った足の先で蹴り上げると、死体は二回三回、ごろごろと転がる。
「使い物にならないな……」
死体の下から出てきたのは、単なる皮製の鞭だった。新たに手に入る武器は何か、と、少なからず期待を膨らませていただけに、利久は、はぁ、と溜息を吐かずにはいられなかった。
「仕方ない。今度に期待するしかないな」
はたして、次に倒す敵はどんなアイテムを落としてくれるのだろうか、と、考えているとなんだか楽しくなってくる。
そう。利久は今、純粋にゲームを楽しんでいるのである。プレイヤーとしてコントローラーを握るのは、もちろん湯川利久。ゲームの中の主人公は白石桜。そして敵は、自分達の前に立ちはだかる愚かな生存者達全て。
自ら直接手を下さずとも、残り少ない生き残りが桜の手にかかって死んでいく。それを離れた場所から見物するというのは、彼にとってはほんの少し贅沢な娯楽でしかなかった。別にこれは異常なことではないはずだ。ボクシングやプロレス、あるいはK−1といった格闘技を楽しんで観戦することと、何ら変わりないだろう。
ゲームをプレイすることにも格闘技観戦にも共通して言えることだが、それらを娯楽として楽しんでいる者たちは皆、テレビ画面の前やリングの外といった、自らには危害が及ばない絶対安全な場所にいる。というより、そうでなければ安心して戦いを楽しむことなんてできないだろう。だから利久も、最前線には桜を送り、自分はその後ろに隠れて、安全な所から成り行きを見ていることにした。その結果、思った以上に楽しむことが出来た。敵は桜の姿にばかり目を奪われるので、利久の存在には気付かない。だから自分に武器を向けられる心配など当然無い。そんなわけで、目の前で人が虫ケラのように死んでいくのを、心置きなく見物することが出来たのであった。
自ら人を殺すのとはまた一味違った快感。なんだか病みつきになってしまいそうだ。
ところで、こちらの本性を知ってしまっていた数少ない人物の一人、雛乃をこうも早く見つけられたというのは幸運だった。おかげで僅かに存在していた不安要素を、早々と取り払うことができそうである。
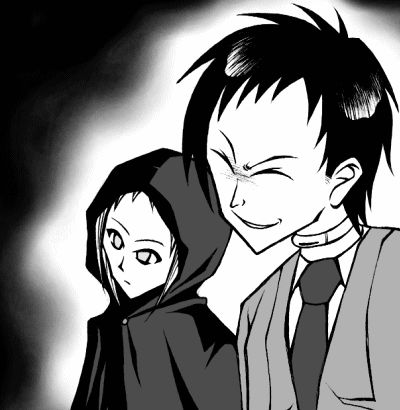
「さあ、さらに奥に進もうか。生存者はまだこの近くに存在している。奴ら全員を追い詰めて、一気に片付けてくるんだ」
逃げた女子は全部で三人。死んだ彩音よりも身体能力的に劣る者ばかりだし、おそらく武装した桜の相手にはならないだろう。しかし、彼女を育成するための餌としては使えなくもない。
ちなみに、前線に立たせた桜が敵の反撃にあって、逆にやられてしまうということも考えられなくはないが、まあ、実際にそんなことが起こる可能性なんてほとんど無いだろう。それでももしものことが起こってしまった場合は、残念だが、桜に握らせていたスコーピオンを回収し、自らの手でゲームを終わらせるしかない。できればそんな味気の無い終わりを迎えたくは無いが。
コンクリートの地面を見ると、赤い血痕が点々と、倉庫街の奥へと向かって続いている。先ほどの桜の襲撃によって、身体のどこかを負傷してしまった者がいるらしい。
なるほど。この血痕を辿っていけば、苦労することなく奴らを見つけることができるというわけか。
毎度おなじみの不気味な笑みを湛えながら、ビーコンのダイヤルをいじる。受信範囲を絞ってしまえば、敵までの距離が近くなれば利久にはすぐ分かる。逆にこちらが気配を殺していたら、雛乃たちには、いつ利久と桜が接近してくるかなんて、察知しようもない。つまりだ。こちらから奇襲を仕掛けることはあっても、雛乃たちから先制攻撃されてしまうなんてこと、絶対にありえない。
余裕だった。
「ちょっと止まれ、桜」
道の上に垂れている血の量から察するに、怪我を負っている者は複数いる。となると、三人の標的たちは、短時間ではそう遠くには逃げられないと思われる。
血痕は北へと向かっている。その先にあるのは大型のコンテナ置き場だ。負傷して行動力が低下している彼女達は、きっと桜を連れた利久が自分たちの後を追ってくるだろうと考えて、思い思いの場所に潜みつつ、じっと身構えていることだろう。
「少し接近の仕方を変えてみるか」
何も相手の思っている通りに登場してやる必要はない。それならば、奴らの想像を逆手にとって行動してみるというのもまた一興。
利久はそんなことを思った。
立ち並ぶコンテナによって形成された巨大迷路を舞台に、命をかけたサバイバル鬼ごっこが、今ここに始まろうとしていた。
【残り 十五人】 |
