出来心で犯してしまったほんの些細な罪。
べつに誰かに迷惑をかけたというわけでも無いし、そんなものはすぐにどこか遠くへと消え去ってしまって、明日にはいつもと変わらぬ日常が戻ってくるはずだと思っていた。だけど不幸にも悪魔に魅入られてしまった私は、元の毎日を取り戻すことも出来ず、だんだんと泥沼へと引きずり込まれていくばかり。
開放されたいという望みは一向に受け入れられず、気がつくともう後戻りできない所にまで来てしまっていた。弱りきった心をさらに締め付けられる毎日は苦痛だった。
そんなある日、何の前触れも無く『あの事件』が起こった。そして耐え難い地獄のような日々は突如終りを告げる。なんということか。皮肉にも、新たに訪れた地獄が、かつて私を苦しめ続けた地獄の上に覆いかぶさり、何もかもをかき消してしまったのだ。もちろんその際に失われてしまったものは多く、とても喜んでばかりはいられなかったが、待ち望んだ自由をついに手に入れたというのも事実。なんとも複雑な思いだった。
数日が経過し、私は落ち着きを取り戻していくにつれて、今度は恐怖に打ち震えなければならなくなった。あの時いくら必死だったとはいえ、どうして私はあんなにも恐ろしい行動を起こせたのだろうか、と。今からすれば、あのときの自分は、もしかしたら他人に操られていたのではないか、なんて思えてくる。しかしそれは単なる現実逃避でしかない。私は自らの意志で動き、そして許され難き罪人となった。これは覆しようのない真実なのだ。いや、それだけならまだ身に覚える苦しみなど、たいしたことはなかったかもしれない。それより問題なのは、私一人だけが負うはずだった罪を、他者にまで『分配』してしまったということ。何故あの時、それを止めることができなかったのだろうか、と、いくら悔やんでも悔やみきれない。
――もはや自らの死をもって償うしかない。
勇気が出なくていつまでも行動に移せなかったその考え、今度こそ実行するべきなのだろうか。
「ねえ雛乃、大丈夫?」
対面する位置に屈んでいる中沢彩音(女子十二番)に肩を揺すられて、松原雛乃(女子十九番)は、はっと意識を取り戻した。どうやら過去の忌まわしい出来事に思いをはせていたせいで、仲間の話をあまりきちんと聞けていなかったらしい。
ちゃんと屋根のある場所で雨を凌いでいたはずなのに、大粒の水玉が額を伝っている。暑くも無いのに汗をかいてしまっていたのだった。
この島の東部には小さな港湾がある。現在雛乃たちがいるのはそのすぐ近くの倉庫街。仲間たちといっしょに、一箇所で小さく固まって雨宿りしている最中だった。
「大丈夫。ちょっと考え事をしていただけ」
七と三の割合に分かれた自らの前髪のうち、三の方を止めているヘアピンに指先で軽く触れながら、雛乃は仲間の問いかけに答えた。しかし「大丈夫」だなんて、どう考えても嘘か強がりでしかない。プログラムの最中にいつもと変わらぬ調子でいられるのなんて、よほど無神経な人間か、心無い殺人者へと化してしまった者くらいだろう。雛乃はそのどちらでもない。
仲間たちは雛乃の嘘には気付いていただろうけれど、誰もさらに追求してきたりはしなかった。気遣いはとてもありがたかった。
「ボーっとしていてごめん。それで、いったい何の話をしていたんだっけ?」
「この倉庫には何が入っているのかな、って話していたのよ。別にどうでもいいことなのかもしれないけれど、何か喋っていないと不安でね」
心ここにあらずだった雛乃のために、他人思いの彩音は面倒臭がることもなく、現在の話の流れを教えてくれた。雛乃は側に建つ倉庫を一瞥する。
「で、雛乃はどう思う?」
「うーん。魚群を捕獲するための網とか。あるいは船そのものとかがあるかもしれない」
「船か――。だったら、この首輪さえ無ければ、無理矢理に運転してでも島から逃げ出してやりたいんだけどね。船舶免許なんて持っていないけど」
周囲には大きな倉庫がいくつも並んでおり、どれもシャッターがしっかりと下ろされている。中が見えないので確かとは言えないが、おそらく船を運航するのに必要な用具なんかが主に保管されているのだと思われる。また、倉庫街の北側が輸送用コンテナの置場となっていることから考えると、これらの倉庫のうちいくつかは、島の外から運搬されてきた物資の置場として使われている可能性も高い。
目の前に立つ倉庫の屋根の向こうには、塔の如くそびえ立つ大型クレーンが、コンテナ一つを高く吊り上げたまま止まってしまっているのが見える。プログラム開催の為に島民達が島から追いやられ、以降ずっとあのままなのであろう。
「それにしても、こういうところも人気が全く無いとなると、なんだかちょっと不気味だね」
「でもそんな不気味な場所に、雛乃も一人でよく来られたよね。おかげであたしたちと合流することができたんだけどさ」
「そうそう。もう二度と会えないかと思っていたから、あの時は本当に嬉しかった」
雛乃の右隣に座る福原千代(女子十七番)が顔をほころばせる。うなじの辺りで縛られた左右の毛束が弾む様は、彼女の喜びをそのまま表現しているかのようだった。
ところで「千代」という名前、個性的で良いなと雛乃は思うが、なんだか年寄りみたいだ、と本人はあまり気に入っていないらしい。
「本当。私もまさか皆に会えるとは思っていなかった」
雛乃は頭の中に根付いている恐怖感を押さえつけながら、半ば無理矢理に笑顔を作る。
もともとは山の中でスタートを切り、森林の奥深くを彷徨い続けていた雛乃。しかし、とある生徒と遭遇してしまったことによって死の恐怖を体感することとなり、一気に膨張した不安に耐えられなくなって、薄暗く不気味な山から急いで駆け下りてきた。そして偶然行き着いたのが、港湾の側にあるこの倉庫街だったのである。背後から誰かに声をかけられたときは心臓が止まりそうになるほど驚いてしまったが、相手の正体が彩音たちだと知った時は、心底ほっとした。彼女達とは前々から仲が良かったので。
そのころ、同じクラブに所属していた山崎和歌子が死んでしまったというショックもあってか、彩音は気持ち的に少し沈んでしまっている様子だったが、時間が経つとともに回復していったようだ。今や、緩やかにカールした長髪をかき上げる姿は、いつもの彼女とあまり変わりない。
そういえば、今ここに集まっているメンバーって……。
雛乃は仲間達の顔を見ているうちに、またしても過去の記憶を引き出しから引っ張り出してしまいそうになった。が、既の所で思いとどまる。あんな出来事はもう思い出したくない。何もかも忘れてしまいたかった。
ちなみに雛乃が仲間入りするよりも前の話となるが、彼女たちはかなり早い段階で合流できていたらしい。プログラム開始直後から広く行動していた彩音が、すぐに千代たちを見つけ出し、一緒にいようと呼びかけたのだそうだ。さすが体育会系というべきか、行動力の良さは雛乃なんかとは比べものにならない。
ただ、出会ったのが偶然にも善人ばかりであったから良かったものの、もしも殺意を抱く人間と鉢合わせていたなら、今はもう彼女の命は無かったかもしれない。「他人を見る目は持ち合わせているつもりだから大丈夫よ」と、雛乃の心配をよそに彩音は簡単に言うが、人間の考えていることなんて見た目だけでは分からないし、いつも思うようにばかりはいかないはずだ。実際、雛乃だってとあるクラスメートの変貌ぶりには、思わず自分の目を疑ってしまったのだから。
「ねえ雛乃。何度も聞いてしつこいようだけど、湯川くんが新田くんを殺したっていう話は本当なの?」
合流してからこの質問をされたのは何度目だろう。突然思い出したかのように口を開いた千代の表情に、うっすらと陰りが生じる。
「ごめんね。私、未だに信じられないの。あの湯川くんが人を殺すだなんて」
千代の気持ちは分からなくもない。利久はいつも笑顔を絶やさない人間で、いかにも平和主義者といった雰囲気を漂わせていたから。しかし雛乃は見てしまったのだ。森林の中で出会った利久の背後で、慶介らしき人間の体が大木の表面に打ちつけられていたのを。さらに決定的だったのは、顔を合わせて言葉の一つも交わさないうちに、容赦なく利久がこちらに銃を向けてきたということ。彼が顔中に湛えていた笑みはとても不気味で、思い出すだけでも鳥肌が立つ。あのとき、もしも荷物を投げ出してでも逃げようとしていなかったら、雛乃はその場で撃たれて、慶介と同じ運命を辿ることになっていただろう。
「信じられないかもしれないけど、湯川くんには注意しなきゃ駄目。彼は本当に危険な人間だから。お願いだから、分かってちょうだい」
雛乃がこうも真剣になって言うのは、皆の命を危険に晒したくはないという思いがあるから。これ以上、クラスメート達が死んでいくのを、ただ黙って見ているわけにはいかない。
すると突然、仲間を説得しようとする雛乃の口に、何かが放り込まれた。甘い味が口の中いっぱいに広がる。
「ちょ、ちょっと。これ何?」
「ただのキャラメル。貴重な糖分だから吐き出したりはしないでね」
左隣に座る少女が、手に持った黄土色の箱を指差している。キャラメルのパッケージだ。
「難しいことを考える時は、少しでも血糖値を回復させておいたほうがいいのよ。鈍った思考能力ではろくな考えが思いつかない」
そう言って自分の口にもキャラメルを放り込んでいるのは熊代フミ(女子六番)。大の甘い物好きであり、いつも何らかのお菓子を持ち歩いている。あるときは飴玉の袋で、あるときはチョコレートの小箱だったりした。で、今回はキャラメルだった、と。
目つきが少し悪いせいで、一見しただけでは暗い印象を受けてしまいがち。雛乃の知らないところで色々と損をしているらしい。
彼女はコンクリート製のブロックに腰掛けたまま、少しだけ前屈みになり、曇り無き眼でこちらの顔を見据えてくる。
「私は信じるよ、雛乃の言っていることをさ」
「あ、ありがとう」
キャラメルが入った口をもごもごとさせながら、雛乃はフミに礼を言う。
「それで、千代は結局どうなのさ? 今もまだ雛乃を信じないで、『湯川くんはそんな人じゃない』とでも言うつもり?」
「いや……。よく考えると、雛乃が私たちに嘘を言っているとも思えないし。となると、やっぱり湯川くんに近づくのは危ないのかなとは思う……」
「あたしも、雛乃の言っていることを信じるつもりよ」
「じゃあ彼には気をつけるってことで決まりね」
そしてここから、『利久のようにやる気になっている者を見つけてしまったとき、どう対処すれば良いか』が議題の中心となっていく。
「気づかれない内にそっと逃げるのが一番だよね」
「でも、四人も固まっていたら、目立たないように行動することは難しいと思う。見つかってしまったときのことも考えておかないと」
「一目散に走って逃げる、っていうのは駄目かな?」
「陸上部の私ならともかく、皆が上手く逃げきれるとは限らないわ。それに、銃火器を持っているかもしれない相手に背中を向けるなんて、そのほうがよっぽど危険すぎる」
意見はなかなかまとまらない。そんなとき、フミの手が小さく挙げられた。
「逃げるのが駄目なら、こちらからも反撃すればいいんじゃない? もちろん、相手が危険な人物だったときに限る話だけど」
皆が一瞬黙り込み、ほぼ同時に息を呑む。
「反撃――って。ようするに、私たちも相手に武器を向けるってことでしょ。同じ教室の中ですごしてきた、かつての仲間に向かって。そんなこと、あたしにはとても――」
「そりゃあ、私だって、できればそんなことはしたくないわよ。でも、今はそのくらいの覚悟がないと、自分が死に追いやられてしまうかもしれないという窮地なのよ。相手を倒すためではなく、自分の身を守るために、そうするしかないの」
とても厳しい内容であるが、雛乃にはフミの言っていることがよく理解できた。クラスメートに出会ってすぐに銃口を向けられたという恐怖は、そう簡単に拭い去ることはできない。
話し合いだけでは窮地を脱せないこともあると、経験者には分かるのであった。
「でも、戦いに消極的な私たちなんかがちょっとやそっと抗ったところで、本当にやる気になっている相手を止めることなんてできないんじゃあ――」
弱音を吐いたのは千代。
「いや。確かにあたしたちは戦いの場においてはほとんど無力だと思うけれど、千代の武器さえあれば、なんとか敵の手を凌ぐくらいはできるんじゃないかな」
彩音が言った途端、皆の視線が一斉に、千代の手元にある『武器』に注がれる。ここに集まっている四人に支給されている武器のうち、大半は少々頼り甲斐に欠ける物であるという中、唯一強力とも言えるそれ。おそらく四人の中だけではなく、このプログラム会場内に存在している全武器中でも、最強の部類に入るのではないだろうか。
「確かに武器は凄いかもしれないけど、こんなの私には扱えないよ。皆の命を守ることなんてできない」
千代の弱音が続くのは仕方のないことであった。彼女の武器が放つ威光を前にしては、誰もが恐れおののいてしまいそうになる。
「ねえ彩音、代わりにこれ持っていてよ。彩音なら力あるし、なんとか扱えると思う」
「冗談やめてよ。そんなのあたしにだって無理」
「じゃあフミは?」
「この細腕を見ても上手く扱えると思う? というより、そんなもの普通は誰も使えないって」
議論の末、結局それは千代が持ち続けるべきだと話が固まった。命の危機が訪れた時、きっと千代もその武器が必要になるはずだと言い包められたのである。雛乃もそれに賛成だった。他人に譲渡してしまったせいで手元に武器が無くなってしまうとなると、万が一の時に身を守ることが出来なくなってしまうかもしれない。
「分かったよ……」
しぶしぶ受け入れる千代。そのとき、上げた目線の先に何かを見つけたのか、彼女は「んっ?」と目を細めて遠くを見つめる。
「ねえ、あれって人じゃない?」
「えっ、どこ?」
千代が指差す方を急いで見る彩音。
こちらから何十メートルか離れたところに、黒っぽい何かが立っているのを、雛乃も自分の目で確認した。倉庫と倉庫の間に伸びる道の真ん中で立ち止まっているそれは、黒いレインコートを纏った人間だった。
先ほどまで誰もいなかったはずの場所に突然何者かが現れたということに、一同動揺を隠せない様子。
「ちょっと、あれ誰よ?」
「分からないよ。敵なのかどうかも」
雨と闇で視界が悪くなっている中、離れた場所にいる相手の正体を見破るのはなかなか難しい。さらにフードで顔を隠されてしまっているとあっては、もう完全にお手上げ状態であった。
俯き加減になっていたレインコートの人物が、不意に右手をゆっくりと持ち上げた。雛乃は言い知れぬ胸騒ぎを覚える。
「いったい何をするつもりかしら」
フミが言ったその直後だった。
「危ないっ、逃げて!」
いち早く危機を察知した彩音が叫ぶ。黒いレインコートと重なっていたせいで気付かなかったが、相手は手に銃器らしきものを握っていたのである。雛乃、千代、フミの三人は、慌てて後方へと走り出す。体勢を整える暇も無かったため、つんのめって転んでしまいそうになった。
「きゃあ!」と千代が叫び声を上げた。恐怖のあまり自分の武器を相手に向けることすら忘れてしまっている。
レインコートの人物の手元から、カメラのフラッシュに似た閃光が連続して発せられた。すると、危険を察知したものの、身体が思うように動いてくれなかったせいで逃げ出すのが遅れてしまった彩音の全身から、赤い血飛沫がいくつも上がった。何発もの銃弾が彼女の身体を貫いていったのである。
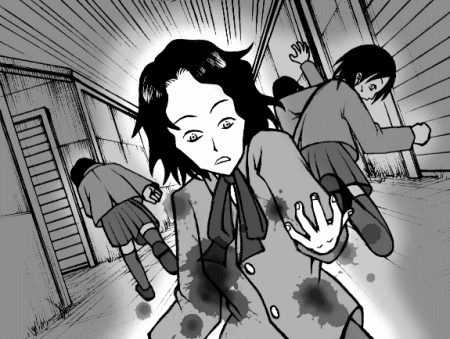
「彩音っ!」
雛乃は走りながら、崩れ落ちる仲間の方を振り返る。彩音が立ち上がる気配はもう無かった。身体中の臓物を一瞬のうちに破壊されてしまった彼女は、ほとんど即死だったに違いない。
溢れ出す涙で滲む視界の真ん中で、銃撃の勢いに耐え切れなくて地面の上に尻餅をついていたレインコートの人物が、ゆっくりと頭を上げた。フードの内側にある顔が見えた途端、雛乃の頭の中は「何故?」と疑問でいっぱいになってしまった。
「どうして桜が……」
そう。レインコートの人物とは白石桜だったのである。
自ら物事を考えて行動できない彼女が、何故こんな凶行に走ったのか、雛乃には分からなかった。だがその直後、桜の後方で倉庫の陰から身体を覗かせた人物を見た途端、全てを理解することとなった。
湯川っ……。
敵が逃亡したと知って、悠々と姿を現したのは湯川利久。かつて雛乃にマシンガンの銃口を向けてきた、悪の塊のような人物である。間違いない。きっと何らかの手を使って、彼が桜を操っているのだ。
逃げ惑うこちらの姿に目を向けつつ不気味に微笑む利久の顔を見て、雛乃は悔しさのあまり奥歯を強く噛み締める。なぜ、もっと早く危険に気付けなかったのだろう、と、後悔するばかりであった。
仲間の死を知りながらも、誰一人足を止めることはできなかった。雛乃も、桜が起き上がるよりも早くどこかに逃げてしまわなければ、と、とにかく必死になって走り続ける。
彩音の脇をすり抜けた銃弾の一つが被弾した腕から、止めどなく血が流れ出しているが、そんなことを気にしている余裕なんて無かった。
 中沢彩音(女子十二番)――『死亡』 中沢彩音(女子十二番)――『死亡』
【残り 十五人】 |
