「私、将来は動物のお医者さんになる」
左右の二重瞼の下から覗く、くりんとした目を輝かせながら、少女は言った。
夏が終わってようやく涼しくなってきたというある日。午前中の授業が終わり、仲の良い友達同士で机をくっつけ合ってお弁当を食べていた時のことだった。昨夜放送されていた音楽番組について雑談していた際、誰かが「私もいつかアイドルになって、あんなふうにテレビの中で身体中にスポットライトを浴びたい」なんて夢のようなことを語ったのをきっかけに、いつしか話題の中心が「将来の夢」に摩り替わってしまったのだった。
羽村真緒(松乃中学校一年生)は話の流れが変わった瞬間に、毎度おなじみの『彼女』の夢話が始まることを予想していたが、事はまさにその通りに進んでしまった。
動物のお医者さんになりたい。
そのフレーズは、この中学に入学してから何度耳にしてきたことだろうか。普段はいたって普通の少女が、自分の夢を語るときだけやたらと熱くなる。その変貌ぶりに初めの頃は戸惑っていたが、今やもう慣れてしまった。熱湯の風呂だって、長くゆっくり浸かっていれば、そのうち熱いとは感じなくなるものなのだ。
しかしまあ、動物のお医者さん――つまり獣医になりたいとは、これまた大層な夢である。
獣医になるためには、第一に獣医師国家試験に合格する必要がある。しかしそれは誰でも受験できるわけではなく、大学の獣医学科に入学し、そこで知識をしっかりと身につけてから卒業することを条件とされる。ところがこれもまたなかなか大変で、獣医学科を卒業するためには六年間もの通学を余儀なくされるのだ。外国の獣医科大学を卒業するか獣医師の免許を取得して審議会で認められる、とか、国家予備試験に合格するなど、別ルートで獣医師国家試験を受ける権利を得ることも可能であるが、それも棘の道であることには変わりない。
医師になるための道のりは相当苦難なものであると、一般によく知れ渡っているが、それは人間の医者だけに限ったことではなく、獣医にだって同じことが言えるというわけだ。まあ、身体の構造が全く異なる様々な動物を扱う存在なのだから、一筋縄ではいかなくて当然であろう。
それなのに何故、少女は幾多の苦難が待ち受けていることを覚悟してまで獣医にばかりこだわるのか。
実は彼女、生まれた時からずっと一緒に暮らしてきたという大親友が、数年前に病気で亡くなってしまったのである。それはかつて知人宅から譲り受けたという、一匹のゴールデンレトリーバー。病気に苦しむ親友に何もしてやれず、そのまま死なせてしまったことに彼女は悲しみ、そして愛犬と同じく病気に苦しむ動物達を助けたいと思うようになった。獣医になるという夢はそこから生じたのであった。とてもありがちで単純ではあるが、誰もが納得できる、ある意味究極の動機と言える。
彼女の友人たちは皆、そんな事情を分かっていた。だからこそ誰一人としてその夢に異議を唱えたりなんてせず、心から応援してあげることが出来たのであろう。
「簡単なことではないだろうけど、あるいは今の葉月ならなれるかもしれないね」
真緒の隣にいる春日千秋(松乃中学校一年生)が、弁当箱の中からお手製の鰻巻きを箸でつまみ上げながら言った。するとその正面に座っていた相沢智香(松乃中学校一年生)も、「ああ、葉月の成績なら確かにね」と続く。
夢を語る少女の成績は、この場にいる四人の中ではもちろんのこと、学年内でも常に上位をキープしている。これぞまさに、日ごろから続けている努力の賜物といえよう。真緒はそんな友人のことを、とても誇りに思っていた。
動物のお医者さんになるという夢を抱いているその少女、名前は醍醐葉月(松乃中学校一年生)という。かつて松乃中学校に入学したばかりの頃、幼馴染同士として元より仲の良かった羽村真緒と春日千秋の間に加わったのが、相沢智香と彼女だったのである。
性格も境遇もバラバラであったが、何故か気が合ってしまった四人は、以来いつも一緒に行動していた。もちろん他にも仲の良い友達なんてたくさんいたけれど、このグループのメンバーは別格だった。クラスの誰にも知られたくないような内緒話だって、この限られた数の大親友達にならすることも出来た。お互いを心から信用していたからだ。
手を滑らせて割ってしまった店の皿を、父親に見つからないようこっそりと処分したことがある、という千秋の秘密。携帯電話の使いすぎで嵩んでしまった通話料を支払うため、年齢を偽って校則で禁止されているアルバイトを短期間だけやったことがある、という智香の秘密。両親が離婚してしまい、今は父親と二人だけで生活している、という葉月の秘密。どれも知っているのは、真緒を含む大親友四人だけ。みんな口は堅いし、これ以上秘密が広まる心配なんて全く無いのだった。
「私、東京大学を目指すことにする」
ある日。最後の授業を終え、その日のスケジュールはホームルームを残すのみというとき、廊下に出て立ち話していた四人の中で、一人がまたもや目を輝かせて言った。葉月だ。声のトーンを抑えていたことから察するに、どうやらこの話はあまり他人には聞かれたくないらしい。しかしどうしてだろう。志望大学くらい、別に誰かに知られてしまっても問題ないだろうに。
「東京大学に行くなんて、そんなイヤミったらしいこと大声では言えない、ということよ」
真緒が不思議そうにしていると、それに気付いた智香がもっともらしい説明をしてくれた。たしかに、大東亜一の関門である東京大学を目指すなんてことを、まだ中学の一年生である少女が軽々と宣言するなんて、妬まれる理由には十分なりえるのかもしれない。ドラマやマンガなんかによく出てくる「主人公のライバルであるエリートキザ野郎」なんてのは、たいてい周りから嫌われているものだし。やはり、いつしかばれる事だとはいえ、自ら堂々と宣言するべきことでは無いのかもしれない。
しかし、よりにもよって東京大学か……。
真緒は少しめまいを覚えた。
「でも、なんでいきなり東大なの?」
葉月にならって、千秋も声の調子を抑えている。幸い周囲にはまばらにしか人はいないし、真緒たちから半径五メートル以内にいる同級生達も同じく雑談に夢中になっている最中らしく、一々こちらを気にしたりはしない。会話内容を誰かに聞かれてしまう心配など無用であった。
それはともかく、千秋の疑問はもっともだ。勉強不足のせいもあるけど、葉月と東京大学の間にどんな繋がりがあるのか、真緒には全く分からない。
「獣医になるためには大学の獣医学科に六年間通わなくてはならないって、以前説明したことがあるよね」
「うん」
かつて葉月が教えてくれたことをまだ覚えていたらしく、千秋が大きく頷いた。
「大東亜にはね、獣医学科がある大学は一六校しか無いの。ちなみに国公立が十一で、私立が五。東京大学はその中の一つなの」
「へぇ、初めて知った」
「意外に少ないんだね」
割り込んできたのは智香。
「そう。獣医師になる為の道ってのは、結構選択肢が少ないの。この十六の内どれかを卒業しなければ、私の夢を叶えることは出来ない。で、考えていくうちに思ったんだ」
「どうせなら、一番難易度の高い道を進んでみたい、と?」
真緒は思ったことをそのまま聞いた。醍醐葉月とは、立ちはだかる壁が高ければ高いほど燃え、よじ登ってでもその向こうを見たくなる、という性分の持ち主なのだ。それにしたって、今回の彼女の選択は、登る山を富士山からエベレストに変更するというくらい、やりすぎな感じもするが。
「そうね。行き着く先が同じとはいっても、やっぱり名高い学校に行った方が色々と融通が利くだろうし。それに、東京大学への進学については、相談に乗ってくれる人がいるしね」
「誰それ?」
「東京大学の卒業生よ」
「そんな人、私達の周りにいたっけ?」
「いるよ。あ、噂をすれば――」
廊下の向こうに何かを見つけたのか葉月が声を上げたので、他三名もつられて同じ方向へと目を向けることとなった。
内緒話に花を咲かせる真緒たちの方へ――、いや、正確には真緒たちのすぐ側にある教室へと向かって、二人の男が歩いてくる。徐々に迫るその顔にはもちろん見覚えがあった。
「もしかして、桑原先生のこと?」
こちらから見て左側を歩いている、四十代半ばほどのひょろりとした体の男性を指差しながら、智香が聞いた。そう、二人の男のうち片方は、自分たちのクラスを担任している桑原和夫だったのである。おそらくホームルームの時に配布するのであろうプリントの山を抱えている。
(それはそうと、人の顔は指差すものでは無いと、智香は親に注意されたことは無いのだろうか)
だが、桑原先生は確か地元の教育大学を卒業していると話に聞いたことがあるし、東大なんかには行っていなかったはず。葉月は案の定すぐに首を振った。
「違う。桑原先生じゃなくて、その隣」
真緒、千秋、智香、という女三人の目は一斉に、桑原先生の隣を歩く男へと動いた。桑原先生を手伝っているのか、同じくプリントの山を運んでいるその男は、科学の授業を担当している北見泰昭教諭であった。人の良さそうな顔つきをしている彼は自分のクラスこそ持っていないものの、授業時間以外にも気軽に相談相手になってくれるということで、生徒達にとても人気があった。歳は確か、ちょうど四十になったばかりだと、本人がつい最近言っていた。
「東大卒って、まさか北見先生なの?」
「そうだよ」
「それって確かな筋から仕入れた情報?」
「こないだ先生にしつこく問いかけ続けていたら、しぶしぶながらだったけど吐いたよ」
初めて聞いた話をすぐに信用なんてできず、女達は次々と疑問を投げかけるが、葉月は順番に軽く答えていく。どうやらガセではないらしい。
「しぶしぶながらってことは、やっぱり北見先生も、自ら高学歴なのを語るべきではないって考えているクチなのかな」
「たぶんそうなんじゃない。北見先生って、よく生徒達の相談に乗ってくれているからさ、どういう言葉が他人にどんな印象を抱かせるかとか、人一倍分かってそうだし。誰かに悪い思いをさせたりしないよう、気をつけているのかもね」
「高学歴で、しかも他人を気遣える先生か。非の打ち所が無いってまさにこのことだわ」
「でもさ、東大卒業しておきながら中学校の教師になるなんて、なんかもったいないね」
葉月の話が本当だと分かってからは、皆の調子は勝手にどんどんと高まっていった。そんな中、自分が女子中学生たちの話題の中心となっているのも知らず、北見先生が悠々と近寄ってくる。
「ゴメン、ちょっと通してもらえないかな」
教室前にたどり着いた北見先生が言うと、出入り口を塞ぐように立って話していた生徒達が、そそくさと自分の席へと戻っていった。話に夢中になりすぎていて、教師達の接近に気付いていなかったらしい。
「じゃあ、ここに置いておくからな」
「悪いね、手伝ってもらっちゃって」
「なあに、どうせここの教室前は通るつもりだったし、気にしないで」
北見先生は教卓の上にプリントの束を置くと、桑原先生と一言二言交わしてから、すぐに教室から出てきた。そしてまだ廊下にいた真緒たちを見つけてもう一言。
「ほら、もうホームルームが始まるから、君たちも早く教室に入りなさい」
「はぁい」
言われなくてもすぐに教室に入るつもりだったので、真緒たちは素直に返事して従った。
「あ、北見先生」
その場から立ち去ろうとしていた北見先生の背中に向かって、葉月が言葉を投げかけた。
「また相談に乗ってくださいね」
「ああ、もちろん。聞きたいことがあったらいつでもおいでよ」
北見先生はいつもの優しい笑みを浮かべながらこちらを振り返り、そしてゆっくりと立ち去っていった。
ちなみに、桑原先生と北見先生の二人が運んできたプリントの山とは全て、先日行われたテストの答案用紙だった。まさかホームルームの時間に返却されるとは予想外。出来のほうは、可もなく不可もなくといった感じだったが、真緒は不意を打たれたことについて苦笑するばかりだった。
千秋もどうやら真緒と同等の出来具合だったらしく、嬉しいとも悔しいとも取れない顔をしている。智香は……少し青ざめているように見えるけど、大丈夫なのだろうか。
葉月は顔を見るまでも無かった。彼女はいつだって優秀な子だから。
平和な日々は変わらずに、いつまでも続くのだと思っていた。しかし数日後、学校中に衝撃が走ることとなった。科学の授業を担当していた北見先生が、交通事故で突然不慮の死を遂げてしまったのである。そういうわけで、葉月は北見先生に相談を持ちかけるなんてことは、今後いっさい出来なくなってしまった。
ところで、北見先生の葬式に出席したいと自ら名乗り出る生徒は数多くいたらしいが、あまり大事にしたくはないという遺族の希望もあって、後に親族だけでしめやかに密葬が行われたのだそうだ。
とにかくこれで学校中に広がっていた騒ぎは静まり、以前と変わらぬ日常が戻ってくるはずだった。ところが、悪いこととは続くもので、北見先生が亡くなってから二週間も経たないうちに、松乃中等学校は地獄絵と化してしまったのである。
「早く、教室から出て下の階に下りなさい!」
隣のクラスの担任教師が、廊下で大声を出しているのが聞こえてくる。何事かと思って真緒が教室から外へと顔を出すと、あわただしく廊下を駆ける生徒達の姿が見えた。まるで何かから逃れようとしているかのように、皆が必死の形相を浮かべている。
「見て! 一階から煙が!」
窓の外を見ていたクラスメートの一人が叫ぶと同時に、教室にいた全員の目が同じ方向を向いた。見たところ、煙はどうやら校舎の西側にある理科実験室から上がっているようだった。
「ひょっとして、これって火事?」
「マジかよ」
「大変! 早く私達も外に出ないと」
クラス中がすぐに騒がしくなり、男子も女子も我先にと教室から飛び出していく。
「真緒! ぼーっとしてないで、あたし達も早く逃げなきゃ」
千秋に肩を揺すられて、真緒は自分が呆然と立ち尽くしていたということに、初めて気がついた。突然の事態にどう対応すれば良いのか処理が追いつかず、頭の中が一瞬真っ白になってしまっていたのだった。
「こっちよ、早く!」
先に廊下へと出ていた智香が、扉の向こうからオーバーなアクションで手招きしている。その脇には既に葉月の姿もあった。真緒は千秋に手を引かれるようにして、智香たちの方へと走る。
「今聞いたんだけど、東階段から逃げた方がいいらしいわ」
智香が言った。
「西階段は駄目なの?」
「火元が校舎の西側だから。薬品やガスに引火したりなんかして、西階段を下った辺りはもう火の海になっているらしいの」
真緒たちがいる三階にも、既に黒い煙がうっすらと立ち込めてきている。いずれは火もここまで上がってきてしまうだろう。助かりたければ東階段を通って、迅速に避難しなければならない。しかし、見たところ東階段は逃げ惑う生徒達でごった返しており、すぐに外に出られる状態だとは思えない。きっと一階の出入り口で人が詰まり、後ろの列もなかなか進まなくなってしまっているのだろう。空のペットボトルにビー玉をいっぱい入れて逆さにしても、口の辺りで詰まってしまう、というのと全く同じ原理だ。皆が我先にと進もうとすると、出入り口の広さが十分にあったとしても、出ることはなかなかできないのである。
「まったく。災害時はパニックになることを避けなきゃいけないってのに。みんな避難訓練のときにちゃんと話を聞いてなかったのかしら」
「仕方ないよ、智香。とにかく今は文句を言っている場合じゃない。時間はかかるかもしれないけど、東階段の列に並んだほうがいい」
葉月の発言はもっともだった。現在唯一の退避路となってしまっている東階段を通るしか、逃げ出す手段は無いのだから。
しかし実際に並んでみて分かったのだが、列の流れは思っていた以上に悪かった。真緒のだいぶ前に並んでいる男子生徒が「早く進め」と階段の中腹辺りから下に向かって叫んでいたが、彼の気持ちはすごくよく分かる。背後から流れてくる煙がだんだんと濃度を増しているのを感じては、焦らずにはいられなかった。
「火だ! 火が上がってきた!」
近くで誰かが悲鳴を上げた。後方を振り返ると、確かに三階廊下の一番西側が赤く灯されているのが見えた。自然との調和を重んじて造られた半木造の校舎は、薪の集合体とほとんど変わり無い。火の回りが早くて当然だ。
「ひぃぃっ!」
真緒たちよりも後方にいた男子生徒が側の窓を大きく開き、突然枠に足をかけた。
「よせ! やめろ!」
周囲の人々が止めるのも聞かずに、完全にパニックに陥っていた男子生徒はそのまま下へと飛び降りてしまった。するとそれにつられて、さらに何人かの生徒も後に続いて、同じように飛び降り始める。しかし、ここは三階。飛び降りたところで助かるはずが無い。
ドシャッ。グシャ。ベチャッ。
下の方からあまり聞き慣れぬ音が聞こえた。真緒には窓の外を覗きこむ勇気など無かった。はたして飛び降りた生徒たちのうち、何人が無事でいられたのだろう。
長い時間をかけてようやく二階に着いたというころには、既に火の手は目前にまで迫っていた。炎の先端との距離は十メートルあるか無いか。熱い空気に身を包まれているせいで、運動しているわけでもないのに身体中から汗がほとばしる。
「千秋! 智香! 葉月! いる?」
あまりに人がごった返しているせいで、親友達の姿を見失ってしまった。背の低い真緒は前後左右を人に囲まれて、何処に誰がいるのか全く分からない。だから大声で一人一人の名前を呼び、安否を確認しようとしたのだった。
「大丈夫」
「ここにいるよ」
「心配しないで」
親友達はそれぞれすぐに返事をしてくれた。声の調子から皆すぐ近くにいるのだと分かり、ほんの少しだけホッとした。しかしそれもほんのつかの間。有毒ガスを含む煙はなるべく吸わないよう気をつけてきたつもりだったが、時間と共に胸がだんだんと苦しくなってきた。周囲には咳き込んでいる者も多い。
再び焦り始めてきたその時、ようやく一階廊下が僅かにだが見えた。やはりそこにももう炎は広がっているようであり、うかうかしてはいられない。意外にも一階の廊下は階段と比べ、あまり人でごった返してはいなかった。
最後の一段を下った瞬間、真緒はすぐに駆け出す。
「真緒、こっちよ!」
少し進んだところで千秋と智香が呼んでいる。二人は真緒よりもほんの少し早く階段を下りきることが出来たらしい。
「葉月は?」
「まだ下りてきてない。でも、もうすぐ来ると思う」
炎はすぐ側で燃えている。しかし、親友一人を残して逃げ出すことはできない。三人は他の人たちが逃げるのを邪魔しないよう、廊下の端で身を寄せ合って葉月を待った。
「あっ、来た!」
ほどなくして千秋が声を上げた。先ほど下りてきたばかりの階段の方へと目を向けると、確かに人の波の中から葉月の姿が出てきた。
「葉月! こっちこっち!」
三人は手を上げて親友を呼び寄せる。集まったあとは四人一緒に外へと逃げればよいだけ。それで皆助かるはずだった。なのに、神様はどうしてこんな意地悪をするのだろう。
真緒たちの姿を確認した葉月は、すぐさまこちらへと走って来ようとしていた。そんな彼女の頭上で、いきなり天井に大きなヒビがはしり、轟音を立てながら校舎が崩れ始めたのである。
同時に何人もの生徒達の声が上がる。それが一つにまとまり、真緒にはとてつもなく大きな一つの悲鳴となって聞こえた。
「葉月!」
そのとんでもない出来事を目撃していた女たち三人は、自分たちの身が危険に晒されることも忘れ、崩れた天井の下へと駆け寄った。現場の状況は酷い有様だった。階段を下りきったばかりの生徒達が何人も、重い瓦礫の下に埋もれてしまい、手を伸ばして必死に助けを求めているのだ。中には、既に亡くなっている者もいるようだった。
「千秋! 真緒! 智香!」
聞き覚えのある声が耳に入ってきた。葉月だ。背中から下を瓦礫に押さえつけられてしまっている彼女は自力では抜け出せないらしく、床に伏したままの状態で、親友達の名を呼んでいる。
「葉月、待ってて。今すぐ助けてあげるからね!」
天井の板やら柱やら、とにかくかなりの量の瓦礫が葉月に圧し掛かっている。その重量は相当なもので、両手を持って引っ張っても、埋もれてしまっている下半身は一向に出てこない。なので、真緒たちはまず、葉月の上に積まれている瓦礫を除ける作業を行わなければならなかった。だが、たった三人の女だけでそれを遂げるなんてほぼ不可能。未だ勢いを増し続けている炎は、その瓦礫の山をも焼き始めており、とても時間が足りなかった。
「私の事なんかいいから、皆もう逃げて」
いつまでも逃げようとしない大切な親友達に向かって、瓦礫に挟まったままの葉月が悲痛な声を上げた。でも、ここで逃げて自分だけ助かるなんてこと、真緒にはとてもできない。
「な、なに言ってるの! 私は葉月一人を置いてなんて行けないよ! 絶対に、あなたを助ける」
真緒は瓦礫へと手を伸ばし、がむしゃらにそれらを除け始めた。真緒だけではない。千秋や智香も同じように、葉月を助けるため懸命に動いている。考えていることは皆同じだったというわけだ。
「そんなの無駄だよ! いいから、みんな早く逃げてよ!」
「逃げられる訳ないよ! 私は葉月と一緒に助かりたい!」
「あたしも真緒と同意見」
「私も!」
必死に廊下を走る者たちを横目に、作業は懸命に続けられる。しかしそんな真緒たちをあざ笑うかのように、炎はだんだんと葉月の方へと迫ってくる。
「熱っ」
真緒の隣で智香がツインテールを必死にはたいている。飛んできた火の粉が髪にかかり、それが燃え移ったらしい。
「もうやめて! これ以上私に関わらないで!」
葉月が何か叫んでいるが、真緒はそれに従うつもりなんて毛頭無い。ここから離れるのは、瓦礫の下から葉月を引きずり出した時だけだと、強く心に決めていたから。どこか別の場所で、また校舎の一部が崩れ始めているようだが、そんなの全くお構いなし。
真ん中で見事に折れている太い木の柱を除けようと一度伸ばした手を、真緒はすぐに引っ込めた。なぜなら、その柱は既に炎に包まれており、素手で触るなんてことはとても出来ないような状態だったからだ。その柱だけではない、気がつくと葉月の上に乗っている瓦礫の大部分が燃え始めていた。
「逃げて!」
葉月がいっそう強い口調で叫んだ。
「嫌だ! 嫌だ、葉月ぃぃぃぃっ!」
真緒の声は完全に泣き声になっていた。当たり前だ。親友は既に身体中を炎で覆われており、みるみるうちに姿を変形させていっているのだから。それを目の当たりにして、平然としていられるはずなどなかった。
「もうだめよ、真緒! 逃げるよ」
「葉月! 助けられなくてごめんなさいっ!」
千秋と智香は真緒の身体を引っ張って、涙ながらにその場から走り出す。引きずられるようにして出口へと向かう真緒は、必死に後方へと手を伸ばしたが、炎の中から伸びる葉月の手に触れることはもう出来なかった。
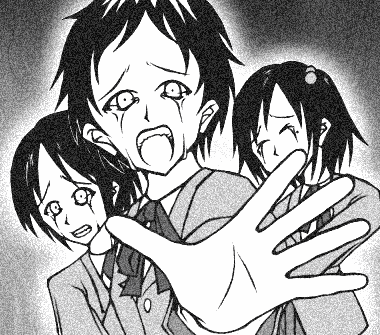
三人の目の前で、醍醐葉月は壮絶な死を遂げた。力が及ばなかったから仕方がないとはいえ、親友を助けられないまま逃げ出してしまったという事実は変わりない。これはもう、自分達が葉月を殺したようなものであった。
真緒、千秋、智香。三人はその罪をそれぞれの胸に抱きながら、そして、葉月という一人の人間が存在していたことを忘れないように生き続けることにした。それが彼女達に出来る償いの一つだったのである。
それと――。
「私、将来は動物のお医者さんになる」
真緒には独自にもう一つ始めたことがある。それは葉月がかつて抱いていた夢を、代わりに受け継ぐということ。それが償いになるのかどうかは分からないけど、彼女の存在と共に、夢も消してしまってはならないと思ったのだった。
【残り 十七人】 |
