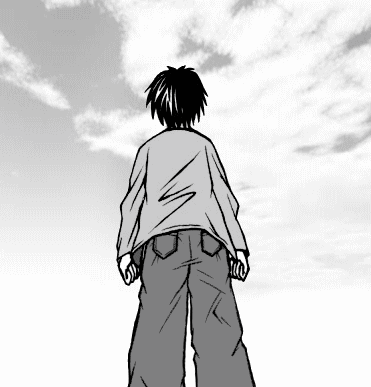138 「靖治! それに、稔!」 信じられなかった。靖治も稔も、雅史にとってはかけがえの無い親友だったが、いずれも三年前のプログラムにて没してしまったはずだ。それなのに、走れば走るほどに、視界の中、鮮明に浮かび上がってくる男達の顔は、まさに彼ら二人に他ならない。 これはいったいどういう事なのだろうか、という疑問は置いておき、雅史はとにかく二人の男に向けて駆け寄った。 二人の姿が画面いっぱいになった時、雅史はもはや耐え切れなくなり、涙を流し始めていた。そしてそのままの状態で、最後の一歩で力強く地を蹴り、男二人の身体をいっぺんに抱きしめた。 「うあぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ、靖治っ! 稔っ!」 雅史はとにかく出せる限りの力で二人を抱きしめた。すると直後、誰かが力いっぱい抱き返してきた感覚を覚えた。夢などではない。 この三年間、雅史はたった一人で苦しい思いをしながら生きてきた。 四十五人もの生命を犠牲に、生き残ってしまった雅史は、クラスメート達の死を無駄にせぬよう、精いっぱい生きようと、プログラムが終了した直後に誓ったのだ。ところが、クラスメート達全員分の想いを背負って生きるということは、思った以上に困難なことであった。 心の中ではいつまでも元気に雅史の名前を呼びかけてくる友人達だが、それがただの虚像であると考える度に、心の中は悲しみに満ちてしまい、すべての気力が吸い取られてしまうのだ。そして彼はいつもこう思うのだった。 あと、たった一度だけでも良い。大切な親友達と生きて会いたい、と。 その願いが、今こうして実現した。 嬉しかった。ただただ嬉しくて、涙が止まらなかった。 相手の胸元へと押し当てていた顔を上げて、その姿をじっと見た。間違い無い。そこにいたのは、やはり雅史が世界で一番大好きだった親友達の姿だ。 「雅史……、俺達、生きて帰ってきたぜ……」 雅史の感情と同調してしまったのか、靖治と稔がほぼ同じに涙を流し始めた。そして再び抱擁を交わす。男同士だろうと関係ない。彼らはこうすることを一番に望んでいたのだから。 彼らはそのまま微動だにせず、しばらく抱きしめ合ったまま静かに時間を過ごしていった。お互いの事を知り尽くしていた彼らには、もはや余計な言葉などは要らなかったのだろう。 雅史はこうしてしばらくの間、至福に浸っていたが、ふと奇妙な事に気がついた。そう、雅史の大切な親友達は確かに目の前にいるが、一人メンツが欠けているのだ。 「そういえば、浩二は……?」 雅史がそう言った途端だった。これまで雅史の身体を強く抱きしめていた二人の腕の力が急に弱まり、力なく目を伏してしまったのは。 「すべては、私がお話しましょう」 そう言いながら近づいてきたのは、雅史をこの場へと導き、自らをトロイの一員であると名乗っていた、謎の中年男性だった。 男がポツリポツリと話したその内容は、雅史にとっては全てが衝撃的な話であった。 断崖絶壁を転げ落ち、仮死状態に陥ってしまった靖治が、偶然にも首輪の拘束から開放され、島から脱出することができたということ。 杉山浩二が提案した脱出計画に賛同し、その結果、人為的に首輪を外す事に成功した稔が、雅史が島を飛び立った後に、密かに本土へと帰還したということ。 車のタイヤにしがみつきながら海を渡った稔が、海岸で倒れていた靖治の姿を偶然見つけたということ。 プログラム会場を遠方から監視していたトロイのメンバーが、二人の生還にいち早く気付き、すぐに彼らを保護したということ。 「浩二は……、他の生徒達を救うために、やはり命を落としてしまったのですね……」 その事実に残念に思った雅史は、影のかかっていた表情をさらに歪めた。それを見て、男は何も言わず、ただこくりと頷いた。 「しかし、何より運が良かったのが、二人の死体が未だに見つかっていないのにも関わらず、その生存を政府に悟られていないという事だ。 プログラムの規定で、終了日の次の日には清掃業者が死体を回収しに来るのだが、遺体の欠片すら見つからなかった二人の消息を、政府は全く不審に思ってすらいないらしい。その理由は、二人が死亡したとされている場所にある。 柊君が死んだとされている場所は、海岸線沿いの岸壁。そのため死体が見つからなくても、おそらく波にさらわれてしまったのだろうと結論づけられ、桜井君が死んだと思われていた住宅地は、他の生徒が放った火によって燃え尽きてしまい、死体も骨の髄まで共に焼き尽くされてしまったのだろうと思われたらしい。それによって、二人は政府の追手に脅える事もなく、こうして今も生き続けていられるというわけだ。 もちろん、浩二の死に関しては残念に思うが、それでもあの極限状態の中、これだけの人間が生還できたことを考えれば、それも仕方がなかったと思わざるを得ない。おそらくあいつも、こうなることを一番に望んでいただろう」 雅史は聞き逃しはしなかった。靖治と稔のことは“柊君”と“桜井君”と呼んでいるのに対し、浩二のことは呼び捨てで話す男の口ぶりに気付き、違和感を抱いた。 「もしかして、あなたは……」 雅史がそこまで言った時に、男は何かを思い出したようだった。 「ああ、すまない、またしても自己紹介を忘れていた。私の名前は杉山祥三。君の親友の一人だった杉山浩二の父親だ」 このときまた一つの謎が解けた。初めて杉山に町で声をかけられたときに、何故か惹かれるものを感じてしまった理由。それは雅史が会いたいと願っていた親友の一人に、男の雰囲気があまりにも似ていたからだったのだろう。 プログラムが終了してから早三年の時が過ぎた今、ようやくその裏に隠されていた事実の全てを知った。 「杉山さん。そろそろ時間がありません」 靖治達が乗ってきたのであろう車の運転席から、突如一人の男が飛び出してきた。どこか幼さの面影が残るその顔つきから察すると、歳はおそらく杉山よりも十ほど下と思われる。 「もうそんな時間か……」 杉山は男が出てきた車へと寄ると、雅史達の方を振り向き言った。 「柊君、桜井君。残念だが、再会の時間はもうお終いだ。急がなくては船の時間に間に合わなくなる」 喜びに満ちていた二人の眼差しに、突如陰りが現れた。そんな彼らの曇った表情を見て、雅史はなにやら言い知れぬ不安を感じた。 「船って……、お前達、いったい何処に行くつもりなんだ?」 靖治と稔の目を交互に見やるが、そのどちらもが目を伏してしまい、視線を合わせようとはしてこなかった。そうして口を噤んでしまった二人の代わりに答えたのは、やはり杉山だった。 「説明するのが遅れてしまったが、実は柊君と桜井君は、今や我々トロイの一員なのです。なにせ彼らは数少ないプログラムからの生還者だ。二人の体験は、我らトロイにとって大変重要な資料となりますからね。そのうえ、彼らの生存は政府にばれておらず、後の消息を追われる心配も無い。まさに、トロイにとってはうってつけの参考人だったのです」 「そうなのか?」 雅史が再び二人に聞くと、言葉は発さずともかすかに頷くのが見えた。 「そして我らトロイの一部の人間は、次なる行動のために、この国から離れ、新たなる土地に移動することとなった。柊君や桜井君も、そのメンバーに含まれています」 「それって、じゃあ靖治も稔も、大東亜を出て何処に行くって言うんだ?」 「それは、我らトロイの行動をこれ以上無関係な人間に知られてはならない為、残念ながらお話することは出来ません」 杉山は雅史達を哀れむような口調でそう言うと、さっさと車に乗り込んでしまった。 ただただ呆然とする雅史。その沈黙を最初に破ったのは、意外にも、口を噤んでいたはずの靖治だった。 「雅史。もしかしたら、俺達はもうこの地へは戻ってこれないかもしれないらしい。そうなると、二度とお前と会うことも出来ないだろう。だから今日、大東亜を出る前に、もう一度だけお前に会いたいと、浩二の親父さんに頼み込んでここに来たんだ」 「僕達も最初は悲しかったけど、もう決心したんだ。この国を変えるために、自分達の人生を賭けて戦うんだって。だから、雅史にも僕達の気持ちを分かってほしいんだ」 靖治に継いで話し出したのは稔だった。 「やっぱり、もう会えないんだな……」 雅史がそう言うと、一度は意を決したはずの二人の表情に、また暗い影が差し込んできていた。それを見て、雅史は自分の発言は間違ってなかったのだろうと直感した。 しかし、このまま彼らと別れてしまって良いのだろうか。このまま一生後悔はしないだろうか。 雅史は思った。このままではいけない。今が彼らと言葉を交わすことが出来る最後のチャンスなのだ。だからここでキチンと伝えるべきだ。胸に抱いている想いの全てを、靖治と稔に向けて、と。 「もう二度と会えないかもしれないというのは、本当に残念だけど、それでも俺は、お前達が生きていてくれたという事実を知っただけでも、満足だ。 思えばお前達と過ごした時間は短かったかもしれないが、それでも俺にとっては、最高に楽しい時間だった。もはや言うまでもないかもしれないが、俺は、お前たちのことが大好きだった。そしてその気持ちは、今も変わらない。だから俺はお前達を応援する。この先、どんな苦しい事が待ち受けているか分からないが、頑張って生きてくれ」 涙を流しながら言う雅史の姿を見て、同じく目を潤ませていた靖治が、ふっと微笑んだ。 「その言葉、そっくりそのまま返すよ。俺達も、お前のことが好きだからな」 既に時間は残されていなかった。三人は最後にもう一度抱擁を交わし、そして別れた。 先に車に乗り込んでいた杉山に頭を下げながら、二人は急いでバックシートに乗り込む。 けたたましく鳴り始めたエンジン音を合図に、車は後部から黒い排気ガスを吐き出し始めた。 雅史は車の外から、バックシートに座る二人へと熱い視線を注ぎ込んだ。すると彼らは内側から車の窓を開いて雅史へと熱い視線を返してきた。 「雅史! 絶対に悔いの残らないように、一生懸命生きてくれよ! 俺達も頑張るから! そして忘れない! 四人で過ごした、あの頃の思い出を!」 車はついに発進してしまった。そのとき、サイドミラーに映る、浩二の親父の顔が、かすかに微笑んでいたような気がした。 窓から身体を交互に乗り出している二人の姿が、徐々に遠き存在へと変わっていくのを感じつつ、雅史はその場で立ち尽くしながら、彼らの最後の姿を目に焼き付けた。 その場に残された雅史は、杉山よりも十歳ほど若そうなトロイの一員によって、元の町へと帰された。 行きと同じワーゲンに乗り込んだ雅史は、窓に映る外の景色を、ただボーっと眺めていた。 ほどなくして、雅史の住む町に着いた。 車から降り、ワーゲンを運転したトロイの男に頭を下げ、そこからは歩いて住まいへと戻ろうとした。 町を歩いていると、いつも見慣れた日常の光景が、次々と彼の視界に飛び込んできた。しかし何故か、その全てがくすんだ色をしているように思えた。 何気に空を見上げると、そこには延々と続く青き天が、世界を包み込むドームの如き広がりを見せていた。 ふと思った。この広き大空の下の何処かで、靖治や稔はこの国を変えるための戦いを始めるのだ。そう、彼らは生きながらにして、日常生活を投げ捨てたのだ。それは生半可な考えで出来る決断などではない。おそらく彼らも自分に誓ったのだろう。自分なりに精一杯生きるのだと。 この先進む道は違えど、同じ空の下、彼らと同じく精一杯生きる。それが、死んだクラスメート達のためにも、日常生活を投げ捨てた二人にとっても、そして、雅史自身にとっても一番最善の選択なのだろう。 もう一度、青き大空を見上げた。そして、同じ空の下で戦いを始める友人たちへと、そして自分自身へと誓った。 皆の分まで精一杯生きるのだと。
【完】 トップへ戻る BRトップへ戻る 137へ戻る あとがきへ進む |