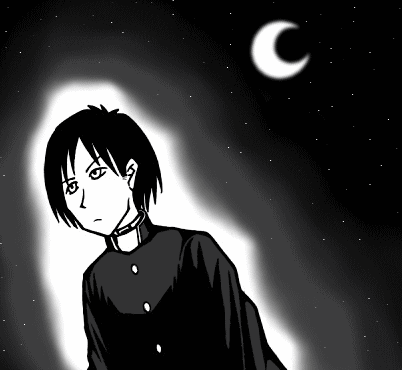136 2002年度、岐阜県私立飯峰中学校三年A組対象、共和国戦闘実験第68番プログラム。強制的に殺し合いに参加させられた四十六人もの尊き生命達は、時間が経つとともにその数を減らしていき、その都度、開催地である獄門島を紅く染めていった。 そんな地獄のような世界の中で、一人の男子生徒もまた、冥界へと旅立とうとしているかのように、真っ暗な闇の中で生死の狭間をさまよっていた。 もはやすべての思考が途切れてしまったかのように、真っ黒に染まりきった彼の頭の中で、正体不明のノイズが延々と流れ続けているが、脳内の回路全ての電源が落とされた今となっては、その雑音を耳障りに感じたりもしなかった。 上空では満天の星空を従えた三日月が、明るいほどに光り輝き、岩場の上に倒れ込んでいる彼の姿を、暗闇の中で鮮明に浮かび上がらせていた。 倒れた男は全身に開いた傷口から血を流しており、その周囲の岩場は真っ赤に染まりきっていた。そんな地獄図のような光景の側を、時折小さな虫のような何かが走り回る。フナムシだ。 男が倒れていた場所。それはプログラム会場である島の海岸線の一角を形成している岩場だった。 すぐ目の前に広がる大海原は、徐々に水位を上昇させ、倒れている男のすぐ側にまで迫っていた。岸壁にぶつかって跳ね上がった海水が、複雑に曲がった足先に触れるも、男はそれにも気付きはしない。ひたすら流れ続けるノイズの波が、彼の脳内を完全に占拠していたのだ。しかし、男はそのノイズの正体が、すぐ側の大海原から発せられている波の音であるということにすら気づきもしなかった。 再び側で跳ね上がった海水が、今度は男の頬に触れた。温度を上昇させつつある大気とは対称的に、夜の海の水は冷たく、それが頬に触れた瞬間、男は「うっ」と声を漏らした。薄れていく彼の意識が、ほんの一瞬だけ現実世界に引き戻されたのだ。しかし、それだけで彼が目を開けることはなかった。 再び跳ねた海水が頬に触れた。そして今度はビクリと身体を震わす。その瞬間奇跡が起きた。真っ黒に染まりきっていた彼の脳内ビジョンが突如点灯し、これまでに見た数々の光景を映し出したのだ。 修学旅行先に向かうバスの中で、親友達と楽しく過ごしていたが、突如睡魔に襲われ、気づいた時には見知らぬ教室の中にいた。するとそこに榊原と名乗る中年男性が現れ、自分達四十六人は今回のプログラム参加者に選ばれたのだと告げられた。そして相次いで殺された、渡辺先生、須藤沙理菜、飯田健二、三人の惨殺死体。 そうだ、俺は確かプログラムに参加してたんだ。 頭の中で次々と蘇ってきた光景を見ている内に、彼の意識はだんだんとはっきりしたものに変わりつつあった。そして、彼の恐ろしき体験の数々は、さらに画面の中に蘇っていった。 目の前に次々と出現する生徒達の亡骸。それらを見る度に、生命が失われていくことに悲しみ、その事実をかみ締めながら、これ以上、無駄な血を流させはしないと誓ったのだった。 そうだ、こんな所でいつまでも転がってはいられない。立ち上がって、早く皆に会いに行かねばならないんだ。 そんな想いが浮かんだ瞬間、閉じられていた男の目が突如開いた。そして両手の力で上半身を持ち上げ、身体を起こした。しかし何故だか立ち上がることはできなかった。 不思議に思った彼が自らの足に目を向けると、その理由は一目瞭然だった。ありえないほどに複雑に捻じ曲がっている彼の足は、どうやら内側で砕けているようだった。不思議と痛みは感じなかったが、これでは立ち上がれるはずもなかったわけだ。 この足ではどうすることもできないと嘆いた彼は、ふと自らの周囲を見渡した。目に入ったのは、暗闇の中で月にかすかに照らし出された岩場と、その側に広がる黒き大海原。それらを見ている内に彼は思った。 ここはいったい何処だ? 自らの身体を包み込んでいるその風景に全く見覚えが無かった。彼が覚えている最後に見た風景は、確かに岩場ではあったが、そこは手が届くほど近い距離に海はなかったはずだった。 そんなことを夢中で考えていた彼だったが、側にそびえ立つ岸壁の存在に気がつくまで、あまり時間は要さなかった。 反り立った壁に気づくや否や、頭を傾けつつ上を見上げる。すると壁の終着点はここから遥か上に存在しているのだということが分かった。そして思い出した。 そうだ。自分はこの崖のてっぺんから突き落とされたんだった。 自分の背中へと両手を伸ばしていた男子生徒の姿を思い出した。 それにしても、これほどまで高い崖から突き落とされて、よくもまあ生きていられたものだと、我が悪運に感心した。 岸壁をじっくりと見ていると、その所々から木々の根や枝が伸びているのが見えた。そこで彼はある仮説を立てた。 岸壁から突き落とされた俺は、そのまま下へと落ちていった。しかし、岩肌から伸びていた木々が順番に、俺の身体を受け止めてくれたおかげで、落下の勢いが弱まり、そして岩に叩き付けられながらも、かろうじて命は取り留めたのではないかと。意識だけは失ってしまったようだが。 おそらく、彼の立てた仮説は間違ってはいなかっただろう。そうでなければ、何十メートルもの高さを誇る断崖絶壁から突き落とされても、こうして生きていられるなどという理由を、他には説明することはできない。 もう一度上を見上げた。絶壁の終着点は、やはり遥か上にあり、両足の折れた彼には、とても上り切れるように思えなかった。しかしいつまでもこんな所で時間を潰している訳にはいかない。早く他の皆に会って、一人でも多くの生徒に殺し合いを止めるように呼びかけねばならないのだから。 焦りを感じた彼は、ふと腕時計に目を向けた。緑色に発光しているデジタル文字は午前二時二十三分を示していた。どうりで辺りが真っ暗なわけだ。 ところが、彼がデジタル時計を見ている時に、あるとんでもなき事実に気が付いてしまった。 デジタル時計に表示されていたのは時刻だけではなく、その隣では簡易カレンダーが今日の日付を表示している。それを見た時、彼は驚愕した。 日付はなんと、プログラムが開始した日の三日後を示していたのだ。 プログラムの日数は最大でも三日間。それを過ぎても優勝者が決定しなかった場合、生き残っている生徒達全員の首輪は爆発してしまうのだと、プログラム担当教官の榊原が説明していたはずだ。つまり、優勝者以外の人間は、三日以上もの時を生きることは不可能なはずなのだ。だというのに、プログラムが開始してから三日間とおよそ一時間半もが経過している現在、彼はなぜかまだ生きている。はたして、これはいったいどういう事なのだろうか? 再び浮上した謎を解くために、彼は優秀な頭脳をフル回転させながら、その解答を見つけだそうとした。 彼がまず最初に考えたのは、生死の縁をさまよっている間に、他の生徒達が全員死んでしまい、その結果、偶然にも自分が優勝してしまったのではないだろうかという仮説だった。それならば、三日以上もの時が経過した今も、こうして生きていられる理由は説明することができる。しかし、そんな上手い話が本当に起こったのだろうか。 彼は自らが立てた仮説に疑問を抱いた。それに壮絶な殺し合いの中で生き残った、たった一人の優勝者を、政府の人間達はこうしていつまでも崖下に放置し続けるのだろうか。 そんなことを考えていると、仮説は間違っているのではないだろうかと思わざるにいられなかった。 ならば、優勝者でもない自分は、どうして今もこうして生きていられるのだろうか? もしかしたら、崖から転落した際に、その衝撃で首輪が壊れたのかもしれないとも考えた。しかしだ。生徒達を拘束していたこの首輪は、対ショック性のうえ完全防水が施されており、絶対に壊れるはずが無いと、これまた榊原が説明していたはずだ。 急いで首輪に触れてみるも、その外装には傷一つ付いた様子すらなかった。どうやら首輪が壊れたという訳でもなさそうだ。 そんなとき、彼はついに驚くべき仮説に行き着いてしまった。おそらく、政府の人間達もこのような事態が起こり得るなど、予想すらしなかっただろう。実際、その仮説を考え出した彼自身が、まさかそんなことが本当にあるのだろうかと疑った。 彼が考えた驚くべき仮設とは、以下のようなものであった。 榊原は確かこんな事も言っていたはずだ。もしも島から逃げ出そうとしても、その生徒が生きている限り、首輪が主の心臓パルスをキャッチし、そのデータがコンピューターへと転送される為、何処に行こうがその動きは手にとるように分かるのだと。 ところが、榊原の言葉から逆の考え方をすると、生徒が死んでしまえば首輪はもうデータを転送してはこない。つまり、首輪はもう作動しなくなると言っているようにも取れる。確かに生徒が死んでしまえば、首輪にはもう役目など残されていないのだから、同時にその機能が停止するということは十分に有り得る話だ。 問題はさらにこの後だ。 それではもしも、死んだはずの生徒が何らかの原因で生き返ったとしたら、一度機能を停止した首輪はどうなるのだろうか。考えるまでもない。首輪が再び機能しだすことなどないだろう。首輪の開発者達が“死んだはずの生徒が生き返ったら、首輪も再起動する”などといったプログラムをわざわざ組み込んだりしていたならば話は別だが、まさかそんな馬鹿げたことなど行なってはいないだろうからだ。 もう一度考えてみよう。もしも死んだはずの生徒が生き返ったならば、その生徒はプログラムから離脱する事は可能だろうか。同じく考えるまでもない。可能だ。首輪が機能しなくなってしまえば、生徒を完全に拘束していた物は何も残されてはいないのだから。 途切れ途切れになって散らばっていた謎が、ついに一つの線として結びついた。 考えをまとめてみよう。 崖から突き落とされた彼は、その後に気を失ってしまったのではなく、一度死んでしまった。正確には“仮死状態”に陥っていたと言うべきだろうか。心拍も脈拍も、その全てが一度停止してしまった事によって、それと共に首輪がもう役割を終えたと判断し、その機能を停止させてしまった。ところが、何らかのきっかけで、男の心拍や脈拍が復活し、彼をこの世へと引き戻した。しかし、一度機能を止めてしまった首輪は再び動き出す事はなく、絶壁の下で、虫の息で生き長らえている彼の存在を、メインコンピューターに伝えたりはしなかったのだ。 その間にプログラムはさらに進行し、ついに一名の優勝者を生み出した。政府の人間達はそれだけに夢中となり、他の生徒の死亡を確かめはしなかった。ここに一人の生徒がかすかに生き長らえていたとは知らずに。 そして三日目の夜を迎えるも、機能を停止した首輪は爆発することなく、彼の生存を許してしまった。その後に、かすかな意識の中をさまよっていた生徒は、ついに目を覚まし、そして今に至る。 とてつもなく都合の良い考えだとも思うが、これ以外に彼が生き長らえる事が出来た理由など考え付かなかった。この仮説が真実だとすると、それはまさに奇跡が起こったのだと言っても良いだろう。 昔見たテレビ番組を思い出した。事故に巻き込まれ、もはやその生命は絶望的だろうと思われていた人が、奇跡の生還者としてこの世に舞い戻ったという話。それと同じだ。彼は誰もが予想すらしなかった奇跡の生還者としてこの世に生き長らえる事となったのだ。 なんにせよ、彼がプログラムから脱することができたと言う事実には変わりない。今はとにかくこの島から脱出し、プログラムがどのような結末を迎えたのかを知る、それが何よりも先決であると考えた。 ふと波打ち際へと目をやると、これまた都合よく大きな流木の姿が見えた。両足の自由を失い、とても海を泳いで渡れるような状態ではなかったが、この流木に掴まりさえすれば、なんとか本島へと帰還することが出来るかもしれないと思った。 幸いな事に、プログラムが終了した為か、島の沖を漂っていたはずの監視船の姿は、忽然と消え失せていた。今ならこの島から脱出する事も不可能ではない。 ポケットから取り出したハンカチを海水で濡らし、額を汚していた自らの血を拭き取り、遠くで黒い影となって浮かび上がっている本州の姿を見ながら、彼は生きて帰るのだと強く誓った。
奇跡によってプログラムからの離脱を実現させた男、柊靖治(男子19番)は、こうして生還を果たすこととなった。 トップへ戻る BRトップへ戻る 135へ戻る 137へ進む |