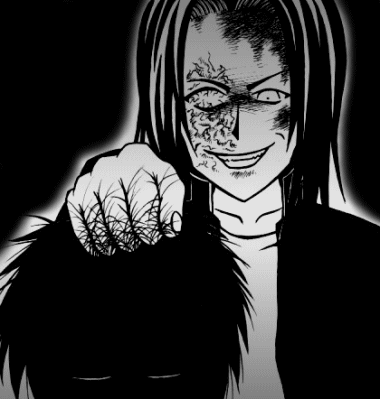118 雅史はその姿を見て驚愕するばかりであった。 須王拓磨。彼は雅史にとっても不気味かつ恐ろしき存在であった。そのため、プログラムが開始した当初から、クラスメート四十六人の中で、最も出会ってはならない人物であると考えていた。その須王が、ついに自らの前に姿をあらわしたのだから、それだけでも驚かずにはいられない。しかし、驚愕の理由はそれだけではない。今の彼の外見は、誰が見ても明らかに異常だったのだから。 何者かとの戦闘時に受けた手負いなのだろうか、須王の顔右半分は火傷でただれており、痛々しく、とても直視できないほどの有様であった。さらに頭部から流れた血液の跡で顔を黒く汚し、それがまた不気味さをより演出している。 今の須王の外見は、明らかに殺人を経験した者の姿。それと対面してしまった雅史の身体は、恐ろしさのあまりか固まってしまい、手足を動かすどころか口を開く事すらままならなかった。蛇に睨まれた蛙とは、まさにこんな状態を指すのだろうと、頭だけは妙に冷静に考えていた。 しかし、実際は冷静でいられる状態などではない。突如飛び出してきた須王の黒き魔手により、仲間であった罪無き少女、石川直美が断崖から突き落とされたのだ。一度崖の下を見下ろし、その斜度と高度を確認済みであった雅史は、おそらく彼女は助からないだろうと思った。 雅史はふと彼女と過ごした短き時間の事を思い出した。 プログラムの中で初めて出会った時の彼女は、友人たちを殺された恐怖と悲しみに錯乱しており、とても普通に話が出来る状態ではなかった。それだけならまだしも、殺人者と間違われた雅史は、彼女に一度銃口を向けられたのだ。そのときの恐ろしさは今でも忘れられない。 しかし、ようやく正気を取り戻した彼女は、自らが体験した恐ろしき事実を、事細かに話してくれて、そして雅史達に心を許してくれた。 それぞれの想いが通じ合い、そして一緒に行動する事となった後の彼女は、不安に怯えながらも、できるだけ明るく振舞おうと努力していた。精神的に軟弱であった直美が、できるだけ元気に徹すよう努力していたその姿に、疲れ切っていた雅史の心は強く打たれ、そして自分も頑張らなければと励まされたのだった。 一緒に行動をはじめた事によって、初めて、直美は純粋無垢で清く正しき心を持つ者だったと知り、雅史の側も完全に彼女に心を許し、そして無意識の内にだが、お互いに大切な仲間であると意識し合い、最後まで一緒にいたいとすら思っていた。だが、そんな直美も、ここにきてついに雅史の前から姿を消してしまった。 直美が須王の手にかかってしまったこの一件は、友人たちの死を知り、絶望に追い込まれていた雅史にさらに追い討ちをかけた。これまで堪えていた涙が今にも溢れそうになり、表情を歪めながら歯を食いしばった。 雅史は顔をうつむき加減に傾けながら、直美を地獄へと突き落とした人物を、睨みつけるかのように見た。火傷と血の跡に彩られたおぞましき悪魔の顔に、笑みすら浮かべるその姿を見て、またしても怒りが込み上げてくる。 ふと、須王の右手に握られている武器に目がいった。日曜大工などでも活躍しそうな小型のチェーンソー。遠くで燃えさかる住宅地の光に照らされ、夜であってもその姿が鮮明に浮かび上がる。刃は人間の血らしきもので真っ赤に染まっている。それは、須王がこのチェーンソーで、クラスメートの誰かを殺害済みであるということを証明している。 となると、既に何人かの生徒を殺害済みである須王が、ここにきて再び殺人を犯したのだと言える。クラスメートを易々と殺してしまう者に怒りを抱いていた雅史にとって、彼はまさに許すまじき存在であったのだ。 雅史はさらに、須王の武器を持つ方とは逆の手へと視線を移した。武器を持たぬ左手には、スーパーかコンビニの物だと思われる白いビニール袋がぶら下げられており、その中に、何かドッヂボール大の塊が入っているのが分かる。 あれはいったい何なのだろうか。 大きなビニール袋をぶら下げたその姿が、須王に似つかわしくないと感じた雅史は、怒りで表情を歪めながら、じっと袋の方を見つめ続けたが、やはり不透明なビニールの中身を断定するには至らなかった。 須王の側は、直美を崖から突き落としたばかりだというのに、まるで何事も無かったかのようにけろっとしている。そして、怒りに打ち震える雅史と大樹の姿を交互に見比べた後、再び顔に不気味な笑みを浮かべつつ、カカカと声を出して笑い始めた。 「何が可笑しい!」 相手の態度が癇に障ったのか、大樹は声を荒げて怒鳴った。しかしそんな気迫に押しつぶされる事無く、須王は笑いを止めずに淡々とした口調で話し出した。 「いや、今まで散々苦労して探し回ってたんだ。そしてようやく見つけたぜ。剣崎、お前をなぁ」 その言葉を聞いた瞬間、大樹の眉がピクリと動いた。 「なんだと。俺を探し回ってただぁ?」 不穏な空気が流れる中、大樹は須王に敵意をあらわにした様子で聞き返した。大樹には須王の言葉の意図を掴む事が出来なかったのだ。もちろん、それは雅史も同じであった。 須王はさらに激しく笑いだし、そして楽しげに続けた。 「ああ。お前、新城の死に悲しんでるんだろ? 教えてやるよ。アイツを殺したのは、この俺なのさ」 大樹は顔を一気に強張らせた。そして噛み締めた歯を剥き出しにして、今にも相手に噛み付かんばかりの怒りの表情を見せた。しかし、まだその話を鵜呑みに出来なかったのか、今にも飛び出しそうな自らの身体を抑えつつ、大樹は出来るだけ冷静に話を続けた。 「はぁ? お前が忍を殺しただと? 馬鹿も休み休み言えよ。アイツがお前なんかに殺されるわけねぇだろ!」 必死で怒りを抑えつつ、あくまでも話を信じようとしない大樹の姿を見て、須王はまた楽しそうだった。 「お前の言うとおり、アイツはなかなかの強敵だったさ。だがな、俺が殺したってのは事実なんだよ。どうしても信じられないってのなら、今からその証拠を見せてやるよ」 そう言うと、彼は一度チェーンソーを地面におろし、左手からぶら下げていたビニール袋の中に右手を突っ込み、そして中に入っていた塊を掴み上げた。袋からついに姿をあらわした塊の正体を見た瞬間、雅史はその衝撃的な光景に、眩暈すら感じてしまった。 「ほれ」
須王が袋の中から取り出した塊の正体、それは紛れも無く、新城忍の頭部であった。 首輪の下辺りでざっくりと、まるでマネキンのパーツのように分断されているその顔には、勿論生気など無く、元気の無くなった瞼が閉じきっておらず、その内から虚ろな目がこちらを見ているように思えた。 切断面である首から流れ出した大量の血液によって、ボサボサに固められた髪を掴み、その頭部を持ち上げている須王は微笑み、そしてこちらの反応を楽しそうに窺っている。 あまりのショックに反応できないのか、大樹はただ呆然とし、全く動きを見せる事はなかった。 「これで分かっただろ。コイツは俺が殺してやったのさ」 その言葉と同時に、須王は右手を後ろに振った後、ボーリングをするかのように、忍の頭部をこちらへと投げた。 忍の頭は大樹の手前二メートルほどの地点で地面に落ち、そのまま真っ直ぐ転がって、大樹の足元でようやく止まった。 地に付いた忍の頭は、まるで大樹を見ているかのように上を向き、大樹もそれに視線を返すかのように下を向いている。 雅史は、そんな一連の出来事を頭の中に焼き付けられ、そして怒りと悲しみの両方が一気に膨らみ、自らの身体が風船の如くはちきれそうになる感覚すら感じた。しかし、その感覚をどうやって静めればよいのかが分からず、ただ苦痛に苦しみ続けるより他にはなかった。 しばらく、誰一人身動きすらしない沈黙が訪れた。重苦しい空気がのしかかってくる中、雅史はもはや立っていることすら限界だった。 「……ぶっ殺す」 突如そんな声が聞こえた。雅史が声の主の方へと目を向けると、今まで視線を下に向けていたはずの大樹が、真っ直ぐに相手と向き合い、そして握り締めた拳をわなわなと震わせながら、すべてを打ち砕かんばかりの恐ろしき闘志を燃やしているのが伝わってきた。 長年、同じ道場の中で共に戦い続けてきた戦友を殺され、怒りのボルテージは最高潮に達し、そしてその全てを放とうとしている大樹の姿は、まさに復讐の鬼のようであった。 「てめぇは絶対にぶっ殺す!」 そう叫んだと同時に、ついに大樹は飛び出した。そして右手に持つアイスピックを悪魔の心臓に突き立てようとしているのか、まっすぐに須王へと向かっていく。しかし、大樹に勝機はあるのだろうか。 須王の武器はチェーンソー。大樹の武器はアイスピック。この点だけを見比べてみれば、須王のチェーンソーのほうが圧倒的に有利であるように思われる。いくら大樹が接近戦で敵無しだとは言っても、この差が戦いに絶大なる影響を及ぼしてくる事は間違いないだろう。となると、このまま大樹だけに戦わせる事は危険なのではないだろうか。 雅史はふと自らの手元へと目を向けた。そこにあったのはコルトパイソン。 須王の悪行が許せなかったのは大樹のみではない。それは雅史も同じだ。それならば、殺された者達の無念を晴らす為にも、怒りに燃える大樹を助ける為にも、自分も戦いに手を貸すべきなのではないだろうか。 そう思い始め、雅史の手が徐々に上がり、銃口が須王の方へと向く直前の事であった。 「きゃぁぁぁぁぁぁぁ!」 雅史の背後から誰かの叫び声が聞こえてきた。その突然の事態に驚いた雅史は急いで後ろを振り向いた。しかし、そこに人の姿など無く、視界に入ってくるのは例の断崖絶壁のみであった。だが、雅史はここで妙な胸騒ぎを感じ、気がつけば断崖絶壁の下を覗き込んでいた。 「あっ」 雅史は自然と声を漏らしていた。そこには驚くべき光景があったからだ。 雅史の立っている位置から二十メートルほど下で、岩肌の隙間から伸びた木の枝を掴んでいる直美の姿があったのだ。 【残り 6人】 トップへ戻る BRトップへ戻る 117へ戻る 119へ進む |