この世に生を受けてから十五年、今ほど悲しい思いをしたことは、おそらく未だかつて無い。
ますます勢いを増していく雨に打たれながら、白石幹久(男子八番)は途方に暮れていた。
突如自分達の前に現れた湯川利久(男子二十番)に、妹の白石桜(女子十番)を人質にとられて、脅されるがままに隠れていた場所から離れて島を徘徊することになってしまったが、それから先どうすればよいのかなんて分からないのだった。
頭の中に蘇る利久の言葉。妹を助けてほしければ、深夜零時の放送までにクラスメートを三人殺せ――。
いくらなんでも、そんなこと出来るはずが無かった。確かに幹久は桜のためなら何だってすると決意していたが、殺しなんて、それとは全く別次元の話だ。こともあろうに三年間机を並べてきた仲間たちを手にかけるなんて、いくら実の妹を救い出すためとあっても、生まれながらに持つ良心が絶対に許さない。幹久と同じように、級友たちにも十五年という短い人生の中で積み重ねてきたかけがえのない経験や思い出があり、それは無関係の者なんかが勝手に切り崩して良いものではないのだから。
妹は取り戻したい。しかし、利久の命令に素直に従って、人の命を奪うなんてことはできない。幹久はそんなどうすることもできない状態の中、ただただ頭を抱えて悩み続けるばかりだった。
桜。お兄ちゃんはいったいこれからどうすれば良いのだろう――?
幹久はどこか遠くの世界へと消えてしまった妹に語りかけた。すると、かつて兄に心地良さを与えてくれていた天使のような微笑を浮かべた桜が、火災によるトラウマで自我を失うよりも以前の姿のまま目の前に舞い降りて、こちらに向かって手を振り始めたではないか。
幹久は手を伸ばしてそれに触れようとする。しかし当然、幸せだったころの記憶と妄想の塊にすぎない虚像にその手は届かない。真っ直ぐに伸ばされた手は誰かに握り返されることも無く、ただ虚しく宙を仰ぐだけで終わるのである。そして、冷え切った我が手を暖めてくれる存在が側にいないことに気付くと、止まっていたはずの涙がまたしても溢れ出してしまうのだった。
幹久は思った。二人はどうして、こんなに無慈悲で過酷な世界の中に生まれてきてしまったのだろうか、と。銀河の片隅に存在するこの星が人類にとっての楽園であるとしても、桜がいなければ自分にとっては単なる生き地獄でしかない。逆に言えば、桜と離れずに済むならば、一生出ることのできない牢獄の中ででも生まれたかった。
あるいは、こうやって兄と妹として別々の身体に生まれてくるのではなく、たった一つの個体として存在したかった。それならば、自分と桜は一つの身体を共有して、一生離れることなく暮らし続けることが出来るのだから。
断っておくが、あくまでもこれらは精神論であって、肉体的に離れたくないという願望ではない。幹久だって、兄妹はいずれ成人し、別々の道を進むことになってしまうと分かっている。大事なのは、二人の身体がどれだけ遠くに離れていようとも、お互いの心をたった一本の生糸で繋ぎ止めておくことが出来るかどうか、ということなのである。
しかし幹久の願いとは裏腹に、兄妹は、二人離れることの無い楽園に身を置くことも、同じ個体の中に生を受けることも出来なかった。結果、桜の心はどこか遠くの世界へと飛んでいき、ぴんと張った一本の生糸が真ん中で切れ、二人はばらばらになってしまった。そして今、さらに妹の生命までもが危険に晒されてしまっている。
命が続くのなら、失われた桜の心もいつかは取り戻せるかもしれないと、希薄ながら望みを持ち続けることは出来る。しかし、死別してしまうならそうはいかない。だからこそ、なんとかして利久の手中から桜を無事に救い出す方法は無いかと必死に模索するのだが、やはり相手の命令に従って他のクラスメートを殺すという以外には、上手い考えなど思いつかなかった。だが、幹久にそんなことが出来るわけが無い。
そんなわけで、頭の中の考えは一向に固まることなく、同じところをぐるぐると回り続けるばかりなのであった。
気がつくと、幹久は視界の開けた場所を歩いていた。森林内から抜け出たのではなく、根の腐った木々がドミノの板の如く大量に倒れて空き地のようになった空間が、山林の中にぽつんと存在していたのだ。
木の葉が密集して出来た屋根が頭上に無いその場所を歩くと、降り注ぐ雨を直接身に受けることになるので、幹久はそこを通るのを避けるために進行方向を変えようかと考えた。だが、太い倒木の間に何かが隠れているのに気付き、身体の向きを返すのを中断。目を凝らしてよく見ると、それは自らの身体を抱えるようにして縮こまっている一人の女生徒だと分かった。
「誰?」
幹久は無意識の内に声を発していた。それに驚いたらしく、少女はびくんと肩を動かして、恐る恐るといった様子でこちらを振り向いた。
「……し、白石くん?」
幹久の姿を見て表情を強張らせたのは叶昌子(女子四番)だった。相当長い間雨に打たれ続けていたようで、軽くパーマをかけたような癖のある髪は、今や水分を大量に含んで、ぺしゃんこになってしまっている。
「来ないで!」
近寄ろうと幹久が片足を一歩前に踏み出したのと同時に、昌子が悲痛な声を上げながら細い腕でツルハシを構えた。彼女に支給された武器なのだろう。クラス一おとなしい彼女は既に精神の限界を迎えているらしく、弱々しく身体を常に震わせ続けている。そんな様子を見て、幹久は昌子のことを不憫に思わずにはいられなかった。
「大丈夫……怖がらなくても大丈夫だから、叶さん」
とにかく昌子を落ち着かせ、そして安心させたいと思い、何も持っていない両手を上げて敵意が無いことを示しながら、ゆっくりゆっくりと前に進む。このときはもう、クラスメートを殺さなければ桜を助けられないなんてことを、考えている余裕は無かった。
対面する二人の距離は徐々に狭まっていく。恐怖感に支配されてしまっている昌子も、ツルハシを構えたままたじろぎ始めるが、周囲を埋め尽くすかのように転がっている倒木に足元を邪魔をされて、思うように後ろ向きに歩くことが出来ないでいるのだった。
「来ないで!」
昌子が再び声を上げた。その直後、倒木に足を取られた彼女はそのまま背中から後ろへと転倒し、構えていたツルハシを取り落とす。
「大丈夫?」
幹久は足を速め、あたり一面に転がる丸太に足を取られぬよう大股になって、倒れた昌子の側へと駆け寄った。そして優しく手を差し伸べる。
「ほら、掴まって」
昌子は少しの間は不思議そうな顔をしたまま動こうとしなかったが、しばらくして恐る恐る幹久の手を握り、引かれるようにして立ち上がった。
「良かった。怪我は無いみたいだね」
全身ずぶ濡れではあるが、倒れた時に上手く受け身をとったのか、昌子の身体にはとりあえず傷らしきものは見られない。
「……どうしてこんなに優しくしてくれるの?」
「えっ」
幹久がすっとんきょうな声を上げると、
「今はプログラムの最中でしょ? クラスの子同士で殺し合わなくちゃならないんでしょ? なのに、どうして白石君は、力も無くて気も弱くて、絶好の標的ともいえる私を殺そうとしないの?」
と、昌子は涙で顔をくしゃくしゃにしながら尋ねてきた。
考えるまでも無い。人を殺すなんて大それたことは、どんな理由があろうとも、やはりできない。自分は生まれた時からそういうふうに作られていた人間なのである。幹久はそう思っていた。
肩に手を乗せて優しく接してあげていると、昌子も徐々に落ち着きを取り戻してきたらしく、ぼそぼそとしていた声は少しずつはっきりしたものに変わっていき、最終的にはこれまでの経緯を自ら話してくれるまでになった。
「本当に、白石君は信じていいんだね?」
うっすらと希望の色を見せ始めた昌子の目が問いかけてくる。
「当たり前だよ。僕は何があっても誰も殺さない」
幹久は心に思い浮かべた言葉を偽ることなく返すつもりであった。ところが、開きかけた口は脳からの命令を拒絶し、出そうとしていた言葉を喉の奥へと押し戻してしまった。突然のことだった。
――妹が死んでもいいんだな?
誰かの声が耳に入り、幹久の身体は硬直してしまった。幹久のものでも、昌子のものでもない、悪意に満ちた第三者の囁き。
――妹を殺すぞ?
慌てて周囲を見渡すが、付近には昌子以外には誰の姿も無い。
「どうしたの?」
目の前の少女は当然、不可解な動きを始めた幹久に疑問を抱き、首を横に傾ける。
――級友は殺せと言っただろう?
聞き覚えのある声が誰のものかは分かっている。間違いなく、幹久の妹、桜を人質に取った湯川利久の声だ。しかし、姿形の見えない彼は、いったいどこから声を出しているというのか。
とっさに、胸ポケットに入っている盗聴器を取り出して見た。もしかしたら、ここから利久の声が聞こえてきているのかもしれないと思ったから。しかし、幹久が持っているのは発信機の方なので、こちらの声が利久に拾われているとしても、向こうの声がこちらに聞こえてくるなんてことはありえない。それでは、この不快な悪魔の囁きは、何故聞こえてくるのだろうか。
このとき幹久は、声を耳にしているのは自分だけで、昌子には全く聞こえていないということに気付くべきであった。結論を述べると、幹久は、本当は利久の声なんて聞いていない。妹が殺されるかもしれないという不安のあまりに幻聴を聞こえてしまうほど、彼の精神がかなり劣悪な状態に陥っていたのだった。
――殺せ。目の前の女を殺せ。
「あああああああああああっ」
極度の恐怖から幹久はついに自我を保つことが出来なくなり、意味を持たぬ奇声を上げながら、突然昌子に襲い掛かった。自らの意志ではなく、まるで誰かに操られるようにして手を振り上げるその時の顔は、普段の温厚な幹久のそれとはまるで違う。驚きの表情を浮かべる少女の顔をバレーボールのように掴み、そのまま容赦なく側の倒木の表面へと叩きつける。
思いもよらぬ奇襲を受けた昌子は抗う術もなく、幹久に押し倒されるがままに、後頭部を硬い樹皮にぶつけ、「ぐげっ」と小さく声を洩らした。
最初の一撃で昌子の頭蓋骨は深く陥没し、命は既に終りの時を迎えていた。だけど幹久の右手は一度掴んだ昌子の頭を離さず、何度も何度も硬い木に叩きつける。その度にゴキッとカルシウムの塊が砕ける音がして、昌子の頭はだんだんと元の形からはかけ離れた姿になっていった。
何十回叩きつけた頃か、幹久はようやく自分の身に何が起こったのかが分かる程度にまで自我を取り戻した。その時にはもう、昌子の頭は元の半分以下の大きさになっており、周囲には見たことも無いようなピンク色をしたゼリー状の物体が飛び散っていた。昌子の脳か何かだと思われる。
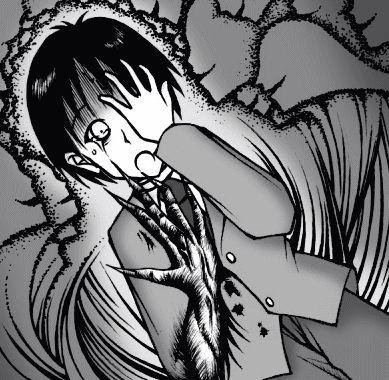
昌子の頭から離した自分の手を見て、幹久は身体の震えを覚えた。
「殺した……。僕は人を殺してしまった……」
殺人をやってのけたばかりの右手は鮮血に染まり、ぽたぽたと赤い雫を滴らせる指からは一向に力が抜ける様子も無く、昌子を殺めたときの形をそのまま維持し続けようとしているかのよう。
一瞬でも汚らわしく思ったせいなのか、自分の手がまるで違うもののように見えてしまった。色の白かった皮膚が黒ずみ、筋肉が隆々と盛り上がって、獣のような長い毛が逆立ち、鋭く尖った爪が長く伸びる。それはまるで悪魔の手。
殺人を犯してしまった僕は、もう人間には戻れない……。こんな汚れた手では、桜とまた手を繋いで歩くなんてことはできない……。
妹を取り戻すがために犯してしまった罪は、皮肉なことに、二人の距離をさらに引き伸ばしてしまう結果となってしまったのだった。
もはや幹久には物事を正しく処理できるだけの冷静さなんて残されてはいない。昌子の死体の側からツルハシを持ち上げたのも、完全に無意識の内の行動だった。
 叶昌子(女子四番)――『死亡』 叶昌子(女子四番)――『死亡』
【残り 十八人】 |
