いじめ、不登校、校内暴力、授業ボイコット、学級崩壊。そんな言葉が蔓延する教育の場において、二十年以上にも渡っていくつかの学校を転々としながら教員生活を送り続けてきた私は、もはや肉体的にも精神的にも疲れ果てていた。幾度となくのしかかってくる問題の数々に、真綿で首を絞められるかのようにじわじわと苦しめられてきたからだ。
そもそも思ったことをはっきりと言えるような性質ではない私は、「気弱で頼り甲斐のない教師」というイメージが強く、ましてや若さと力に溢れた生徒達の間に割って入れるような器なんかではなかった。だから遠目に問題を直視しながら、結局何もできないまま場をやり過ごしてしまうということは多く、そうしているうちに自分の無力さを悲観するようになり、果ては教師という仕事を続けることにすら疑問を感じ始めてしまうのだった。
もともと教員としての資質が無かったのだ。と、何度自分に言い聞かせたかは分からない。けれど、それでも私は長年続けてきた仕事と縁を断ち切るなんてことはできなかった。教育大に通っていた若いころから頭に思い描いていた「生徒達との楽しい毎日」という教員生活の理想図に、まだ未練が残されていたからだろう。
そんな私に転機が訪れたのは今から二年半前の四月。兵庫県立松乃中等学校に就任したことが、教員としての生活に大きな変化をもたらしたのだった。
松乃中等学校、そこは本当に素晴らしい所であった。自然との調和を重んじて造られた半木造の校舎は、何十年か時を遡ったかのようなレトロな雰囲気を漂わせながらも美しく、初めて敷地内に入ったときなんか、思わず息を呑んでしまったほどだった。だがこの学校の良き点として注目すべきは建物ではなく、学校中を包む穏やかな気風の方といえよう。
指導が行き届いているからなのだろうか、それとも本質的に良く出来た生徒たちばかりが集まっていたのか、理由は定かでは無いが、とにかくここは私が今までに見てきた中で、最も平和な中学校であった。
生徒達は皆仲が良くて、喧嘩やいじめなんて滅多なことでは見られない。理由も無しに欠席する学童なんているはずも無く、授業は滞ることなくスムーズに進めることができた。こんなことは以前の学校からは考えられなかった。そうそう、生徒達から「桑原先生」なんて親しみを込めて呼ばれたのも、ここの学校に来てからが初めてだったかもしれない。
たかだか片方の手の指で数えられる程度の中学しか見てきていない私には、こんな松乃中が「異彩」なのか、それとも単に今まで働いてきた学校が他より悪かっただけなのか分からない。けれども、どんなに走り回っても生徒達の背中を追いかけることで精一杯だった私が、苦労もなく全員の顔と向き合うことが出来たというだけで、こここそが追い求めた理想郷であると信じて疑わなかった。
こちらから歩み寄らなくとも、生徒達から集まってきてくれる。そんな至福に満ち溢れた日々は、長年に渡って蓄積した私の疲れをきれいさっぱりと洗い流してくれた。
これ以上、求めるものは無い。
若葉に囲まれた生活に満足した一本の老樹は、こんな生活がただずっと平和なまま続いてくれることだけを望んだ。だけど、松乃に就任してからたったの半年後、赤い悪魔は突如襲来し、私のささやかな願いを跡形もなく焼き尽くしてしまったのだった。
兵庫県立松乃中等学校大火災として知られる大惨事は、本当に前触れも無く突然起こった。可燃性の高い薬品なんかが多くある理科実験室が火元であったことが、被害拡大に拍車をかけたのだろうか。知らせを聞いてすぐに駆けつけたにも関わらず、数回の爆発に見舞われた火災発生現場では、既に炎は黒い煙の中でかなり勢いを増していた。
急いで現場付近にいた生徒達に避難するよう指示し、私は理科実験室の前から伸びる廊下を真っ直ぐに走り出した。突き当りを曲がってすぐの所に、消火器が一つ備え付けられているはずと記憶していたので。
理科実験室で燃え盛る炎はだいぶ大きくなってはいたが、今ならまだ校舎中に燃え広がるのを阻止できるかもしれない。そう考えてのことだった。
全速力で廊下を駆けた私はすぐに突き当たりに到達した。そこから消火器を持って理科実験室に戻り、消火活動を開始する。これくらいなら三十秒もかからずにできるであろう。そしてこれ以上の被害の拡大を防ぐことも出来る、はずだった。だけど実際に蓋を開けてみればどうしたことだろう、廊下の隅に常設されていたはずの消火器が、私が駆けつけたときには、まるで手品にかけられたかのように消え去っていたのだ。一瞬、興奮のあまり見落としてしまったのかと思ったが、それにしてもあんな目立つ赤い色をした物体に気付かないはずが無い。このとき、消火器は確かにあるべきはず場所に無かったのだ。
すぐに別の場所から消火器を持って来ようと走り出したがもう遅し。二階へと伸びる階段の手前に差し掛かった瞬間、火元である理科実験室でまた大きな爆発が起こったのである。より可燃性の高い薬品に引火したのか、それともガス漏れが起こったのかは分からないが、とにかくその時の爆発はこれまでとは比べものにならないほど大きく、もはや私一人ではどうにもできないほどにまで火は巨大に成長してしまったのだった。
このころにはもはや学校中がパニック状態。我先にと出口に向かって走り出す生徒達の流れは『濁流』と喩えてもよいほどの勢いがあり、それに飲まれてしまった私は生徒達を誘導することなんて出来るはずも無く、そのまま出口から外へと押し出されてしまった。しかし、校舎の中に生徒を残したまま教師が先に逃げるなんてどうかしている。
私は未だ火中から出てこない生徒達を連れ出すために、すぐにまた灼熱地獄と化した校舎の中に戻りたかった。が、他の教員に止められてしまっては、さすがにそれは叶わない。
「大丈夫ですよ。消防署にはもう通報してありますから」
若い男性教員が言った。きっと悲壮な表情を浮かべている私を少しでも落ち着かせたかったのだろう。不本意だが、私は十も年下の同僚に従って消防車の到着を待ち、消火活動や人命救助はその道のプロに任せることにした。まあ普通に考えればそれが妥当であろう。私のようなどんくさい男が一人校舎に飛び込んだところで、きっと救助される人間が一人増えるだけだろうから。
ところが、このときに限り、その判断は大きな間違いであった。どういうわけか、通報から消防車が火災現場に到着するまで、実に通常の倍もの時間がかかったのである。瞬く間に炎が広がる木造校舎の火災において、その遅れは致命的であった。
結局、消火活動が遅れたせいで校舎は全焼してしまい、逃げ遅れた多くの生徒が命を落とすこととなってしまった。もしも消防車が遅れることなく到着していれば、被害はもっと少なくて済んだだろう。なんて、考えれば考えるほどやりきれない気持ちになってくるのだった。
とにかくこうして、私のささやかな願いを託された松乃中学校という楽園は、ほんの短時間の間に、ただ真っ黒いだけの消し炭と化してしまった。これはある意味、私の教員としての生活にも終りの時が来たのだと判断するのに十分すぎる材料であった。長年探し求めてようやく見つけ出した私の居場所が、きれいさっぱりと無くなってしまったのだから。
しかし結局、私が教員を辞めることは無かった。松乃で働いていたころの熱心な指導ぶりを買われたのか、事件の生還者たちが新たに通うことになった兵庫県立梅林中学校の『被災者特別クラス』の担任に抜擢されてしまったから。いや、された、なんて言葉は使うべきではないだろう。これは私自身が心底で望んでいたことでもあったので。
もう一度教員として、かの素晴らしき教え子たちと向き合うことが出来る。それは私にとって大変喜ばしきことだった。もちろん校舎が変わると同時に環境も一変してしまうだろうが、半年間時を共にしてきた生徒達とまた一緒に過ごせるというなら、それだけでもう十分だった。そして被災者達の心に刻み込まれた悲しみの記憶を少しでも取り除いてやりたいと思う私は、いっそう熱心に教育者としての職務を全うするのであった。
そして、事件当時の一年生が中学の最高学年になった今、私こと桑原和夫(三年六組担任)は、とある島の中に立つ小さな分校の一室で、ただぼんやりと時間を過ごしている。信じられないことに、梅林中就任以来ずっと担当し続けてきた被災者特別クラスが、今年度のプログラムに選ばれてしまったらしい。
通常、プログラムが実施されるよりも先に、担任は自分のクラスが参加するということを承諾しなければならないのだそうだが、桑原は担当教官からその話を聞いた途端、頭の中が真っ白になってそのまま意識を失ってしまったのだった。なんとも情けないことに。そのせいで家に帰されることも無く、あるいは命を奪い取られることも無く、こうして会場にまで連れてこられてしまったわけだ。どうやら政府は何があっても、プログラム参加の同意を得るまで担任教師を拘束しておくつもりらしい。
既に始まってかなりの時間が経つ今回のプログラムについて、今さら話をつけることに何の意味があるのかは分からない。ただ、形として定められている儀式は全て消化しなければならないというのが、政府側のルールであるのかもしれない。
近いうちに、話をつけるためにと担当の者がやってくるはず。その時に私は何と答えればよいのだろうか。プログラム参加に同意する意志を伝えさえすれば、私だけは何事も無く釈放されるかもしれない。しかし、もし向こうが求めている答えに反する返事をすれば、きっとただでは済まされない。最悪の場合、このまま殺されてしまう可能性だってあるわけだ。
べつに死ぬことに対して恐怖を覚えたりはしない。しかし未練というものが残されている以上は、もう少し長く生きていたいというのが本音である。
桑原はどうしても知りたかった。生涯見てきた中で最も素晴らしかった教え子たちが、なぜあんなにも酷い惨事に巻き込まれなければならなかったのか。それと、ほんの些細なことのようにも思える謎の数々を、本当に不運や偶然といった言葉で片付けてよいのかどうかも。
まずは消えてしまっていた消火器についてだが、桑原の記憶に間違いが無ければ、事件前日の午後にはまだいつもの場所に置かれていたはずだった。それがなぜ火災発生時には無くなっていたのだろうか。
それから事件現場に遅れてきた消防車。後々に聞いた話によると、消防署から松乃中へと続く道の途中で玉突き衝突事故があったとかで、消防車の列は大きく迂回して現場へと向かうこととなり、そのせいで通常の倍もの時間を要してしまったというわけらしい。はたしてこれは偶然なのか。
消火器が消えたこと。消防車が遅れたこと。いずれも火災の被害を拡大させるのに一役買った出来事だ。事件の裏に得体の知れない何かが隠されているように思い始めていた桑原は、これらを単なる偶然や不運が重なって起こっただけの出来事とは、とても思えなかった。
桑原は数時間前にここを訪れた一人の兵士に向かってそのことを打ち明けた。いわば敵ともいえる政府側の人間に、どうして話してしまったのかは自分でもよく分からないけど、もしかしたら、少し不思議な雰囲気を纏っていたその相手のことを、にわかに信用してしまったのかもしれない。
兵士は桑原が受け持つクラスのメンバーの一人である春日千秋さんと面識があるらしく、彼女の安否をしきりに心配しているようだった。なるほど、春日千秋さんといえば、父親が経営する飲食店の手伝いをしていることで知られていて、いつも元気よくはきはきと喋るとても良い娘だった。そんな彼女と繋がりのある人間だと知り、多少なり親近感を覚えてしまったのだろう。とすれば、事件のことを兵士に打ち明けたのは、自分自身の死を予感しながらも松乃中火災の真相が明らかになる日が来るのを待ち焦がれていた桑原の、一種の遺言だったと言えるかもしれない。
もしそうなのなら、桑原にはもはや事件について干渉する必要など無い。運命という流れに身をまかせ、謎を明らかするもしないも、後のことは全て生ある者に委ねてしまえば良いのである。
「大変お待たせしてすみませんねぇ、桑原先生」
音を立てて開いた扉の向こうから、背中に銃を背負った兵士三名を引き連れたアフロヘヤーが姿を現した。
「もうお分かりでしょうが、今回のプログラム参加に了承してくださるかどうか、お話を伺いにきましたぁ」
「遅かったですね。私が目覚めていたのには、かなり早くからお気づきになっていたと思いますが」
「いやなに、別に私はあなたのことなんて全く興味が無かったものですからねぇ、すっかり忘れていたのですよ、ええ。ただ今のところプログラムに面白い展開は見られそうに無いのでぇ、それなら今の内に余計な仕事を済ませておこうと考えたわけです」
「面白い展開が見られない? それはつまり、しばらく教え子たちは誰も死にそうにないということですか? それは私にとってはとても好都合ですね」
悪態には悪態で返す。他人に向かってこんなに憎たらしい口を利いたのは初めてかもしれない。
「ふふふ、まあお話は場所を移して続けましょうや」
桑原の言葉が癇に障ったのだろうか、口で笑いながらも担当教官の田中一郎は怒りに満ち溢れた顔をしていた。
田中に続いてゲストルームから廊下へと出ると、桑原の前後左右を囲むように兵士達も歩き出す。はじめから逃げ出すつもりなんて更々無かったが、こうやって動く人間の檻の中に閉じ込められてしまうと、妙に緊張するものだった。
先頭を歩いていた田中が立ち止まると、続いて兵士達も足並みを崩すこともなくきれいに立ち止まる。行進さながらに揃ったその動きは見事なものだ。
「さあさ、どうぞ入ってくださぁい」
田中が開いた引き戸へと誘導するので、私は促されるままに部屋へと踏み込んだ。
そこは教室だった。内装は少々古めかしいものの、鉄の骨組と木で作られた学習机と椅子が並んだ、どこの学校でも見られるごく自然な光景が広がっている。
「昨日の夜、あなたの教え子さんたちはここでプログラムの説明を受けたんですよぉ」
そう言って田中が両の手を広げて見せたとき、桑原は教室中に漂う生臭い匂いに気がついた。それから床の上に広げられたビニールシートのふくらみ。
あの下には何があるのだろう。
「さて、それでは早速ですが本題に入りましょう。今回、あなたが受け持つ梅林中三年六組がプログラムに選ばれましたぁ。ので、担任である桑原先生には、そのことについて了承してもらいたいと思います」
「了承しません」
キッパリと言った。すると田中は、おやおや、と顔をしかめる。
「まだ寝ぼけているのですかぁ? いいですか、梅林中三年六組はプログラムに選ばれ、あなたが気を失っている間から戦い始めているのですよ? 既に多くの死者が出ていますしぃ、今さら担任が反対したところでもう止めようはありませぇん。それでもあなたは政府の決め事に反対すると言うのですかぁ?」
悲しい運命を背負った生徒達を見殺しにして、自分一人だけ生き延びようなど、教師の考えることではない。桑原は断固として首を縦に振らなかった。
「そうですかぁ。それなら仕方がないですねぇ。おい、桑原先生に見せてやれ」
田中がなにやら顎で指示すると、兵士達は教室の中心部へと動き出し、そして桑原が先ほどから気にしていたビニールシートを、さっと取り払った。
「あっ」
教室の真ん中に現れたものを見て、驚きのあまり思わず声を上げてしまった。シートの下に隠されていたのは少女の遺体。何かが爆発したのか、首もとの肉はほとんどが周囲に飛び散っており、そこから流れ出したのであろう大量の血液が床に赤く大きな染みを作り出している。血の気が引いて変色した顔は、生前のころの面影をほとんど残していなかったが、頭の左右で結んだツインテールを見て、すぐにそれが相沢智香さんであると分かった。
「いやぁ、私もこんな酷いことはしたくなかったんですけどねぇ。しつこく楯突いてくるものだから、ついつい見せしめに殺しちゃったんですよぉ」
聞いてもいないのに説明を始めた田中は、へへっ、という笑いで言葉を締めくくった。
「私が何を言いたいのかお分かりですかぁ? つまりぃ、これ以上政府に歯向かい続けるようならば、今度はあなたもこの娘みたいなことになっちゃいますよぉ、ってことです」
「脅し、というわけですか……」
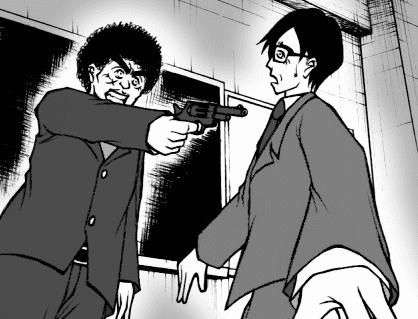
いつの間にか田中の手にはリボルバー式の拳銃が握られており、銃口はしっかりとこちらに向けられている。さすがにこれには緊張しないわけにはいかなかった。しかも死体を見せられた直後だからか、その圧力はより重く感じられ、恐怖のあまり口から勝手に「分かりました」と、意思に反した言葉が危うく出てきそうになる。しかし、桑原はそれをギリギリのところで飲み込むことができた。
「何をしようが、私はあなたたちの前に屈するつもりはありません。プログラムには断固反対です」
明るい笑顔を周囲に振り撒いて、暗く沈んでいたクラスに元気を取り戻そうと、微力ながらも貢献してくれた智香にはいつも感謝していた。だからそんな彼女の命を奪った政府の言いなりになるなんて、桑原の良心が絶対に許さなかった。
「そうですか。まあ最初からこうなることを見越して、あなたをこの部屋に連れてきたんですけどね。ほら、どうせ血で汚れるなら、先に生徒を殺した部屋で行った方が、掃除が一度で済んで楽ですからねぇ。結局、ウンコちゃんたちの師はウンコちゃんだったということですねぇ」
ふぅ、と溜息をついたかと思えば、田中はすぐに構えていた銃の引き金を絞り始める。
これでよかったんだ、と桑原は自分に言い聞かせた。
生徒達の命を売ることもなく、共に同じ地で人生に終りを迎えることが出来た。教師としてこれほど幸せな幕引きはない。二年前の事件について分からないことが多く残されたままなのは残念だけど、それも私がいなくとも、いつか誰かの手によって暴かれるかもしれない。
それから私の可愛い教え子達。助けてやれなくて本当にすまなかった。二年前に続いて今回も何の力にもなれなかった無力な私を、どうか許してくれ。まだまだ言い足りないことは沢山あるけど、とにかく、君たちと出会えて本当に良かった――。
田中の手の中で一発の銃声が轟く。そしてその瞬間、テレビの電源が切られたかのように、相沢智香の側に倒れた桑原の思考はすぐに途絶えてしまった。
 桑原和夫(三年六組担任)――『死亡』 桑原和夫(三年六組担任)――『死亡』
【残り 十九人】 |
