茂みの奥から姿を現した利久は雨に濡れた草をガサガサと踏みしめながら、ゆっくりとこちらに近寄ってくる。幹久や桜のことを危険な人物ではないと信じ切っているのか、全く警戒していない様子だ。
自分の身を守るためにも、桜を危険な目に遭わせないためにも、出来るだけ誰も近づかせない方が良いということは分かっている。だけど、いつも屈託の無い笑顔を見せていた利久が口から牙を生やして襲い掛かってくるなんてこと、想像することも出来なかったから、幹久は相手の接近を拒もうとはしなかった。
「こんなところに隠れていたんだ。でも駄目じゃないか、茂みからはみ出した頭のてっぺんが向こうから見えていたよ」
手を伸ばせば相手の身体に触れられるというくらいの距離にまで迫った時、彼は来た方角を指差しながら、ボリュームを落とした声で言った。
「本当に? ちゃんとしっかり隠れられていると思っていたんだけど」
「目を凝らせば意外と容易に見つけられたよ。もっと姿勢を低くしないと危ないよ」
しかし幹久は逆に、自分達よりも利久こそがもっと注意を払うべきではないかと思った。こちらがプログラムに乗り気でなかったから今回は助かったものの、もしも相手が殺意を内に秘めていて、それに気付かず無防備に近づいていれば、利久はその餌食にされていたかもしれないのだ。
そのことについて一応意見してみる。しかしそれに応える利久の口調は軽い。
「たしかにそれは正論だろうけど、性格上幹久くんが自分からゲームに乗るなんて考えにくいからね。それにもしも銃か何かを持っていたら、僕が姿を現した時点で構えていたはずだし――。もちろん僕が最初に名を呼んだとき、幹久くんが少しでもそんな怪しい素振りを見せていたら、すぐに逃げ出したと思うよ」
幹久は殺しに興じるような人間ではないと信用されているらしい。それはまあ喜ばしいことなのだろうけれど、相手に全く警戒されないというのも、「戦いになっても幹久が相手なら負けることは無いだろう」なんて思われているようでなんだか悲しい。確かにスポーツというものが全般的に得意ではない自分は、正面からの対決でも、追いかけっこでも、利久に負けてしまうかもしれないけど。
「まあそれはともかく、ここには何時ごろからいたの?」
しばらくこの場に居座るつもりなのだろうか。利久は兄妹と対面するような位置に身を屈め、中腰のまま質問を始める。平和な日常の中では見せていた朗らかな微笑みはさすがに消え、今はちょっと真剣そうな面持ちをしている。
「正確な時間は分からないけど、ここに来てから一時間以上は経っていると思う」
「結構長い間いたんだね。それで、これまでに誰かと会ったりした?」
「遠目に何度か人影を見たくらいで、相手が誰だか判別できたことは一度もないよ。桜以外の人とは、できる限り接触を避けようとしてきたから」
「それじゃあ今までに会ったのは、桜さんと僕だけだと考えて良いんだね」
「そういうことになるね」
聞かれて困るようなことは何も無いので、幹久は一つ一つ正直に答えた。それに、プログラムに巻き込まれてからのクラスメート達の動きをよく分かっていない今、情報交換はとても大切なことだと思ったので。
「湯川くんは誰かに会ったりした?」
自分達にとって有益な話が聞けることを期待して、幹久は今まで自分が受けてきた質問をそのまま相手に返した。「誰々は危険だ」とか、そんな話でも身を守るためには十分役立たせることが出来る。
しかし利久は「僕も幹久くんたちと同じで、誰との遭遇も無かったよ」なんて返事をしてきたので、残念ながら結局参考になるような情報は何一つとして得られなかった。
「ごめんね、役に立てなくて」
「いいよ、お互い様だから」
利久が軽く頭を下げるのを、幹久は少し慌てて止めようとする。実際、こっちだって利久が欲するような話なんて欠片すら持っていなかったわけだし、一方的に頭を下げられるような立場ではない。かといって二人がお互いに頭を下げるというのも、かなり滑稽かつ無駄な気がするので、自分までもが頭を下げなければならない状態にならぬよう、なるべく相手に下手に回られたくはないのであった。
ちなみに、男二人が話す隣に座っていながらも、桜は相変わらず表情一つ変えずに黙ったままだった。
「ところで、二人に支給された武器は何だったの? 僕はこんなのだったんだけど」
そう言って利久が見せたのは拳銃。といっても、実銃特有の重量感は全く感じられず、本物ではないとすぐに分かる。
「モデルガン……、いや、玩具と言ったほうが適切なのかな?」
「笑っちゃうでしょ。トリガーを絞ると中からプラスチックの弾が飛び出すんだ」
利久がそれを構えて指を動かすと、プラスチックの部品がバネをはじく「カコンッ」というマヌケな音がして、銃口から飛び出したカラフルな色の弾が近くの木に跳ね返って落ちる。どう見ても当たり武器とは言い難い代物だった。
笑い事じゃないけれど、利久が使い物にならないような武器を支給されていたことを知って、同じような状況下にいる幹久は変に共感してしまった。
「こっちも似たようなものだよ。桜に支給された武器はまだしも、僕のなんてとても役立たせられそうな物じゃないし」
「幹久君は何を支給されたの?」
「えーと、盗聴器のセット」
使う機会は無いと思ってデイパックの中に仕舞い込んでいたそれらを出して見せると、利久は少し苦笑いした。
「専用受信機と薄型の発信機か……。たしかに使い所なんて無さそうだね。それで、桜さんの武器は?」
「防弾チョッキ。ブレザーの下に着せてはいるけど、これだけでは安心なんて出来ないよ」
「ふぅん。なんとなく君達の状況が分かったよ」
ふいに利久の口の両端が蛇のようにつり上がった。刹那、彼は素早く立ち上がって一歩後ろに下がり、無言のまま座り込んでいた桜の首根っこを掴んで手前に引き寄せた。そして後ろに回した手で怪しく黒光る何かを掴み、桜のこめかみ付近に突きつける。銃だった。先ほど見た玩具なんかではなく、もう一回りサイズの大きい本物――マシンガンだ。今まで気付かなかったが、まさかずっと背中に隠し持っていたのか。
「これはいったいどういう冗談なんだ、湯川くん?」
前触れ無く起こった出来事に驚き、幹久は訳が分からないまま桜に近寄ろうとしたが、利久に「動くと妹を殺すぞ」と脅された途端、両方の足は急にロックがかかったように動かなくなった。
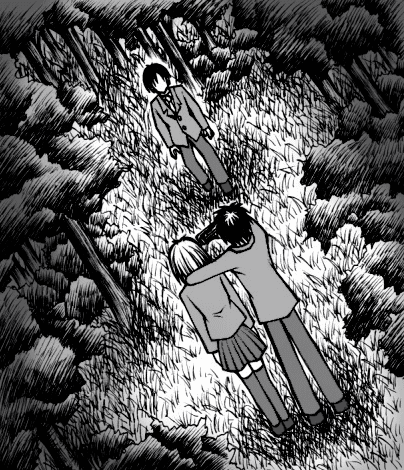
「冗談なんかじゃないさ。とりあえず知りたいことは全て聞き尽くしたことだし、演技し続けるのを止めたというだけのこと」
「演技だって?」
見たことの無い不気味な微笑を顔中に湛える利久は、既に桜に向けたマシンガンのトリガーに指をかけている。ほんの少しでも力が入れば、妹の頭は粉々に吹き飛ばされてしまうだろう。相手を刺激せぬよう言葉遣いには細心の注意を払わなければならない。
幹久はそんなことを考えはしたが、実際は軽いパニックを起こしている頭に言葉を選ぶ余裕なんて全く無いのだった。
「まさか、最初から騙すつもりで僕達に近づいたとでも言うの?」
すると利久はあっさりと頭を上下に動かして、肯定の意を示す。
「本来の姿を偽りの笑顔の下に隠してきたという点では今回に限らず、入学以来ずっとクラスメート達全員を騙し続けてきたのだとも言えるけど、まあそういうことだ」
なんだか自分たちのことが釣り針の存在に気付かずにまんまと撒餌に集まってしまった魚のように思えて悔しい。
「じゃあ、さっきの玩具の銃はなんだったんだ?」
「あれはそもそも俺の武器じゃない。ついでに言えばこのマシンガンもな。俺に支給された武器はもう一つ別にある」
「まさか――」
幹久は嫌な予感を覚えた。自分に支給されたわけでもない武器を手にしている理由なんて、そう色々と考えられるものではない。他人の武器を譲り受けただけというのもありえない話ではないけれど、利久の本性を見てしまった以上、殺した相手の物を奪い取ったのではないか、としか思えないのだった。
「なんとなく察したようだな。そう、俺はもうクラスメートを殺している。直接手を下した者だけでも二人」
固まってしまった表情を見ただけで、利久はこちらが考えていたことをなんとなく読み取ってしまったらしい。それにしても、「直接手を下した者だけでも二人」ということは、他にもさらに間接的にでも死に追い込んだクラスメートがいるのだろうか。もちろんそれは幹久の知るところではなかった。
「とにかくだ、これで俺が冗談を言っているわけではないと分かっただろう。お前の妹だって今すぐにもぶっ殺せるんだぜ」
「やめてくれ! それだけは――」
首に肩をかけて桜の動きを封じている利久に向かって、幹久は妹には手を出さぬよう必死に懇願した。桜は自分自身の力で逃げようとはしないし、今までに複数の生徒を殺してきたという利久が、急に考えを変えて妹を解放してくれるとも思えない。兄である幹久が何かしなければ、桜は絶対に助からないのだ。
「僕は殺していい! だけど、妹にだけは手を出さないでくれ!」
「おいおい、お前を殺すなんてのは最初から決めていたことだぜ。交換条件にもなりゃしねぇよ」
「何でもするから……何でも言うことを聞くから、だから妹の命だけは――」
恥も外聞も捨てて濡れた地面の上に平伏す。感情があったころの桜だったら、こんな兄の姿を見たらきっと悲しんだであろう。だけど、利久の手中に落ちてしまった彼女は、焦点の定まらない目をこちらに向けているだけで何も言ってはくれない。耳に入ってくるのは利久の含み笑いのみであった。
「妹のためならなんでもする、か……。ちょうどいい。このままただお前達を殺すってのも、なんだか味気無いと思っていたところだ」
立ち上げるよう言われ、幹久は地に伏していた身体をゆっくりと起こす。草の上だったので泥まみれになったりはしなかったけど、水分を吸った制服はやはり重く感じられた。
「さて、問題は何をして楽しむかだが、そうだな――」
相変わらずマシンガンの銃口を桜の頭に触れさせたまま、利久はしばし考えに耽っていた。その間、妹を奪い去る隙は無いかとうかがい続けたが、当然マシンガンをしっかりと持つ相手を前にどうすることも出来なかった。
「こんなのはどうだろう」
なにかろくでもないことを思いついたのか、利久はまた不気味に笑い出す。
「おい、盗聴器の受信機だけこちらに渡せ。それから発信機はお前の内ポケットに入れるんだ」
いったい何のつもりなのか理解できないけど、反抗は禁物であると分かっているので、言われた通りに受信機だけを利久へと放り投げた。
「発信機はもう内ポケットに入れた」
「よしよしいい子だ。それでは、妹を助けるための試練を発表するとしよう」
試練だって? 何だそれは?
幹久は相手の口の動きを凝視する。
「もうすぐ三回目の放送の時間だから、そうだな、さらにその次の深夜零時の放送までを制限時間とする。それまでに、自分自身の手で生き残っている生徒達を出来るだけ多く殺してくるんだ。ノルマは最低で三人。それを下回ったら妹は絶対に助からない」
「なっ……」
幹久はついつい絶句してしまった。これまで机を並べて一緒に暮らしてきたクラスメート達の命を自らの手で奪うなんてこと、考えるだけでも恐ろしい。
「おいおい、出来ないなんてことは無いだろう? お前さっき言ったじゃないか。『なんでもする』って」
「それはそうだけど、こ……こんなこと出来るはず無いじゃないか。だいたい、こんなのに何の意味があると言うんだ」
声が震えているのが自分でもよく分かる。恐ろしさに完全に怯えきってしまっているのだ。
「理由か……。俺が生き残るのに邪魔な奴らを掃除してきてほしいというのもあるが、それよりも楽しみたいというのが本当の理由かな」
「楽しみたい?」
「お前が誰かを殺す時の声や物音は、盗聴器を介して俺の耳にまで届くだろ。まさに殺しの実況中継だ。リアルタイムで聞けば、きっと興奮すること請け合いだろう」
この男、狂っている。
幹久の背筋に悪寒が走り、全身に鳥肌が立った。
「だ、だけど、今はプログラムの最中であって、湯川くんだっていつ誰に襲われるとも限らないのであって――」
だからそんな愚かなことを娯楽にするような余裕など無いのでは、と続けるつもりだったのだけれど、混乱したせいで話を上手くまとめられなくなり、尻すぼみになった言葉はそのまま途切れてしまう。
「もちろんこんなのは俺が生き残るのを前提とした話さ。マシンガンのほかにビーコンまで兼ね備えている俺が、他の誰かに殺されるなんてこと、今のところ全く考えられないからな」
彼のもう一つの武器がビーコンであるということは今初めて知ったが、そんなことはもうどうでも良い。
「とにかく、妹の命を助けてほしければ、何も考えずに三人消して来い。もちろんノルマ以上なら何人殺したって構わない。そして時間になったらここに戻ってくるんだ。一応忠告しておくが、下手な真似はするんじゃないぞ。もしも誰かに助けを求める声なんかが盗聴器から聞こえたりしたら、即座に妹を殺すからな。そう肝に銘じておけ」
「でも……」
「分かったらとっとと行け。十秒以内にここから消えないなら、俺に逆らったと考えて妹の頭をぶち抜く」
桜のこめかみに押し付けた銃をぐりぐりと動かして、いつでも殺せるぞ、なんてアピールをされてしまっては、もはや幹久にはどうすることも出来ない。声を出してカウントし始めた利久に背を向けて、とにかくこの場から離れなければならなかった。
武器も持たずにどうやって戦えというのか。いや、そもそも他者を傷つける気すら全く無かった自分が、クラスメートを殺せるはずなんて無いのだ。いくら妹のためとはいっても。
いったい僕はどうすれば良いんだ。
一度振り返って桜の方を見る。首に利久の腕が巻きついて身動き取れない状態の彼女は、相変わらず何処を見ているとも分からない目をしながら、ただじっとそこに存在し続けている。
生き残ることが前提の話だというなら、幹久が何をしようとも利久が桜を生かすはずは無い。それはちょっと冷静に考えるだけで分かるはずだったが、残念ながら今の幹久には冷静さなんて完全に欠落していた。だけどどっちにしろ、自分のことよりも妹の命を大切に思っていた兄は、二度と桜に会えないかもしれないと思うと、溢れた涙を止めることもできないのだった。
【残り 十九人】 |
