僕にとって大切な命は二つある。一つ目はもちろん自分自身、そして二つ目は、親の血を分けた唯一の存在である、たった一人の妹。
桜と僕は同じ日の同じ時間に生を受けた双子。二卵性双生児なので瓜二つというほどでもなかったが、それでも母親の特徴を色濃く受け継いでいた僕らの幼げな顔つきは、生まれた時からかなり似通っていた。親類はともかくとして、初めて会った人間なら、どちらが兄でどちらが妹なのか一目では判別できないほど。実際これまでに、僕が妹と間違われることなんて数え切れないほどあった。たぶん首もとの辺りで切り揃えた髪の長さがほとんど同じだったせいもあったのだろう。
桜は優しくて可憐な少女だった。彼女の無邪気で明るい微笑みは、童話に登場するお姫様のそれよりも輝いていて、見ていると元気が沸いて出てくる。
桜の笑顔さえ側にあれば、他に求めるものは何も無い。そんな思いから、僕は妹と手を繋いで離れようとはしなかった。いくら兄妹とはいえ少々べったりしすぎだったかもしれないけど、幸いにも桜はこんな兄のことを慕ってくれていたし、特に気にするような事は何も無かった。
僕が手を引っ張れば、桜は黙って後からついて来てくれる。そんな関係がとても心地よかったからか。それとも、「兄が先に生まれてくるのは、後から生まれる妹を引っ張ってあげるため」と、幼少の頃から親に言い聞かされてきたからだろうか。とにかく、僕は何をするにおいても、常に妹の前を歩き続けた。
桜が勉強に困っていたらいつも教えてあげていたし、悩みの相談に乗ってあげたのも、鉄棒で逆上がりを教えてあげたのも、妹が道に迷いそうになるたびに力になってあげていたのは全て僕。そして桜は桜で、親愛なる兄が立てた標を忠実にたどり続けてくれたので、人生に分かれ道なんて数え切れぬほどあるというのに、二人が違う道筋を歩んだことなんて一度も無かった。もちろん公立の学校に通う双子が同じクラスになることは無く、授業中なんかは必然的に離れ離れになってしまうけど、それでも心はいつも繋がっていたのだった。
僕達は小学校を卒業すると、そのまま県立の松乃中等学校に入学した。もちろんここでも二人は同じクラスにはなれず、僕は一年B組で、桜はその隣のC組に入ることになった。初めての中学校とはいっても、周りにいる生徒達の三分の一程度は同じ小学校の出身だったし、兄妹共それなりに社交的な性格であったため、どちらも比較的スムーズにクラスの中に溶け込むことができた。
そうして特に何事も無くスクールライフを満喫しつつ迎えた夏のある日、桜のいるC組に、少し変わったお客様が現れたのだった。
「何を読んでいるんだ?」
クラスの用事で帰宅時間が遅れた僕は家に着くなり、ダイニングテーブルの上に平積みした三冊の本を真剣そうに読む妹へと、何気なく近寄った。
桜が今手にしているのは、『野鳥大百科』という分厚い本。積まれているのは、上から『インコの飼い方』『ツバメの一生』というタイトルの、先の本と比べるとかなり薄めの冊子。鳥という共通点を持つ三冊の背表紙には、アルファベットと数字が並ぶシールが貼り付けられており、どれも学校の図書室から借りてきたものであるとすぐに分かる。
「お兄ちゃん、ツバメの雛って何食べるか知ってる?」
「ツバメの雛? どうだろう。育てたことも無いからよく分からないけど、やっぱり虫の幼虫とかじゃないかな」
「幼虫かぁ」
読んでいた本をぱたんと閉じ、桜はテーブルの上に上半身を倒した。
「やっぱり鳥を飼うって大変そう」
「いったいどうしたの?」
冷蔵庫から取り出したカルピスを氷と冷水で適度に薄め、二つのグラスのうち片方を桜に手渡してから、テーブル越しに向かい合う椅子に腰掛けた。そして、かき混ぜ棒代わりに挿したストローでグラスの中をぐるぐる回しながら、話を聞く姿勢に入る。
桜も兄と同じようにカルピスをかき混ぜながら、事情を説明し始めた。
今日の昼休み、校舎の外壁に作られていた巣から落ちて地面の上でのた打ち回っていたツバメの雛を、桜のクラスの女子数人が教室にまで連れてきた。担任の教師は、親鳥のもとに返してやるべきだ、と、至極当然の意見を述べていたものの、巣の作られた位置は高く、屋根のひさしを伝ってそこまで雛を連れて行くのはあまりに危険だった。雛を巣に返してあげるという最善の案を実現させることはなかなか難しい。しかし、かといってそのまま見殺しにすることもできない。
「それならクラスで飼ってあげれば良いではないか」
誰かが言ったその言葉はクラス中に受け入られ、すぐに皆その気になってしまった。学級委員長が代表となって頭を下げて担任教師から了承を得てくれたおかげで、晴れてC組はそのツバメの雛を飼えることになった。
桜の説明を要約すると、だいたいこんな感じである。
つまり桜が図書室から借りてきた本は、クラスで飼うツバメの雛をどう育てればよいのかを調べるためのもの。しかし、野鳥であるツバメの飼い方がそのまま載っている本なんて、そう易々と見つけられるはずも無く、とりあえず一般的な飼い鳥の育て方とツバメの生態について調べようと考えたところ、こんな三冊が揃ってしまった、というわけ。
「しかし、本当にツバメなんて育てられるのか?」
ツバメに限らず、野鳥を飼うことの難しさは、飼育経験の無い者にとっては全くの未知数だ。それに発育途上の雛鳥なんかは非常にデリケートで、ほんの少しの環境の変化が生死に大きな影響をもたらすと聞いたことがある。巣から落ちてきた野鳥の雛を介抱しようとしても、すぐに死なせてしまうというケースは多いらしいし、飼い鳥の代表ともいえる、カナリア、ブンチョウ、インコなどを普通に育てるのとは違って、色々と大変なはずだ。
「大変なことだってのは分かってるよ。だけど、だからと言って何もしなかったらあの子は死んじゃうし、頑張ってみる」
ストローから離した口で桜は強くそう言う。しかし、頑張ろうにも、手元にある本から得られるツバメについての知識なんてたかが知れている。
スズメ目、ツバメ科。全長約十七センチ。夏鳥であるツバメは春から秋にかけて日本にやってきて、人家や店など人間が造った建造物におわん型の巣を作る。飛翔力、旋回性能に優れ、時速二百キロで飛ぶことも可能。上面は黒く、青い光沢をおびる。額と頬は赤褐色で、胸は白い。
それ以外に「ツバメの巣は中華料理の高級食材」ということは桜も常識として知っていたようだが、これだけの情報で雛の世話なんてできるはずがないし、とても不安だ。
だけど僕は妹のポジティブな考えは後押ししてあげたい性質であり、幾ばくかの不安を抱えていようとも、最後には応援する形で話をいつも締めくくってしまう。それはこの時も同じで、「まあ命を救うってのは良いことだし、最後まで頑張れ」なんて言いながら、グラスの底に数センチ残っていたカルピスを吸い上げつつ、一緒になって本のページをめくり始めてしまうのだった。
人海戦術の効果とは恐ろしいもので、翌日に桜のクラスメート達が持ち寄った情報を合わせると、僕達が二人がかりで探しても全く分からなかった「ツバメの飼い方」が、かなり鮮明な形となって浮かび上がってしまった。
有力な情報を持ってきた者の多くは、インターネットを情報源として活用していたらしい。なるほど、それはパソコンを回線に接続していない我が家ではできなかったことだ。
とある動物保護団体のホームページから情報を収集した者曰く、人間の匂いがついてしまった雛は親鳥からエサをもらえなくなる事があるらしく、巣に返さなかったのは正解かもしれない、とのこと。
肉親であるはずの親に見向きもされなくなってしまう雛鳥――、考えただけでもなんだか可哀想だ。
それはともかく、その親鳥の代わりとなって雛を育てるための最低限の知識は揃ったわけだが、これから後が少し大変だった。
桜と一緒にツバメについて調べていた日からちょうど一週間後、学校から帰ってくると、何故か家の中に鳥の鳴き声が響いていた。その声につられてダイニングへと向かった僕の目に飛び込んできたのは、テーブルの真ん中に置かれた鳥かご。近づいて中を覗いてみると、予想通りツバメの雛が一羽、元気良く大口を開けて鳴いていた。
「なんで家にこの子がいるんだ?」
たしか巣から落ちたツバメの雛は、C組の教室で飼われることになったはず。それがどうして今目の前に存在しているのか理解できず、側の椅子に座っていた桜に回答を求めずにはいられなかった。
「うーん、それがね、どうもツバメの子を世話するのって思った以上に大変らしくて――」
ツバメの子は一日三度の決められた食事を取るわけではない。少量の餌を一日に何度にも分けて取るため、常に誰か一人が側にいてあげないとだめなのだそうだ。また気温にも実に敏感で、適温である三十度をできるだけ保ち続けなければならない。幸いこの頃は平均気温三十度という季節だったので、その点についてはあまり気にかける必要は無かったけど、涼しい日なんかはカイロなどで暖かくしてやる必要もあるらしい。
「それで、夜はクラスじゅうの子が順番で、雛の面倒を見ることになったと?」
「そういうこと。もっとも、今のこの子の成長具合から考えると、あと半月程度で飛び立てるようになるらしいから、今日がウチで過ごす最初で最後の夜になるだろうけど」
半月ということは、およそ十五日。桜のクラスは三十人弱。なるほど、確かにクラスの子達が順に面倒を見るとなると、もう二度と桜の番になることはない。
「初日に連れて帰ったのが委員長で良かったよ。早いうちからペットショップに話を聞きに行っていた彼女じゃなかったら、そんな細かい世話なんて誰もできなかっただろうし」
「それはそうと、まだこの子に餌やらなくていいの?」
僕が指差す先では、大口を開けた雛が餌を求め続けている。そういえば、僕が帰ってきてから、桜が餌をやっているところは一度も見ていない。
彼女は少し嫌な顔をしつつ、脇に置いてある円形プラスチックケースへと視線を移した。中に何かいるらしく、もぞもぞと動くものの姿が見える。
「なにこれ?」
「雛の餌。お兄ちゃんが言っていた通り、やっぱり虫の幼虫を食べるんだってさ」
ケースの中に入っていた幼虫はミルワーム。ゴミムシダマシ科の甲虫の子供だ。あまり長い時間暖かい空気に晒していると成虫になることがあるので、できれば早く食べさせて、残りはケースごと冷蔵庫の中に戻したいところ。しかし、桜はこういう幼虫の類が苦手なので、なかなか手を出すに出せないでいる。
ちなみにミルワームだけでは栄養不足なので、インコの雛用のパウダーフードと野鳥のすり餌を混ぜたものも与えるのだが、それをとくためのお湯がまだ暖まっていないので、今の段階ではそちらから手を出すことはできない。
「ピンセットとか使えば大丈夫でしょ。何も直に触るわけじゃないんだから」
見かねた僕は桜の脇から餌のケースとピンセットを引き寄せて、代わりに餌をやることにした。といっても手本になるだけで、最後までやるつもりはないけど。
潰さないように優しくつまんだワームを、雛の口元へとそっと持っていく。よほどお腹がすいていたのか、可愛らしい声で鳴いていた雛は、驚くほど素早く餌を取り込んでしまった。そして一匹目を食べ終えるとまた、餌を求めて鳴き始める。その姿があまりにも可愛らしかったからだろうか、本当は一匹目で止めるつもりだったのに、二匹目もついつい僕の手でやってしまった。
「ほら、なにも怖がることなんて無いだろ。桜もやってみなよ」
十分に手本を見せつけた後に、ピンセットを桜へと手渡した。嫌な顔は相変わらずだったが、可愛い雛鳥に先に餌を与えられてしまったことに嫉妬したのだろうか、全く手を伸ばそうとしなかったミルワームを、彼女は初めて掴み上げた。できるだけ早く手元から離したいという思いからか、すぐにそれを雛の方へと持っていく。ツバメの子は実に食欲旺盛で、三匹目となる餌も簡単に平らげてしまった。
「ね。別に大丈夫だったでしょ」
僕が微笑みかけると、桜も「そうだね」と言って小さく微笑んだ。幼虫嫌いを克服したわけではなく、きっと自分の方を向いて餌を求めてくる雛のことが可愛くて、ついつい良い気分になってしまったのだろう。
それからしばらくぎこちない手つきで三十分おきに餌をあげていた桜だったが、次第に慣れてきたらしく、最後はもう本当の親鳥のように馴れた手付きで雛の面倒を見続けていた。それは深夜になっても終わることなく、僕が寝る直前にトイレに向かった時も、ダイニングの電灯は明々と灯されたままだった。
妹は本当に雛鳥のことを気に入ってしまったようだが、世話係は順番交代だとクラスの中で決まっている。次の日雛を学校へと連れて行けば、その夜はまた別の家が世話をすることとなる。そんなわけで、ツバメの子はもう二度とウチには来ないはずだった。だけどいったいどうしてしまったのだろうか、一ヵ月後になってツバメはもう一度我が家に来てしまった。それも鳥かごに入ったまま。
「なんで? もうとっくに飛び立ってしまったんじゃなかったの?」
当然の疑問を妹にぶつける僕。籠の中の鳥はもう大きく成長しており、一ヶ月前にはあった幼さなんて全く感じられない。それなのにどうして未だ外に出してやっていないのか。
「もしかして、人間に懐きすぎて飛び立たなくなってしまった?」
桜のクラスメート達が集めた情報の中に、雛は人間に慣れさせ過ぎない方が良い、というものがあったはず。僕は真っ先にそれを思い浮かべていたのだが、桜はゆっくりと首を振る。
「違うの。いつまでも飛ぶ様子を見せない雛のことが気になって、クラスの子達と一緒に動物病院に連れて行ったの。そしたらお医者さんが、『この子は生まれながらの奇形だ』って」
「奇形?」
「うん、だから飛べないの。それから、この子が巣から落ちたのは事故じゃなく、たぶん自分の子に異常があるのに気付いた親の手によって、故意に落とされたのだろう、って――」
話しているときの桜の顔は本当に悲しそうで、今にも泣き出してしまいそうだった。
雛のことを大切に思う気持ちが強ければ強いほど、医師の言葉は辛いものであったに違いない。桜は本当に雛のことを可愛がっていたし、事実を知ったときのショックは大きかったはず。息子が重度の病気であると知ったときの親の気持ちと、なんら変わりないだろう。
僕は桜に何と言ってやれば良いか分からなかった。だけどこのまま放っておけば、彼女は悲しみの迷宮から出られなくなって、いつまでも彷徨い続けることになる。そんなことを思った。だけどそれは間違っていた。
「でも大丈夫。飛べなくたっても、この子が生きている限り面倒を見続けるって決めたから」
「決めた、って、クラスで?」
「もちろんそうだけど、私はクラスというまとまりに捕らわれず、個人的にこの子を愛でるつもり」
桜は溢れ出す涙をすんでの所で堪え、あの輝かしい笑顔を無理矢理とはいえ作り上げて見せてくれた。どうやら、いつの間にか妹は兄の思う以上に成長していたようだ。
この時の一件については不憫に思わずにはいられなかったが、その反面、強くなった妹を見て、少し嬉しい気持ちにもなってしまった。
その後も桜のクラスはツバメを大切に飼い続けた。もう飛べなくなってしまったという事実を哀れに思っていたからか、成鳥となったツバメに対しても皆優しかった。だけど、一番の愛情を注いでいたのは桜だったと言い切れる。それは僕が彼女の兄であるからそう思っているのではなく、誰が見ても一目瞭然なのである。
いくらツバメに優しくしている人間がクラスじゅうにいるといっても、哀れむ気持ちを全く顔に出さず、満面の笑みで鳥かごの中に語りかけていた人物なんて一人だけ。それが桜だったのである。
どんなに重い病気にかかっていても、親が自分の子を愛する気持ちは変わらない。それと同じだ。最初の頃はさすがにショックを隠しきれなかったようだが、気を持ち直して以来は悲しい気持ちなんて全く表に出さなかった。
「きっとこの子は自分がどれだけ悲しい運命を背負っているのか気づいている。だから私はそれを思い出させないくらい、この子と面と向かう時は明るく話し続けてあげるの」
桜がそう言ったのを聞いたとき、飛べないツバメも幾らか救われたのではないかと思った。
「ところでお兄ちゃん。私、この子に名前付けてあげたの」
「どんな名前?」
「小さい時ピーピー鳴いていたから、ピーちゃん」
「そのまんまだな」
僕が思うままに突っ込むと、彼女は「えへへ」と笑って返してくれる。
このまま全てが平穏のまま過ぎ去ってくれれば、どんなに良かったことだろう。あの悪夢が襲い掛かってきたのは、その日から一月と経たぬ間のことだった。
大きく膨れ上がった赤い炎の前では、僕達のいる松乃中学校の校舎なんて小さなものだった。
今から二年前に起こった兵庫県立松乃中等学校大火災は、大東亜の歴史に残るほどの惨事であっただけあり、当時の様子は目を覆いたくなるほど酷い有様だった。
蜂の巣をつつかれたように教室から飛び出してきた生徒達で、階段も廊下もごった返しており、とても迅速に外へと逃げられるような状態ではなかった。逃げ遅れて階段の手前から全く前に進むことができないでいた僕は、既に三階へと上ってきていた炎を背後に感じて怯えつつも、桜は無事に外へと逃げられたのか心配し続けていた。
大丈夫。彼女は意外にしっかり者だし、きっともうとっくに避難しているに違いない。
そう信じて疑わなかった僕が驚いたのはすぐのこと。ようやく階段の列が動き始めたというころに、突然背後から呼ばれたのである。
「桜のお兄さん! 桜が大変なんです! すぐに来て下さい!」
それは桜のクラスメートの声だった。妹が大変なことになっていると聞いた僕は、嫌な胸騒ぎを感じて、背後から来る生徒達を掻き分けながら、声の主に導かれるように元来た道を戻り始めた。向かう先は一年C組――桜のクラスの教室だ。
下の階から窓の外を伝って上ってきた炎に占拠され、教室内はとても人が入り込めるような状態ではなくなっている。廊下ももう煙に満たされており、長く留まることは非常に危険。それなのにC組の教室の前では何人かの生徒がもみあって団子になっている。目にしみる煙のせいで視界は悪く、何が起こっているのか、いまいち理解し難いが、どうやら燃え盛る教室の中へと飛び込もうとしている女生徒を、他のクラスメート達が必死になって止めているようだ。
「離してっ! ピーちゃんが! ピーちゃんが!」
「駄目だって桜! 今教室の中に入ったら、あなたもただじゃ済まないわ!」
「そうよ! 早くここから離れようよ!」
「嫌だっ! 嫌だっ! 嫌だっ!」
煙の向こうから聞こえる声に僕は驚愕した。桜はまだ逃げていなかった。それどころか、今もまだ教室の中に残されているツバメを助けるために、すぐにでも灼熱の教室の中に身を投じようとしている。
すぐさま団子になっていた女達に駆け寄って、桜を教室の前から引き剥がそうと試みた。だが小柄なはずの桜のこの時の力は信じられないほどに強く、いくら引っ張っても石の様に動かなかった。
「桜! 気持ちは分かる! だけど今は逃げるんだ!」
「嫌だっ! ピーちゃんを置いたままなんて行けないっ!」
「駄目だ! すぐにここから離れるんだ!」
「嫌ったら嫌だっ!」
「桜っ!」
「嫌だっ!」
全く聞く耳を持たない妹は、何を言っても折れてくれそうにない。
妹を助けるため。多少混乱していた僕は、ほとんど無意識で彼女の頬を叩いていた。生まれて初めてのことだった。そのことに驚いたのだろうか、桜を支配していた何かが一瞬だけ解け、すかさず僕は脱力した彼女を抱えて廊下を走り出した。桜はすぐに「下ろして」と騒ぎ出したけど、僕は足を止めることなく走り続けた。
はしご車に乗った消防隊の方が僕達の前に現れたのは幸運だった。おかげで僕も妹も、逃げ遅れていた桜のクラスメートも一命を取り留めることができた。ただし、飛べないツバメ――ピーちゃんが助かることはなかった。あまりに凄まじかった炎に飲み込まれた成鳥は跡形も無くなり、後日真っ黒になって変形した鳥籠だけが現場から見つかったのだった。そのときのショックのせいなのだろうか、救出された直後から、桜は意志や感情といったものを失ってしまい、虚ろな目が何を見ているのかも、全く分からなくなってしまった。そして、頭髪からは色素が抜け落ちて、数日後には真っ白に染まってしまった。
昔は兄妹を間違われるほど似ていた僕の分身は、全く異なった姿になってしまった。そしてそれ以来、僕が妹と手を繋ごうとしても、意志を無くした彼女が手を握り返してくれたことは一度も無い。
事故から一ヵ月後。松乃中大火災の生存者達は、同市内の梅林中等学校の三年六組に『被災者特別クラス』として集められ、皮肉にも、火災に巻き込まれたおかげで初めて、僕達兄妹は同じクラスになれたのだった。だけど、ずっと隣にいるはずの妹はどこか遠くの世界に行ってしまったように思え、寂しさが消えることは決して無かった。
現在、白石幹久(男子八番)は、とある無人島の森林奥地にて佇んでいる。どうしてそんなところにいるのかと言うと、彼等のクラス、梅林中三年六組がプログラムに選ばれてしまったから。
二年前に地獄のような経験をした自分達が、まさかさらにプログラムにまで選ばれてしまうなんて、全く思いもしなかった。宝くじの一等を当てるよりも低いと言われる確率の中、見事参加クラスに当選してしまったと聞いてしまえば、クラス中が何かに呪われているのではないかと疑わずにはいられない。それほどありえない話だった。
最後の一人になるまで戦い続けなければならないというルールの下では、体力に自身があるわけでなく、身体も小さい幹久みたいな人間には、生きて帰れる可能性なんてほとんど無いかもしれない。当然死の恐怖に怯えなければならなくなる。だけど彼は自分のことなんかよりも、妹のことが気になって仕方が無かった。
双子の妹である白石桜(女子十番)は、二年前の松乃中大火災以来、意志や感情などといったものを失っており、たった一人では何もできないような状態にある。そんな彼女にプログラムを生き抜く術なんてあるはずが無く、兄である幹久は彼女のことを心配しないわけにはいかなかった。
出発前、自分自身で動き出そうとしない妹を、立ち並ぶロッカーの所まで連れて行ったのは幹久。四十六あるうちの一つは爆弾入りのハズレという並びから、彼女が入るロッカーを選択したのも彼だ。
全く知らぬ無人島の中で離れ離れになってしまった兄妹が、無事に再会を果たせるかどうかなんて分からない。もう二度と会えないという可能性も大きい。だから幹久は、閉まるロッカーの扉の向こうに消える妹の姿を目に焼き付けつつ、別れを惜しみながら自分自身も別のロッカーへと入ったのだった。
幸いなことに、幹久が入ったロッカーはアタリだったらしく、ロッカーの中に仕込まれていたスピーカーから田中の声が聞こえた後、自動的に開錠された扉はあっさりと開いた。
幹久の出発地点であった竹林のど真ん中には頭上を遮ってくれるようなものは何も無く、一歩外に出たとたん激しく降る雨に身を撃たれてしまった。しかし彼はそんなことなど全く気にもしないで、とにかく妹を探すことのみに専念した。
手がかり一つ無い状態で、たった一人の人間を見つけるということがどれだけ難しいことなのかは分かっていたが、尻込みしていては事態が好転することなんて絶対にない。とにかくひたすら島の中を歩き回って、一際目立つ白髪の少女を求めて彷徨った。
何度か人の姿を見かけたこともあったが、それが妹じゃないと分かると隠れてやり過ごした。妹と会う前は、極力他人との接触を避けようと決めていたから。
どれくらい経ってからだろうか。森林の中を歩いていた幹久は、奇妙なものを目にした。プログラム開始からはかなりの時間が経過しているというのに、未だ扉が閉まったままのロッカー。息を潜めてゆっくり近づくと、内部からは人の気配が感じられる。
胸騒ぎを覚え、恐る恐る扉を開いてみると、驚いたことに、そこには妹の桜がいた。意志の無い彼女は扉が開錠されている今になっても動き出そうとせず、箱に入った人形の如く、何も映らない虚ろな目をしたまま、ただそこに存在し続けていたのである。
とにかく無事に妹との再開を果たすことができた幹久は、すぐに彼女をロッカーから引っ張り出して、自分達二人が身を潜められるような場所を探して移動した。厚い茂みがそこかしこに生茂っているので、人目につきにくいであろう隠れ場所はすぐに見つかり、それからずっとそこに兄妹二人は留まり続けていたのだった。
「じっとしてて」
妹の頭から水滴が滴っているのに気がついた幹久は、ハンカチを取り出して濡れた髪を丁寧に拭いてあげる。手に触れる毛髪はどれも真っ白で、とても自分の分身のものであるとは思えない。
「お腹すいただろ? ほら、これ食べて」
支給品である固形タイプ栄養調整食品を差し出されると、桜はコクリと頷いて、ゆっくりと食べ始める。ただそれだけだ。言われたことには素直に応じるが、物事を考えられない彼女が自分の意志で話し出すことは無く、当然兄の奉仕に対して礼を言うことなんて無い。
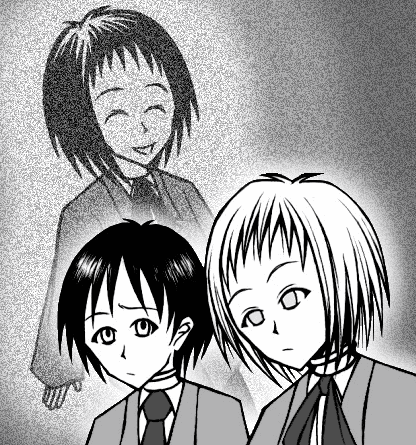
彼女の笑みが見られなくなって久しい今、時々自分は兄として認識されているのかどうか不安にすら思えるときがある。そういう時は決まって、昔桜が大切にしていたツバメの雛が頭に思い浮かぶ。
大切な肉親に見向きもされなくなってしまった哀れな存在――。まさに今の自分と同じだ。だけど僕はあのツバメと同じ運命を辿りたくはない。桜が意志感情を取り戻し、僕が彼女の兄に戻れる日が来るのを信じて生き永らえる。それを邪魔するような何かが前に現れるとしても、僕は桜のためだったらなんだってする。クラスメートの命を奪うなんて事は考えられないけど、妹のために僕は守る戦いを続けてやるんだ。
強く決心したその時、背後に人の気配を感じたので振り向いた。
「幹久くんじゃないか。それに桜さん」
誰かが茂みを掻き分けながらこちらに近づいてくる。聞こえた声や体格を記憶と照合させたところ、すぐに相手の正体は湯川利久であると分かった。
「湯川くん」
記憶の中に存在する湯川利久の人物像は極めて平和的なイメージしか持っていない。そのため、幹久は相手の正体を知るや否や、張り詰めていた警戒心をついつい解いてしまった。
しかしこの気の緩みが後々の後悔を招くことになるなんて、この時の彼は全く考えてもいなかった。
【残り 十九人】 |
