何とか傾斜面を上りきった千秋は、ダムの手前で立ち止まっていた圭吾に追いつくと、歩を止めてようやく一息つくことができた。
いくら真緒が小柄とはいえ、人間一人を背負っての山歩きは過酷であり、疲労の激しい両足はもうガクガクだ。呼吸もかなり荒くなっている。
出発してからどのくらいの時間が経っているのかは分からないけど、歩いた距離はかなりのものだ。ポケットから地図を取り出して確認したところ、ここは島の中心から少し南にずれた位置に広がる黒部(こくぶ)ダムに、どうやら間違いないようだ。自分達が今ダムのどの辺りにいるのか正確には分からないけど、いずれにしろ廃ビルから五百メートルほど進んだことになる。
それはともかく、あれだけ自分勝手に先へ先へと歩いていた圭吾が立ち止まったということは、彼らの本拠地に到着したということだろうか。
千秋は辺りを見回す。
土や岩で形作られた堤の表面にコンクリートを塗り固めた、いわゆる表面遮水型ロックフィルダムは、全長およそ五百メートル。ちょうど千秋たちが歩いてきた距離に相当する。孤島のダムにしては、なかなか立派な大きさだ。
千秋たちの立ち位置から少し離れたところに、水面近くまで伸びるスロープがあり、その先に一艘のボートが停まっている。後部にエンジンを積んだそれはたぶん、誰かがルアーフィッシングに興じる際にでも用いられるのだろう。こういう山中の貯水池なんかには、たいていブラックバスやらブルーギルなんかが生息しており、技術と知識さえあればかなりの数を釣り上げることも可能なはず。今のような雨で水が濁っている日なんかは尚更。泳ぐ魚を肉眼で確認できるほど水が澄んでいる日のほうが釣りやすいなどと、素人はよく勘違いしがちだが、実は湖面が濁っていて水中からこちらの姿が見えないくらいの方が、魚はよく針に食いついてくれる。多少天気が悪い方が好都合だったりするのだ。
だけど天気が悪いにも程がある。止むことなき雨の勢いは激しくなるばかりで、無数の波紋が広がる湖面に、周りの斜面から泥水がさらに流れ込んできている。水位は上がっていく一方だ。
底の見えないカフェオレ色の濁り水にある種の恐怖を覚え、千秋は目線を水面から逸らした。
ダム池を取り囲むのは、山の斜面と無数の木々ばかり。圭吾たちの本拠地と言うからには、雨風をしのげる屋内だろうと勝手に想像していたが、見渡したところ周囲にそれらしき建物は見られない。
何か見落としているのだろうかと思い、もう一度目を凝らして辺りの様子を窺った。すると、濃霧のせいで今まで気がつかなかったが、遥か遠くの対岸にぼんやりと水門の姿が見えている。特別巨大なものではないが、ダム池に相応のなかなかに立派な造りである。
新たに見つけたのは結局それだけだった。
いったいどういうことかと思い、ちらりと横目で圭吾を見た。
彼はだまってダム池を見つめていた。時折視線をずらして陸の方を見たり、対岸の水門を気にしたりもしているようだったが、彼が何を考えているのか全く想像もできない。
「ねえ、ちょっと――」
やきもきしながら千秋が近寄ろうとしたところ、圭吾は突然身体の向きを返して歩き始めた。それもどういうわけか、樹林の奥へと戻るような方角に。
もう訳が分からない。
「これはどういうこと? 目的地に着いたんじゃなかったの?」
真緒を背負ったまま急いで彼の後を追い、前方へと回り込んだ。
「あんなところがアジトなわけないだろう。目的地は別の場所だ。もうしばらく歩かなければならない」
眉一つ動かさない圭吾にあっさりと抜き返され、千秋はぽかんと口を半開きにしてしまう。
正直言って、身体はもうバテバテで、できればもうあまり歩きたくはない。彼だってそれはもう知っているはずに、どうして真っ直ぐ目的地に向かわず、わざわざあんな所に寄り道したのだろうか。気の向くままにフラフラ歩いているうちに、ダムに出てしまっただけという下らぬ理由だったなら、先ほど真緒の精神に負担をかけぬよう注意されたばかりだけど、さすがにもう黙ってはいられない。
足の動きを早めて、再び圭吾の前に回り込もうとした。その刹那、彼はいきなり腰のベルトに固定していた鞘から刀を抜き、左前方へと刃を突き出したではないか。見事な抜き打ち――とはちょっと違うけど、とにかくその動作は素早くて迫力があった。驚きのあまり千秋がその場で硬直してしまったほど。
一瞬さっきみたいに自分達に刃が向けられるのかと思ったが、どうやら今回は違うらしい。彼が突き出した刀の切っ先は、側の茂みの中へと潜り込んでいる。
「手を挙げたままゆっくり立て。少しでも余計な動きを見せたらこのまま刺す」
圭吾は突然茂みの中へと向かって話し出した。すると刀が潜り込んでいる辺りの茂みがガサガサと音をたてて揺れ、何者かがゆっくりと立ち上がったではないか。警告に従って両手を挙げ、上半身を茂みから出したのは男だった。
「安藤くん!」
千秋の背中の上で真緒が驚いて声をあげた。
たしかに、薄暗くて人相が少々分かりづらいが、広めの額が目立つ安藤幸平(男子一番)を見間違えようは無かった。
彼はずっとここに一人で隠れていたのだろうか。そして殺し合いへの不安のあまり震え続けていたのだろうか。
濡れ鼠になっている幸平が、首に刀の先を当てられて怯えた表情になるのを見て思った。
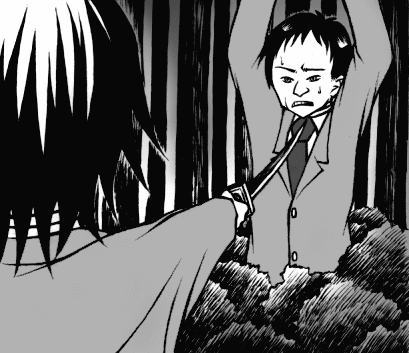
「油断するな。こいつ今、俺らを殺そうとしていた」
「えっ?」
圭吾の言葉に千秋が驚くと同時に、幸平の顔が真っ青になった。
「ちょ、ちょっと待ってくれよ! 俺は知らねぇぞ、そんなこと!」
「今さらとぼけてもムダだ。お前の手に握られているそれは何だ?」
「これは――」
幸平は挙げたままの手に目を向け、言葉に詰まってしまう。
千秋はこの時になってようやく、幸平の右手に銃が握られていることに気がついた。大口径の自動拳銃だ。
「俺達が近づいたのを見計らって、茂みの中からそいつで一気に片付けるつもりだったんだろう」
「馬鹿言うなよ! 俺はただ、誰かが近づいてきたみたいだったから、隠れてやりすごそうとしただけだ」
玉になった汗が幸平の額からだらだらと流れ出している。いや、もしくはただの雨の雫かもしれないが、そんなことは千秋たちの知ったことではない。
「引き金に指がかかったままの状態で言い訳してもムダだ。それに、目を見ればお前が嘘を言っているとすぐに分かる」
圭吾の言うとおり、幸平の目は水槽の中の金魚のように泳ぎ回っている。これでは千秋にすら嘘を言っていると見抜かれてしまう。
「念のために言っておくが、この場での抵抗は全く無駄だからな。お前がその手を下ろして銃を構えるよりも、俺がお前の首を貫く方が圧倒的に早い」
ゴクリと幸平の喉が鳴った。そりゃあ、首に刀を当てられたままあんなことを言われれば、誰だって息を呑んでしまう。
「抵抗は無駄だと分かってもらったところで、一つ取引しよう」
「取引だと?」
「ああ。今回は命だけは助けてやるが、その代わりにその銃をこの場に置いていってもらう」
「何言ってるんだ! そんなことできるわけ無いだろう!」
幸平が少し声を荒げた途端、彼の首から一本の赤い線が垂れた。圭吾が握っていた刀の先が、皮膚を突き破って首を数ミリ傷つけたのだった。
「お前は馬鹿か。プログラムのルールに乗っ取って今すぐにでも殺せるというのに、あろうことか見逃してやると言ってるんだ。その銃をここに置いて、さっさと立ち去るのが懸命だと思うが」
「そんなこと言って、俺が背中を見せたら殺すつもりなんだろう」
先の脅しが効いたのか、幸平の声は随分と大人しくなっている。
「殺すつもりなら、そんな悠長なことしないで、今この瞬間にやってるさ」
「ちくしょう!」
ようやく諦めたらしく、幸平は両手を挙げたままの状態で拳銃を足元に落とし、「これでいいんだろ!」とこちらを睨みつけてきた。
「それでいい」
言いながら、圭吾は全力を込めた足で幸平の腹を思いっきり蹴る。すると幸平はうめき声を上げながら後方へと吹っ飛び、茂みの中へと消えた。
「さっさとここから立ち去るんだ。殺されたくなければな」
足元に落ちていた銃を拾い上げて森の奥へと向ける圭吾。するとその先で幸平がよろよろと立ち上がり、「覚えてやがれ」と捨て台詞を吐きながら、どこかに走って行ってしまった。
ほんの数分間の出来事。だけど千秋にはそれが物凄く長い時間であったように感じられた。誰もいないと思っていた場所に人が隠れていて、自分達が狙われるなど、プログラムの最中においてはごく当然のことであるが、圭吾の行動ばかりを気にするあまり、すっかりと念頭から除外してしまっていた。これもまた疲れに影響されているのかもしれない。
「ありがとう」
一応圭吾に礼を言っておいた。あれだけの至近距離だ。彼が幸平に気付かなければ、幼馴染もろとも殺されていたに違いない。
「気にするな。あいつを追い払ったのは俺のためでもあるからな。それに、銃も一丁手に入れておきたかった」
そう言えば、幸平が置いていった銃は圭吾が拾い上げたのだった。
「デザートイーグルだ。紅月だけでも充分に戦えるが、やはり接近戦でなければ勝ち目は薄いしな」
「紅月?」
「支給されたこの刀のことだ。代々持ち主の心を奪い、何度もつじ斬り事件を起こした妖刀だと、付属の説明書に書いてあったな」
言いながら腰の鞘へと収め、茂みの中から幸平のデイパックを引っ張り出す。
「銃の弾以外は捨てても構わないから、こいつもお前が持て」
千秋の肩にデイパックを引っ掛け、相変わらずほとんど手ぶらなまま先に歩き出してしまう圭吾。だけど、不思議ともう怒りは込み上げてこなかった。
ようやく分かったのだった。どうして彼は人や荷物を千秋に任せたまま先に行ってしまうのか。
たぶん、向かう先に危険があれば、それにいち早く気付くことができるからだ。そしてもし危険を察知したら、幸平のときのように、道を切り開く役目を自ら買って出る。だけどその時に重い荷物やらを背負っていては素早く対応できない。千秋が真緒を任されたのは、きっとそういう理由からだ。無愛想だったのも、周りに気を配って神経を研ぎ澄ましていたため。
それから、彼は何らかの理由があって、本当はもっと急いで本拠地に戻りたいと思っているのではないだろうか。走りたいくらいに。だけど千秋たちがいることによって、そうすることもできない。早く帰りたいが、千秋達を置いて行くわけにもいかないという、そんな微妙な心理が、仲間を待たずに先へ先へと進んでいってしまうという状態にさせていたのかもしれない。
謎一つ、自己解決とはいえ消化。だけどその代わりに、目的地に向かう途中でダムに立ち寄った理由は分からずじまい。
結局、千秋の中で比田圭吾という人物は謎のままだった。
【残り 十九人】 |
