「なによこれ! ど、どういうことよ!」
智香自身も音の発生源が自分の首元だということに気づいたらしく、両手で正体不明の首輪を引っ張る。しかしそれくらいのことで外れはしない。
事態を飲み込めず、ただ慌てふためく彼女を見て、田中はケタケタと笑い始める。
「いやっはっは、先生またうっかりしてましたよぉ。そういえば皆さんに装着されている首輪についての説明をしてなかったですねぇ。その首輪は『ラ・サール五号』と言いましてぇ、皆さんに私達の言うことを聞かせるための重要なアイテムなんでぇす。
万が一私達の意に背くようなウンコちゃんが現れた場合、こちらから電波を送って、首輪に内蔵されている爆弾を作動させることになっていまぁす。だから、悪いウンコの相沢さんの命はあとたった数秒しかありませぇん」
智香の顔から血の気が急激に消え失せた。
「ちょっ、ちょっと何言ってるのあんた! こんなの卑怯だわ! 止めて! 止めなさいよ!」
「だめでぇす。一度発動させてしまった首輪はもう止めることができませんので、相沢さんには潔く死んでいただきまぁす。さあ、汚いウンコは教室の隅ででも死んでてくださぁい」
田中は走り寄ってきた智香を問答無用で突き飛ばした。突き飛ばされた智香は背中から床に倒れる。
「智香ぁ!」
真緒が叫ぶ。すると智香は上体だけを起き上がらせて真緒と千秋の方を見た。
「真緒! 千秋! 助けて!」
彼女の口から悲痛な声が飛び出す。しかし首輪はあざ笑うかのようにカウントを進めた。それから電子音が数回鳴った時だった。ボンッと爆音を放ちながら智香の首輪は爆発した。
「智香!」
今度は千秋が叫んだ。しかし相手からの返答はない。首元から血を撒き散らしながら上体を倒した智香は、もうぴくりとも動かなかった。
胴体と頭部が首の骨で繋がっている以外、首周辺の肉全てが吹き飛んでしまった智香の死は一目瞭然。床に鮮血の水溜りが広がっていく様を見て、千秋は身震いした。
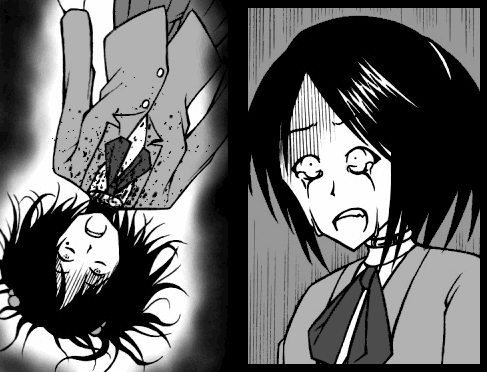
父に続き、大親友の智香までもが、目の前の男、田中によって殺された。
押し殺してきた怒りという感情が急激に膨らんでいく。もはや千秋は自分の感情をコントロールできなくなっていた。そして気がついたときには、立ち上がり、自らの机を蹴り倒していた。
教室内に机が倒れる激しい音が鳴り響くと、愉快に笑っていた田中の顔が急に引き締まった。
「おやぁ春日さん、どうしたのかなぁ?」
もはやお馴染みとなってしまった不気味な口調で田中が問う。しかし怒りの頂点に達していた千秋は怯えもしなかった。
「……よくも、よくも智香を!」
田中へと向かって走り出す千秋。このまま何者の遮りもなければ、田中に飛び掛っていたに違いない。そして智香と同様に首輪を作動させられるか、あるいは相手の手から放たれる凶弾の餌食となっていたであろう。
千秋は冷静なる強者によって救われた。
「止めるんだ春日!」
田中に食い付く寸前だった千秋の腕を、何者かが掴んで止めた。
「放して! 腕を放してよ!」
千秋は自分を捕らえた腕を振り払おうとするが、圧倒的な腕力を誇る相手には全く通用しなかった。それもそのはず、千秋の腕を掴んだ人物とは、三年六組内でも最強レベルの力を持つ男子生徒、磐田猛(男子二番)だったのだから。
「気持ちは分かるが、今は耐えろ! じゃないとお前も相沢みたいに死ぬことになるぞ!」
「いやよ! あたしは今、この男に復讐する! だから腕を放して!」
必死に説得しようとする猛の声も、もはや千秋にとっては雑音でしかなかった。五感全てが捕らえていたのはただ一つ、目の前でほくそ笑みながら胸ポケットのリモコンへと手を伸ばしている男の姿のみである。
千秋は再び猛の手を振り払おうとする。しかしやはり放してはくれない。
サッカーとは一見すると足だけを使っているように思えるスポーツだが、実際は上体のバネも重要な役割を果たしている。そのため、サッカー部キャプテンである猛の腕力も、千秋の細腕なんかとは比べ物にならないほどに発達していたのだ。
「お前、分かってるのか! この男にこれ以上逆らったら、本当にお前の命が危ないんだぞ!」
「そんなのもうどうでもいいよ! とにかくその腕を放して!」
田中に復讐することしか頭にない千秋と、正義感に満ち溢れた猛、どちらもお互いに一歩も譲らない。そんな硬直状態の中、田中一人だけが不気味に微笑み、ポケットからリモコンを取り出す。
「千秋! もうやめてよ!」
これまで猛の声を聞こうともしなかった千秋の耳を、真緒の叫びが貫いた。するとこれまで興奮した牛のように止まることを知らなかった千秋が、急に声の主のほうを振り向いた。
「真緒……」
千秋は急に力を失った。目の中に飛び込んできたのは泣きじゃくる幼馴染。弱りきった精神に鞭を打って、必死に千秋に訴えかけようとする真緒の姿があった。
「もう……もう無茶なことをしないで……。千秋の気持ちは分かるけど……私、千秋にまで死なれちゃったらもう……。だから……だから、お願いだからもう誰も死なないでよぅ……」
ブレザーの袖で涙を拭きながら、真緒は声を必死になって押し出していた。
感情に任せて動いてしまっていた千秋は、今ほどに自分を恥じたことはなかった。
忘れていた。自分にはもう一人、羽村真緒という大切な人が存在していたのだ。もしこのまま千秋が生命に終わりを迎えてしまったならば、真緒はたった一人で地獄の中に取り残されてしまう。だから、自分はまだ死んではならない。この弱々しい幼馴染の側にいてやるために、今はまだ耐えなければならない。
「……分かったよ」
千秋は田中から視線を外し、肩を下ろした。
急に静まった千秋を見て、もう大丈夫だと判断したのか、猛は強く握り締めていた千秋の腕を解放した。
ゆっくりと席に戻っていく千秋と猛の後ろ姿を眺めつつ、田中は残念そうにリモコンを胸ポケットに戻した。
「さて、色々あって時間がかなり削られてしまったのでぇ、そろそろこのプログラムのルールを簡単に説明させていただきまぁす」
田中は急に生徒達に背を向け、白チョークで黒板になにやら図形らしきものを描き始めた。
「皆さんが今いる場所はこんな形をした島でぇす。今回はこの『鬼鳴島』と呼ばれる島の中で皆さんに殺し合いを繰り広げてもらいまぁす。住人の方達には事前に島から避難してもらってますのでぇ、どこへ動き回ってもらって結構でぇす。
さて、この島は南北にAからJ、東西に一から十というように、合計百のエリアに分かれておりましてぇ、殺し合いを円滑に進めるために、一時間ごとにランダムで一つのエリアを立ち入り禁止としていきまぁす。もしもこの通称“禁止エリア”と呼ばれる場所に立ち入ってしまったら、皆さんの首に巻きついてるラ・サール五号が自動的に爆発しちゃいますのでぇ、その一点には気をつけて行動してくださいねぇ」
皆が一斉に自身の首元へと手を伸ばす。先ほど智香の首輪が爆発するのを目の当たりにした直後なので、その話の緊迫感がリアルに伝わってきたのだ。
田中の説明はまだまだ続いた。
皆の首に取り付けられたラ・サール五号は、対ショック、完全防水となっていおり、そのうえ無理やり外そうとしたら爆発するように作られているため、取り外すことも壊すこともできないということ。
会場から外に出たときも、禁止エリア進入のときと同じく首輪が爆発するので、脱出は不可能だということ。
万が一のときに備えて、島の沖合いでは武装した数隻の監視船が常に目を光らせているということ。
そのどれもが、生徒達の微かな希望を木っ端微塵に砕いていく。
「説明はこんなもので十分でしょう。それではぁ、そろそろゲームを開始したいと思いますのでぇ、皆さん席を立ってください」
もはや抵抗できる者など誰一人おらず、全員が田中の指示に従ってその場で立ち上がった。
「ではこれから校庭へと移動しますのでぇ、皆さん速やかに私の後についてきてくださぁい」
そう言うと、田中は先にそそくさと教室の前の扉から廊下へと出て行った。
生徒達は一瞬迷っていたが、意を決した一人が出て行ったのをきっかけに、それに続いて次々と教室内から姿を消していった。
気がつくと、残されたのは千秋と真緒だけとなっていた。
「……行こうか、真緒」
固まってしまっている幼馴染の手を握り、千秋は彼女の手を引きつつ出入り口へと向かっていった。
廊下へと出る前に、一度教室内を振り返った。そこには変わり果てた智香の姿があった。もちろん、千秋の視線に気づいてこちらを振り向いてくれはしなかった。
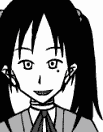 相沢智香(女子一番)―――『死亡』 相沢智香(女子一番)―――『死亡』
【残り 四十四人】
|
