驚きの表情のまま口を開ける光輝。おそらく「なんで?」とか「どうして?」とか、そういった類の言葉を出したかったのだろうけど、包丁の刃によって、いくつかの臓器に壊滅的なダメージを受けてしまった彼の口から出てきたのは、ひゅうひゅう、と、まるで隙間風が漏れているような、そんな微かな音だけだった。
もはや足腰には立っていられるだけの力も残されていないのか、光輝はその場に膝をつき、崩れるようにして、どさり、と後方へと倒れ込んでしまった。その後、最後の力を振り絞っているのか、眼球のみをぐぐっと動かし、怯えて震えている由美子を悲しそうな目で見ていたが、それも長くは続かず、瞳の中に映し出された少女の姿も、数秒後には消え失せていた。
光輝が動かなくなったのを見た由美子は、冗談であるのを信じて、彼の身体に、そっと触れてみた。しかし、光輝からの反応は無く、名を呼んでみたり、身体を揺らしてみたりもしたが、痙攣の一つすら見せない。そうなって由美子は、生ある者など、そこにはもはや存在していないのだと悟った。その途端、これまで感じていた“死が迫る恐ろしさ”とはまた違う、別種の恐怖感が頭の中を侵食し始めた。
耐えがたいほどの恐怖と後悔に襲われた由美子は、無意識のうちに自らの頭を抱えていた。
違う違う違う! こんなつもりじゃ……こんなつもりじゃなかった! 私はただ、亜美を殺した犯人から、自分の身を守ろうとしただけなのに!
そう、彼女はなにも、仲間を刺そうなどとは露ほどにも思っていなかった。ただ、正体不明の殺人者の存在に怯えていたとき、突然すぐそばの扉が開いたので、驚きから自己防衛本能が発動したのか、刃物を持つ手が無意識のうちに動き出してしまった。そして気が付けば、由美子が握る肉切り包丁の刃が、光輝の胸元へと深く潜り込んでいた。ただそれだけのことだった。
膝を折り曲げた状態で、上半身を仰向けに倒し、胸に刃物を付き立てられたままの光輝の死に様は、とても滑稽だった。これがコメディ映画か何かのワンシーンだったなら、関西弁の面白人間が奇怪な体勢のままぶっ倒れたとして、館内には笑いと拍手が溢れていたことだろう。だがもちろんのこと、これは映画でもドラマでも、由美子が好きだったギャグマンガでもなく、あくまでも現実の話。自分のしたことに後悔しながら、光輝の遺体を見下ろしたところで、絶望感は湧き上がっても、笑う気など起こるはずが無い。それこそ、自分が完全に狂ってしまわない限りは。いや、錯乱状態に陥り、何も考えないまま光輝を刺し殺してしまった点から考えると、由美子は既にどこか狂い始めていたのかもしれない。
自分が殺した少年の遺体を目の前にした恐ろしさのあまりか、由美子の身体は一度、ぶるっ、と大きく震えた。
このままでは、現場を誰かに見られてしまう。もしも私が杉田君を殺したことが明らかとなったなら、皆は私に対してどのような感情を抱くだろうか。これからも私を仲間だと思ってくれるだろうか。考えるまでも無い。仲間の一人を無残に殺してしまった私のことを、皆は許してくれないだろう。そして、私をこの建物内から追い出すなり、どこかに縛り付けるなりするに違いない。いや、それだけならまだいい。もしかしたら、危険分子は排除すべきだと判断され、信頼どころか生命までもを断ち切られてしまう恐れもある。当然ながら、それだけは絶対に嫌だ。
この危機的状況を乗り越えるための手段を、由美子は必死に模索した。その結果、由美子の頭は、とある考えを弾き出した。それは、精神状態が正常だったなら、怖がりな由美子には到底思い付くはずのない考えだった。
犯行がばれてしまったら、由美子は仲間殺しの汚名を着せられてしまう。しかし逆に、犯行さえばれなければ、何も心配することは無いとも考えられる。幸いにも、光輝の身体からは肉切り包丁は引き抜いてはいないので、凶器を抜いた際に噴き出すであろう返り血を、まだ浴びてはいない。問題は死体だけだ。死体さえ誰にも見つかりさえしなければ、一見して由美子が殺人者だと気づく者など、誰一人としていないはず。
そこまで考えれば話は早かった。
隠せばいいんだ、杉田くんの死体を。
由美子はとっさに、堂々と廊下に転がったままになっていた光輝の身体を、自分が隠れていた小部屋へと引きずり込んだ。決して小柄ではない光輝の身体は、由美子のような非力な少女にとっては、かなり重く感じられるはずなのだろうが、これぞ火事場の馬鹿力とでもいうのか、不思議と苦ともせずに引き入れることが出来た。
とりあえず、これで廊下や階段を通った人間に、すぐ遺体が見つかってしまうという心配は無い。だが、油断はまだ禁物。いつ誰がこの空間へと踏み込むとも限らないので、完璧に隠す必要がある。
何か良い方法はないかと部屋内を見回すと、まさにこの時を待っていたと言わんばかりに、白い金属棚の上に、律儀に折り畳まれたブルーのビニールシートが乗っかっているのが確認できた。
これだ。
遠足の昼食時の要領で、狭い床の上いっぱいに、ブルーシートを広げる。次に、脇に放置したままだった光輝の遺体を、丸太を転がすようにしてシートに乗せた。
あとは、遺体を包んで棚の奥に押し込めるだけ。そうすればもう、誰の目にも止まる事は無いはず。
一度小さく息を吸って、シートの端を持ってプレゼントの箱を包み込むかのように、遺体にかぶせようとした。が、由美子は少し考えた後、作業の手を止めた。もしものときのことを考え、遺体から凶器を引き抜き、自分の手元に置いておくべきだろうか、と考えたのだった。
亜美を殺した犯人の存在もあることだし、何より、プログラム内で丸腰でいることは、大変危険である。
自分の死を絶対的に恐れていた由美子は、すぐさま決断した。
壁と棚の間に挟まっていた、スーパーかなにかのくたびれたビニール袋を手にかぶせ、横を向いて寝かした光輝の背後に回り込み、胸部に突き立てられたままだった包丁の柄を強く握って、ゆっくりと引き抜く。すると、傷口と包丁の間に生じた隙間から、真紅の血液が噴き出し、床を覆うブルーのシートの表面に、鮮やかな斑点模様が描かれた。だが、手に被せていたビニール袋のおかげで、由美子自身には返り血は付着していない。まさに計算どおりだった。
いつもの気弱な由美子なら、こんな恐ろしいことなど出来るはずが無かったが、このときはもう気がおかしくなっていたのか、自分でも不気味に思うほど落ち着き払っていた。
さて、血が付着した肉切り包丁は、堂々と持ち歩くわけにはいかないので、あとでしっかりと刃の汚れを拭き取る必要がある。だがそれは後回し。まずはこの“邪魔な荷物”を、誰の目にも届かぬように隠す。それが先決だ。
光輝の遺体を、ビニールシートで今度こそ包み込んだ由美子は、それを持ち上げて、金属棚の奥へと押し込もうとした。だが、男一人の身体はやはり重く、引きずるのとは訳が違い、一番下の段にまで持ち上げることですら、か弱い女一人だけでは、相当に苦労した。それだけに、気力を振り絞って、シートに包まれた死体を棚の最下段に乗せる事ができたときは、本当にほっとした。
さあ、あとはこの遺体を奥に押し込めるだけ。
運動会の大玉転がしでもするかのように、光輝の身体に両掌をあて、腕に力を入れようとした瞬間だった。突如出入り口の扉が、ばん、と音を立てながら勢いよく開いたので、由美子は驚きのあまり心臓が飛び出すような思いをした。
「由美子、ここにいたの? 大丈夫?」
薄暗い空間の中にいる由美子からは、逆光のせいで入り口に立つ人物の姿は鮮明には見えなかったが、声は間違いなく春日千秋のものだった。あっけらかんとした声を装っていたが、あれで彼女も亜美の死に相当参ってしまっているに違いない。春日千秋とはそういう人間だ。
光を背に受けている千秋の姿は、やはりよく見えはしなかったが、どうやら部屋の中をぐるりと見回しているようだった。そして、勢い良く開いた扉からの風をうけ、空気中に舞い上がった埃に喉をやられたのか、何度か派手に咳き込んでいた。
「ここ、なんか埃っぽいね。鉄がさびた匂いもするし。ところで、それなに?」
由美子は再び、心臓の高鳴りを感じた。棚の奥に隠そうとしていたブルーシート包みの遺体を、千秋が不思議そうに指差していたからだ。
計算外の大事態を前にして、由美子は上手い言い逃れ方を見出すことはできず、
「な、なんでもないよ。気にしなくても大丈夫だよ」
と、苦し紛れの返答をすることしかできなかった。
千秋は、ふーん、と鼻を鳴らしながら、少し不思議そうにしていたが、目の前の光景をさほど重要とは思わなかったらしく、
「まあいいや。それよりも、由美子も一人でいたら危ないし、早くこんなところから出て、皆と一緒にいたほうがいいよ」
と言って、それからは痛いところを追及してはこなかった。
「分かった。すぐ行くから、先に戻ってて」
由美子が言うと、千秋は素直に「分かった。先行ってるね」と返し、早々に立ち去ってくれた。だが、由美子の緊張は、そこで解けはしなかった。いや、むしろシートに包まれた遺体を棚の奥に押し込もうとしていた現場を見られたことは、これ以上ないほどの痛手でしかなかった。
もしも、後にこの遺体が発見されてしまったら、彼女の証言によって、私が遺体を棚の奥に押し込もうとしていたことは、皆に知られてしまうだろう。そして当然、杉田光輝殺しの疑いもかかるはずだ。そうなれば、先にも考えていた通り、私の生存は危うくなる。どうにかして、そうなることだけは避けなければならない。
自分の生死に関する思想以外は全て頭の中から取り除き、事態を乗り切るための方法のみを、必死になって考える由美子の姿は、もはや以前の彼女のものではない。挙動不審に眼球を震わせ、笑っているのか怯えているのかも分からないような形で口を半開きにしている姿は、まるで精神異常者を思わせるほどに変貌していた。
そして、彼女はある考えに行き着いた。
傍らに置いたままだった、血濡れの肉切り包丁を拾い上げて、両手でぐっと握り締める。
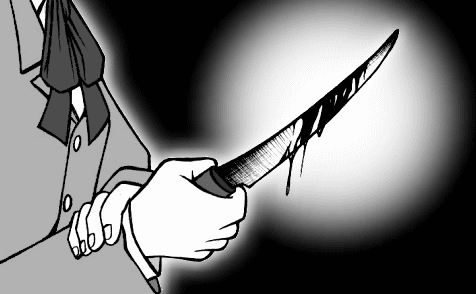
不幸中の幸いか、千秋はブルーシートの中身の正体には気づいていないらしく、床に転がっていた、血にまみれた包丁の姿も目に入っていなかったらしい。さらには、部屋内に漂っていた血の香りも、鉄の錆びた匂いだと勘違いしてくれているようだ。
そう、まだ私の犯行は、誰の目にも明らかにはなっていない。ならば、光輝の遺体が誰かに見つかってしまうよりも前に、重大な手がかりを握る情報源さえ潰してしまえば、私に疑いがかかることは無くなるはず。そのために、私が出来ることと言えば唯一つ。
殺さなきゃ……春日千秋を殺さなきゃ!
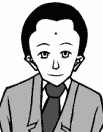 杉田光輝(男子九番)――『死亡』 杉田光輝(男子九番)――『死亡』
【残り 二十五人】 |
