廃ビルの出入り口を探し、その周囲を反時計回りに歩く千秋たちだったが、半周回った今もまだその姿は見えない。
裏側だろうか?
そう思いながら次の角を左に回ったときに、出入り口が姿をようやく現した。
コンクリート製の壁のど真ん中に、縦横に二メートルほどの大きさの穴をぽっかりと開けているだけの簡素な入り口。かつてはガラス製の扉があったらしいが、人の手によってか、あるいは長きに渡る自然の力かによって無残に割られてしまったらしく、その残骸が今も足元に散らばっている。
それにしても不思議な建物だ。どうやらかつてはオフィスビルだったと思われるそれは、どう見てもこんな山奥には似つかわしくないような存在だ。いったい誰が何のために建てたのかが疑問に思うところだが、バブル時代に調子に乗った実業家が山地の土地を購入し、そんな不便な場所で後先考えずに会社を設立したが、後に訪れる不況の波に耐えられず、あっけなく潰れてしまった、とまあこんなところだろうか。
別に経済知識に長けているわけでもなかったが、そんな憶測を勝手に並べてみる千秋。
二人は出入り口へと向かい、そしてそこからゆっくりと中を覗き込んだ。
四方壁に囲まれた建物内は案の定暗くてあまり視界が利かなかったが、所々に開けられた窓が、ほんの僅かに差し込んできている日の光を内に取り込んでくれているおかげで、おぼろげながら中の様子が見て取れた。
出入り口から一歩踏み込んだそこは、一階から三階まで吹き抜けになっており、天井はかなり高い位置にある。一階フロアの脇に階段への入り口の姿が見えるので、そこから上がれば上の階から今千秋たちがいる場所を見下ろすことができるのだろう。
また一階もいくつかの部屋に分かれているようで、フロアの端の壁にはいくつかの出入り口の姿が見られた。腐食が進んだ木製扉は崩れかけているが、まだこのビルが使われていた当時の名残を僅かに残している。
そして壁際にはダンボールをはじめ、何かの資材が所狭しと積まれている。オーナーがこのビルを後にする際に置き去りにしていったのだろう。これもまた部屋に入り込んできた雨水に長い時間さらされ続けたためか、変色や変形が進んで見るも無残だ。時間の流れというものをひしひしと感じる。
「おい、誰かいるか」
辺りを一通り見回し終えた猛が声を出した。事が上手く進んでいるなら、何人かの仲間達は既にこの場に到着しているはずだ、とそう考えたのだろう。しかし猛が呼びかけたのにもかかわらず、ビル内はしんとしたままで一向に返事が返っては来なかった。
千秋と猛はお互い目を見合わせる。
もしや、自分達二人が最初に到着してしまったのだろうか……。
だが千秋は気がついた。一階フロアの奥、別の部屋への出入り口の扉が半開きになっており、そこから二つの目がこちらを見ているということに。
それだけではない。吹き抜けになっている二階や三階にも目を向けると、そちらからもいくつかの目がこちらを向いている。
その数合計で十。二つの目を持つ人間が五人、このビルの中に隠れていたのだ。
やはり自分達以外のメンバーも、既に何人かが到着していた。そう思った千秋は安心し、猛に続いて自らも呼びかけた。
「あたしよ、春日千秋! それに磐田君も一緒にいるわ! お願い皆、返事をして!」
すると突如一階の別の部屋から覗いていた人物がこちらへと駆け迫ってきた。
相手の正体が分からぬ今、万が一にと思ったのか猛は身構えた。しかしそれは無駄な心配だったとすぐに分かった。
こちらへと駆けてきた人物は、無防備だった千秋の身体に飛びつき、そして抱きしめてきた。
「千秋! 会いたかったよ!」
その声を聞き、千秋は自分を抱きしめている人物の正体をようやく把握した。
「真……緒……?」
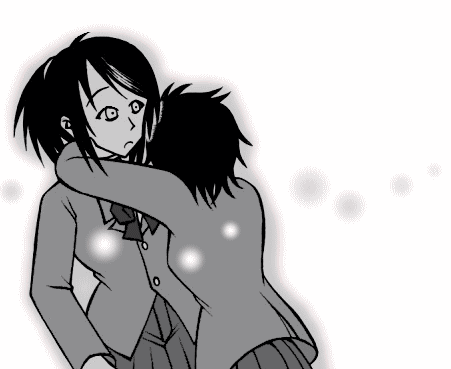
嬉しさに震えている幼い子供のような声、そして千秋を抱きしめてくる華奢で小さな身体は、紛れもなく無二の親友羽村真緒(女子十四番)のものに他ならなかった。
自分を抱きしめている人物の正体を把握できた途端、千秋の中は安堵の思いで満たされた。そして大切な親友に無事再会できたことに喜び、ほとんど衝動的に相手の身体を強く抱き返した。
「あたしも会いたかったよ! 真緒!」
これまで抑えてきた恐怖と緊張の糸がほぐれ、千秋は自分でも気づかぬうちに泣き出していた。もちろん泣き虫の真緒も豪快に涙を流し続けている。
二人は涙で顔をぐしゃぐしゃにしながらも、もう二度と離れないと誓い合うかのように、お互いをさらに強く強くと抱き締め合った。
そんな二人を、すぐ脇で猛は、まるで演劇の大団円でも前にしているかのように見ていた。そんな彼に向けて、真緒とはまた別の人物が階段を駆け下りて迫ってきた。
「よぉやりおったなぁ磐田。ただこの場に来るだけやのうて、まさか春日まで一緒に連れてくるとは」
梅林中は関西圏内にあるにも関わらず、中国地方との境目に近いためか、あまり関西弁が浸透していない。そんな中でこのコテコテの関西弁を耳にして、彼の正体が分からぬ者はいないだろう。
「杉田。お前も無事に到着してたんだな」
「あたりきしゃかりきや。ワイは何があろうと絶対に皆と再会したかったからなぁ」
このひょうきんな態度もまた彼の特徴。杉田光輝(男子九番)は丸めた自らの頭を手のひらで撫でながら、その元気な姿を猛に見せつけた。
「しかしまあ、よく羽村の奴もここにつれてくることができたな」
未だ抱き合っている千秋たちのほうを見ながら猛が言うと、光輝とは別の人物の声がそれに応えた。
「私がここに来る途中で偶然見つけたんだ。トラックの中で千秋が真緒に会いたいって言ってたのを思い出して、すぐさま事情を話して連れてきたってわけよ」
メガネをかけたその姿が知的な印象を受ける藤木亜美(女子十八番)の声だ。とにかく元気で明るい性格の持ち主である彼女もまた、このビルに無事にたどり着いた一人だった。
「そうか。ところでいったい何人が集まっていたんだ?」
「五人。磐田と春日を合わせてようやく七人目までが集まったわけさ」
いつも笑顔を絶やさない湯川利久(男子二十番)が応えた。
「なるほど、あと数人がまだこの場に到着していないわけか。まてよ、羽村に杉田、藤木と湯川、そして春日と俺を合わせて六人。あと一人は何処にいるんだ?」
「ああ、それは……」
利久の細い目がフロアの端へと向けられる。その先に最後の七人目の人物がいた。身体を小さく折り畳んで、体操座りしながらガタガタと震え続けている少女。小島由美子(女子七番)。
「彼女、ここに着いてからずっとあの調子なんだ。元気付けようといろいろと声かけたりしてみたんだけど、まあこの状況じゃあ、ああなってしまうのも無理は無いだろうね」
利久が表情を少し陰らせて言った。その途端、一同を包む空気が少し重くなったようだった。だが基本的にしんみりとした雰囲気が苦手な光輝が、なんとか場を和らげようと話し出した。
「まあまあ、とにかくまた仲間が集まったのは良かったやないか。今までに集まったのは七人。こらこのまま上手く他のメンバーも全員が集まってくれば、クラスの四分の一が集結するのも夢やないで」
彼の希望ある考えを聞き、一同が目を輝かしたようだった。だが、それに素直に喜べない人物が二人いた。千秋と猛だ。
二人はここに来る途中、既に仲間の一人が殺されているのを見ていた。そのため、トラックの中で再会を誓い合った仲間達全てが、この場に集結するということは、もはや不可能となってしまっているのを知っていた。だから、光輝の「全員が集まれば」という言葉を聞いても、ただビクリと身を震わすだけだった。
真緒と抱き合いながらも、千秋はそのことを皆に伝えるべきかとも思った。だけど、光輝の言葉が実現することを望み、皆が目を輝かしているのを見ては、そんな残酷な真相を伝えれるわけがなく、自分もただ喜んでいるというふりをして押し黙るしかなかった。それがとても悲しかった。
【残り 三十三人】
|
