四人は茂みの影に隠れながら、地中から頭を出している岩の上などに適当に腰を下ろし、ほんのひと時の休息をとった。
プログラム開始から一度も休むことなく、ゆうに三時間以上もの間、険しい山中を歩き続けていたので、怪我人の渉や体力不足の誠は当然ながら、運動部の健康児である正義でさえ実は疲れはじめていた。なのでこの休憩時間は本当にありがたい。
だが休憩中だからといって気を抜くのは禁物だ。こんな山奥だろうと、いつ敵が現れるとも限らないからだ。なので正義は常に周囲を警戒し続けていたが、何者の姿も見えることなく、当然足音なども聞こえはしなかった。耳に入ってくるのは激しく流れる水の音のみ。
音は自分たちの休憩場所からたったの五メートルという距離を流れる川から聞こえてくる。
数時間前まで降り続いていた雨によって勢いを増したのか、その流れはとても激しく、水と岩がぶつかる場所には渦までもが発生している。
もしもこんなところに落ちてしまったら、自分はいったいどうなってしまうのだろうか。と、カフェオレ色に濁った濁流を見ているうちに不安になった。
本当ならばこんな不気味な川の側など一刻も早く離れたいところなのだが、深い山中を闇雲にさまようのは危険だし、下流へと続いているこの川に沿って歩いているほうが、確実に下山することができると地図を見て分かっていたので、実はこれまでも彼ら四人はむしろ川の流れを見失わないように気をつけてきたのだ。そしてこれからもそれは変わらず、下りきるまではこの川沿いから離れる気など無い。その光景がいくら薄気味悪くとも。
「さて、休んだのは良いとして、これからどうするかだ」
正義は気を取り直し、息を潜めながら向かい合う形で座っている三人の仲間達を見回して、それぞれに意見を求めた。
「どうするって、この薄気味悪りぃ森から出るんだろ。だったら今は下山することだけを考えて、他の余計なことは考えなくて良いんじゃねぇか?」
そう言ったのは茂貴。
「たしかにお前が言うように、とりあえずはこの山から下りることに専念したい。だが、山から下りた後はいったいどうすればいいんだ? 俺達に提示された目的は級友同士で殺し合うということのみ。逃げ出したいのは山々だが、その方法も未だ考え付きはしない今、素直にプログラムのルールに従って、仲間同士で殺し合うか? それとも目的も無く、ただ闇雲にさまよいながら死期が訪れるのを待つか? 違うだろ。考えれば何かあるはずだ。お互いに殺し合わず、事態を少しでも好転させることのできる手段が。だがいつ危険が迫るとも限らない今、悠長に物事を考えている余裕は無い。休んでいる今という時間を惜しんででも、早くこれからの目的を定めるべきだ。と俺は思っている」
この意見は皆に受け入れられたらしい。正義に誰一人反対することなく、黙ってはいるが全員が確かに頷いた。
「ならば順番に聞いていこう。長谷川、お前は何か考えてることはあるか?」
グループの指揮は正義によってとられているということを、もはや誰もが自然に思っているらしい。彼のペースで進められていく話に、皆が当たり前のようについていく。
「ボ、ボクは特に何も考え付いては……」
「オッケー分かった。次、岸本」
あまり誠をあてにしていなかった正義は、できるだけ無駄な時間を作らぬために、問いかけをさっさと茂貴へと向け直した。
「俺か? 俺もまあここから逃げ出す方法とか色々と考えてはみたんだけど、ワリィ、やっぱ良い案は思い浮かばなかった」
「そうか……」
先のサイコロの件から、茂貴は少々頭の切れる人間だと分かっていたので、誠なんかよりも遥かにあてにしていたのだが、どうやら虫が良すぎたらしい。
しかし二人ともが何も考え付かなかったというのは、よく考えれば当たり前のことであると分かる。
1947年の第一回大会を始めに、既に六十年にもわたって続けられてきたこのプログラムで、異常事態が発生したという話はほとんど聞いたことが無い。ほぼ百パーセントの確率で殺し合いは成立し、きちんと一名の優勝者を生み出している。
だが正義には全ての参加者がルールを了承し、殺し合いに参加していたとは思えない。どの大会にでも殺し合いに納得ができず、そのルールに抗おうとする者はいただろう。それにもかかわらず、ゲームは滞りなく進行していく。
これはつまり、自分たち中学生がいくら頭を悩ませてゲームから脱する方法を考えても、綿密に構成されているプログラムの管理を前にしては全くの無力なのだということを意味している。そうでなければ、こうも長い年月の間プログラムが成立し続けているはずが無い。実際出発前に聞いた田中一郎の説明でも、脱出は不可能、生きて帰るには自分以外の者を全員殺すしかない、と言っていた。
要するに、たった四人集まって、それぞれが陳腐な脳で思考を繰り返したとしても、そう簡単に良い案など浮かぶはずが無いということだ。そりゃあそうだ。ここですぐに打開策が浮かんでしまうくらいなら、プログラムなんて前世紀の間に成立しなくなっているはずだ。
ここまでの考えだけだと、正義たちに残された道はもはや絶望しかないと思われる。だがたった一つ、僅かながら希望の光となりうる出来事が過去に発生しているのは事実。
97年度に行われたプログラムのうち一つで、参加者二名脱走、および担当官達が殺害されるという事件が起こった。世間一般で『沖木島脱走事件』と呼ばれている出来事だ。
兵も含め、担当側の人間全てが死滅していたことにより、この事件の真相は未だに闇に包まれたままである。そのため、脱走した二人というのは、いかなる手段を用いたのかも不明だ。もしかしたら、単に担当側の人間が何らかのミスを犯したのを発端に起こっただけの事件なのかもしれない。だがこれによって一つだけ分かったことがある。それは一見隙が無いように思われるプログラムも、実は完璧ではないということだ。
もちろん、その事件から十年が経った今、その僅かなヒビも塞がれてないとは限らない。だが所詮は人間が考えたこと。このプログラム、まだどこかに穴はあるはずだ。
つけ入る隙が無いわけでもないと考えた今、これしきで諦めてしまうわけにはいかない。
正義は希望を捨てなかった。
「俺も良案は思い浮かばないけど、一つだけ考えたことがあるんだ」
茂貴の次に指名された渉が、皆の顔色を伺いつつ話し始めた。
「ほぉ、言ってみな」
「うん。あのさぁ俺が思うに、この四人だけでなくて、もっと仲間を集めたらどうかと思うんだ。人数が多ければそれだけ建設的な意見が生まれる確率も高まるだろうし、なにしろ仲間が増えるのって心強いだろ」
「会った人間が殺意を秘めた敵かもしれないぞ。それに向こうが話の分かる人間だったとしても、こちら側のことを信用してくれるとも限らねぇし」
「それは大丈夫だと思う。こっちは四人もいるんだから、敵もたった一人で襲い掛かっては来ないだろうし、ゲームに乗った者同士が四人で手を組んでるってことも考えにくいだろうから、事情を話せば怖がられることも無いよ」
この意見が正しいことなのかどうかは誰にも分からない。だけど、少なくとも正義は悪く考えはしなかった。
渉が言うように、この四人だけで行動してても、いつまで経ってもらちが明かないだろうし、仲間が増えれば心強いということにも同意だった。事実、サッカー部チームメイトの磐田猛や土屋怜二とは手を組めば心強いことこの上ない。
「反対意見は?」
正義が聞く。茂貴も誠も、特に異議を唱える様子は無かった。
こうして彼らに目標ができた。もちろん、この仲間集めを進めたとして、事態の好転に繋がる確率は低いと考えて良い。だが何もせず、ただ夢遊病者のようにさまよっているうちに死ぬよりは幾分マシだ。
「決定だな」
そう言って立ち上がろうとしたとき、正義の目に何か動くものの姿が飛び込んできた。
「待て! その場で静かに伏せてろ」
正義に続いて立ち上がろうとしていた茂貴を急いで制止する。
事態を飲み込めずに不思議そうにこちらを見る三人を尻目に、正義は川の対岸へと目を向けた。
深夜でまだ暗いうえ、こちら側と同様に鬱蒼と植物が繁っている対岸の様子は、肉眼で確認するには困難だった。
一瞬、先ほど見たのは小動物だったか、あるいは風が木々を揺らしただけだったかとも思った。だが正義は確かに見た。川の側をおぼつかない足取りでフラフラと歩く人影を。
「誰だありゃ?」
茂貴も気づいたらしく、正義の隣で身体を小さく丸めながら対岸の様子を覗き込んでいる。それに続いて残る二人も対岸へと意識を集中する。
人影はゆっくりと下流へと向かっている。どうやら正義たちと同じく、向こうもここから下山しようとしているらしい。その歩みはゆっくりで、敵の来襲を恐れているのか、しきりに辺りを警戒しているように見える。
あれはいったい誰なんだ。
周囲に緊張が走った。
「あれは、久川さんじゃない? ほら、あの子って頭の左側だけ髪結んでるだろ」
両眼の視力2.0の渉が言った。
久川菊江(女子十五番)といえば、美術部に所属していて絵を描くのが大好きだという少女だ。正義は定期試験前に彼女からノートを借りたことがあるのだが、その中は物凄い数の落書きで満たされていて、大人しい菊江の意外な一面を見たとして驚いた記憶がある。
彼女は一年のときから変わらず、おかっぱ頭の左側を常にゴムで結んでいた。そして渉が言うように、確かに人影も髪を結んでいるように見える。
あれは久川か?
正義がさらに目を凝らして見ようとしたときだった。正体不明の人影の足元の地面が突如崩れだした。雨によってやわらかくなっていた上に人の体重が加わったことによって、地面は形成を保つのに限界が来たのだろう。
土塊と共に落下した人影は、大げさなほどの水しぶきと音を上げながら、濁流の中へとその身を埋めた。
「お、おい。ヤバイんじゃないかあれ」
茂貴がそう言うよりも先に、正義は川の中へと飛び込んでいた。
このまま放っておけば、あの人は死んでしまうかもしれない。俺達が見ていたというのに、助けの手を差し伸べなかったせいで。
正義はなぜか二年前の松乃中大火災のときのことを思い出していた。
逃げ遅れた自分が燃え盛る廊下を駆け抜けようとしていたとき、崩れた壁や天井の下敷きになって助けを求めていた生徒達の姿が、あちらこちらに見られた。それはまさに地獄図を実現化したかのような光景だった。
それらの人たち全てに助けの手を差し伸べてやりたかった。だが校舎そのものの崩壊が目前に迫っていたそのとき、正義は諦めてその場から走り去ってしまった。そう、正義は自分の命可愛さに、何人もの生徒を見殺しにしてしまったのだ。
事件後、そのことを思うたびに自らの罪に打ちひしがれた。
もしもあのとき、自らの危険を顧みて他人を助けることを選んだならば、いったい何人の命が助かっていただろうか。
そう考えるたびに、正義は自分のした行いが愚かに思えて仕方なかった。
生まれたときに母によって与えられた名前「正義」。その読み方を「せいぎ」と間違われたことは数知れない。だが母はまさしく正義感ある子に育って欲しいと思い、この名を付けたのだろう。
正義は決めたのだ。この名に恥じぬよう、そして火災のときのように二度と悔いぬよう、自分のことよりも、まずは他人のことを思いやれる人物になろうと。だから彼は自らの危険をも顧みず、その身を飲み込まんばかりに大口を開いている濁流の中へと飛び込んだ。
「どこだ!」
立ち泳ぎしながら、先に落ちた人物へと叫んだ。だが返答は無い。
必死に辺りを見回す。しかし捜索は難航を強いられた。思ったとおりに増水した川の流れは激しく、足が着かないほどに深い。このままでは自分が沈んでしまうのも時間の問題だ。
畜生! 死ぬんじゃねぇぞ! 今度こそは俺が助けてやるんだ!
もしかしたら水中に沈んでしまっているのかもしれないと考え、濁った水の中に潜水を開始しようかと思ったとき、川の少し下流の方から茂貴の声が聞こえた。
「いたぞ! 来い、宮本ぉ!」
そちらを見て驚いた。なんと正義に続いて、茂貴も、さらには誠までもが濁流に浸かっているではないか。
そう、正義の正義感に触発されたか、一人のクラスメートを助けるために彼らも動いたのだ。
ほとんど衝動的に飛び込んだ正義とは違い、彼らは冷静に川を見て、先ほどの人物は何処を流されているのかを把握した上で飛び込んだらしい。
全く見当違いなところで探していた正義は、一人で恥じた。
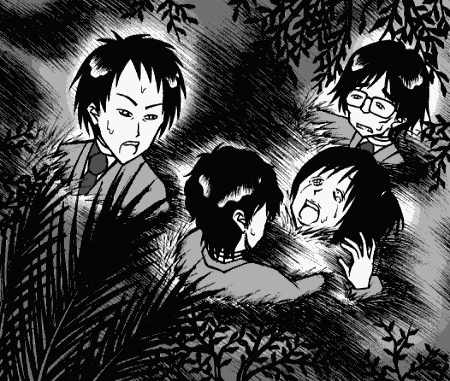
正義はすぐさま皆のいる下流へと泳ぎ始めた。そこには茂貴と誠、そして茂貴によって水中から引きずり出された少女の姿があった。渉が言ってた通り、その正体は久川菊江だった。
「大丈夫だ。ちょっと水を飲んでるらしいが、意識もあるし息もしてる」
そう言う茂貴に抱き上げられながら、菊江は苦しそうにむせている。
「てめぇら、足の不自由な渉を一人きりにしやがって!」
「まあそう言うな。それよりもこの流れはマジでやべぇ! さっさと岸に上がるぞ!」
たしかに、川の流れは凄まじく、このままではいつ誰が溺れてしまうとも限らない。いや、むしろこの状態で泳げているほうが不思議なくらいだ。
「さぁずらかるぞ! 早くしないと流されて、武田のいる位置からどんどん離れちまう」
菊江を抱きかかえた状態で、茂貴は岸へと向かおうとした。今一番大変なのは、一人の人間を抱えている彼なのだ。
「そうだな。おい、いくぞ長谷川」
正義は背後の誠を振り返った。だがそのとき、何処からとも無く飛んできた小さな注射器のような物が、誠の首元に突き刺さるのを見た。
【残り 三十七人】
|
