時の流れの早さには往々にして驚かされるものである。
あの悲劇に満ち溢れていた梅林中プログラムから六年もの月日が経過し、当時の出来事は人々の記憶から徐々に薄れつつある。当事者にとってそれはありがたいことではあったが、反面なんだか寂しくも感じられるのであった。
自らを含めたクラスの皆が、生きるために過酷な運命に立ち向かってきたという証までもが、粉々に砕けてしまいそうに思えたからだ。
こちらのジメジメとした心情とは対象的に明るく真っ青に広がっている空を、ガラス張りの天窓越しに、私は恨めしげに見上げる。
こんな清々しい天気の下ですら爽やかな気持ちになれないとは、なんて不幸なことだろうか。
入口の脇に「獣医学部」と書かれた建物から一歩外に出ると、澄み渡った空気がより鮮明に感じられた。雲一つに遮られることもなく降り注ぐ直射日光は、身長の半分ほど引き伸ばした私のシルエットを、コンクリートの地面にこれ以上無いというほどにくっきりと浮かび上がらせていた。
だがこれほど晴天であるにも関わらず、身体の内まで染み渡るような肌寒さを感じていた。それもそのはず、季節は秋へと入っており、この大学の敷地内もすっかり紅葉に彩られている。
今日は天候が良さそうだが服装はどうしようか、と家を出る前に悩んでいたが、厚めのコートを羽織ってきていて正解だったようだ。
コンクリの渡り廊下から、わざと少し横にずれて歩いてみると、黄土色に変色した芝の柔らかさがブーツの底から伝わってきた。
かつては二度と踏み締めることができないだろうと思っていた本土の感触。プログラムで優勝したこと自体には何の喜びも感じなかったが、生きて再びこの感覚を味わえたことはとても感慨深かった。
死に塗れたあの島の冷たい地面とは違い、まるで床下暖房の如く私の心を暖めてくれる。
だからこそ、北風に吹かれて冷え切った身体でもなんとかやっていけるのだ。
しかしそんな暖かな地面の上も、堂々と歩くような気分にはなれない。いくらプログラムが合法の下で行われているとは言っても、クラスメート達の命を犠牲にして帰還したということに負い目を感じずにいられるほど、私は無神経ではない。それにプログラムの優勝者に対して白い目を向ける人間も、世間には少なからずいるのである。
「よう、明日香」
ふいに背後から誰かが私の肩を掴んできた。“明日香”とは現在私が使っている偽名である。ちなみに苗字は“山本”としている。これは私がプログラムの優勝者であるという素性を隠すための策の一つ。当時ニュース番組や新聞など多くのメディアで、私の本名が取り上げられていた。だから今、私の名前を覚えている人がいて、さらにはそれに鉢合わせてしまうようなことがあってもおかしくはないのだ。
プログラム優勝者の中には、日常に戻ってからも元の名前を使い続けている人間もいるらしいが、私にはとても理解ができなかった。
「おい、何ボーっとしているんだよ」
私が反応を見せないでいると、背後に立っていた人物はぐるりと正面に回り込んできた。
背の高いシルエットに視界を覆い隠される。
「あんたさぁ、やっぱりそのテンガロン似合ってないよ」
のけ反り気味に見上げて言うと、男が自らの頭を押さえながら口を尖らせた。
「そうかな。俺は結構気に入っているんだけど」
「なんか被っているというより、被せられているって感じ」
「それはお前が、ニットを被った俺の姿を見慣れてしまっているからだろう」
「そうね、ニットのほうが違和感に関してはマシだったわ。別に凄く似合っていたというわけではないけれど」
刺々しい言葉の連続攻撃に観念したのか、男は渋々と帽子を取った。長くも短くもない中途半端な長さの茶髪が、柔らかそうに舞いながら彼の耳にかかる。
「帽子、被ってないほうがいいんじゃない? 今の髪形は結構似合っていると思うしさ」
「凹むようなこと言うなよ。結構奮発した買い物だったんだぜ、これ」
と帽子を指しながら、しょぼくれたような顔をする彼の姿は見ていて面白い。これだから虐め甲斐があるってものだ。
「三千九百円ごときの買い物で奮発? まあ、貧乏学生の財力なんてそんなものか」
「あのなー、俺たち付き合い始めてからもう一年経つんだぜ。そろそろキツイこと言うのは止めにしないか?」
「いいわよ。あんたが目上の人間に対する馴れ馴れしい口調を改善させてくれさえすればね」
「なんだよ、お前と話すときは敬語を使えってか? 彼氏彼女の間柄でそれは不自然だろ。いくら俺のほうが年下っつってもさぁ」
そう、彼は獣医学部の同級生だが年齢は私より三つも下だった。サークルの飲み会の帰り道で、二人っきりになったところで交際を持ち掛けられた。それが付き合い出すきっかけとなった。
かつては年下の男に興味を持てなかった私だが、とある勇敢で頼れる男子と出会って以来考えを改め直していたこともあって、その時の告白に対しては自分でも驚くほどあっさりとOKを出したのであった。
結果、今はとてつもなく幸せである。元より彼とはウマが合ったが、付き合いだしてからは相手からの愛情や、些細な優しさまでもが、はっきりとした形となって見えてくるようになったのだ。また彼は背が高くて容姿もそれなりに良く、見てくれに関しては文句の付け所が無い。あえて難点を探すならば口の悪さが挙げられるが、それもまた愛嬌の内だ。
今となっては、年下というだけで男を遮断し続けていたあの頃の自分が馬鹿馬鹿しくすら思える。その頑なさのせいで、いったいどれほど損を積み重ねてきただろうか。昔持っていた考えのように、告白してきた男の多くは精神的に幼過ぎて満足な交際なんて叶わなかったかもしれないが、中には私を輝かしい思いで満たしてくれるような者が一人や二人くらいいたかもしれない。
「ところでさ、お前、明日って時間空いてる? ちょっと行ってみたいショップがあってさ、付き合ってほしいんだけど」
そういえば、今週辺りからちょうど冬物のバーゲンを始めている店舗が多い。彼の買い物に付き合うついでに、掘り出し物はないか探ってみるのも良いかもしれない。しかし、なぜ明日なのだ?
「今日じゃ駄目なの?」
「この後バイトがあるからさ、できれば明日がいい」
明日は金曜。平日とはいえあまり講義を取っていない曜日なので、本来ならば夕方からは自由に過ごせるはずなのだが、今週に限っては例外であった。
「ごめん。明日はもう予定が入っていて、どうしても空けられないんだ。あ、そうそう、学校にも来られないからさ、だから悪いけど明日の講義、代わりに出席しておいてもらえないかな」
「なんだよそれ。俺の願いは聞き入れないでおきながら、自分ばっかり勝手なことを言って――」
「いいじゃない。この前あんたがさぼった講義、代わりに出席してあげたでしょ」
すると彼は「ちぇっ」と舌打ちしながらも、結局は私の言いなりになるしかなかった。二人の間での力関係でいうと、私のほうが上なのである。
「しかし珍しいよな。お前が講義さぼるなんてさ、入学以来初めてじゃないのか? いったい明日から何の予定が入っているって言うんだ?」
「昔の男と二泊三日で温泉旅行。羨ましいでしょー」
悪戯にクスッと笑ってみせた。
「畜生、誰だその男! 殺してやる!」
「あはは。冗談だってば。冗談」
やっぱり彼を弄ぶのは楽しい。狙っていた通りの反応がそのまま戻ってくると、なんだか快感を覚えるのであった。
私って完全にSだな、とぼんやり思う。
「ちえっ。俺で遊ぶのはやめろよな……。それじゃあ本当は何なんだよ? お前が明日来られない理由っていうのはよぉ」
「残念ながらそれは言えない」
彼はずいずいと詰め寄ってくるが、本当の理由は口にはできない。これまで隠し続けてきた私の正体を明かしてしまうようなことだったから。せっかく手に入れた平穏な日々が、また遠いところに行ってしまうような真似だけは避けたかった。
「そうね……、じゃあ、可哀想だからこれだけ教えてあげるわ……」
私は両手で軽く彼を突き飛ばした。そして、よろめきながら後ろに下がる姿を前に、無理に微笑してみせる。
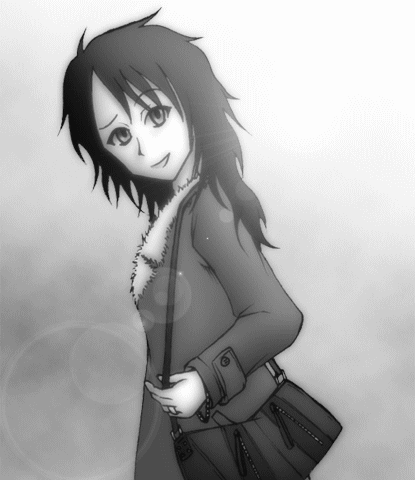
「明日はね、私にとって特別な日なの――」
|
