力が抜けて、地面の上で仰向けになったままピクリとも動かない霞の身体。膨らんでいた筋肉は完全に収縮し、鬼に支配されていた頃の面影を一切残していない。
生命の鼓動が完全に途絶えており、近くで見ていてはっきりと分かった。つい今しがた、御影霞は死んだのだ、と。
首からかけていた太陽の形のネックレスが、彼女のブレザーの胸元から零れ落ちて鈍く光っている。
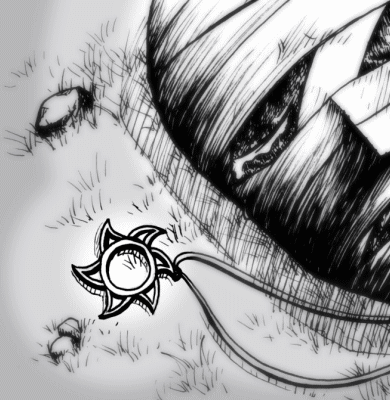
「安らかな顔つきだ……」
怜二は亡骸を見下ろしながら呟いた。どこか安心している様子だった。
彼が言った通り、確かに霞は穏やかな表情のまま目を瞑っており、幸せそうにも見える。復讐のみに囚われて、殺意で表情を鬼のように塗り固めていたころとは大きく違う。
薬の幻覚作用でひとしきり暴れた後、死に際になって彼女の表情はみるみるうちに緩んでいったのだが、心境に何か大きな変化でも起こったのだろうか。
良い夢でも見たのかもしれない。
今となっては、真相は分からず仕舞いだが、霞の中でプラスになる出来事があったのは間違いないだろう。でなければ、あんなにも柔らかい顔をすることなんて出来るはずがない。
「これで、良かったんだよな……」
千秋の隣で怜二が崩れる。地面に膝をつきながら、うっすらと涙を浮かばせていた。
霞を復讐の鬼にしてしまったのは自分達なのだ、と彼はずっと責任を感じていたのだろう。
火事の中から少女の命を助け出した当時は、正しいことをしたつもりになっていた。だが、延命がかえって新たな悲劇を生み出すという最悪な結果に繋がり、自らを責め立てるようになってしまった。そして今度こそ霞を心の闇から救い出し、この憎悪に塗れた殺人劇に終止符を打つ、と自ら誓った。
結果的に、殺し合いはなんとか終結したが、あまりに時間がかかり過ぎた。多くの血と涙が流された一連の悲劇は、怜二にとって悔やんでも悔やみきれないことだっただろう。
そんな彼にとって唯一の救いだったのが、最後の最後に霞が憎悪の渦から解き放たれたのかもしれない、ということだろう。とてつもなく些細なことであるが、不幸ばかりに満たされていた地獄の中では、そんな小さな光ですらこの上ない喜びとなり得る。
もしかしたら、怜二は霞に対して好意を持っていたのかもしれない。それがいかほどのものだったかは想像もつかないが、もしそうなのなら、彼が霞を救うことに執着していたのも、より納得できるのだった。
まあ、わざわざ聞くのも気が引けるし、今となってはどうにもならないことなので触れはしないけれど。
「これからどうする?」
千秋は別の話題を持ち出すことにした。
霞の仕掛けた爆弾によって分校が破壊されたという今、はたしてプログラムは継続して行われるのかどうかも分からない。もちろん、元々殺し合いになんか乗るつもりは無かったけれど、この理不尽ゲームがこれで終了するのかどうかによって、行動方針は変わってくる。
帰還の準備を整えるか、もう一度政府に歯向かうか。
「とりあえず、御影の爆弾でプログラム本部がどうなっているのか、確認しに行くとするか」
千秋達が今いる場所は分校よりも高台にある。少し移動すればプログラム本部を見下ろすことも可能なはず。しかし、その前にやるべきことが一つあった。
「土屋君。ここへと来る途中で蓮木さんを見なかった? あたし、彼女と一緒にいたんだけど、はぐれちゃって……」
出来るならば彼女を捜し出すのを手伝ってほしい。そんな心境を怜二なら汲み取ってくれるに違いない。そうでなくとも、彼ほどに他人のことを思いやれる人物ならば、黙っていても手を貸してくれそうだ。
千秋は大きな期待を抱いていた。それでも次の瞬間には驚かされることになった。
「ああ、蓮木なら――」
いかにも何かを知っているような口ぶりだった。
「まさか、会ったの?」
千秋は思わず飛び付いた。その勢いに少しビックリしたのか、怜二は上半身をやや後ろへと仰け反らせる。
「ああ、ここに来る途中、倒れているのを偶然見つけたんだ。息はあるようだったけど気を失っていたから、背負って歩くことにしたんだが――、御影とお前を見つけて、背負ったまま間に割って入るのは危険だと思って、死角となる場所にとりあえず下ろしたんだ」
「それって何処?」
「そこの薮の後ろだ」
聞くや否や、千秋は怜二が指差す方に駆け出していた。骨が突き出るほどの重傷を負った肩が激痛を発していたが、そんなことを気にしてはいられなかった。
薮の裏に回り込むと、たしかにそこには少女が一人倒れていた。全身ずぶ濡れで、衣服はあちこちが破れてボロボロ。キュロットスカートには腰の辺りからスリットが走り、あられもない格好になっている。血の気が失せて人相が変わってしまっているが、蓮木風花に間違いない。水に流されている間に岩にでもぶつけたのか、露出した肌に紫色の痣がいくつも見られた。骨折もあるかもしれない。そして、聞いていた通り、意識は無い。弱々しく呼吸はしているが。
「溺れていたのか、水を大量に飲んでしまっていたようだ。幸運にも自力で吐き出したようだが、そうでなければこうして生き延びてはいられなかっただろう」
怜二はダム破壊計画を知らない。きっと風花が濁流に飲まれてしまったのは、単なる事故とでも思っているのだろう。
「蓮木さん!」
軽く頬を叩きながら呼び掛けた。だが返事は無い。
「俺も相当呼び掛けたけど、駄目だったよ」
力無く言う怜二。
「どうしよう……。蓮木さん、助かるの?」
「分からない。あとは彼女の生命力次第だ」
結局、今は願っていることしかできない。手当てする用意は整っていないし、医療の知識も無いに等しいので。
思えば、風花の生存は奇跡と言えた。ダムを破壊する前から血液不足で体調を崩し、水に飲まれて長距離を流されてきたのだ。普通なら命を失っていてもおかしくない。
千秋は思った。
欲張りな願いかもしれないが、もう一度風花に奇跡が起こってほしい。
「お願い! 蓮木さん、目を開けて!」
千秋は声のボリュームを上げながら顔を近づけた。
すると、目の前の瞼がゆっくりと開いた。
「……うるさいわね……。そんなに大きな声を出さなくても……、聞こえるわよ……」
こんなにも簡単に奇跡は起こるものなのかと戸惑った。
呼び掛けに一切応えなかった風花が、急に目を醒ましたのだ。
信じられない。だが、身体じゅうの痛みをはっきりと感じるし、夢ではない。
「蓮木さん!」
嬉しさの余り、もう一度相手の名前を呼んで抱き着いた。この幸せを、互いに共感したかった。
「……やめてよ。……痛いんだから……」
と風花は顔を歪める。傷を圧迫されるとかなり痛むようだ。だが力ずくで千秋を振り払おうとする素振りは見せない。彼女もまた、こうして生きて人と触れ合うことができて喜びを感じているのかもしれない。
「あ……、ご、ゴメン」
相手の身体を気遣って、千秋は風花の背中に回していた腕を解いた。
「痛かった?」
「……そう言ってるでしょ……。身体がちぎれるかと思ったわ……」
傍の木にもたれながら風花が溜息をつく。
そんなに強く抱きしめたつもりは無かったのだけど……。
「生き残りはこれで全員?」
風花が千秋と怜二の間で視線を行き来させる。
「そうらしい……。前の放送の時点ではもっといたんだが……」
「そう……」
残念そうに俯く。風花はもしかすると、比田圭吾が生きている可能性をまだ頭の中に残していたのかもしれない。だがそれも今、単なる夢物語となって消えてしまった。
「だが、もう生命を脅かすような人間はいない。多くのクラスメートが亡くなったのは残念だが、これ以上は人が殺されるようなことは起こらない」
まるで風花の心情を読み取ったかのように、怜二が発言した。
悲しみの連鎖はもう終わり。だからこれ以上苦しまされることは無い。
しかし、そのとき既に風花は別のことに意識を向けていたようだった。眉をひそめながら、辺りを注意深く見回している。
「……ねぇ、何か聞こえない?」
ふいに彼女は耳に手をあてて目を細めた。
「何かって?」
「人の声……。男の人の……。放送とは違う」
つられて、風花以外の二人も耳を澄ませる。
『生き残っている人達! 聞こえますか!』
確かに聞こえる。機械を介して無理矢理にボリュームを上げているような声が。
「行ってみよう」
自力で動けそうにない風花を背負い上げて、怜二が声のする方へと移動を始める。すぐさま千秋も後に続いた。
草木を掻き分けるように、林の中を進むと、ほどなくして視界が開ける。
分校を見下ろせる高台の先端で、怜二は風花を背中から下ろした。
「燃えている……」
誰かが呟いた。
二年前の大火災を彷彿とさせるような、大きく赤い炎。
プログラム本部のある分校が完全に飲み込まれていた。壊滅的だった。
『皆さんにお知らせしたいことがあります!』
尚も聞こえる、機械を介した声。だが燃える校舎の中に生きている人間がいるとは思えない。
脱出することができた誰かがどこかにいるのかと、目を凝らして探す。
「あそこ……」
地べたに座り込んだ姿勢のまま、風花が指差している。
運動場の真ん中に誰か立っていた。拡声器を手に何か言っている様子。声の主に間違いないだろう。
千秋はその言動に集中することにした。
『不測の事態発生により、プログラム本部は壊滅的なダメージを受けてしまいました! 沿岸の警備艇が消火に駆け付けてはくれるでしょうが、もはやこれ以上プログラムを続行することは不可能です。よって、前代未聞のことではありますが、今回のプログラムはこれにて中止とさせていただきます!』
全員が耳を疑った。
「オイオイオイ……。マジかよ……」
「聞いたことが無いわ……。優勝者が決まっていない状態で、参加者全員が死に絶えた訳でもないのにプログラムが終了するだなんて……」
「信じられない……。けど、これであたし達、皆助かるってこと?」
三者三様に驚いた顔をしている。これから先どうするべきか考えていた矢先に、こんなにもあっさりと問題が解決するなんて誰も予想していなかった。
「まさか、政府の策略じゃないだろうな」
「どういうこと?」
「本部が壊滅してプログラムを続けることが不可能になった今、奴らはさっさと俺達を片付けてしまおうと考えた。そして、餌を撒いて生き残りを安心させ、集まった全員を一気に殺してしまうことを思い付いた――。政府の奴らなら考えかねない」
こんな有り得ないような状況下では、彼のように疑ってかかってしまうのも無理はない。
しかし、拡声器越しに必死に呼び掛けを続けている男の姿は、とても偽りに思えなかった。
「じゃあ、この呼び掛けには応じないことにする? もしかしたら本当に助かるかもしれないのに」
「もしかしたら、という程度の可能性で、相手の話に乗ってしまうのは危険すぎる」
風花と怜二が互いに押し問答している。とても間に割って入ることはできなかった。事の真偽を判別しようがないからだ。一応男の言動を信じつつはあるものの、それが真であると証明することはできないし。
あたふたしていると、いきなり誰かに名前を呼ばれた。
『聞こえていますか! 春日千秋さん!』
驚きながら声の方を向く。校庭の男が呼び掛けを続けているのが見えた。
彼が千秋の名を口にしたのは間違いない。
しかし何故――。
不思議そうにこちらを見つめてくる風花と怜二。どうして千秋が呼ばれたのか説明して欲しそうな顔をしている。しかし、どういうことなのかはこっちが聞きたい。
『桂木幸太郎という男を知っているな?』
「桂木さん?」
無意識に声に出していた。
もちろん知っている。松乃屋の良き常連さんだ。
『彼は軍の人間で、今回は急遽、プログラム補佐を勤めることになっていた! 参加者のことをあまり詳しく知らなかった彼は、この島で君に出会ったことに心底驚いていた!』
男の呼び掛けが続く中、千秋は言葉の一つ一つを必死に整理する。
「桂木さん……。やっぱり、出発のときに見たのは、あの人に間違いなかったんだ……」
軍服に身を包んだ男の姿を思い出す。
「まさか本当に軍人だったなんて……」
少なからずショックを受けた。あの優しく誠実な桂木が、自分達を地獄に突き落とした側の人間だったなんて、と。
『あえて言う。これは紛れも無く事実だ! 勘違いしないでほしいのは、彼は君達の敵ではなかったということ』
「敵ではない?」
思考が追い付かず、相手の言葉をただ繰り返すだけとなっている千秋。
『君達はプログラムからの脱出を企てていたね? 桂木はいち早くそれに気付き、首輪の盗聴回路を――っと、その前に説明が必要かな。君達に巻かれている首輪にはマイクが内蔵されていて、政府はそれで全員の動向を監視していたんだ。もしも醍醐――、いや、田中に脱出計画を知られてしまったら、君達はすぐさま消されてしまう。桂木はそれを案じて、盗聴用の回路を不能にさせるために動いたんだ。自らの身の危険も省みず』
風花が力の入らない手つきで、首もとを探っている。
「気付かなかった……。マイクが仕込んであったなんて……」
どうやら思っていた以上に、あたし達が渡っていたのは危ない橋だったらしい。もしも桂木の助けが無かったら、と考えると血の気がひいた。
『だがそんな彼も、突然起こったこの原因不明の火災で犠牲となってしまった……』
……桂木さんが死んだ?
衝撃が走る。
もう悲しまなければならないようなことは無いだろうと思っていたのに。もう知っている人間が死ぬことは無いだろうと思っていたのに。それなのに、あってはならないことがまた起こってしまった。
『彼の死に際、俺はあることを託された。春日千秋さん! 君を救ってほしいと言われたんだ!』
まともに物事を考えられなくなっているのに、不思議なことに、頬を伝って涙が流れ出す。
『俺はここに誓う! 今この島に生きている全員を、必ず元の世界へ連れて帰ると!』
もはや男の言っていることが嘘だとは思えなかった。思い付きなんかで、ここまでよく出来た話を構成できるはずがない。そう思っているのは千秋だけではなかったようだ。
「俺達……本当に助かるのか……」
張り巡らされていた緊張の糸が切れて、怜二は力無く膝から落ちる。
「もう、戦わなくていいのね……」
下を覗き込みながら風花がボソリと言った。炎に照らされて赤くなったその顔には喜びが満ちている。
千秋は桂木に感謝した。だが心の中で想うだけでは、いくら感謝しても全然足りない。
もしも彼が生きていたなら、あたしはどうやってお礼をするだろうか。言葉で伝えるのは当たり前。あたしにできる他のことで、桂木が喜んでくれることといえば……。
懸命に考えた。答えは一つしかない。
心の篭った美味しい料理を作って差し出す。
桂木の喜ぶ顔が容易に浮かんだ。
そうだ。帰って落ち着いたら、真緒も大好きだった肉じゃがを作ろう。
楽しいことが次々と浮かんできて、次第に心が温まっていく。
「さあ帰ろう――。あたし達の生きるべき所へ――」
海原の向こうに浮かぶ霞みがかった本島を、高台の上から三人が見つめていた。
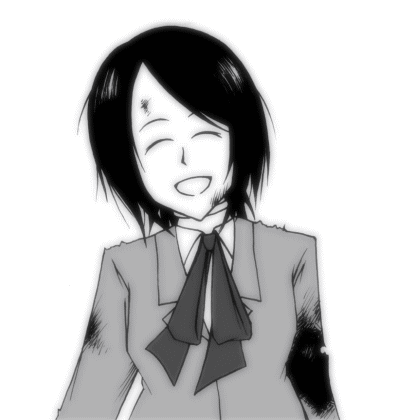
もうすぐで全てが終わる――。
泣くのをやめて笑えばいい――。
夢にも見た自由を、あたし達は手に入れたのだから――。
【残り 三人】 |
