両手で抱えるように腹部を抑えながら崩れ落ちた桂木。床に膝をついて傷口に触れていると、ドクドクと内側から血液が溢れ出しているのが感触で分かる。
銃で撃たれる、というあまりに非日常的過ぎる出来事。しかし戦時中でもない現世にそれは、紛れも無く桂木の身に降りかかった。
もちろん軍に属していた彼は、ごく一般の市民と比べれば銃火器に触れる機会が多かったが、それにしたって自分が撃たれることなんて一生に一度あるか無いか――いや、一度でも撃たれる人間なんて軍の中を探し回ってもほとんどいないに等しいだろう。
まるで桂木を死にいざなうかのように激痛が走る。かつて記録映画等を観つつ想像していた痛みを超越していた。
「急所でなく腹を撃った意味が分かるか? 政府と軍を裏切った重罪人であるお前たちは、簡単には殺さないほうがいいだろうと判断したからだ。金属の塊に腹を貫通された痛みに苦しみながら、緩やかに死に飲み込まれていくがいい」
と言って御堂が笑った。わざと桂木たちの視界に入るように、ぐっと顔を近づけながら。
「うぅぅ……」
うずくまった醍醐が悲痛な唸り声を上げている。撃たれた箇所はたしかに急所ではないものの、出血量と内臓の欠片が周囲に飛び散った様から察するに、このままではいずれ生命の危機に繋がるであろうと容易に察することができた。そしてそれは桂木にも言えた。二人の撃たれた箇所はほとんど同じ。傷の深さにも大差はなさそうだ。となると、他人のことばかり心配してもいられない。今この瞬間にも、桂木の元に死は確実に迫りつつある。
「苦しそうな顔をして、どうかしたか、桂木?」
御堂がまた顔を覗き込んでくる。大人しめに髭をたくわえた口元がにやけ、憎たらしさを演出している。
「なんだぁ、その目は? 命を握られているというのに、えらく反抗的な態度じゃあないか」
気付かなかったが、御堂の言葉からすると、桂木は知らず知らずのうちに相手を睨みつけてしまっていたらしい。それほどに、思惑通りに一度は動き出していた場の流れをぶち壊した男のことが憎かった。
「……お前の思い通りにばかり事が進んでたまるか。今に見ていろ。正義を容赦なく握り潰してきた貴様には、きっといつか大きな天罰が下る」
喋るごとに振動が腹に響いて激痛に襲われた。思わず顔をしかめてしまう。
「ははは。威勢がいいのは口だけだな。表情が苦痛に歪んでいるぞ。さすがに今回は強がって平静を装うこともできんか」
御堂は笑う。桂木たちを悔しがらせるためにわざとしているのではなく、堪えきれなくなって思わず吹き出してしまったといった様子だった。
「それにしても、天罰か……。面白いことを言うじゃないか」
唇を噛み締めている桂木を、御堂が冷ややかな目で見下ろす。
「桂木さぁ、そんなことが起こると本気で信じているのか? だとしたらお前はほんっとに馬鹿だな」
「俺は思い付いたことをそのまま言っただけだ……。昔から言うだろう。悪いことをすれば必ずばちがあたる、と……」
「昔から迷信が嫌いでね。生まれてこのかた神に向かって手を合わせたことなどないし、そもそもそういうのは信じられん。それに私は罪に値することなど何一つしていないしな。そう、自分にとって正義は政府。それに従っている以上、裁かれなければならない理由などそもそも無いのさ」
心底から政府を信じきっている御堂。この男にはこれ以上何を言っても無駄だと、桂木は思った。醍醐のときには僅かでも見られた改善の余地が、今回に関しては皆無だった。
「それでも天罰はあると言うのならば、是非見せてもらいたいものだな。そうだ、もしも本当にお前が言った通りに天罰が下ったら、この場で土下座してやろう」
彼は完全に桂木をおちょくっている。自らの正義を信じて疑わないあまりに、他の言葉は一切耳に入ってこないのだ。周りが見えていない、話も通じない、まともに相手にされない。コミュニケーションを断絶されたに近いといった状況に、桂木は悔しんで力無く拳を床に叩きつけた。
それを見て笑う御堂。目論み通りに反逆者たちが緩やかに弱っていく様が、とても面白おかしいようだ。
「クソッタレ……」
桂木が憎らしげに吐いた弱々しい声は、高笑いに飲まれて誰の耳にも入らず消えてしまう。
悔しい。そして腹の傷があまりに痛い。苦しい。息を吸い込むたびに肺が悲鳴をあげているようだった。
しかし弾の当たり所のほんの僅かな違いか、それでも桂木はまだ幾分マシだったのかもしれない。途切れ途切れにでも悪態を吐いている桂木に対して、同じく腹を撃たれた醍醐は倒れてからずっと黙ったままだ。喋ることもままならないのか、時折唸り声をあげるくらいで、身体もほとんど動かさない。彼の下では血溜まりがなおも拡大を続けている。
「さあさあどうした。天罰とやらが起こる前に、このままじゃあお前たちのほうが先にくたばってしまいそうじゃないか」
と御堂が身を乗り出してきたとき、突然近くで耳をつんざくほどの爆音が鳴り響いた。木造の校舎全体が激しく揺れ、材木の軋む音が周囲一帯から鳴り響いてくる。大勢の悲鳴のような声も聞こえてきた。どうやら本部にいる兵士たちの声らしかった。そういえば、音は本部の方向から発されていたように思われる。
「なんだ! いったい何が起こった!」
地震でも起こったかのような揺れは少し続いた後、次第に落ち着きを取り戻していく。しかし動揺した御堂が驚きの声を上げるのと同時に、爆音は再び鳴り響いた。今度のは先程よりもさらに近いところから聞こえてきたようだった。
御堂と同様に事態を把握できない桂木が顔を上げると、窓ガラスがけたたましく音をたてながら割れ、そこから金属の板のようなものが室内に飛び込んでくるのが見えた。窓を外から覆っていた分厚い鉄板の欠片だった。
「がぁっ!」
形容しがたい短い声が聞こえた。それは御堂の断末魔だった。
フリスビーのように回転しながら飛んできた鉄板によって、御堂の首は、まるで狙い澄ましたかのように見事にスッパリと切り落とされたのだ。
それでも勢いを失わなかった鉄板は、窓とは反対の廊下側の壁面に深々と突き刺さった。鋭利な断裂部から鮮やかな色をした血が滴り落ちる。
瞬間的に形成された悲痛な表情を保ったまま、御堂の頭部は床の上をごろごろと転がった後に、部屋の隅でピタリと止まった。あまりに突然過ぎる出来事に、彼はどうして自分が死んでしまったのか理解できなかっただろう。いや、それどころか、自分が死んでしまったことにすら気付けなかったかもしれない。しかしそれも仕方ない。全てをしっかりと目に焼き付けることができた桂木だって、たった今起こった事の詳細についてはほとんど何も分かっていないのだから。
ところで、頭を無くした御堂の身体だが、首の切り口を下にして床に倒れ込んでいるせいで、まるで頭を地面にめり込ませながら力いっぱい土下座しているようにも見えた。つい先ほど御堂が面白半分に喋っていたことが、丸々そのまま起こってしまったかのようだった。
「こ、これはいったい……」
唐突に目の前に作り出された異様な光景に呆然とする桂木。ほんの数秒前までの、御堂に銃を向けられていたときの事が幻のように思えるほどに辺りの様子が一転したのだ。状況判断が追い付かないのも当然だった。
そうだ、と醍醐の存在を思い出し、桂木は痛みを堪えつつ倒れたまま身体を反転させて見た。
「おい、大丈夫か!」
今、桂木が危惧したのは、醍醐の腹の重傷についてではない。首を撥ね飛ばされた御堂のように、先の爆発で醍醐が新たに大きな怪我を負わされていないかどうかが気になったのだった。
「醍醐っ!」
桂木の問い掛けに醍醐はとくに応えるそぶりを見せたりはしない。だが一見して、とりあえず彼の怪我は増えてはいないようだった。
だが安心したのもつかの間、爆音はまた辺りに轟く。しかも今回は間髪空けずに、二発、三発と連続して起こる。ガスなどの漏れによる爆発事故なんかではない。音の様子からして一連の爆発の大きさはどれもほとんど同じ。計算して作られた爆弾による爆発としか考えられないような状況から、本部の破壊を狙う何者かの陰謀が潜んでいるよう思えてならなかった。
建物を支える軸がいくつか破壊されたのか、天井や壁が先程よりも激しく揺れる。降り注いでくる材木の断片を避けるように頭を抱えていると、また本部の方から悲鳴と騒ぎ声が聞こえてきた。急いで火を消せだの、扉を開けろだの聞こえ、なにやら大混乱の様子だ。
爆発の規模からして、御堂のように命を落とした者がいたかもしれない。それも一人や二人ではなく、本部が受けた被害の大きさによっては、何人も、何十人も――。
いったい今、ここで何が起こっていると言うんだ。
これ以上は何も起こるな、という願いとは裏腹に、爆発はさらに頻発して起こる。そのどれもがやはり本部を飲み込まんとしているように思えた。
「くっ!」
落ちてくる天井板を腕で防いでいると、柱がミシミシと軋みだした。そして直後に落ちてくる梁。真上から落ちてくる重たいそれは避けようがなかった。
梁は桂木の胸の上に落ちてきて、身体の動きを完全に抑える。
衝撃が骨格を破壊する音が自分の耳にも届いた。
「ガハッ!」
あばらの何本が使いものにならなくなっただろうか。口から血を吐いた桂木は、自分の胸が重みで異様な形に潰されているのをすぐに感じ取った。触れてみずとも、何十キロもある重たい梁が胸部にめり込んでいる様が、大体想像できる。
銃で撃たれた傷といい、桂木の身体はもうむちゃくちゃだった。梁に抑えつけられているかいないかなど関係なく、もはや自力で立ち上がることなんてできそうもない。
天井を支えていた梁が落ちてきて、教室の有様はよりいっそう酷くなった。建物の破片がひたすら降り注ぎ、動くことの出来ない桂木の上にさらに圧し掛かってくる。
全身にかかる重圧は次第に大きくなり、手足の僅かな動きすらも困難になっていく。それでも頭だけは庇い続けていたおかげで、首を回して周囲を見ることだけは辛うじてできた。
頭を横にすると醍醐の姿を確認できる。彼の上にも天井の一部が圧し掛かり、身体の大部分が埋まったような状態になっていた。
助け出さなければ、と桂木は思ったが、動けないのは自分も同じ。
崩壊を続ける建物の中で、恐怖がひたすら拡大を続けた。
誰か、助けてくれ。
強く願っても何も起こらない。突然扉が開いて誰かが飛び込んでくることがなければ、神が奇跡を起こして救ってくれることもない。
奇跡とは滅多に起こらないからこそ奇跡と言うのだが、こういう大変な時にこそ本当に何か起こってくれたっていいじゃないか、と無茶なことを思ってしまう。
自力での脱出も再度試みるが、やはりどうにもならなかった。それどころか、一部の瓦礫に腕の脈を圧迫され続けたために、鬱血して指先すらも思い通りに動かせなくなってきた。
急接近する死を感じる。まさに身動き一つ取れない今、真っ暗な闇の中に一人放置されてしまった時のような恐怖だった。
はたして精神が限界に迫っているのか、妙な幻聴すら聞こえてくる。タタタタ、と迫ってくる誰かの足音。しかしそれは幻聴とは思えないほどに、次第に鮮明なものへとなっていく。
まさか、と桂木は視線を扉の方へと向けた。
助けが来ることなんて絶対に無いと思っていた。しかしそれとは裏腹に、確実に何者かが廊下を走ってこちらに近づいてきている。
まさか……まさか……。
建物の瓦礫が次々と振ってくる中で、次の瞬間、桂木たちが倒れている教室の扉が勢い良く開け放たれた。そして一人の男が飛び込んでくる。
桂木はその顔を見たとき、これは夢ではないかと思った。
「うわっ、こ、これは……」
御堂の土下座死体を前にし、驚きのあまり一歩後ろに飛び退く男。それは桂木と共謀してプログラムからの生徒達脱出を企てた、木田聡であった。
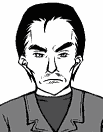 御堂一尉(プログラム補佐官)――『死亡』 御堂一尉(プログラム補佐官)――『死亡』
【残り 四人】 |
