千秋の目に映る限られた範囲の景色の中で、霞の姿が占める割合がだんだんと大きくなってくる。
ただ近づいてきているだけなのに、なぜか敵が本当に巨大化していっているような、そんな錯覚にとらわれた。
自分との距離が縮まるごとに膨らんでいく恐怖感が、じわじわと精神を蝕んでいっているのかもしれない。とても平常心を保っていられる状況ではなかった。
千秋は思うように動けない。まさに蛇に睨まれた蛙。ぬかるんだ地面に足を取られてしまったわけでもないのに、一歩後ろに下がることもできなかった。
カチカチと、カスタネットに少し似た音が耳に入ってくる。恐ろしさのあまりか、顎が震えて上下の歯がぶつかり合っていた。
血塗られたナタを握る霞の腕。同い年の少女のものとは思えないほど、筋肉質でかなり太い。腕だけではない。胴体と、そこから四方に分岐する手足――全身の筋肉がレスラーの如く発達している。
何回思い返してみても、やはり炎上する廃ビルで前に会ったときとは、あまりに様子が違いすぎる。あの時も確かに、霞からはただならぬ威圧を感じはしたが、包帯ずくめでありながらも身体のシルエットには全体的に丸みがあり、中学生の少女そのものであった。それが今では素手で岩を砕くことが出来そうなどころか、むしろ彼女自身が岩のようにも感じられる。
この短期間で霞にいったい何が起こったのは分からない。とにかく、戦ったところで勝てるわけがないのは一目瞭然だった。
そんな中で千秋はふと気付く。
相手の体格の変化にばかり目を奪われてしまっていたが、改めてよく見ると、霞は全身に幾つもの傷を負っているではないか。しかもそのどれもが掠り傷など浅いものというわけではなく、銃で撃たれたらしき深いものがたくさん見受けられた。身体の機能に影響を及ぼすほどの、深刻なものもあるように思われた。
ここまで深手を負っていたら、普通なら苦痛に顔を歪めるくらいはしそうなところだ。だが、霞はそんな様子など微塵も見せない。目の前の獲物に向かって、狩りの前の獣のような顔を見せるばかり。痛みなどまるで気にしていないか、むしろ感じてすらいないようだった。
ここまでくるともう、人間として異常だ。
霞は炎の中で身を焼かれているうちに、人外の力を手に入れてしまったのではないか。千秋は真剣に思った。極端に言えば、彼女は人間であることを捨て、悪魔か化け物にでもなってしまったのではないか、と。そうでなければもう説明が付かない。短期間で身体の能力を劇的に向上させる方法と、身体が傷ついても平気でいられる理由が。
千秋の肩に負けず劣らず、霞の身体につけられた銃創からの出血は相当酷い。臓器や骨格にまでダメージが及んでいるであろうし、もはや彼女が二本の足で立てていることが不思議なほどだった。
いつ崩れてもおかしくないような、ひびわれた鋼鉄の塊。今の霞を形容するには、こんな言葉が適切なのかもしれない。
「……ねぇ」
突然、霞が声を発する。
「あなた……さっき、私のことを悪魔か化け物とでも思っていたでしょう」
驚きのあまり胸が高鳴る。心の中を読み取ったかのように、霞は千秋が考えていたことを正確に言い当ててみせたのだ。
「驚くほどのことではないわ。恐々と私の姿を見るあなたの様子から、考えていたことはだいたい想像することが出来る」
獲物を前に目を光らせている彼女の姿には似つかわしくない、落ち着いた、それでいて少し上品な口ぶり。
「そりゃあ、この身体を見たら、そんなことも考えるでしょうね。あまりに現実離れしすぎているし。事実、間違ってはいないわ」
持ち上げたナタを肩の上に乗せて、霞は言った。
「私、悪魔に魂を売ったの」
その言葉の意味を、千秋は理解することが出来ない。童話の中の話じゃあるまいし、人間と悪魔が関わりを持つなんて、現実に起こり得るはずがないというのが頭の中にあった。
もう訳が分からない。しかし、霞は自身の変化について、それ以上説明を重ねてくれはしなかった。彼女にとっては、千秋が事を理解するかしないかなんて、どうでもよかったのだろう。ただ気まぐれで少し話してみただけのこと。
「喋りすぎたかしらね。どうせこれから死ぬという人間が、何を知っても無意味なのに」
霞は肩の上からナタを浮かし、高い位置で構える。
「頭、ぐちゃぐちゃに潰してあげるわね。私、いかにも異質な者を見ているっていう、今のあなたみたいな目つきが凄く嫌いなの」
突如、霞の目つきがいっそう厳しくなった。そして、ナタを握る手に、これまで以上の力が込められる。
「それじゃあね」
バイバイ、とでも言うように、彼女は前に出した左手をひらひらと振って見せた。既に千秋との距離は大股一歩分ほどで、手を伸ばせば十分に届く。
振り下ろされた刃が頭を真っ二つにする様子が、自然と目に浮かぶ。
今まで何度もピンチを切り抜けてきたが、今度こそ終わりだと真剣に思った。
「待て!」
その時、唐突に何者かの声が二人の間に割って入ってきた。場の空気が乱れ、さすがの霞も驚いたか、ナタを振り下ろす動作を中断し、急いで声のした方を見る。
「お前は……」
霞はナタを足元に落とし、腰に挿していたマシンガンを手にとって構える。
千秋もすぐさま、霞と同じ方向に目を向けた。
少し離れた木々の間、腰から下を藪の中に埋めた状態で誰かが立っていた。
「もう止めるんだ、御影」
男の声だ。
霞の動作を中断させたその人物は、一見しただけで千秋よりも背が高く、がっしりとした体格をしているのが分かる。
「あなた……、土屋君じゃないの……」
霞が言った。そう、この場に突然現れた人物は、男子唯一の生き残りである土屋怜二(男子十二番)だった。千秋が彼の姿を確認したのは、プログラム開始からでは今回が初めてであった。
はたして、怜二は千秋にとって敵なのか、それとも味方なのか。判断する材料は少ないが、霞の殺戮行為を止めようとする先の発言からすると、いきなり襲い掛かってくるなんてことはなさそうだ。
「数少ない生き残りの一人……。この島の中で探し出すのは大変だろうと思っていたけれど……、まさか自らのこのこと殺されに来てくれるなんてねぇ」
クスクスと笑う霞。すると、傍らの樹に手をつきながら、怜二が言った。
「やっと見つけた……。お前のことを、ずっと探し回っていた」
彼は少し息を荒げている。これまで山の中を走り回り続けてきたのか、かなり疲労しているようだった。
千秋は疑問に思う。怜二は何のために、霞を探し出そうとしていたのだろうか、と。見たところ武器を持っている様子はないし、戦う意志があるわけでもなさそうだ。
霞も同じところに引っかかりを覚えたのか、訳が分からないとでも言いたげな表情をしている。マシンガンをしっかりと構えてはいるが、怜二がいきなり攻撃の姿勢をとったりでもしない限り、引き金を引くような様子はない。
怜二は少しの間だけ俯き加減になって肩を上下させていたが、呼吸を整えてから頭を上げ、霞の方に真剣な眼差しを向けた。
「俺は、お前を止めに来たんだ」
彼が言った途端、周囲の木々が風を受けてざわついた。
一瞬、その場にいた人間全員が黙り込んでしまう。しかし、すぐに霞の小さな笑い声がそれをかき消す。
「何を言い出すのかと思ったら、ばっかじゃないの? あなた一人が割り込んできたところで、状況は何も変わりはしないわ」
完全に狂気に支配されてしまっている目つきに、千秋は身を震わせる。だが怜二は全く臆する様子を見せない。
「その身体……。まさか御影、悪魔に身を委ねたか」
「あら、春日さんと違って、あなたはすぐに状況を理解したみたいね。そうよ。悪い?」
「馬鹿な……」
どうやら怜二は、霞が言った『悪魔に魂を売る』ということの意味について、何か知っているようだ。
「お前、その薬がどれだけ大変なものか分かっているのか?」
「そりゃあね。でも、こんなのもうどうでもいいの。皆を殺し尽くせるなら、ね」
霞が不敵な笑みを浮かべるのを、千秋は黙ったまま見つめるばかり。
「そこに倒れているのは……、白石か。彼女を殺したのも、お前か?」
霞の背後に倒れている、変わり果てた少女の亡骸に目をやりながら、怜二が聞く。霞は悪びれる様子も無く、至極軽い調子で答えた。
「そうよ。何か問題でも?」
すると、霞の攻撃に備えていつでも樹の後ろに退避できる位置に陣取っていた怜二が、茂みの中から一歩前に踏み出して姿を完全に露にした。
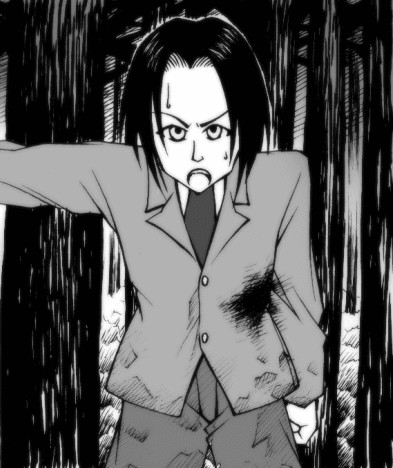
千秋の目線はすぐに、彼の左脇腹へと向いた。何者かの攻撃を受けたらしく、酷く出血していたのだ。さらに、全身に泥がまみれて、みすぼらしく染みになっている。千秋の服の汚れも今や相当なものだが、それをも遥かに凌ぐほどだった。いったい彼は、これまでにどれほどの距離を駆け回ってきたと言うのだろうか。とても想像が付かない。
「酷い格好ね。そんな状態で本当に、私のことを止めてみせるつもり?」
「……残念だよ、御影さん」
ふいに怜二は身体の前で手袋をはめた自らの右手を掲げて見せた。
「俺は君の暴走を止めあげたいと、心から思っている。しかしそのためには、思い出したくもないであろう、あの日の出来事の――真実を見せなくてはならない」
おもむろに手袋が外されると、指先から手首にまで渡って酷く焼け爛れた、彼の肌が姿を現した。
【残り 四人】 |
